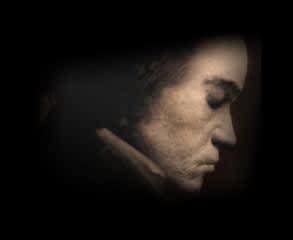
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
聴覚というのは、音楽家にとって不可欠の器官である。ウィーンに来て六年、やっと成功への道が開けた二十七歳のベートーヴェンをおそったのは、その聴覚の異常だった。1801年6月に、友人の内科医ヴェーゲラーと牧師のアメンダに書いた本人の手紙によると、それは3年前(つまり1798年)から始まっていた。まだ「演奏や作曲にはほとんど障害にならない」が、困難なのは人との対話だった。相手の声は聞こえるのだが、絶えず続く耳鳴りのために言葉が聞きとれない、かといって誰かが大声をあげたりすると耐えがたい、というのだ。また、以前は同業の誰よりもよい耳の持主だったのに、いまでは劇場で俳優の台詞を聞きとるためにはオーケストラ・ボックスのすぐそばまで行かねばならないという。
しかも、3年間に少なくとも4人の医師にかかってさまざまな治療を試みたが、一進一退をくり返しながら次第に慢性化していった。また治療といっても当時は耳に扁桃油を注入するくらいで、あとはもっぱら彼の持病である胃腸疾患の改善に向けられていた。医師も当人も、それが難聴の原因だと信じていたようだ。
それにしても、新進音楽家として世間の注目を集めていた当時のベートーヴェンにとって、それは試練の歳月だった。治る希望と不治の絶望のくり返しの間で苛立ちながら、しかも職業柄この秘密を人に知られまいと神経をすり減らしたからだ。敵対する人々がもしこのことを知ったら、何と言うだろうか? それゆえ、人の集まる場所への出入りを避けて孤独に閉じこもり、難聴をさとられまいとした。相手が親しい友人であろうと、その目に少しでも哀れみの色が浮かぶと、それが彼の自尊心には耐えがたかったからだ。もともとベートーヴェンは剛毅で大胆な反面、繊細で傷つきやすい感性の持主でもあったのだ。そして、こうした苦しい経験を経ながら、結局十数年後には完全な失聴者となっている。
青木やよひ著 『ベートーヴェンの生涯』 平凡社新書より抜粋
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今週末の演奏会、ならびに
水曜日のクラシック音楽道場の準備をするにあたって、
ベートーヴェン研究を進めているところです。
ベートーヴェンに関しては、
いくつかの迫力ある(!?)文献があり、
(あの有名なロマン・ロランなども!!)
それらの本の言葉・文字を追うと、ベートーヴェンの
人間・音楽家としての姿を目の当たりにするかのようで、
それは時に感動的ですらあります・・・
そんな文献のひとつと言いたく思います、ただいま私が頁を読み進めている
青木やよひ著『ベートーヴェンの生涯』
この本は、著者:青木やよひさんの「白鳥の歌」となった作品・・・すなわち、
これを書きあげ、その月に亡くなられたという・・・
一人の人間の、最期の大仕事・・・そんな凄い本なのです
内容・文章そのものに、
この方の生涯の大きな時間をかけて、まるで
ベートーヴェン研究がご自身の血肉となって一体化して湧き出ているかのような!!
溢れんばかりのベートーヴェンに関する文章は、私の心を強く打ちます。
彼女に敬意を表し、
その一部、「ベートーヴェンの難聴」に関する記述が
きれいに見事にまとまっているように思われ、
インターネットを通して、
ベートーヴェンという人物・作曲家に関する大きなポイントである「難聴」の問題、
その状況・真実が、分かりやすく、より広く多くの人々に伝わることを願い、これを
アップさせていただきたく思いました。
青木やよひさんのご冥福を
心よりお祈りいたします

♪
聴覚というのは、音楽家にとって不可欠の器官である。ウィーンに来て六年、やっと成功への道が開けた二十七歳のベートーヴェンをおそったのは、その聴覚の異常だった。1801年6月に、友人の内科医ヴェーゲラーと牧師のアメンダに書いた本人の手紙によると、それは3年前(つまり1798年)から始まっていた。まだ「演奏や作曲にはほとんど障害にならない」が、困難なのは人との対話だった。相手の声は聞こえるのだが、絶えず続く耳鳴りのために言葉が聞きとれない、かといって誰かが大声をあげたりすると耐えがたい、というのだ。また、以前は同業の誰よりもよい耳の持主だったのに、いまでは劇場で俳優の台詞を聞きとるためにはオーケストラ・ボックスのすぐそばまで行かねばならないという。
しかも、3年間に少なくとも4人の医師にかかってさまざまな治療を試みたが、一進一退をくり返しながら次第に慢性化していった。また治療といっても当時は耳に扁桃油を注入するくらいで、あとはもっぱら彼の持病である胃腸疾患の改善に向けられていた。医師も当人も、それが難聴の原因だと信じていたようだ。
それにしても、新進音楽家として世間の注目を集めていた当時のベートーヴェンにとって、それは試練の歳月だった。治る希望と不治の絶望のくり返しの間で苛立ちながら、しかも職業柄この秘密を人に知られまいと神経をすり減らしたからだ。敵対する人々がもしこのことを知ったら、何と言うだろうか? それゆえ、人の集まる場所への出入りを避けて孤独に閉じこもり、難聴をさとられまいとした。相手が親しい友人であろうと、その目に少しでも哀れみの色が浮かぶと、それが彼の自尊心には耐えがたかったからだ。もともとベートーヴェンは剛毅で大胆な反面、繊細で傷つきやすい感性の持主でもあったのだ。そして、こうした苦しい経験を経ながら、結局十数年後には完全な失聴者となっている。
青木やよひ著 『ベートーヴェンの生涯』 平凡社新書より抜粋
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今週末の演奏会、ならびに
水曜日のクラシック音楽道場の準備をするにあたって、
ベートーヴェン研究を進めているところです。
ベートーヴェンに関しては、
いくつかの迫力ある(!?)文献があり、
(あの有名なロマン・ロランなども!!)
それらの本の言葉・文字を追うと、ベートーヴェンの
人間・音楽家としての姿を目の当たりにするかのようで、
それは時に感動的ですらあります・・・
そんな文献のひとつと言いたく思います、ただいま私が頁を読み進めている
青木やよひ著『ベートーヴェンの生涯』
この本は、著者:青木やよひさんの「白鳥の歌」となった作品・・・すなわち、
これを書きあげ、その月に亡くなられたという・・・
一人の人間の、最期の大仕事・・・そんな凄い本なのです
内容・文章そのものに、
この方の生涯の大きな時間をかけて、まるで
ベートーヴェン研究がご自身の血肉となって一体化して湧き出ているかのような!!
溢れんばかりのベートーヴェンに関する文章は、私の心を強く打ちます。
彼女に敬意を表し、
その一部、「ベートーヴェンの難聴」に関する記述が
きれいに見事にまとまっているように思われ、
インターネットを通して、
ベートーヴェンという人物・作曲家に関する大きなポイントである「難聴」の問題、
その状況・真実が、分かりやすく、より広く多くの人々に伝わることを願い、これを
アップさせていただきたく思いました。
青木やよひさんのご冥福を
心よりお祈りいたします

♪




















