唯今お寺に関する本を興味深く読んでいるところで、
ふと思ったことがありました。
京都・宇治にある平等院鳳凰堂、
池をはさんで対岸に建物を見るとき、
こちら側が此岸(俗世)
あちら側が彼岸(来世)
という設定なのだそうです。

彼岸・・・という言葉で思い出すのは、
「お彼岸」!?
↑というと、
日本の習わしで今日なお、
お彼岸というと、お墓参りへ出掛けたりと、
ご先祖様との交流をする日があるわけですが・・・
今更ながら改めて考えてみると、
お彼岸とは、「来世」について思いを馳せる日、
と理解してよろしいのでしょうか。
人間として、必ず訪れる運命について、目をそらさず、受け止める・・・
西洋風にいえば、
「メメント・モリ」というのだそうです。
そして改めて、自分のこと、自分の携わっている
クラシック音楽のことを思い返してみますと、
おこがましいかもしれませんが申し上げますと、
自分はしょっちゅう、ピアノという楽器を前に
お彼岸をしているような気がするのです。
ベートーウ゛ェンの後期《ピアノソナタ》群を弾いているとき。
ショパン《幻想ポレネーズ》や後期の《ノクターン》を弾いているとき。


シューマン最後のピアノ独奏曲《暁の歌 op.133》を弾いているとき。
ブラームス晩年の作《クラリネット・ソナタ op.120-2》を弾いているとき。

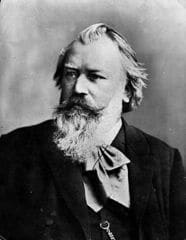
・・・どの作品も、作曲者の後期の音楽ばかりですな・・・
いや、
ラヴェル《亡き王女のためのパウ゛ァーヌ》は、

ラヴェルの若い頃の作品でした。
この音楽も、私には一種の「お彼岸」のように思えるような気がしております。

♪
P.S.
この記事を書いた翌日、平等院鳳凰堂の本堂、阿弥陀如来像の裏側に
新たに壁画の下書きが発見されたというニュースを目にしました。
ちょうどこの寺院について考えていたところ、
このような出来事とリアルタイムに重なるとは!?
なんだかちょっと、不思議な気がいたしました・・・
↓↓↓↓↓
http://mainichi.jp/kansai/news/20100325k0000e040014000c.html
ふと思ったことがありました。
京都・宇治にある平等院鳳凰堂、
池をはさんで対岸に建物を見るとき、
こちら側が此岸(俗世)
あちら側が彼岸(来世)
という設定なのだそうです。

彼岸・・・という言葉で思い出すのは、
「お彼岸」!?
↑というと、
日本の習わしで今日なお、
お彼岸というと、お墓参りへ出掛けたりと、
ご先祖様との交流をする日があるわけですが・・・
今更ながら改めて考えてみると、
お彼岸とは、「来世」について思いを馳せる日、
と理解してよろしいのでしょうか。
人間として、必ず訪れる運命について、目をそらさず、受け止める・・・
西洋風にいえば、
「メメント・モリ」というのだそうです。
そして改めて、自分のこと、自分の携わっている
クラシック音楽のことを思い返してみますと、
おこがましいかもしれませんが申し上げますと、
自分はしょっちゅう、ピアノという楽器を前に
お彼岸をしているような気がするのです。
ベートーウ゛ェンの後期《ピアノソナタ》群を弾いているとき。
ショパン《幻想ポレネーズ》や後期の《ノクターン》を弾いているとき。


シューマン最後のピアノ独奏曲《暁の歌 op.133》を弾いているとき。
ブラームス晩年の作《クラリネット・ソナタ op.120-2》を弾いているとき。

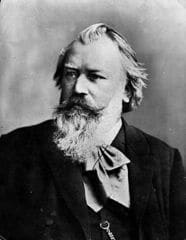
・・・どの作品も、作曲者の後期の音楽ばかりですな・・・
いや、
ラヴェル《亡き王女のためのパウ゛ァーヌ》は、

ラヴェルの若い頃の作品でした。
この音楽も、私には一種の「お彼岸」のように思えるような気がしております。

♪
P.S.
この記事を書いた翌日、平等院鳳凰堂の本堂、阿弥陀如来像の裏側に
新たに壁画の下書きが発見されたというニュースを目にしました。
ちょうどこの寺院について考えていたところ、
このような出来事とリアルタイムに重なるとは!?
なんだかちょっと、不思議な気がいたしました・・・
↓↓↓↓↓
http://mainichi.jp/kansai/news/20100325k0000e040014000c.html




















