モーツァルトの《トルコ行進曲》
といえば、
きっと誰もが知るクラシック音楽における有名曲だと思います。

その《トルコ行進曲》を、先日レッスンにて
生徒さんと楽譜を見ながらご一緒していたら、
なんと、
クラシック音楽における
ある「魅力絶大な和音」が、
モーツァルト自身の指示・書き込みにより
それが示唆されていることを見付けたのです。

それは、上の譜例の丸で囲ったところ。
この和音を下から見ると
― F(ファ)A(ラ)Dis(レ♯)C(ド)となり、
この和音には、ある名前がつけられており、
それは
【German Sixthジャーマン・シックス】と呼ばれるものです。
ほんのちょっと音楽和声の話にお付き合いいただきたいのですが、
この【ジャーマン・シックス】をインターネットで調べてみると、
これは
【VI度の和音】
この《トルコ行進曲》の調性であるa-moll(イ短調)でいうと、
― F(ファ)A(ラ)C(ド)に、
【増六度が加わったもの】
ここでいえば
― Dis(レ♯)
という合わせて四つの音からなる和音が【ジャーマン・シックス】
であるという説明が多く見つかりました。
この増六度が特徴的だからこそ「シックス」という名称が
ここに付いていると理解してよいでしょうか。
ちなみに、
私がドイツ留学にて
和声学の師匠から教わったこの【ジャーマン・シックス】の姿は、
【ドッペルドミナント】
a-moll(イ短調)でいうと、
― H(シ)Dis(レ♯)Fis(ファ♯)
という音に【7と9】という音が付き、
― A(ラ)C(ド)
さらに複雑なことに、
【根音が省略】され、そして最後に、
【第5音が下方変異】されたものが【ジャーマン・シックス】である
と習ってきました。
まとめて言うと、ようするに
― Dis(レ♯)F(ファ)A(ラ)C(ド)
という和音になるわけですが・・・
いずれにしろ、
【ドッペルドミナント】という和音は、
音楽において非常にインパクトの強い
魅力ある和音なのですが、それがさらにレヴェルアップして
【ジャーマン・シックス】と呼ばれる特殊な和音になっていることについて、
クラシック音楽を志す人たちであれば、
この魅力は是非とも会得しておきたいものです。
この和音は、
クラシックの星の数ほどあるレパートリーにおいて
少なからず、色々なところで見受けることができるものです。
今回、
モーツァルトの《トルコ行進曲》において見付けた
【ジャーマン・シックス】に特別驚いたのは、
モーツァルト自身の手により、この和音に(さらに言えば、
「この和音にのみ」と言っても間違いではなく)
「f(フォルテ)」
という強弱記号がつけられているという事実なのです。
(★ちなみに、譜例はNMA(新モーツァルト全集)のもので、
今日のモーツァルト原典版における
最も信頼のおける楽譜といえましょうから、
この「f」という指示が
モーツァルトの手によるものであることを
疑う必要はないでしょう)
わざわざこの【ジャーマン・シックス】の和音に
「f」と書き加えるモーツァルト・・・
モーツァルトは、もちろん、
当たり前といえば当たり前なのですが、
この和音が【ジャーマン・シックス】であることを知っており、
その活力を十二分に意識していたということが
ここに証明されているといってもよいでしょう。
モーツァルトは知っていたのです、
【ジャーマン・シックス】という和音の魅力を・・・
ちなみに、
ベートーヴェンだって、ブラームスだって、
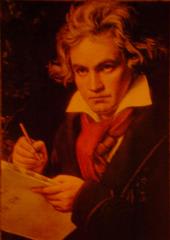
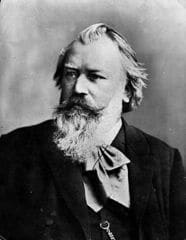
さらには過去にさかのぼってJ.S.バッハだって

この【ジャーマン・シックス】を使っています。
そして、我々にとって重要なことは、
これらの大作曲家達が「当然」のごとく知っている
この【ジャーマン・シックス】という和音の魅力を、
しっかりと受け止められるられるよう、
「知識」と「感性」と「技術」を持って、
伝統あるクラシック音楽の広く深い世界を
掘り下げてゆくことなのだと思う今日この頃なのでした。
この記事がお役にたちましたら、


↑ブログランキングに↑応援クリックよろしくお願いします
…………………………………………………………………
この記事に関するコメントやご連絡等ございましたら、
以下のアドレスまでメッセージをお送り下さい。
PianistSegawaGen@aol.com
…………………………………………………………………
といえば、
きっと誰もが知るクラシック音楽における有名曲だと思います。

その《トルコ行進曲》を、先日レッスンにて
生徒さんと楽譜を見ながらご一緒していたら、
なんと、
クラシック音楽における
ある「魅力絶大な和音」が、
モーツァルト自身の指示・書き込みにより
それが示唆されていることを見付けたのです。

それは、上の譜例の丸で囲ったところ。
この和音を下から見ると
― F(ファ)A(ラ)Dis(レ♯)C(ド)となり、
この和音には、ある名前がつけられており、
それは
【German Sixthジャーマン・シックス】と呼ばれるものです。
ほんのちょっと音楽和声の話にお付き合いいただきたいのですが、
この【ジャーマン・シックス】をインターネットで調べてみると、
これは
【VI度の和音】
この《トルコ行進曲》の調性であるa-moll(イ短調)でいうと、
― F(ファ)A(ラ)C(ド)に、
【増六度が加わったもの】
ここでいえば
― Dis(レ♯)
という合わせて四つの音からなる和音が【ジャーマン・シックス】
であるという説明が多く見つかりました。
この増六度が特徴的だからこそ「シックス」という名称が
ここに付いていると理解してよいでしょうか。
ちなみに、
私がドイツ留学にて
和声学の師匠から教わったこの【ジャーマン・シックス】の姿は、
【ドッペルドミナント】
a-moll(イ短調)でいうと、
― H(シ)Dis(レ♯)Fis(ファ♯)
という音に【7と9】という音が付き、
― A(ラ)C(ド)
さらに複雑なことに、
【根音が省略】され、そして最後に、
【第5音が下方変異】されたものが【ジャーマン・シックス】である
と習ってきました。
まとめて言うと、ようするに
― Dis(レ♯)F(ファ)A(ラ)C(ド)
という和音になるわけですが・・・
いずれにしろ、
【ドッペルドミナント】という和音は、
音楽において非常にインパクトの強い
魅力ある和音なのですが、それがさらにレヴェルアップして
【ジャーマン・シックス】と呼ばれる特殊な和音になっていることについて、
クラシック音楽を志す人たちであれば、
この魅力は是非とも会得しておきたいものです。
この和音は、
クラシックの星の数ほどあるレパートリーにおいて
少なからず、色々なところで見受けることができるものです。
今回、
モーツァルトの《トルコ行進曲》において見付けた
【ジャーマン・シックス】に特別驚いたのは、
モーツァルト自身の手により、この和音に(さらに言えば、
「この和音にのみ」と言っても間違いではなく)
「f(フォルテ)」
という強弱記号がつけられているという事実なのです。
(★ちなみに、譜例はNMA(新モーツァルト全集)のもので、
今日のモーツァルト原典版における
最も信頼のおける楽譜といえましょうから、
この「f」という指示が
モーツァルトの手によるものであることを
疑う必要はないでしょう)
わざわざこの【ジャーマン・シックス】の和音に
「f」と書き加えるモーツァルト・・・
モーツァルトは、もちろん、
当たり前といえば当たり前なのですが、
この和音が【ジャーマン・シックス】であることを知っており、
その活力を十二分に意識していたということが
ここに証明されているといってもよいでしょう。
モーツァルトは知っていたのです、
【ジャーマン・シックス】という和音の魅力を・・・
ちなみに、
ベートーヴェンだって、ブラームスだって、
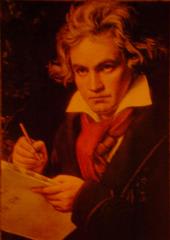
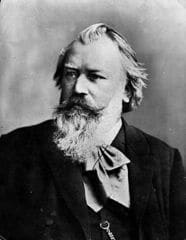
さらには過去にさかのぼってJ.S.バッハだって

この【ジャーマン・シックス】を使っています。
そして、我々にとって重要なことは、
これらの大作曲家達が「当然」のごとく知っている
この【ジャーマン・シックス】という和音の魅力を、
しっかりと受け止められるられるよう、
「知識」と「感性」と「技術」を持って、
伝統あるクラシック音楽の広く深い世界を
掘り下げてゆくことなのだと思う今日この頃なのでした。
この記事がお役にたちましたら、


↑ブログランキングに↑応援クリックよろしくお願いします
…………………………………………………………………
この記事に関するコメントやご連絡等ございましたら、
以下のアドレスまでメッセージをお送り下さい。
PianistSegawaGen@aol.com
…………………………………………………………………




















