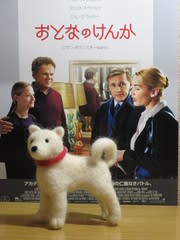普通に生きている“正義の味方”
* * * * * * * * *
長岡弘樹さんのミステリ短篇集。
まずは、表題作「傍聞き」。
この題名は、「かたえぎき」と読みます。
耳慣れない言葉ですが、
人は直接自分が聞いた話より、自分とは直接関係ない人同士が話している言葉を漏れ聞いたときに、
その話に信憑性を感じる、ということを表した言葉です。
女性刑事羽住啓子は忙しい毎日ながら、
最近娘の菜月とうまくいっていないことが気にかかります。
そんなとき、以前に彼女が逮捕したことのある男が別の事件で取り調べのため留置されます。
そしてなぜか彼女に面会を求める。
啓子はそれを以前の逮捕の逆恨みで、男が自分に脅しをかけているのではないかと疑います。
やがて男の釈放が迫り、啓子は娘が男に危害を加えられるのではないかと恐れますが・・・。
"傍聞き"の効果を狙ったものが二箇所あり、
それも悪意ではなく、善意で行われたという意外性がうまくできていまして、
とても満足感の高いストーリーでした。
この本の主人公は、救急隊員、刑事、消防士など、
人を助ける立場の人達が多いのです。
ですが、ことさらヒーローとして描かれているのではなく、
ごく普通の悩みや楽しみを持った人たち。
けれどもやはりほんの少し人より正義感は強く・・・、
ミステリというよりは人情話を読んだような感覚が残ります。
日本推理作家協会賞(短編部門)受賞
「おすすめ文庫王国」国内ミステリー部門 第1位
それほどボリームはなくお手軽に読める割には、
内容の満足度も高く、お得な一冊。
「傍聞き」 長岡弘樹 双葉文庫
満足度★★★★☆
自分で言っておきながらなぜ★★★★★ではないのか。
う~ん、満足ではありますが大満足とまでは行かない。
・・・短編故にというところで、ご勘弁を。
 | 傍聞き (双葉文庫) |
| 長岡 弘樹 | |
| 双葉社 |
* * * * * * * * *
長岡弘樹さんのミステリ短篇集。
まずは、表題作「傍聞き」。
この題名は、「かたえぎき」と読みます。
耳慣れない言葉ですが、
人は直接自分が聞いた話より、自分とは直接関係ない人同士が話している言葉を漏れ聞いたときに、
その話に信憑性を感じる、ということを表した言葉です。
女性刑事羽住啓子は忙しい毎日ながら、
最近娘の菜月とうまくいっていないことが気にかかります。
そんなとき、以前に彼女が逮捕したことのある男が別の事件で取り調べのため留置されます。
そしてなぜか彼女に面会を求める。
啓子はそれを以前の逮捕の逆恨みで、男が自分に脅しをかけているのではないかと疑います。
やがて男の釈放が迫り、啓子は娘が男に危害を加えられるのではないかと恐れますが・・・。
"傍聞き"の効果を狙ったものが二箇所あり、
それも悪意ではなく、善意で行われたという意外性がうまくできていまして、
とても満足感の高いストーリーでした。
この本の主人公は、救急隊員、刑事、消防士など、
人を助ける立場の人達が多いのです。
ですが、ことさらヒーローとして描かれているのではなく、
ごく普通の悩みや楽しみを持った人たち。
けれどもやはりほんの少し人より正義感は強く・・・、
ミステリというよりは人情話を読んだような感覚が残ります。
日本推理作家協会賞(短編部門)受賞
「おすすめ文庫王国」国内ミステリー部門 第1位
それほどボリームはなくお手軽に読める割には、
内容の満足度も高く、お得な一冊。
「傍聞き」 長岡弘樹 双葉文庫
満足度★★★★☆
自分で言っておきながらなぜ★★★★★ではないのか。
う~ん、満足ではありますが大満足とまでは行かない。
・・・短編故にというところで、ご勘弁を。















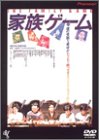












 「子羊」
「子羊」