「である」ことと「する」こと 第三段落
「である」社会と「である」道徳 ⑨~⑫
⑨ 次に、右のような典型の対照をより明瞭にするために、徳川時代のような社会を例にとってみます。言うまでもなく、そこでは出生とか家柄とか年齢(年寄り)とかいう要素が社会関係において決定的な役割を担っていますし、〈 それら 〉はいずれも私たちの現実の行動によって変えることのできない意味を持っています。したがって、〈 こういう社会 〉では権力関係もモラルも、一般的なものの考え方の上でも、何をするかということよりも、何であるかということが価値判断の重要な基準となるわけです。
⑩ 〈 人々の振る舞い方も交わり方も 〉ここでは彼が何であるかということから、いわば自然に「流れ出て」きます。武士は武士らしく、町人は町人にふさわしくというのが、そこでの基本的なモラルであります。各人がそれぞれ指定された「分」に安んずることが、こうした社会の秩序維持にとって生命的な要求になっております。こういう社会では、同郷とか同族とか同身分とかいった既定の間柄が人間関係の中心になり、仕事や目的活動を通じて未知の人と多様な関係を結ぶというようなことは、実際にもあまり多くは起こりませんが、そういう「『する』こと」に基づく関係にしても、できるだけ「である」関係をモデルとし、それに近づこうとする傾向があるのです。
⑪ こういう社会でコミュニケーションが成り立つためには、相手が何者であるのか、つまり侍か百姓か町人かが外部的に識別されることが第一の要件となります。服装、身なり、言葉遣いなどで一見して相手の身分がわからなければ、どういう作法で相手に対してよいか見当がつかないからです。しかし逆に言えば、こういう社会では、人々の集まりで相互に何者であるかが判明していれば――また事実そこでは未知の者の集会はまずあまり見られないのですが――別段討議の手続きやルールを作らなくても、また「会議の精神」を養わなくても、「らしく」の道徳に従って話し合いは〈 おのずから軌道に乗る 〉わけなのです。
⑫ 言い換えるならば、〈 赤の他人の間のモラル 〉というものは、〈 ここ 〉ではあまり発達しないし、発達する必要もない。いわゆる公共道徳、パブリックな道徳と言われているものは、この赤の他人どうしの道徳のことです。たとえば儒教の有名な五倫という人間の基本的関係を見ますと、君臣、父子、夫婦、兄弟、朋友であります。このうち初めの四つの関係は縦の上下関係とされ、朋友だけが横の関係です。そうして友達関係をさらに超えた他人と他人との横の関係というものは、儒教の基本的な人倫の中に入ってこない。つまりこれは儒教道徳が典型的な「である」モラルであり、儒教を生んだ社会、また儒教的な道徳が人間関係の要と考えられている社会が、典型的な「である」社会だということを物語っております。これに対して〈 赤の他人どうしの間に関係を取り結ぶ必要が増大 〉してきますと、どうしても組織や制度の性格が変わってくるし、またモラルも「である」道徳だけでは済まなくなります。
言葉の意味
「モラル」 … 道徳・倫理
「安んずる」… 満足する
Q15 「それら」の指示内容を抜き出せ。
A15 出生とか家柄とか年齢(年寄り)とかいう要素
Q16 「こういう社会」で価値判断の基準となるのは何か。10字で抜き出せ。
A16 何であるかということ
Q17 「人々の振る舞い方も交わり方も」とあるが、人々はどうすることが求められたのか。25字以内で抜き出せ。
A17 各人がそれぞれ指定された「分」に安んずること
Q18 17(の答え)のような考え方のことを、筆者は端的にどう名付けているか。8字で抜き出せ。
A18 らしくの「道徳」
Q19 「あかの他人の間のモラル」とは何か。言い換えた語を二つ抜き出せ。
A19 公共道徳、パブリックな道徳
Q20 「ここ」とはどこか。60字以内で説明せよ。
A20 服装、身なり、言葉遣いなどによって一見して相手の身分がわかり、
お互いにどうコミュニケーションすべきかが判断しやすい社会。
Q21 「赤の他人どうしの間に関係を取り結ぶ必要が増大」した、社会における要因とは何か。
それが書かれている部分を、次の段落から35字以内で抜き出せ。
A21 生産力が高まり、交通が発展して社会関係が複雑多様になるにしたがって
Q22 「徳川時代のような社会」とはどのような社会か。本文に即して50字以内で述べよ。
A22 個人の意志や行動では変えることのできない本人の属性が、
すべての価値判断の基準となり、各人の行動を規定する社会。
⑨徳川時代
出生・家柄・年齢etc … 決定的な役割
↓
何であるか … 価値判断の基準
↓
振る舞い方・交わり方が決まる
∥
「分」に安んずる
人間関係 … 既定の間柄(同郷・同族・同身分)が中心
↑
↓
未知の人と多様な関係を結ぶ
⑪こういう社会のコミュニケーション
相手が何者であるのか・外部的に識別されること
↓
ふるまい方は決まる
∥
「らしく」の道徳
↑
↓
⑫赤の他人の間のモラル(公共道徳、パブリックな道徳)
↑
↓
儒教道徳 … 典型的な「である」モラル










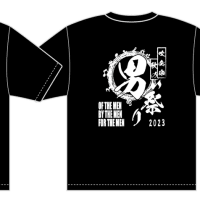





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます