「である」ことと「する」こと 第5段落 ⑱~⑲
政治行動についての考え方
⑱ ところで政治行動とか経済活動といった社会行動の区別は、「する」論理から申しますと当然に〈 機能の区別 〉であって、人間や集団の区別ではない。近代社会の場合では〈 こうした機能 〉はあらゆる人間や集団に横断的に分布しているわけです。もちろん政府や政党のようないわゆる政治団体は主として政治活動をするし、会社や労組のような経済団体は主として経済活動をするにちがいない。しかしたとえば、政党も土地の売買をするときには、経済活動をしているわけだし、アメリカの労組のような「経済主義的」傾向の強い労組でも選挙などのときには活発に政治活動をする。ところが「である」思考と「らしく」道徳の強い社会では、とかくそうした「はたらき」の区別が特定の人間や集団の区別からもっぱら出てくるように考えられます。つまり文化活動は「文化団体」や「文化人」に、政治活動は「政治団体」や「政治家」にそれぞれ〈 還元 〉されてしまうから、文化団体である以上、政治活動をすべきでない、教育者は教育者らしく政治に口を出すなというふうに考えられやすいのです。
⑲ 〈 こういう傾向 〉が甚だしくなってくると、政治活動は職業政治家の集団である「政界」の専有物とされ、政治を国会の中にだけ封じ込めることになります。ですから、それ以外の広い社会の場で、政治家以外の人によって行われる政治活動は本来の〈 分限 〉を超えた行動あるいは「暴力」のように見なされるようになる。ところが言うまでもなく、民主主義とはもともと政治を特定身分の独占から広く市民にまで解放する運動として発達したものなのです。そして、民主主義を担う市民の大部分は日常生活では政治以外の職業に従事しているわけです。とすれば、民主主義は〈 やや逆説的 〉な表現になりますが、〈 非政治的な市民の政治的関心 〉によって、また「政界」以外の領域からの政治的発言と行動によって初めて支えられると言っても過言ではないのです。
Q35 「機能の区別」と同じ意味の言葉を9字で抜き出せ。
A35 「はたらき」の区別
Q36 「こうした機能」とは何を指すか、17字で抜き出せ。
A36 政治行動や経済活動といった社会行動
Q37 「還元」の意味を記せ。
A37 物事をもとの状態にもどすこと
Q38 「こういう傾向」とは何か、本文の言葉を用いて40字以内で記せ。
A38 さまざまな社会行動の機能の区別が、
特定の人間や集団の区別に還元されていく傾向。
Q39「分限」の意味を記せ。
A39 身のほど 身分 分際
Q40「やや逆説的」とあるが、なぜそう言えるのか。40字以内で記せ。
A40 民主主義という政治活動は、
非政治的な人に支えられて成立していることになるから。
Q41「非政治的な市民の政治的関心」とは何か。
A41 日常生活においては政治と無関係人が、主権者として政治に対してもつ関心。
近代社会
社会行動の区別=機能の区別 → あらゆる人間・集団に分布
↑
↓
「である」思考と「らしく」道徳の強い社会
はたらきの区別=人間・集団の区別










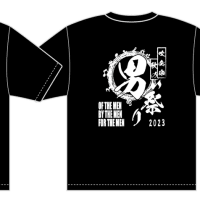





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます