今日で2月も終わり。
28日しかないのだから早く感じるのも当たり前か。
さて,夕方のこと。
ゆきたんくの楽しみの一つは机の上に乗っているお菓子である。
誰かが置いてくれるのだが,それが楽しみであるのだ。
今日は,ちょっと前にゆるキャラで日本一になったお方である。
これだ。

ぐんまちゃんのビスケット。
腹減りゆきたんくである。
写真を撮ったらすぐにいただいた。
今日で2月も終わり。
28日しかないのだから早く感じるのも当たり前か。
さて,夕方のこと。
ゆきたんくの楽しみの一つは机の上に乗っているお菓子である。
誰かが置いてくれるのだが,それが楽しみであるのだ。
今日は,ちょっと前にゆるキャラで日本一になったお方である。
これだ。

ぐんまちゃんのビスケット。
腹減りゆきたんくである。
写真を撮ったらすぐにいただいた。
2月24日は義父の法事だった。
その後に小石川後楽園の梅を見に行った。
そこで思い出した。
ここには戦争遺跡がある。
そして見つけた。

今まで写真で見るだけだった一品。
ところで,この一品は工廠で使用していた弾丸製造機の一部と言われているがそれ以上は分からない。
かつて,この地には旧陸軍東京砲兵工廠があった。
徳川の庭園が陸軍省の所轄となり,工廠になったのだ。
庭園の中にある九八屋という蕎麦屋の横にポツンとある。
なんの解説もない。
梅を見に来ている人たちはみんなスルーしていく。
これじゃぁいけないよねぇ。
ゆきたんくの女房のりたんは研究者である。
そしてその研究に関わることでモルモットになることになった。
うん,180㎝・95㎏のモルモットである。
ウン百万円する体重計で体重を計り,腹回りを計り,血液検査をする。
前夜から飯は抜いているので,お弁当が出た。

実にヘルシーそうなお弁当。
まぁ,薄味であるが美味しくいただいた。
今までMECと称して,肉・卵・チーズを中心に頑張って食べてきた。
この実験は,炭水化物も摂りながらその健康状態を調べようというものである。
期間は1か月。
気持ちが持つかどうか・・・
この間(かん),旅の楽しみとして沖縄旅行のことを書いてきた。
戦争遺跡に関する内容が多い中で,間違えたことを書いてはいけないと思った。
本を数冊購入して読んだ。

貪るように読んだ。
学術的な本ではないが,実際に戦火の中に身を置いた方々や,戦後史を検証しようと書かれた本である。
戦火の中に身を置いた方は,実際の体験に基づいて書かれている。
同じ場所であっても,人によってその時の状況に差があることもある。
同じ場所で,同じ時刻に,同じ人たちで聞いた話ではないだからだろう。
「伊原第一外科壕と伊原第三外科壕に移動する時には,ジャンケンで負けた者が第一,勝った者が第三へ行くことになった。」
と書かれていたり,
「追い出されるように出た。」
という内容のものもある。
もっとも,もともといた場所が同じでないことも考えられる。
一つが糸州壕で,もう一つが山城本部壕であるかも知れない。
運を天に任せるような状況だったということだ。
そこにしっかりした作戦がなかったということだ。
学徒隊は1945年6月18日に突然解散命令が出て,自分たちの身は自分たちで守らねばならない立場に追い込まれた。
被弾か,自決か・・・
自分はこのような立場に追い込まれたことはない。
その当時の方々の気持ちが少しでも想像できるほどの勉強もしていない。
また沖縄に行かねば・・・
義父が亡くなって1年になる。
義母も小さくなってしまった。
寂しくない訳はない。
まあ,こういう時にみんなで集まることは良いことだ。
賑やかさが大好きだった義父。

来たよ。

静かなお寺さん。東大近くにある願行寺。
その義父が,ゆきたんくの長男おーちゃん,次男つっくんのうるささに閉口したことを思い出してしまった。
今は成人して静かな長男,次男はその時のことを覚えている訳がないか・・・
ゆきたんくの奥方のりたんが宿泊を伴う出張に行っている。
毎日のゆきたんく家の行事。
それは,夜に時代劇チャンネルで「大岡越前」を見ることである。
のりたんは1週間ぐらいは見れないのだ。
そこで,これをラインを送ってあげた。
それだけで大喜びののりたんである。
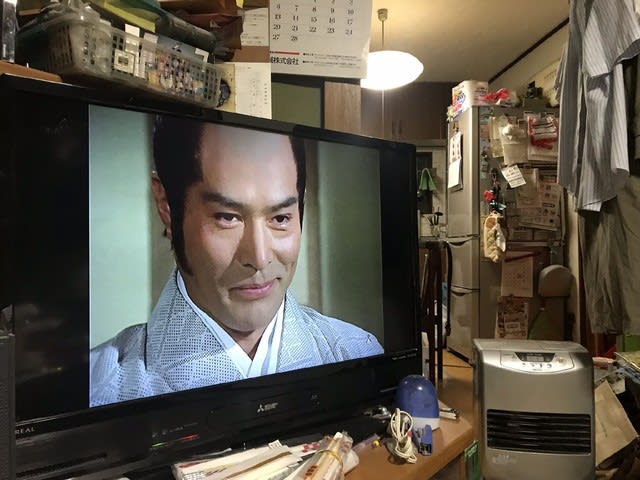
昨日みた「大岡越前」。
ひめゆりの塔があったのが伊原第三外科壕である。
そこから車で2分と離れていない所に伊原第一外科壕がある。
随分と違う。
何がって人がいない。

この碑があったので場所が分かった。
戦跡の特徴だが,気温の高い時は草が茂っていてその姿を十分に見ることができないことがある。
大きな碑があったので,場所がすぐ分かったのだ。
ところで,伊原第三外科壕は地面の高さで目の前に穴が開いていた。
ここの穴(ガマ)はどこか・・・
「こっちだ。」
同行したY氏が先陣を切る。
碑の左手の方にどんどん吸い込まれていく。
その時にY氏が撮ったゆきたんくだ。

どれだけ深く降りていくのだろうか。
何かこの雰囲気はチビチリガマに似ているか。
あそこは階段が設けられていた。
そして地面の高さからみると深かった。
降りていくうちにガマの入り口が見えてきた。

鍾乳石が歯のように並んでいる下にガマが口を開けている。
ゆきたんくは体が大きいので入れないような穴に見えた。
まして閉所恐怖症である。
穴に近づいてみた。
この中に100人くらいを収容できる広い空間があるという。
・・・「ひめゆりの沖縄戦…伊波園子著」より

更に近づいてみる。

中は水蒸気が満ちているようだ。
1年を通して一定の温度であるはずだが,たくさんの人間が長い時間入っていたのなら中に環境はさぞ酷かったことだろう。
この中で砲弾の嵐を凌いでいたというのが実情で,実際に運ばれてくる負傷者の手当はキャリーオーバーだったという。
後に書く山城壕から伊原第一外科壕と伊原第三外科壕に分かれて来たひめゆり学徒も,第三外科壕の方はあの悲劇に逢うのだ。

カメラは構えたが,何かを考えてシャッターを押せずにいるゆきたんく。
「ひめゆりの塔」を初めて知ったのは22歳の時。
さだまさし氏の「しあわせについて」を聴いた時だった。
映画の主題歌なんだ。
「ひめゆりの塔」ってなんだろう。
ギターの弾き語りができるようになった。
でも「ひめゆりの塔」ってなんだろう。
言葉だけが残って,それに近づかなかったゆきたんくである。
これは氏の「防人の詩」の時も同じであった。
これも映画「二百三高地」の主題歌だ。
両者の共通項は戦争だったのだ。
当時のゆきたんくは戦争と聞いただけでそこから深入りしなかった。
さだまさし氏のファンだと言っても,その意味の深いところまでを理解していなかったのである。
さだまさし氏の楽曲は短編小説のようで好きだなんて得意になっていただけなのだ。
旅をするようになり,勉強嫌いだったのが多少予習をするようになった。
その面白さを知ると,あちらこちらに行きたくなる。
ここ20年の間,少しずつ自分が変化してきた。
35年前に知ったひめゆりの塔に今回会うことができた。
もちろん事前に勉強をした。
いやぁ,参ってしまった。

高さが1mもない大きさだ。
次の目的地はティダヌチジガマ。
事前地図で調べて,その場所についた。
グーグルさんに載っている写真とおなじものを見れた。
ただガマらしきものがない。

グーグルさんのマップにあったペイントのある壁。 → Map

その近くの道沿いにあるプロック塀。
車を路駐して近辺を歩いてみたのだが,それらしきものはなかった。
この時,ゆきたんくとY氏はきっとこの建物の中になってしまっているのだと納得して場所を後にした。
帰宅後調べてみるが,情報が非常に少ない。
分かったことは,ちゃんとした避難壕であったことだ。
別の場所にあるのかもしれない。
地元の人に聞くのが一番かもしれない。
次回の宿題だね。
さて,お墓からティダヌチガマを目指す。
少し時間を使ったので取り戻さねばと思いながら気持ちは楽しい。
車の窓からふっと見えたものが。
今度はゆきたんくがY氏に
「車を停めて,何かあったよ。」

ヌヌマチガマの表示である。
なんと白梅学徒とある。
戦前沖縄には21の中等学校があっだ,沖縄戦ではこれらずての男女中等学校の生徒たちが動員されたという。
主に看護活動に当たったのは女子生徒で,男子生徒は上級生と下級生に分かれた編成で与えられた仕事をこなしていった。
つまり,ひめゆりだけを予習していたゆきたんくが,ここで脳髄に鉄槌をくらった訳である。
それも完璧な不意打ちだったので,より強烈な一撃となったのだ。

戦争遺跡が公園として残る。なんと素晴らしいことか。歴史の証人であるのだ。

今度沖縄に来るときにはここも絶対に再訪する。
そう,結果的にもうけたのである。
だいたい目的地がはっきりしているのに,途中で寄り道をするやつの気が知れない。
と,いつも思われているゆきたんくである。
糸数アブチラガマに振られ,次の目的地テイダヌチガマに向かう途中道をザワワァ,ザワワァと走っている時にそれは起きた。

サトウキビを道の両端に見て走る。
きっと沖縄の伝統的なお墓だろう。
取材したいなと思った時にY氏が車のブレーキを踏んだ。
「ごめん,〇〇ちゃん,ちょっと良い?」
Y氏とゆきたんくのストライクゾーンはどうやら同じらしい。
車を停めるや否や飛び出して取材である。

家一軒ほどの大きな墓である。

こりゃあ,取材せずにはおかれないよな。 → Map
Y氏にはいいよ,いいよと言いながら,自分もすかさず写真撮影をしているゆきたんくである。
このような行動に出る時に我々二人では止める者がいないではないか・・・
これは後々に響くこともあるが,学校での授業と授業の合間に休み時間のように最初から遊び時間を設定するしかないな(笑)
墓は二基あった。良い取材であった。
大失敗である。
いや,失敗は成功の元か・・・
旅に出て施設を利用する際は,事前に予約が必要かどうか直接その施設に尋ねるのが良い。
こんなことは基本中の基本だと言う人もいるだろう。
ゆきたんくも仕事の時はそうしている。
旅の時は対して気にしてないことが多い。
せいぜい,行き帰りの足,ホテル,レンタカーくらいだ。
まぁ,昨年の「軍艦島」は慎重に予約したさ。
知念岬の後は糸数アブチラガマを覗こうと思っていた。
それこそ,チビチリガマやシムクガマのように見れると思っていのだ。
事前にネットも覗いたが,団体以外は行くと入れたという旅行者の話を読めた。
地図で示されている所へ行ったら「南部観光総合案内センター」がある。

南部観光総合案内センター → Map
受付に女性がいた。
ガマのことをここで聞くことにした。
事務所の方「あっ,ご予約済みですか?」
ゆきたんく「予約がいるのですか?」
事務所の方「前日までにいただくことになっています。」
ゆきたんく「分かりました,資料などいただいて良いですか?」
事務所の方「明日ならご案内できますよ。」
ゆきたんく「本日4時の飛行機で帰るのです。千葉から来ました。」
なんて会話をしながら,資料をいただきガマの入り口を確認することにした。

案内板に従って移動する。あと30mのところに細かい説明があった。
アブは深い縦の洞窟,チラは崖のこと。
この言葉で壕の形状がどのようなものか少しは想像できる。
270mのガマに600人もの傷病兵がいたということ。
その世話をしたのはひめゆり学徒である。
人生の多感な時期を国のために捧げたのだ。

入り口を見つけた。地図より100m西にある。

覗くと受付がある。
行けるところまで行って見ようと歩を進めると受付から若い男性が出てきた。
これまでの顛末を話し,せめて場所だけでも確かめるためにきたことを話すと,いろいろと丁寧に説明をしてくださった。
そして入り口だけでもとお願いしたら写真撮影をさせてくれたのである。

糸数アブラチガマの入り口だ。
基本中は撮影禁止なので,取材としては目的を果たすことができたゆきたんくである。
今度は中に入って当時の様子を学習したいと思う。
沖縄の海。
イメージしていたのはエイトマンの歌だった。
エイトマン?
1963-64のアニメだから知っている人は50代だね。
♪光る海 光る大空 光る大地 行こう無限の地平線♪
光っているけれど青いんだよな。
それを実際自分の目で見たことが嬉しい。

この青さはなんだ。

浅いところまで青いぞ

たまらん。
行きの飛行機は,この上を飛んでいたのだが,この辺りの写真は撮っていなかったようだ。
くやし・・・
首里城は戦跡であった。

第32軍合同無線通信所跡の表示
爆撃で破壊された壕があった。
園比屋武御嶽のすぐ横である。
第32軍の大規模な地下壕があった場所だ。
大戦末期に編成され,司令部があったのが首里だ。
首里が陥落し,南部への撤退,司令官と参謀長の自決により軍としての機能は終わりを告げている。
1年3か月の戦いだった。
その中心部だったところを自分の目で見ている。

第32軍合同無線通信所跡

司令部跡
このような戦争遺跡を見るにあたり,首里城が完璧に破壊されたことが理解できる。
しかし大戦末期によくこれだけのものを作ることができたと思う。
首里城が琉球王国の司令塔であったと聞いた。
そもそも琉球王国についても知らなかったゆきたんくである。
現在の琉球諸島を中心にし、琉球國としてい450年間、奄美群島、沖縄諸島、先島諸島を統治したという。
それが、琉球列島とも呼ばれている訳だ。
離島の集合体で総人口17万人にも満たない小さな王国であった。
これが、琉球王国の概要だ。
その司令塔であった、そう王がいたのが首里城だ。
それをフラグメント(断片)として自分の感想を述べる以外の方法を持ち合わせていない。
自分の目で見たものを、自分の感じたままに書いてみるのが、「伝えたんく」のコンセプトなので悪しからず。

一番最初の門、守礼門。
首里城には実にたくさんの門がある。
しかし、門の紹介が目的ではないのでここ一つにしておく。
そして沖縄では各所で耳にする御嶽(うたき)という言葉。
琉球王国が制定した聖域の総称で各地方の呼び名で呼んでいたという。

園比屋武御嶽石門(そんひゃんうたきいしもん)
守礼門をくぐってすぐの北側に御嶽がある。
その入り口である石門。
この向こうの森の中に神聖な場所がある。
御嶽の多くは森の空間や泉や川などで、島そのものであることもあるという。
霊的な存在である感じも受ける。
そしてこの御嶽が琉球王国とともにあったということ。
祖先崇拝の場所であり,保水力の乏しい琉球石灰岩の土地柄水が神聖化されたこととも無関係ではないと考える。