【日銀】:あるぞ追加値上げ…「次のタイミング」は7月か? 悩める植田総裁の“胸の内”
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【日銀】:あるぞ追加値上げ…「次のタイミング」は7月か? 悩める植田総裁の“胸の内”
日銀がマイナス金利を解除して「利上げ」したのに1ドル=151円台の円安に進んでしまった。想定外の事態になり、物価高加速で家計を圧迫する懸念が強まっている。
<picture> </picture>
</picture>
物価高抑制のために「次の利上げ」を…(参院財政金融委員会での植田和男日銀総裁)/(C)日刊ゲンダイ
そんな中、日銀の植田総裁は21日、参院財政金融委員会に出席。19日にマイナス金利解除に踏み切ったことについて、自民党議員から「物価安定目標の達成を見極める前に正常化を焦ってはいないか」などと問われた。これに対し植田総裁は、政策転換のタイミングが遅れた場合に「物価が2%の上昇率できちんと止まるかどうか、はっきりしない。アップサイド(上昇方向)のリスクも上がってくることを考え、判断した」と説明した。
■11月の大統領選までに
「利上げが4月ではなく3月だったのは、日銀が11月の米大統領選を意識しているからのようです。大統領選の結果次第で状況が不安定になる前に、次の追加利上げを実施したいと考えている。次回4月の金融政策決定会合は25、26日ですから、4月では遅い。3月なら11月まで半年以上の期間があります。次は短期金利の誘導目標である政策金利を、現状の0~0.1%から0.25%へ引き上げることになるでしょう」(金融ジャーナリスト・森岡英樹氏)
日銀の政策変更後、円相場が一気に2円も円安方向に進んだのには、「次の利上げ」を求める市場の催促相場の意味合いもあるという。投機的な動きも絡む急激な円安に、21日は鈴木財務相も「高い緊張感を持って注視したい」と牽制していた。
日銀は物価高抑制のために、追加利上げで早めに動かざるを得なくなるのではないか。
「21日の国会での植田総裁の答弁でわかるように、日銀はインフレ対策が後手に回っているという意識をかなり持っていますよ」と言うのは経済評論家の斎藤満氏だ。さらにこう続ける。
「中央銀行は本来、インフレを未然に抑えなきゃいけない。学者の植田総裁はよくわかっていると思います。日銀は本音ではもっと早いタイミングで利上げしたかった。もっとも、植田総裁が『緩和的な金融環境を継続』と言ってしまったこともあり、次の利上げは緩やかなタイミングにならざるを得ない。四半期に1度なら許容範囲。次の利上げは7月と、日銀は考えているでしょう。順調に行けば、年内12月に、もう一度利上げして0.5%まで戻したいのではないか」
利上げでも円安基調を受け、東証は21日、4日につけた史上最高値を更新した。植田総裁には悩ましい日々が続く。
元稿:日刊ゲンダイ DIGITA 主要ニュース マネー 【トピックス】 2024年03月22日 13:50:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。












 </picture>
</picture>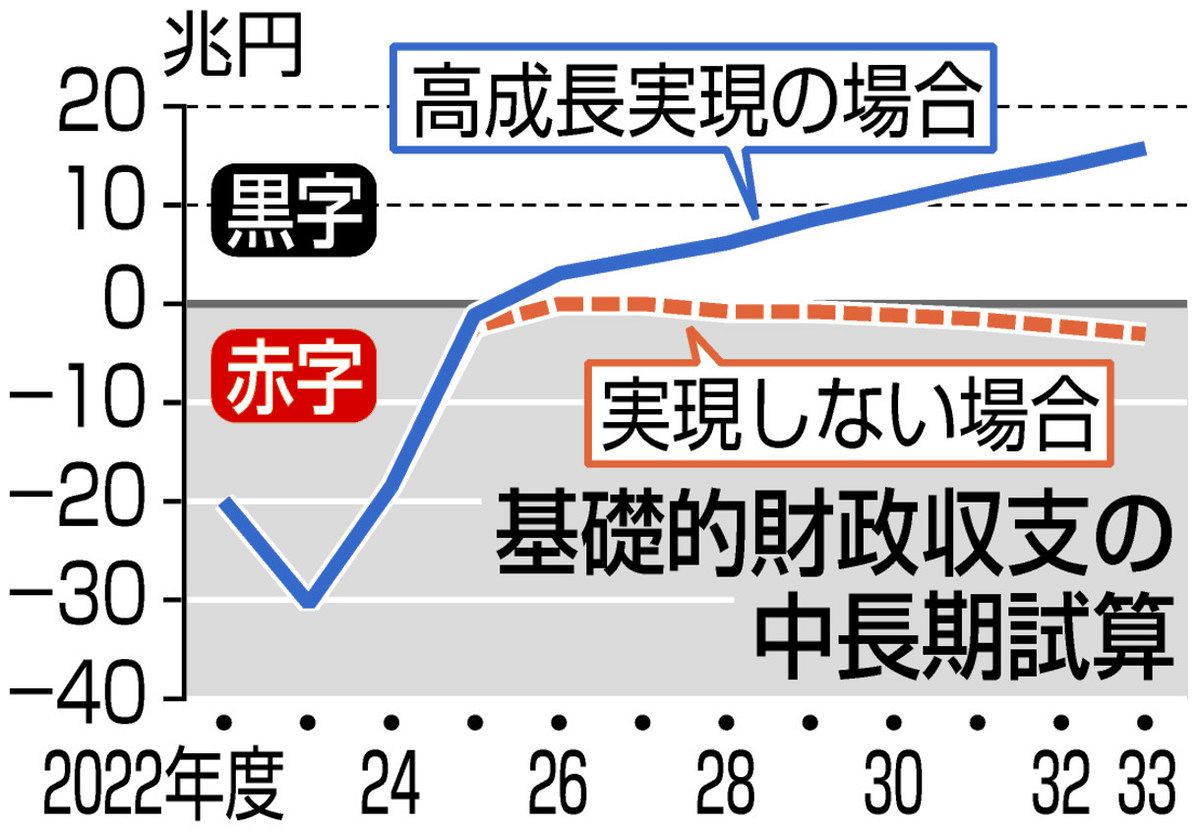




:quality(40)/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/YDLLEEQ3FBIADAX3S743R7I6HY.jpg)
 </picture>
</picture>
 </picture>
</picture>





