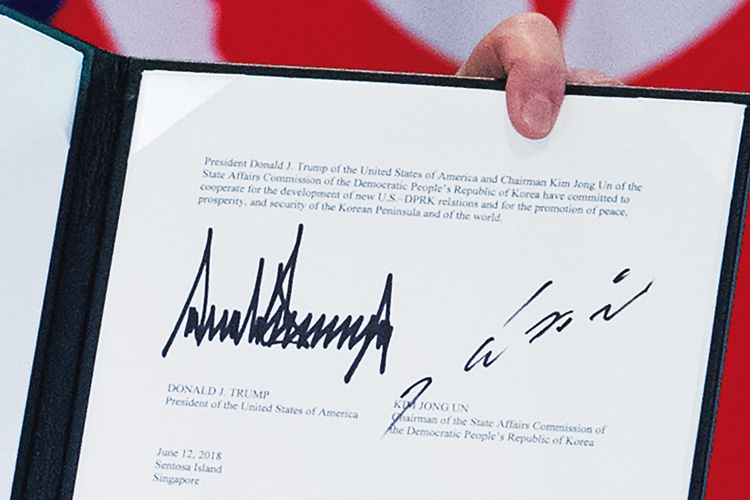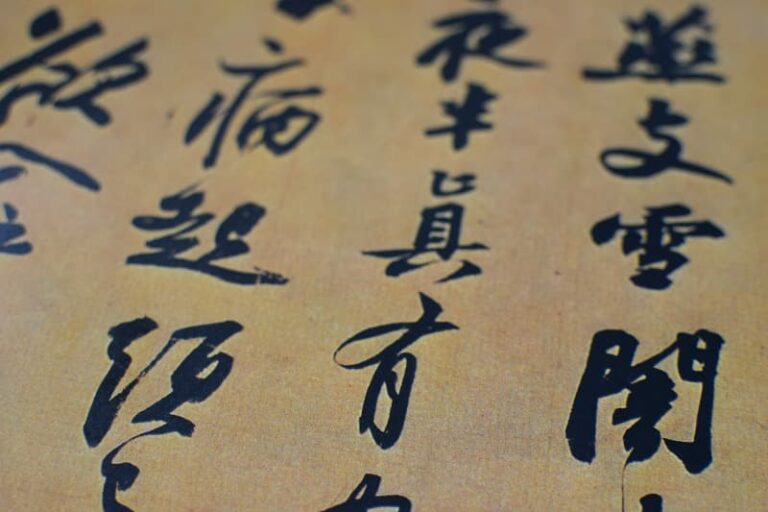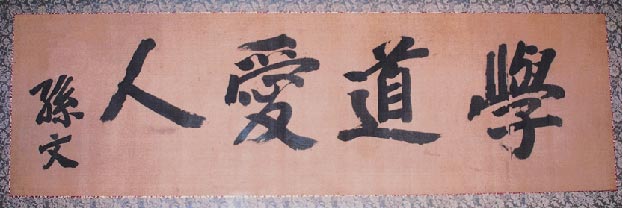ブログ主・・・中国共産党政府は、台湾に与する国々を敵視しているが、このような強硬な手段をとる理由として、国内の「反習近平」の動きに恐れ、また彼の配下も多く「粛清」されている。この動画は1年前のものだが軍幹部・国営企業・司令官・人民銀行の幹部など多くが粛清された。しかも賢い政治家ではないこともデッチアゲがバレてきている。王毅らは表向きには習近平の側近のようだが、外交部も一枚岩ではないようだ。中国の歴史では内部の分裂が少しづつ広がってきたと思った時は既にどうにもならない局面にきていることが多い。
「台湾」独立の声に敏感なのは、台湾どころか国内の分裂も意識せざるを得ない段階にきているからであろう・・・そして習近平の独裁が中国の経済を潰してしまったことも、「ゼロ・コロナ」対策をして都市封鎖など強権的な手法で苦しめたことも、頭のよくない習近平政権の政治がもたらした弊害である。
(バカさでは日本も・・・「一党独裁」の真似事をしていた・・・)
「AI習近平」政策をすすめる方針も、笑い話ではない。これは中国の政治の敗北である。
中国で『AI習近平』誕生。「習近平思想」記した著書十数冊や公式文書で強化 (msn.com)
相次ぐ解任、病死、行方不明 中国習近平氏「ロケット軍」幹部を大粛清【日経プラス9】
ブログ主・・・「台湾有事は日本の有事」と安倍元首相は言ったが、こうして「ひとこと」で唱えるのは多くの間違いを生じさせる。
台湾は「現状維持」であり「独立」ではない、そして選挙もない中国本土も「香港」での中国政府のやりかたに疑問を持っている人も多い。・・・困るのは日本には台湾どころか自国を護る力もシェルターなどの設備もないのに、勇ましい言葉で台湾に期待させる酷い「政治運動」で、台湾はもとより日本にも破滅を招く恐れがいまのところ多いのだ。
私が行った2000年ごろの中国と今の中国を比べれば「締め付け」は驚くほどひどくなっている。
(この頃の私は老親介護でどこにも行けなかったが、東京の妹が一週間だけ来てくれて介護を替わって引き受け、それでやっと行けたのだった。)
今、中国へ行くと一つ間違えれば逮捕監禁投獄といった恐怖がある。それは帰国前に突然、ということが多く、恐ろしい。
 奥山篤信氏のお書きになったエッセイが「月刊日本」に毎月掲載されている。
奥山篤信氏のお書きになったエッセイが「月刊日本」に毎月掲載されている。
最新の6月号は発売したばかりなのだが、奥山篤信氏のご厚意で私のブログに転載をさせていただいた。
記事を写した写真があるが、ブログ内にはうまく入らないので、記事の内容は文章をそのまま転載をします。
ゴジラシリーズの70周年記念作品として、『ALWAYS三丁目の夕日』などで知られる山崎貴が監督・脚本・VFX(視覚効果)を担当した怪獣映画である。全米歴代邦画実写作品の興行収入第1位を記録するなど大ヒットを記録し、第96回アカデミー賞では日本映画として初めて視覚効果賞を受賞した。
VFXは「Visual Effects」の略で、視覚効果という意味。現実には見られない画面効果を実現するための技術を指すこともある。本作のVFXは日本人の器用さや繊細さの賜物といえる見事なものだった。
本作は保守系の評判が良く、友人に勧められたて鑑賞したが、日頃から日本映画の凋落ぶりに呆れ果てている僕はあまり気乗りせず、重い足取りで映画館へ出かけて渋々観始めたのだが、結論から言えば「観に行ってよかった!」と思える作品であった。
自由主義社会は原則的に個人の自由を尊重し、国家もそれを保障する。
だが、有事になれば国家は国民に自己を犠牲にすることを求め、しばしばそれを強制する。
この事情は国家に限らず、あらゆる集団に共通のものだろう。
ある集団が存亡の危機に直面した時、全体として生き残るためには誰かが自己を犠牲にして全体に殉じなければならない。
この時、〈個人と全体のジレンマ〉が生まれ、全体主義のリスクが高まる中で、個々人は決断を迫られる。
そしてある人は命や自由を選んで自分や家族を守ろうとし、ある人は使命感や義務を選んで集団のために自己を犠牲にする。この姿を〈自ら命を捧げた英雄譚〉と見るか、〈死を強制された悲劇〉と見るかも、個々人に委ねられている。
もっとも、〈右〉も〈左〉も「人間は自由意志の主体である」という近代的人間観は一致している。
だが、現実には自己犠牲も含めて人間の行為が自由意志によって自ら選んだものか、それとも外部から強制的に選ばされたものであるかを見極めることは本人でも難しいのである。
しかし、それは自己犠牲を肯定する〈右〉の思想、それを否定する〈左〉の思想を超えた結果を生み出し、物語は意外な結末を迎える。

ブログ主・・・私は奥山篤信氏のエッセイを読んで、大きな感動を隠しきれなかった。
かつては保守は命すらも惜しまず、護国に命を捧げるという話を競うようにしていた。
しかし、私はそのことが「きれいごと」になってその中で「保守はこうしたものだ」という思想的強制が有無を言わさず、
息まいている偽善を感じていた。また左派の人権を言う為に必死なのはわかるが、それ以外に「人権」を振り回したあげく、別の人の立場を糾弾し「人権ゴロ」となることの危うさも感じていた。
そして平和はいつまでも続くものでないことも痛いほど感じるこの頃、この国土が焦土となり、「建物の中に入ってください」とか「シェルターを作るおカネはありません。戦前はみんなが防空壕を掘っていました(今はアスファルトで道は固められ、どこにも掘るのは無理)という居直りは、国民側にとっては「戦え」と要求されながら家族や友人を護るだけの設備もないことを威張って言う神経の異常さにあきれはてた。
・・・そしてそれに音頭をとる人物がいた。「こうして国民皆兵になるようにすればいいですね」って。
そういう暴言もその政治家はわかっていながら?票のためと思ってか、ニッコリした。「私も少し撃てるかな?」って。
国の為に戦え、というのはウクライナを見て、他人事ではない辛さを思う、さらにイスラエルやウクライナ、その他西欧のようにシェルターもない、それもミサイルは何度も繰り返し襲ってくる現実を思うと、できる限り戦争は避けたい、美化して陶酔しないで、と思った。
こんな時、このエッセイを読んで「救国のエッセイ」と思ったのだ。
「こうあらねばならない」というのから精神が解き放たれた、バカな政治家や運動家らには絶対に言えないことだ。
「月刊日本」にも神国日本といわんばかりの論文もある。・・・しかしこういう人の本当の姿を見てきた私は、「また何かいってるのかい」と軽蔑した。ひれ伏さんばかりの天皇崇拝、その他の「臣民」はその他そのもの、保守を偽る売文家であり、
こういうのほど「豹変」する。私はそれを見てきた。
そんな中で奥山氏のエッセイはなんと自由で清々しく、国民として解き放たれた思いがした。
サンサーンスのオペラ「サムソンとデリラ」のサムソンのように不可解な偽善を完全に廃墟とさせて自由を得た、という精神の勝利である。
「戦争」の背景は複雑だが、バカなトップの勝手な都合によって、国民の命を「道具」のように扱われ、その後、尊崇を受けてもそのような名誉は本当に納得するものかどうか・・・それを堂々と論破された文、今、これを書く評論家がいるだろうか。
奥山篤信氏は次のように締めくくってお書きになっている。
ウクライナ戦争やガザ紛争で〈個人と全体のジレンマ〉が再び生身の人間を引き裂いている今、我々はこのジレンマを引き起こす戦争そのものを止揚しなければならない。
ブログのティールーム
本日はウイーンの作曲家ヨハネス・マイヤーが「ハンス・メイ」というペンネームで1933年に発表された曲です。
ドイツの名テノール、フリッツ・ヴンダーリヒが歌います。
May: Ein Lied geht um die Welt
歌詞和訳
歌は世界中を駆け巡る。
好きな曲。
メロディーは星々に届く。
私たち一人一人はそれらを聞くのが大好きです。
歌は愛を歌い、
歌は忠誠を歌い、
そしてそれは決して消えることはなく、
永遠に歌われるでしょう。
時が経っても、
歌は永遠に残る。
ウイーン