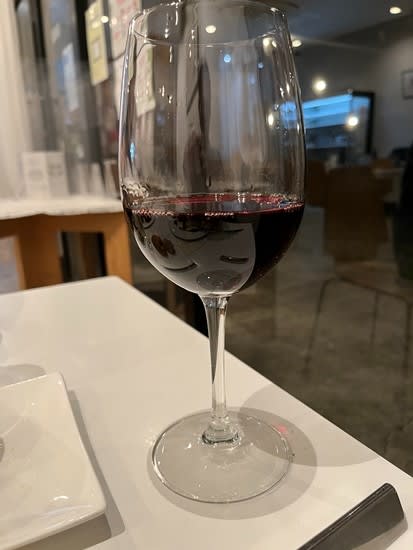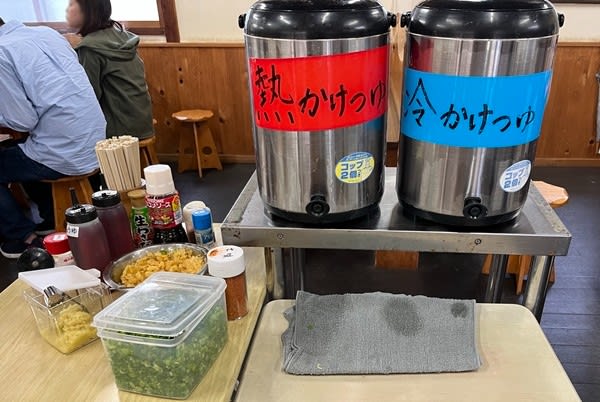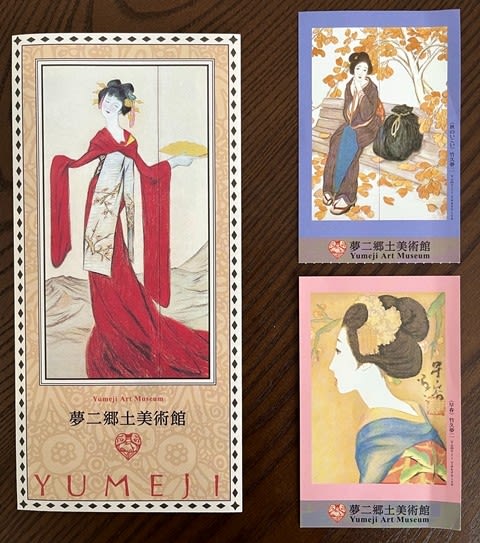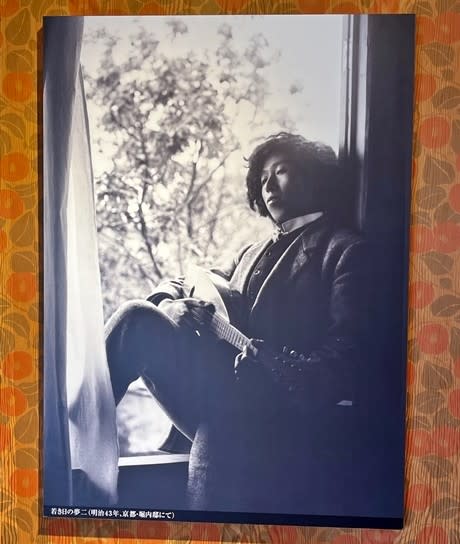休暇村志賀島をチェックアウトし、マリンワールド海の中道へ。
入口で出迎えてくれるイルカは本物そっくり。躍動感あふれるモニュメントです。

私たちが福岡県民になってもうじき15年。近くの志賀島や海の中道海浜公園には、ネモフィラやコスモスの時期に何度も通ったのに、何故かこの水族館に来るのはこれが初めてでした(^^ゞ

椰子の木が並ぶプロムナードの先にあるのは、うみなかラインの渡船場。高速艇マリンライナーが、博多湾の向こう側、ももち浜や福岡タワーがあるシーサイドももち海浜公園からマリンワールドを片道20分で結んでいます。福岡市街と海の中道を船で往来するのも楽しそうですね。

それでは、水族館の中を見ていきましょう。

巣穴の小さなガラス瓶から大きな目を覗かせたスナダコ。ホタテガイの殻が蓋の代わりです。

見た目がシダ科の植物に似ているため「ウミシダ」と呼ばれますが、プランクトンなどを餌にする動物で、ヒトデの仲間です。真ん中にある足を動かして移動することもできるのだとか……。

エラが張ったひょうきんな顔、コチの仲間でしょうか。

頭の上にトサカのような突起があるギンポ。愛嬌のある表情でこちらを見つめていました。

ひらひらと舞うように水中を漂うミズクラゲ。

九州の西岸ではよく見られるアマクサクラゲ。毒性が強く他の種類のクラゲを捕らえて食べるのだそうです。

砂から首を伸ばしたり引っ込めたり、動きが珍妙なチンアナゴ。

サンゴに隠れているのは、色鮮やかなシャコの仲間です。

珊瑚の海。

産卵の機会を除いて、一生を海で過ごすウミガメ。(これはタイマイです)

大型の魚が悠々と泳ぐ外洋水槽。

サメ(シロワニ)の飼育数が多く、ゆっくりと自分に向かって泳いでくるように感じられました。

悠然と目の前を通り過ぎるマンタ。

通常は表層から降りてくることのないイワシの群れ。上層を泳ぐのはシュモクザメです。

しかし、餌やりタイムになると様相が一変。エサを求めてダイナミックに動き回ります。

その様子がこちらです。(音楽が流れます。ボリュームにご注意ください)
ペンギンやアザラシ、アシカを間近に見ることができる「かいじゅうアイランド」。

なかでもペンギンは人懐っこく、ごく近くまで寄ってきてくれます。

優しい表情のスナメリ。ボールで遊ぶ姿が可愛らしかったです。

マリンワールドでは、ラッコも間近で見られます。

エサのイカめがけてジャンプ!

最後に挨拶に来てくれました。

その様子を妻が撮っていました。こんなに近いんですよ~。

博多湾に面したイルカとアシカのショープール。

この日は、イルカ5頭、クジラ1頭(一番右)によるショーでした。

コミュニケーション能力に優れたイルカ。ジャンプのタイミングもぴったりです。

そろって観客に挨拶。

大きな体のクジラの一発勝負。迫力のジャンプを見せてくれました。
下関の海響館以来、久しぶりの水族館でした。様々な海の生物の展示はもちろんですが、イルカやアシカ、ラッコやペンギンなど、飼育員さんとの信頼関係や双方向のコミュニケーションが素晴らしくて魅了されました〜🐬
入口で出迎えてくれるイルカは本物そっくり。躍動感あふれるモニュメントです。

私たちが福岡県民になってもうじき15年。近くの志賀島や海の中道海浜公園には、ネモフィラやコスモスの時期に何度も通ったのに、何故かこの水族館に来るのはこれが初めてでした(^^ゞ

椰子の木が並ぶプロムナードの先にあるのは、うみなかラインの渡船場。高速艇マリンライナーが、博多湾の向こう側、ももち浜や福岡タワーがあるシーサイドももち海浜公園からマリンワールドを片道20分で結んでいます。福岡市街と海の中道を船で往来するのも楽しそうですね。

それでは、水族館の中を見ていきましょう。

巣穴の小さなガラス瓶から大きな目を覗かせたスナダコ。ホタテガイの殻が蓋の代わりです。

見た目がシダ科の植物に似ているため「ウミシダ」と呼ばれますが、プランクトンなどを餌にする動物で、ヒトデの仲間です。真ん中にある足を動かして移動することもできるのだとか……。

エラが張ったひょうきんな顔、コチの仲間でしょうか。

頭の上にトサカのような突起があるギンポ。愛嬌のある表情でこちらを見つめていました。

ひらひらと舞うように水中を漂うミズクラゲ。

九州の西岸ではよく見られるアマクサクラゲ。毒性が強く他の種類のクラゲを捕らえて食べるのだそうです。

砂から首を伸ばしたり引っ込めたり、動きが珍妙なチンアナゴ。

サンゴに隠れているのは、色鮮やかなシャコの仲間です。

珊瑚の海。

産卵の機会を除いて、一生を海で過ごすウミガメ。(これはタイマイです)

大型の魚が悠々と泳ぐ外洋水槽。

サメ(シロワニ)の飼育数が多く、ゆっくりと自分に向かって泳いでくるように感じられました。

悠然と目の前を通り過ぎるマンタ。

通常は表層から降りてくることのないイワシの群れ。上層を泳ぐのはシュモクザメです。

しかし、餌やりタイムになると様相が一変。エサを求めてダイナミックに動き回ります。

その様子がこちらです。(音楽が流れます。ボリュームにご注意ください)
ペンギンやアザラシ、アシカを間近に見ることができる「かいじゅうアイランド」。

なかでもペンギンは人懐っこく、ごく近くまで寄ってきてくれます。

優しい表情のスナメリ。ボールで遊ぶ姿が可愛らしかったです。

マリンワールドでは、ラッコも間近で見られます。

エサのイカめがけてジャンプ!

最後に挨拶に来てくれました。

その様子を妻が撮っていました。こんなに近いんですよ~。

博多湾に面したイルカとアシカのショープール。

この日は、イルカ5頭、クジラ1頭(一番右)によるショーでした。

コミュニケーション能力に優れたイルカ。ジャンプのタイミングもぴったりです。

そろって観客に挨拶。

大きな体のクジラの一発勝負。迫力のジャンプを見せてくれました。
下関の海響館以来、久しぶりの水族館でした。様々な海の生物の展示はもちろんですが、イルカやアシカ、ラッコやペンギンなど、飼育員さんとの信頼関係や双方向のコミュニケーションが素晴らしくて魅了されました〜🐬