散歩の途中でのスナップ。携帯替えてから普段の写真はiPhoneXs。 CanonEOS6D FUJI X70はサブに
散歩の途中で… お腹がすいたよ~♪
杉浦日向子の食・道・楽
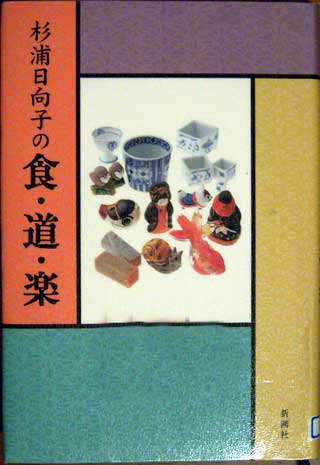
早いもので、あの9・11から5年。
この5年の間に、日本も含めて取り返しのつかない方向に踏み出してしまった、と感じているのは私だけでしょうか?
話は変わりますが、去年の7月に46歳で亡くなった杉浦日向子氏の最近の著作をまとめたものが、一周忌にあたる今年の7月に新潮社から出版されました。
氏は言うまでもなく、江戸文化の研究で名高かく、蕎麦好きのebi1953としては、その道の先達として、書き下ろしのソバ屋ガイド「ソバ屋で憩う」(97年11月初版)を座右の書として全国の蕎麦屋巡りに際し首っ引きで参考としてきました。
カバーや中のページに散りばめられた、愛用の酒器も趣きがあってなかなか綺麗だし、巻中、江戸人は「闘病」という言葉を用いず「平癒」を願っていたことなど紹介されており、氏の日常の考え方が偲ばれる好著です。
初出・発表誌未詳となっているので、氏がいつ何を思って書いたのかは判りませんが、巻末にある 「《最後の晩餐》塩ご飯」 を紹介します。
『なにか一品と問われれば、答えるものは、決まっている。塩ご飯。
冷や飯に塩をパラッと振る。冷や飯とは、その日炊いた飯が、室温に冷めたもので、冷蔵庫に一旦入れた飯では困る。昨今、飲み屋でヒヤというと、ガラスの盃を出され、ふっとイヤな予感がすると同時に、キンキンに冷えたのが来る。本来ヒヤとは室温に定まっている。キンキンのは、はっきり「レイシュ」と呼ぶべきだ。
米、炊き方、塩は、頼む人に任せる。深い木椀、しっかりした木の箸で、もくもくと食べたい。白湯の冷ましがあれば重畳。
家族にも、もし先立ったら、仏壇には塩ご飯と頼んである。酒は好きだが最期に飲みたいと思わない。ほんとうの酒飲みではないのかもしれない。 =後略=』
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
長坂 翁
京都でいただいたお蕎麦の記事をアップしようとして、ふと振り返ると「翁」の記事がないじゃないですか!で、慌てて書いたページがこちら。
前回訪れたのは8月下旬。石和温泉に泊まって翌日の昼食にお邪魔しました。その前が4月中旬。山高・神代櫻の盛りの頃、我ながらあの不便な所にある蕎麦屋に随分足繁く出没したもんだと思います。
(神代櫻については、記念すべきこのブログの第1ページの「神代櫻」からリンクを張ったアルバムをご参照ください。)
お店は静かな林の中。前の庭には普通の家が一軒立つくらいのスペースの贅沢な犬小屋?というより「運動場」と、お客さん用のベンチがあってウェイティングできます。

お蕎麦は「ざる」と「田舎」の二種類。4月に行ったときには「田舎」をいただきました。

挽きぐるみで香りもコシも強い「田舎」。しっかり・どっしりとした食感です。

8月に再訪したときには「ざる」をいただきました。

蕎麦の殻を剥いてから挽いてあるので、淡いうぐいす色です。
「田舎」と比べると香りはやや弱めですが、喉越しのよさではこちら!

いつか機会があれば、は翁の創業者・高橋さんがいる広島まで行ってみたいな
前回訪れたのは8月下旬。石和温泉に泊まって翌日の昼食にお邪魔しました。その前が4月中旬。山高・神代櫻の盛りの頃、我ながらあの不便な所にある蕎麦屋に随分足繁く出没したもんだと思います。
(神代櫻については、記念すべきこのブログの第1ページの「神代櫻」からリンクを張ったアルバムをご参照ください。)
お店は静かな林の中。前の庭には普通の家が一軒立つくらいのスペースの贅沢な犬小屋?というより「運動場」と、お客さん用のベンチがあってウェイティングできます。

お蕎麦は「ざる」と「田舎」の二種類。4月に行ったときには「田舎」をいただきました。

挽きぐるみで香りもコシも強い「田舎」。しっかり・どっしりとした食感です。

8月に再訪したときには「ざる」をいただきました。

蕎麦の殻を剥いてから挽いてあるので、淡いうぐいす色です。
「田舎」と比べると香りはやや弱めですが、喉越しのよさではこちら!

いつか機会があれば、は翁の創業者・高橋さんがいる広島まで行ってみたいな
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )





