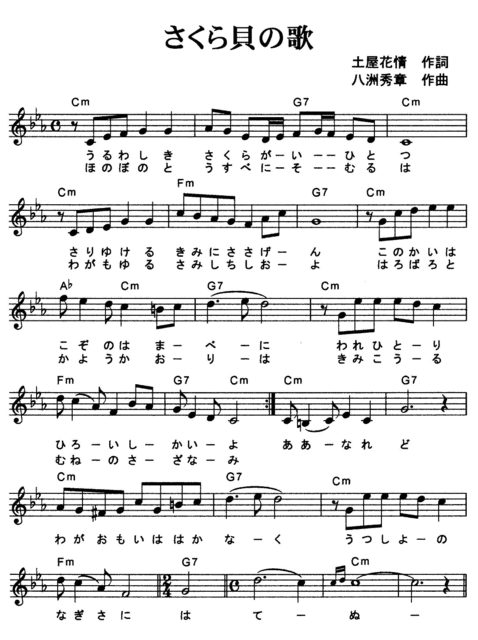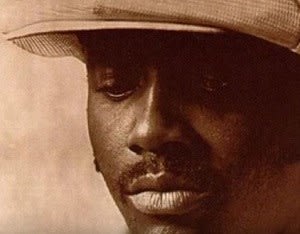![]()
宣公13年~襄公20年 鞌(あん)の戦い / 晋の復覇刻の時代

※ 夫の安否は問わず:
まんまと謀られたと知った韓厥は、逢丑父を郤克のもとに引っ立てていった。
郤克は、すぐさま逢丑父の処刑を兪じた。すると逢丑父が大声で、「わが身
を捨てて主君の命を救ったこのわたしを殺すというのか。さようなことをすれ
ば、今後、主君のために尽くす人物がいなくなるぞ」
鄙克は、はっと気づいた。
「死を賭して主君を逃れさせた忠義者を殺したりしては、わたしの身に天罰が
くだろう。赦して忠臣の手本といたそう」
と言って処刑をとりやめさせた。
一方、逃れた斉侯は、なんとか逢丑父を救出しようと、三たび晋の陣内に押し
寄せた。出陣のたびに、尻込みする兵士を叱陀して先頭に立ち、ついに狄の陣
へ突入した(秋は晋とともに出陣していた)。
ところが、斉を恐れている狄の兵士たちは、斉侯をとらえる気がまるでない。
晋の手前、戈をふりあげていちおう打ちかかるが、片手の楯で斉侯の身体をま
もり、衛の陣へ押しやった。衛の軍もわざとこれをとり逃した。こうして斉侯
は、徐関から都へもどった。
斉侯は、城邑の守備兵たちに言った。
「わが軍は敗れた。しっかり守ってくれ」
都に入り、道で一人の婦人に出会った。その婦人が、斉侯とは知らずにたずね
た。
「主君はご無事でしょうか」
「無事だ」
「では、鋭司徒は」
「無事だ」
「主君と父が無事とうかがえば、それ以上の望みはもちますまい」
と言って走り去った。
斉侯は、まず主君の安否を問い、つぎに父の安否を問いて、夫のことはたずね
なかったことに感じ入り、あとでその婦人の身もとを調べさせた。それは鋭司
徒の妻であった。石窌の地をあたえて、その心根をほめた。
【ZW倶楽部とRE100倶楽部の提携 Ⅵ】
● IoT 機器の電池寿命を延ばす超小型の充電 IC
8月10日、トレックス・セミコンダクター社は、20~100mAh クラスの小容量リチウム電池で駆動す
る小型IoT機器やウェアラブル端末などに向けて、❶ 待機時の電池消耗を従来比2分の1以下に抑え
ることのできるリニア充電IC「XC6808」を発売。リチウム電池から充電ICへのシンク電流(バッテリ
ー消費電流)を従来比30分の1以下に抑える。充電ICは、充電を行わない待機時でも入力と出力の
電圧比較コンパレーターを動作させる必要があり、蓄電池から微量の電力供給し電力を消費する。こ
の待機時に消費するシンク電流(吸い込み電流)は、スマートフォンなどモバイル機器に搭載される
充電ICであれば、2~3μA程度(詳細仕様は下写真ダブクリ参照)。


尚、このXC6808は、昨今のリチウム電池の充電完了電圧の高電圧化に対応。充電完了電圧として、
従来の4.20Vだけでなく、4.35V、4.40Vにも対応し、幅広いリチウム電池用充電ICとして使用できる。
さらにXC6808は、2.0×1.8×0.33mmサイズの超低背モールドパッケージ「USP-6B07」を採用。「パッケ
ージの高さを0.4mm以下に抑える必要のあるスマートカードにも実装可能。補聴器や完全ワイヤレス
型イヤフォンなど小型パッケージが要求される用途などにも適した充電IC」となっている。また、サ
ンプル価格が100円(税別)である。
この事例のように、蓄電池を構成するデジタルデバイスは、省エネ、ダウンサイジングを実現すると
同時に充電時間を短縮、電池寿命を延ばすことができるなどのメリットをもたらす。下記に特許事例
を参考掲載する。
❏ 特開2010-081790 電子機器 パナソニック株式会社
携帯電話やポータブル型のCDプレイヤー、デジタルスチルカメラ(DSC)等のポータブル型など
の電子機器の電源にはリチウムイオン(Li-ion)やニッケル水素(Ni-H)等の充電式バッテリー(充
電池)が使用されている。従来、この種の電子機器には、その機器本体のシステム制御を行うメイン
マイクロコンピューター(=メインマイコン)が、機器本体を介して、充電式バッテリー(=バッテ
リー)にACアダプターからの電力を充電する制御を行っているが、❶この種の電子機器は、その機
器本体を起動する必要がない充電時であっても、メインマイコンの起動に伴い機器本体が起動して
しまいACアダプターからの電力の一部を機器本体で消費することになり充電効率がい。❷また、電
子機器の機器本体の起動で発生する熱でバッテリーを加熱することとなり、バッテリーの温度上昇し
充電中のバッテリー温度上昇が許容温度以上になり、充電電流を抑える必要が生じ、充電時間が長く
なる。
バッテリーの充電時に、本体機器を制御する制御手段のON動作に伴う機器本体の起動により、充電
動作に寄与しない消費電力が増加し、またバッテリーも加熱されるため、十分な充電電流が流せない
ため、下図のように、自装置としての機器本体10の制御を行う主制御装置としてのメインマイコン
5と、バッテリー6の充電を行う充電IC2と、充電マイコン3とを備え、充電マイコン3は、メイ
ンマイコン5が動作しているか否かを監視し、ACアダプター1が機器本体10に接続されている場
合において、メインマイコン5が動作しているとき、充電IC2による充電動作を禁止する一方、メ
インマイコン5が動作していないとき、充電IC2による充電動作を許可する機構で、主制御手段と
は別に充電制御に特化した消費電力の小さい充電制御手段を設け、主制御手段が動作していないとき、
充電手段による充電動作を許可することで、充電動作に寄与しない消費電力の低減を実現できるよう
にする。

【符号の説明】
1 ACアダプター 2 充電IC(充電手段) 2a メモリー 3 充電マイコン(充電制御手段)
4 電源管理IC 5 メインマイコン(主制御手段)6 バッテリー(充電池)6a メモリー 6b
温度センサー 10 機器本体
【特許請求範囲】
- 電力の供給を受けるために外部と電気接続可能な接続手段と、充電池を装着可能な装着手段と、
前記接続手段を介して供給された電力を用いて、前記装着手段に装着された充電池を充電する
充電手段と、自装置を制御する主制御手段と、前記主制御手段が動作しているか否かを監視し、
前記接続手段が外部に接続されている場合において、前記主制御手段が動作しているとき、前
記充電手段による充電動作を禁止する一方、前記主制御手段が動作していないとき、前記充電
手段による充電動作を許可する、充電制御手段と、を備える、 - 前記充電制御手段は、さらに前記接続手段が外部に接続されたか否かを監視し、前記接続手段
が外部に接続され、前記主制御手段が動作していないことを認識した場合に、前記充電手段に
よる充電動作を開始させる、請求項1に記載の電子機器 - 前記装着手段には、定格容量の異なる複数種類の充電池が装着可能とされ、前記装着手段に装
着された充電池の種類を検出する種類検出手段をさらに備え、前記充電手段は、前記種類検出
手段により検出された種類の充電池の定格容量に対応する電力を前記充電池に充電する、請求
項1または2に記載の電子機器 - 充電中に定期的に所定の処理を行わせるために前記主制御手段の起動が必要になった場合に、
前記充電制御手段が、この充電制御手段に設けたタイマーにより所定時間が経過したことを検
知した際に、前記充電手段への通電をOFFさせるとともに、前記主制御手段への通電をON
させて、自装置の制御を開始させて、前記所定の処理を行わせ、この後、前記充電手段への通
電をONさせるとともに、前記主制御手段への通電をOFFさせる、請求項1~3の何れか1
項に記載の電子機器。 - 充電池に当該充電池の容量を記憶する領域を有するメモリーが設けられ、充電中に、前記充電
制御手段が、この充電制御手段に設けたタイマーにより所定時間が経過したことを検知した際
に、前記充電手段への通電をOFFさせるとともに、前記主制御手段への通電をONさせて、
前記充電池の前記メモリーへの容量の書込み処理を行わせ、この後、前記充電手段への通電を
ONさせるとともに、前記主制御手段への通電をOFFさせる、請求項4に記載の電子機器。 - 前記主制御手段は、前記充電池の温度情報に基づいて、前記充電池の充電量を補正し、補正し
た値に対応する容量の充電池の前記メモリーへの書込み処理を行わせる、請求項5に記載の電
子機器。 - 電子機器がビデオカメラであることを特徴とする請求項1~6の何れか1項に記載の電子機器。

読書録:村上春樹著『騎士団長殺し 第Ⅱ部 遷ろうメタファー編』
第45章 何かが起ころうとしている
「いつものように拡が朝食を用意しました。今朝あの子はほとんど口をききませんでした。でも
それはいつものことです。時としていったんしゃべり出すととまらなくなることがありますが、
普 段は返事だってろくにしません」
秋川笙子の話を間いているうちに、拡もだんだん不安になってきた。時刻は十一時に近づいて
いるし、もちろんあたりは真っ暗になっている。月も雲に隠れている。秋川まりえの身にいった
い何か起こったのだろう?
「あと一時間待って、もしまりえと連絡がつかなかったら、警察に相談してみようかと思いま
す」と秋川笙子は言った。
「その方がいいかもしれませんね」と拡は言った。「もしぼくに何かできることがあったら、遠
慮なく言ってください。遅くなってもかまいませんから」
秋川笙子は礼を言って電話を切った。拡は残っていたウィスキーを飲み干し、グラスを台所で
洗った。
そのあと私はスタジオに入った。明かりをすべて点し、部屋をすっかり明るくして、イーゼル
に載せられた描きかけの『秋川まりえの肖像』をあらためて眺めた。絵はあと少し手を加えれば
完成するところまできていた。そこには十三歳の無口な少女の、あるべきひとつの姿が立ち上げ
られていた。ただ彼女の姿かたちばかりではなく、彼女の存在が孕んでいる、目には映らないい
くつかの要素がそこに含まれているはずだった。視覚の枠外に隠されているそのような情報をで
きるだけ明らかにすること、それらが発するメッセージを別の形象に置き換えていくこと、それ
が私が自分の作品にもちろん営業用の肖像画は別にして――求めることだった。そういう意味で
は、秋川まりえは私にとってずいぶん興味深いモデルだった。彼女の姿かたちには、多くの示唆
がまるで朧し絵のように潜んでいたからだ。そして今朝から彼女の行方がわからなくなっている。
まるでまりえ白身がその服し絵の中に引き込まれてしまったみたいに。
それから私は床に置いた『雑木林の中の穴』を眺めた。その日の午後に描き上げたばかりの油
絵だ。その穴の絵は『秋川まりえの肖像』とはまた違った意味合いで、別の方向から、私に何か
を訴えかけているようだった。
何かが起ころうとしているのだ、とその絵を見ながら私はあらためて感じた。今日の午後まで
はあくまで予感でしかなかったものが、今では現実を実際に侵食し始めている。それはもう予感
でもない。すでに何かが起き始めているのだ。秋川まりえの失踪はその『雑木林の中の穴』と何
か繋がりを持っているに違いない。私はそう感じた。私が今日の午後にその『雑木林の中の穴』
の絵を完成させたことによって何かが起勤し、動き出したのだ。そしておそらくその結果、秋川
まりえはどこかに姿を消してしまった。
でもそれを秋川笙子に説明するわけにはいかない。そんなことを言われても、彼女はわけがわ
からなくて余計に混乱するだけだろう。
私はスタジオを出て、台所に行って水をグラスに何杯か飲み、口の中に残っていたウィスキー
の匂いを洗い流した。それから受話器を取り上げて、免色の家に電話をかけた。三度目のコール
の途中で彼が電話口に出た。その声からは、誰かからの重要な連絡を待っていたときのような、
いくぶんこわばった響きが微かに聴き取れた。電話をかけてきたのが私であったことに彼は少し
驚いたようだった。しかしそのこわばりは瞬時にほどけ、普段の冷静で穏やかな声に戻った。
「こんな夜分に電話をして申し訳ありません」と私は言った。
「かまいませんよ、ぜんぜん。私は遅くまで起きていますし、どうせ暇な身です。あなたとお話
ができるのはなによりです」
挨拶は抜きにして、秋川まりえの行方がわからなくなっていることを、私は手短に説明した。
その少女は学校に行くと言って朝に家を出たきり、まだ帰宅していない。絵画教室にも姿を見せ
なかった。免色はそのことを知らされて驚いたようだった。少しのあいだ言葉を失っていた。
「そのことで、あなたには心当たりみたいなものはないんですね?」、免色はまず私にそう尋ね
た。
「まったくありません」と私は答えた。「寝耳に水です。免色さんの方には?」
「もちろん思い当たることは何もありません。彼女は私とはほとんど口をきいてくれませんか
ら」
彼の声にはとくに感情は混じっていなかった。ただ単純に事実を述べているだけだ。
「もともとが無口な子なんです。誰ともろくに口をききません」と私は言った。「しかしとにか
く、まりえさんがこの時刻になってもまだ帰宅しないことで、秋川笙子さんはずいぶん混乱して
いるみたいです。父親はまだ帰ってこないみたいだし、∵Λきりでどうしていいかわからない様
子です」
免色はまたひとしきり、電話口で黙り込んだ。校がそのように何度も言葉を失うのは、私の知
る限りきわめて珍しいことだった。
「それについて、何か私にできることはありますか?」、彼はようやく目を開いた。
「急なお願いですが、これからこちらに来ていただくことは可能ですか?」
「あなたのお宅にですか?」
「そうです。そのことに関連して、少しご相談したいことかあるんです」
て私にそう尋ね
免色は一瞬間を置いた。それから言った。「わかりました。すぐにうかがいましょう」
「何かそちらでご用事があるわけではないんですね?」
「用事というほど大したものじやありません。なんとでもなることです」と免色は言った。そし
て小さく咳払いをした。時計に目をやるような気配があった。「今から十五分ほどでそちらにう
かがえると思います」
受話器を置いてから、私は外に出る支度をした。セーターを着て、革ジャンパーを用意し、大
型の懐中電灯をそばに置いた。そしてソファに座って、免色のジャガーがやってくるのを待った。
 Berliner Mauer
Berliner Mauer
第46章 高い強固な壁は人を無力にします
免色がやってきたのは11時20分だった。ジャガーのエンジンの音が聞こえると、私は革ジ
ャンパーを着て家の外に出て、免色がエンジンを切って車から降りてくるのを待った。免色は紺
色の厚手のウィンドブレーカーに、黒い細身のジーンズという格好だった。首に薄手のマフラー
を巻いて、靴は革製のスニーカーだった。豊かな白髪が夜目にも鮮やかだった。
「これからあの林の中の穴の様子を見に行きたいのですが、かまいませんか?」
「もちろんかまいません」と免色は言った。「でもあの穴が、秋川まりえの失踪となにか関係し
ているのですか?」
「それはまだわかりません。ただ少し前から、不吉な予感がしてならないんです。あの穴に開運
して何かが持ち上がっているのではないかという予感が」
免色はそれ以上何も尋ねなかった。「わかりました。一緒に様子を見に行きましょう」
彼はジャガーのトランクを開け、中からランタンのようなものを取り出した。そしてトランク
を閉め、私と一緒に雑木林に向かった。月も星も出ていない時い夜だった。風もない。
「こんな夜中にお呼び九てをして、申し訳ありませんでした」と私は言った。「でもあの穴の様
子を見に行くのに、あなたに一緒に来ていただいた方がいいような気がしたんです。もし何かあ
ったとき、一人ではうまく処理しきれないような気がしたものですから」
彼は手を仲ばし、ジャンパーの上から私の腕をとんとんと軽く叩いた。励ますように。「そん
なことはぜんぜんかまいません。気にしないでください。私にできることならなんでもします」
我々は木の根に足をひっかけたりしないように、懐中電灯とランタンで足もとの地面を照らし
ながら、慎重に歩を連んだ。我々の靴底が積もった落ち葉を踏む音だけが耳に届いた。夜の雑木
林には、それ以外どんな音もしなかった。まわりにいろんな生き物が身を隠し、息をひそめて
我々をじっと見守っているような重苦しい気配があった。真夜中の深い関がそのような錯覚を生
み出すのだ。事情を知らない誰かがこんな我々の姿を目にしたら、これから墓荒らしに出かける
二人組だと思うかもしれない。
「ひとつだけ、あなたにうかがいたいことがあるのですが」と免色は言った。
「どんなことでしょう?」
「秋川まりえがいなくなったことと、あの穴とのあいだに何か関連性があると、どうしてあなた
は思うのですか?」
私は少し前に彼女と一緒にその穴を見に行ったことを話した。彼女は教えられる前から、既に
この穴の存在を知っていた。この一帯は彼女の遊び場なのだ。このあたりで起こった出来事で彼
女の知らないことはない。そこで彼女が口にしたことを、私は免色に教えた。その場所はそのま
まにしておくべきだった、その穴を開いたりするべきではなかった、とまりえは言ったのだ。
「彼女はあの穴を前にして何か特別なものを感じているみたいでした」と私は言った。「どう言
えばいいのだろ・・・・・・たぶんスピリチュアルなものを」
「そして関心を特っていた?」と免色は言った。
「そのとおりです。彼女はあの穴に警戒心を抱いていたのと同時に、その姿かたちにとても心を
惹かれているようでした。だからあの穴に関連して彼女の身に何かが起こったのではないかと、
ぼくとしては心配でならないんです。ひょっとして穴の中から出られなくなっているかもしれな
いと」
免色はそれについて少し考えていた。それから言った。「あなたはそのことを彼女の叔母さん
に言いましたか? つまり秋川笙子さんに?」
「いいえ、まだ何も言っていません。そんなことを言い出したら、そもそも穴の説明から始めな
くてはなりません。どういう経緯であの穴を関くことになったのか、なぜそこに免色さんが関わ
ってくるのか。とても長い話になるし、ぼくの感じているものはうまく伝わらないかもしれませ
ん」
「それに余計な心配をさせるだけだ」
「とくに警察が絡んでくれば、話は更に面倒になります。もし彼らがあの穴に関心を抱いたりし
たら」
免色は私の願を見た。「警察が既に絡んでいるのですか?」
「ぼくが彼女と話をした時点では、まだ警察に連絡はしていませんでした。しかしたぶん今頃は
もう捜素願が出されているはずです。なにしろもうこんな時刻になっていますから」
免色は何度か肯いた。「まあ、それは当然のことでしょうね。十三歳の女の子が真夜中近くに
なっても家に戻ってこない。どこに行ったかもわからない。家の人としては警察に連絡しないわ
けにはいかない」
しかし警察が関与してくることを、免色はどうやらあまり歓迎してないようだった。彼の声の
響きにはそういう雰囲気が聞き取れた。
「この穴のことは、できるだけあなたと私だけのことにしておきましょう。あまりよそには広め
ない方がよさそうだ。たぶん話が面倒になるだけです」と免色は言った。私もそれに同意した。
そして何よりも騎士団長の問題かおる。そこから出てきた騎士団長としてのイデアの存在を明
かすことなく、その穴の特殊性を人に説明するのはほとんど不可能に近い。そんなことをしても、
免色が言うようにたぶん話がより面倒になるだけだ(それにもし騎士団長の存在を明かしたとし
ても、誰がそんなことを信じてくれるだろう? 私の正気が疑われるだけだ)。
我々は小さな祠の前に出て、その裏手にまわった。ショベルカーのキャタピラに無残に踏みつ
よされ、いまだに倒れ伏したような格好のままのススキの茂みを踏み越えていくと、そこにいつ
もの穴があった。我々はまず明かりをかざしてその蓋を照らした。蓋の上には重しの石が並べら
れていた。私はその配置を目で調べた。ほんの少しではあるが、石が勤かされたような形跡があ
った。このあいだ私とまりえがその蓋を開けて閉めたあと、誰かがその石をどかして蓋を開け、
それからまた蓋を閉めて、石をできるだけ前と同じように並べ直したようだった。そのちょっと
した違いを私は見て取ることができた。
「誰かが石をどかせて、この蓋を開けた形跡があります」と私は言った。
免色は私の顔をちらりと見た。
「それは秋川まりえでしょうか?」
私は言った。「さあ、どうでしょう。でも知らない人はまずここにやってこないし、我々以外
にこの穴の存在を知っている人間といえば、彼女くらいのものです。その可能性は大きいかもし
れない」 もちろん騎士団長はこの穴の存在を知っている。なにしろ彼はそこから出てきたのだ
から。しかし彼はあくまでイデアだ。そもそも形のない存在だ。中に入るのにわざわざ重しの石
をどかせたりはしないだろう。
それから我々は蓋の上の石をどかせ、穴の士に被せていた厚板をすべてはがした。そして直径
ニメートル近くの円形の穴が、再びそこに出現した。それは前に見たときよりもより大きく、よ
り黒々として見えた。でもそれもやはり夜の開がもたらす錯覚だろう。
私と免色は地面にかがみ込むようにして、懐中電灯とランタンで穴の中を照らしてみた。しか
し穴の中には人の姿はなかった。何の姿もなかった。いつもと同じ高い石壁にまわりを囲まれた、
無人の筒型の空間があるだけだった。しかし一つだけ前とは違っていることがあった。梯子が姿
を消していたのだ。石塚をどかせた造園業者が厚意で置いていってくれた折りたたみ式の金属製
の梯子だ。最後に見たとき、それは壁に立てかけてあった。
「梯子はとこにいったんだろう?」と私は言った。
梯子はすぐに見つかった。それは奥の方の、キャタピラに踏みつよされなかったススキの茂み
の中に横だわっていた。誰かが梯子を外して、そこに放り出したのだ。重いものではないから、
持ち運びにそれはどの力は要しない。私たちはその梯子を運んで、元のように壁に立てかけた。
「私か下に降りてみましょう」と免色が言った。「何かが見つかるかもしれません」
「大丈夫ですか?」
「ええ、私なら心配ありません。前にも一度降りたことはありますから」
そう言うと、免色はランタンを片手に何でもなさそうにその梯子を降りていった。
「ところでベルリンの東西を隔てていた壁の高さをご存じですか?」と免色は梯子を降りながら
私に尋ねた。
「知りません」
「三メートルルです」と免色は私を見上げて言った。「場所にもよりますが、だいたいそれが基
準の高さでした。この穴の高さより少し高いくらいです。それがおおよそ百五十キロにわたって
続いていました。私も実物を見たことかあります。ベルリンが東西に分断されている時代に。あ
れは痛々しい光景だった」
免色は底に降り立ち、ランタンであたりを照らした。そしてなおも地上にいる私に向けて語り
続けた。
「壁はもともとは人を護るために作られたものです。外敵や雨風から人を護るために。しかしそ
れはときとして、人を封じ込めるためにも使われます。そびえ立つ強固な壁は、閉じ込められた
人を無力にします。視覚的に、精神的に。それを目的として作られる壁もあります」
免色はそう言うと、そのまましばらく口を閉ざした。そしてランタンをかざしてまわりの石壁
と、地面を隅々まで点検した。まるでピラミッドのいちばん臭にある石室を調査する考古学者の
ように、怠りなく丹念に。ランタンの明かりは強力で、懐中電灯よりずっと広い範囲を照らし出
した。それから検は地面の上に何かをみつけたらしく、膝をつくようにして、そこにあるものを
子細に観察していた。しかしそれが何なのか、上からはわからなかった。免色も何も言わなかっ
た。彼がみつけたのはどうやら、とても小さなものであるらしかった。検は立ち上がり、その何
かをハンカチにくるんでウィンドブレーカーのポケットに入れた。そしてランタンを頭上に掲げ、
地上にいる私を見上げた。
「今から上がります」と検は言った。
「何かみつかりましたか?」と私は尋ねた。
免色はそれには答えなかった。そして梯子を注意深く登り始めた。一歩上がるごとに身体の重
みで梯子は鈍く軋んだ。私は検が地上に戻ってくるのを、懐中電灯で照らしながら見守っていた。
身の動かし方を見ていると、検が日頃から身体中の筋肉を機能的に鍛え、整えていることがよく
わかった。身体に無駄な動きがない。必要な筋肉だけが有効に使用されている。検は地面の上に
立つと、一度大きく身体を仲ばし、それからズボンについた上を丁寧に払った。それほど多くの
上がついていたわけではなかったのだけれど。
 Israeli West Bank barrier
Israeli West Bank barrier
一息ついてから免色は言った。「実際に下に降りてみると、壁の高さにはずいぶん威圧縮かあ
ります。そこにはある種の無力感が生まれます。私は同じような種類の壁をしばらく前にパレス
チナで目にしました。イスラエルがこしらえた八メートル以上あるコンクリートの壁です。てっ
ぺんには高圧電流を通した鉄線がめぐらせてあります。それが五百キロ近く続いています。イス
ラエルの人々は三メートルではとても高さが足りないと考えたのでしょうが、だいたい三メート
ルあれば壁としての用は足ります」
彼はランタンを地面に置いた。それは私たちの足もとを明るく照らし出した。
「そういえば、東京拘置所の独房の壁の高さも三メートル近くありました」と免色は言った。
「なぜかはわかりませんが、部屋の壁がとても高いのです。来る日も来る目も目にするものとい
えば、その高さ三メートルののっぺりした壁だけです。ほかには何も見るべきものがありません。
もちろん壁には絵とかそういうものは飾られていません。ただの壁です。まるで自分か穴の底に
置かれているような気がしてきます」
私は黙ってそれを聞いていた。
「少し前のことになりますが、私はわけあって一度、東京拘置所にしばらく勾留されていたこと
があります。それについては、たしかまだあなたにお話ししていませんでしたね?」
「ええ、まだうかがっていません」と私は言った。彼が拘置所に入っていたらしいことは人妻の
ガールフレンドから聞いていたが、もちろんそれは言わなかった。
「私としては、その話をあなたによそから耳に入れてもらいたくなかったのです。ご存じのよう
に噂話というのは、おもしろおかしく事実をねじ曲げてしまうものですから。ですから私の口か
ら直接事実をお伝えしておきたいのです。とくに愉快な話でもありませんが、ことのついでとい
うか、今ここでお話ししてもかまいませんか?」
「もちろんかまいません。どうぞ話してください」と私は言った。
免色は少し間を置いてから話を始めた。「言い訳するのではありませんが、私には何ひとつや
ましいところはありませんでした。私はこれまでいろんな事業に手を染めてきました。多くのリ
スクを背負って生きてきたと言っていいと思います。しかし私は決して愚かではありませんし、
生来用心深い性格ですから、法律に抵触するようなことにはまず手を出しません。そういう線引
きには常に留意しています。しかしそのとき私がたまたま手を組んだ相手が、不注意で無考えだ
ったのです。おかげでひどい目にあわされました。それ以来、誰かと手を組んで仕事をするよう
なことは一切避けています。自分ひとりの責任で生きるようにしています」
「検察が持ち出した罪状は何だったのですか?」
「インサイダー取り引きと脱税です。いわゆる経済犯です。最終的に無罪は勝ちとりましたが、
起訴にはもち込まれました。検察の取り調べが厳しく、かなり長いあいだ拘置所に入れられてい
ました。いろんな理由をつけて、勾留期限が次々に延長されました。壁に囲まれた場所に入ると、
今でも懐かしささえ感じてしまうくらい長い期間です。さっきも申し上げたように、私の側には
法で罰せられるような落ち度は何ひとつなかったのです。それはあくまで明白な事実でした。し
かし検察は起訴のシナリオを既に書いてしまっていて、そのシナリオには私の有罪もしっかり組
み込まれていました。そして彼らは今更そのシナリオを書き直したくなかった。官僚システムと
いうのはそういうものです。いったん何かを決めてしまうと、変更することがほとんど不可能に
なります。流れを逆行させると、どこかの誰かがその責任をとらなくてはなりません。そんなわ
けで払は長期にわたって東京拘置所の独房に収容されることになったのです」
この項つづく
 ● 今夜の一曲
● 今夜の一曲
「悲しい自由」(かなしいじゆう)は、1989年7月26日にリリースされたテレサ・テンのシングル。
発売元はトーラスレコード(のちに解散。現在はユニバーサルミュージックから発売)。
ひとりにさせて 悲しい自由が
愛の暮しを 想いださせるから
ひとりにさせて 疲れた心が
いつか元気を とりもどすまで
あなたを近くで愛するよりも
心の宝物にしていたいから
So-long このまま ちがう人生を
So-long あなたの 背中見送るわ
ひとりにさせて 淋しい約束
何も言わずに 時のせいにするわ
ひとりにさせて 優しくされたら
きっと昨日に 帰りたくなる
あなたのすべてを 愛するよりも
綺麗なお別れ 選びたいから
So-long 涙を いつか微笑に
So-long 想い出だけを置きざりに
So-long このまま ちがう人生を
So-long あなたの 背中見送るわ
スピーカー大音量に迷ひぴと八十二歳をさがすゆふぐれ
真夜中に点けしラジオにテレサ・テンの繊く優しき歌ごゑひびく
もはや世にあらぬ歌ごゑテレサ・テンの人を慰撫してやまぬ歌ごゑ
歌ごゑに時をり交じる拍手よし鄧麗君の母語ライプ版
正調の北京語にテレサ・テンうたふ「夜来香」の”香”に聞き惚る
丹波真人 / 𩛰(たべ)る禽(とり)
● 晴れ時々右脳
本当に歌が書けなくなるんだ。目一杯左脳を使いパンパンの日々をつづけていると、あれほど短歌を
書き綴った日々が嘘のようで何も浮かばない。ということで「角川 短歌」7月号を購読し時折眼を
通していて、今夜は鄧麗君を読める「丹波真人/𩛰る禽」がめにとまる。中国から帰国する1982年の
個人的に開催してくれた送別会(通訳をつとめてくれた青年一名、女性二名)を思いだし、その後、
「天安門事件」につながっていったことを思いだし(このエピソードはブログ掲載)、鄧麗君の「悲
しい自由」をユーチューブし思い出を再確認する。その話はさておき、右脳を使わなくてはと考え、
前はテーマが浮かばないときは「花言葉」をつづることで連想空間を広めるという手法をとっていた
ので、今回も、関心のある「植物図鑑」を整理し、それをプロモータに「短歌の宅トレ」を再開させ
ようと考える。が、本家の「宅トレ」は日曜の奉仕作業の疲れで腰痛が再発し中止中とうまくいかな
いものだ。