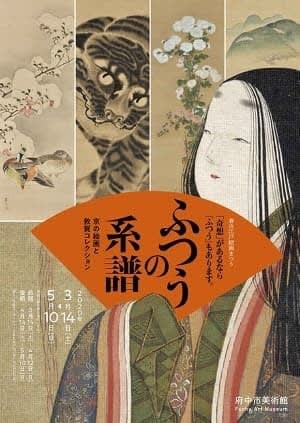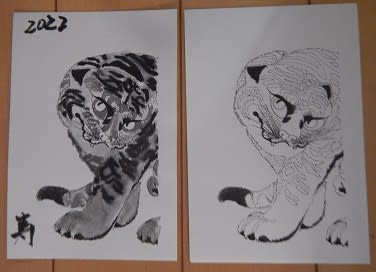20220503
ぽかぽか春庭アート散歩>2022アート散歩春(2)奇想のモード展 in 庭園美術館
春休み自宅待機中に、花見を兼ねて庭園美術館でひとり散歩。娘は現代美術が苦手で、シャガール以外のシュルレアリスト作品は好まない。
「奇想のモード・装うことの狂気またはシュルレアリズム」と題された展覧会。シュルレアリストたちがモードの世界に参画したさまざまな衣装や装身具、靴や帽子が展示されていました。
古今東西、人々が「美しい」と感じて愛でたものが、現代の目から見るとなんでこれを「すばらしい美」と思った?と思わずにいられない「美」の展示もありました。
エントランスから中へ。旧館の歴史的な作品は撮影禁止ですので、1階展示については、すべて借り物画像です。今回、新館の作品は撮影自由。
「Chapter1プロローグ」大ホールにある、シュルレアリスト、サルバトール・ダリのブロンズ彫刻。「炎の女」1930
後ろにある白い像は「引き出しのあるミロのビーナス」1936-1964
バレエ・リュスに衣裳・舞台装置などでシュルリアリストたちが参画していることは知っていましたが、さまざまなファッション分野に参加していたこと、知りませんでした。絵画や彫刻だけでなく、ヴォーグの表紙を作成しているほか、多様な分野で思い思いの形と色を追求していました。
プロローグChapter1の「有機物への偏愛」。
昆虫の羽を使ったブローチや黒い猿の毛を使ったジャケットなどが玄関わきの小部屋にありました。ホールには玉虫の羽を使ったヤン・ファーブルの襟飾り(甲冑カラー)。「昆虫記」のアンリ・ファーブルのひ孫だそうです。さすがの昆虫使い作品。玉虫の羽が見る角度によって、真っ黒に見えたり「玉虫色」に輝いたりする襟飾り、きれいでしたけれど、着こなすには思い切りが必要かも。
甲冑カラー
Chapter2<歴史にみる奇想のモード>
中国唐時代末から清朝時代が終わってもなおしばらくは続いた中国千年伝統であった「女性美」がありました。「纏足」です。
貴族社会上流社会の女性は、子供のころから足指を折り曲げてをきつく縛り、足が成長できないようにしました。足が小さければ小さいほど「美しい」とされ、纏足をしていない女性は、上流社会では結婚の対象にもされなかったそうです。上流男性はどんな美形の女性よりも、できる限り小さい足の持ち主を「美しい女性」と感じたのです。
足の奇形のために女性はよろよろよちよちとしか歩けず、その「だれかを頼らずには生きていけない風情」がなにより美しいとされたのです。
展示されていた女性の靴はサイズ10センチ。一般的な女性より小さい足の私でさえ22.5センチですから、通常の育ち方をしたのでは、10センチは保てない。
この習俗を現代の眼から見て、「奇習」と言えるでしょうか。
20世紀になるまで、西洋社会では女性の腰は細いほど美しいとされ、コルセットできつく縛り込みました。
19世紀後半の南北戦争時代の南部アメリカ社会を描いた「風と共に去りぬ」の映画冒頭部分。スカーレットがパーティ衣裳を身に着けるために、乳母に腰をきつく締め付けさせていたシーンを思い出します。
庭園美術館1階の展示。細い腰の美を示すコルセット。大人の女性で「美しい」のは38センチ以下のウエスト。50センチでは、もはや「醜い」。
「コルセット」1880年頃 イギリス、神戸ファッション美術館蔵
現代でもウエストサイズが小さいほど「スタイルのいい女性」と考える人も残っているようです。
また、現代で顕著な「女性美」と考えられているのが「大きな乳房」です。ペチャパイだのボインだのと、乳房を表すことばも次々に流行語になるくらい、乳房の大きさに対する関心は強い。
より大きな胸になろうとする豊胸手術は、二重瞼手術とともに、美容整形外科の稼ぎ頭。シリコンでふくらんだ胸を「美しい」「セクシー」と思う人がいる限り、整形美容科医はもうかる。後世の人から見て、「人工の詰め物をしてまでふくらんだ大きな胸を欲しがる時代があったなんて」と、その奇習に驚かれるかもしれません。
髪に対する意識も、時代時代の女性美観とともに変遷しました。平安時代の人々にとって、黒くたっぷりした長い髪こそが女性美の最たるものでした。長い間、短い髪は出家した女性を表しました。平安人が現代女性をみたら「なんと、この国では女人は全員尼になっている」とびっくりするでしょう。
髪への偏愛とともにあったファッション。
Chapter3は、「髪へと向かう狂気の愛」。
愛し合う二人髪の一房を交換し、ロケットペンダントやブローチの中に髪を納めて肌身離さぬことが、「愛の証」とされました。家族がなくなったときも、その髪を装身具に仕立てて喪に服す証としていました。
そんな髪への偏愛が究極のファッションになって展示されていました。
ヘルベルト・ロイピン「パンテーン社ポスター」1945
渦巻く髪の束。髪そのものが物質としてデザインされており、パンテーン社の製品をアピールしました。
小谷元彦「ダブル・エッジド・オヴ・ソウト(ドレス02)」1997
このワンピースの素材は、すべて人毛です。実際に着用できるそうですが、私は着たくないなあ。鬘には抵抗ないけれど、ワンピースだと、ちょっと、、、、ぞわぞわしてくる。
Chapter4
エルザ・スキャパレッリというデザイナーの存在を初めて知りました。ココシャネルの同時代人にしてライバル。しかし、シャネルの会社がよい後継者を得て、現在まで世界有数のブランドとして生き残っているのに対して、スキャパレッリは、1954年のコレクションを最後にメゾンを閉鎖、以後は隠遁生活を送り、1973年パリで死去。
ふたりの女性の差はなんであったか。戦争をめぐり、利口に立ち回れたココに対して、不器用で損な役回りばかりしていたエルザの違い。デザイン力はエルザのほうがあったかもしれないけれど、企業運営力人間関係構築力はココが強かった。ココは、戦争中にドイツ人将校を恋人にしていたことなど、戦後はなかったことにしてしまいました。政治力。
デザイナーとしてのスキャパレッリ。「ショッキングピンク」という大胆にして鮮やかな色彩の命名者として、もっと称揚されていい人だと思います。
スキャパレッリのデザイン。イヴニングケープ&ドレス。手前に横になっているケープも大胆な装飾でした。
新館には、靴のデザインを中心に、現在売り出し中の作品が並んでいました。レディガガが気に入ってステージで着用したという靴もあり、「これって、ほんとに履いて歩けるの?」と思う靴もありました。
新館入り口
ユアサエボシ「着衣のトルソーと燃えている本、二匹のさかな、八つの砲弾」
舘鼻則孝、永澤陽一、串野真也などの現代作家のほか、東京競技場のデザインが「金かかりすぎる」と拒否され、2016年に亡くなったザハ・ハディトがデザインした靴が展示されていました。ハディトが設計した建物は、「実現不可能建築」として有名でした。靴も「これ履いて歩けるかな」と思いましたが、とにかくユニーク。靴を見るにつけ、ハディトによる国立競技場を見てみたかった、と思います。歴史に残る建物になったでしょうに。ザハのデザインに似通ってはいるけれど、常識の範囲内の形になった隈研吾の競技場。お金はザハの設計よりもかからなかったかと思いますが、ザハのほうがTokyo2020のモニュメントになったんじゃないかな。
お金をかけない、というコンセプトのもと、史上もっともごじんまりとした(政治的に正しくない表現では「ショボい」)演出となった開会式パフォーマンスとともに、惜しいことでした。(コロナの中開催できただけでもよかった、ということにすべきしょうけれど)。
「NOVAshoe」2013 ザハ・ハディト&ユナイテッドヌード
タイトルの「shoe」がshoesでないのは、履くのは片足だけだから?
新館の、靴の展示。
これも履き物
永澤陽一「ジョッパーズパンツ」(2008)
「ジョッパーズパンツ乗馬ズボン」というタイトルで、馬皮やシマウマの皮を使っていますが、実際に履くことはできないらしい。シマウマパンツを履いてシマウマにまたがって登場したら、レディガガもびっくりかも。
新館第2室は、紫外線から目を守る眼鏡をつけて入室。直接目で見ると紫外線によって目を損なう、という注意書き付き。
スプツ二子(1985- Sputniko!(尾崎マリサ優美。両親とも数学研究者で日本人父とイギリス人母のもとで育ち、17歳でロンドン大学留学。現在は東京大学美術デザイン科准教授)。
私は、NTTコミュニケーションセンターで開催された「アノニマス名を明かさない生命」展(展示期間:2012年11月17日~2013年1月14日)に出かけたおり、スプツニ子!の「菜の花ヒール」などの作品を見たはずですが、現代美術へのアンテナが弱くて、この時は桂米朝ロボットが落語を語るのを熱心にみていただけで、スプツニ子!作品にまったく反応していませんでした。
今回のスプツニ子!作品は、串野真也とのユニット「Another Farm」による「Modified Paradice」
、

光るクラゲなどの遺伝子組み換えで生まれた蚕を飼育し、光る繭を作り出す。その光るシルクで西陣織の布を織りあげ、仕立てられたドレスが展示されています。
21世紀、遺伝子組み換え食品は、知らぬ間に私たちの日常に入り込んでいますが、遺伝子組み換えの衣服というのがすでにできあがっている衝撃をうけました。こんなのは20世紀人間のスローモーな反応なのでしょうが、これからの社会に遺伝子組み換えの肉やら魚やら、衣服やら身の回りに増えていくことを受け入れなければならないのでしょう。
古いアナログ人間は、社会の変化においてきぼりになるばかり。
iPS細胞の角膜が治験を終え、承認されるところまできた、という今朝の医療ニュース。
さて、これから人造人間を作るマッドサイエンティストも絶対出てくるね。
」
<つづく>