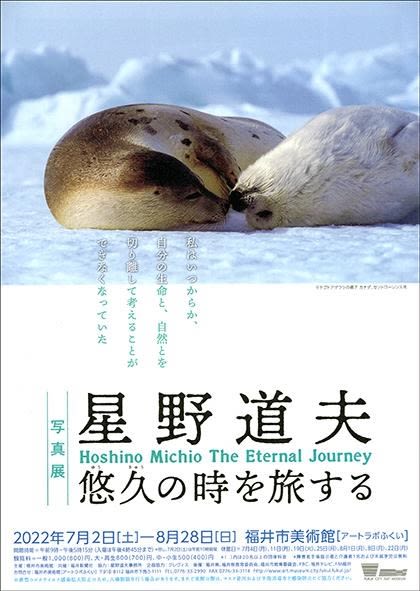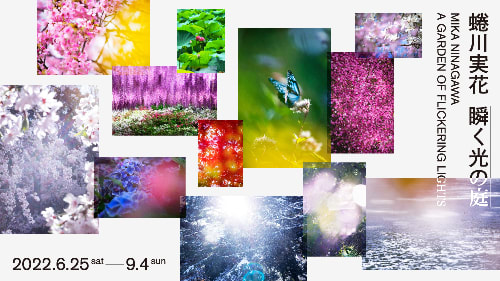20221204
ぽかぽか春庭アート散歩>2022アート散歩写真を見る(2)藤原新也展 in 世田谷美術館
藤原新也の写真、写真エッセイの本。1981年に発表した『全東洋街道』 から2011年までの作品はかなり見てきたのですが、最新作については、「大鮃(2017年)」も「沖ノ島 神坐す海の正倉院(2017年)写真集」も、雑誌の抜粋ですら見ていませんでした。
今回の世田谷美術館での「初期写真から2020年まで、藤原新也の全貌」という展覧会、楽しみにしていました。日曜美術館で紹介があったので、週末は混むだろうから、会期はじまったばかりの水曜日にでかけ、展示室にいるのは、私ともう一人くらい、というゆったり空間で見ることができました。
山口百恵大島優子らのタレント写真は肖像権があるので撮影禁止ですが、それ以外はすべて撮影してもよい、というので、思い出写真もたくさんとりました。もちろん、本物の写真が手に入ればいいのでしょうが、ショップで売っていたのは、A3サイズくらいで25万円でしたから、高値の花。せめての思い出にと、図録は購入。シルバー券払ってハガキ1枚買ったので、1000+195+2970円=3650円。+砧公園内のパークスという休憩所で長崎ちゃんぽんを食べて600円。占めて本日の行楽費4250円。
会期: 2022年11月26日(土)–2023年1月29日(日)
世田谷美術館の口上
1944年に福岡県門司市(現 北九州市)に生まれた藤原新也。東京藝術大学在学中に旅したインドを皮切りに、アジア各地を旅し、写真とエッセイによる『インド放浪』、『西蔵(チベット)放浪』、『逍遥游記(しょうようゆうき)』を発表します。1983年に出版された単行本『東京漂流』はベストセラーとなり、社会に衝撃を与えます。また同年に発表された『メメント・モリ』は、若者たちのバイブルとなりました。1989年には、アメリカを起点に西欧へと足をのばし、帰国後は自身の少年時代を過ごした門司港で撮影した『少年の港』をはじめ、日本にカメラを向けます。そして旅のはじまりから50年後、現代の殺伐を伝えるニュースを背に、大震災直後の東北を歩き、コロナで無人となった街に立って、これまでの道程と根幹に流れる人への思いを「祈り」というタイトルに込めます。そして藤原の見た、人が生き、やがて死へと向かうさまは、現在形の〈メメント・モリ(死を想え)〉へと昇華され、新たな姿でわたしたちの「いま」を照らします。
藤原の表現活動で特筆すべきは、写真、文筆、絵画、書とあらゆるメディアを縦横無尽に横断し、それぞれの領域において秀でた表現を獲得していることにあります。
本展は、祈りをキーワードに、初期作から最新作までの作品を一堂に展示して、藤原新也の多彩な仕事を立体的に展開します。
会場に入ると最初に目に入る蓮の花の写真
初期の作品は見覚えのある、写真集などでながめてきたものでしたが、ある時期から藤原の写真をまとめて見ることも少なくなってきました。藤原がある種の「権威」になってしまったことに対して、素直になれない自分がいたからです。
今回の会場をゆっくり回って(会期はじめの水曜日だったので、どのブースも人が少なかった)、やはり迫力があるすごい写真が多いとは思ったけれど、なんといっても初期作品が好きです。
「人は犬に喰われるほど自由だ」
あの人がさかさまなのか、私がさかさまなのか。
最後の出口付近に、私も視聴した「日曜美術館」への感想が載っているのを読みました。
日曜美術館。藤原が自分自身のルーツである場所への旅をドキュメントしていました。
こどものころの藤原を我が子のようにかわいがってくれた叔母が暮らした結核療養所。かってあった場所をたずねて、路傍に咲く白い百合の花を接写し、そのユリにバッタがはりついている写真を見ての若い女性からの感想でした。
肺病を病む人の特徴である「色が透き通るように白く美しかった」という早世したおばさんへの思いとバッタの生命力が重なり、感動のシーンでしたが、NHKに届いた若い女性の感想として「私も生きていこうと感じた」というような内容の感想した。
そのような感想を持つ若い純粋な心、すばらしいです。
でも一方で「藤原新也の、あいだみつお化ですねぇ」という思いが不純な老婆の胸に残ってしまった。不純です。
花について。「花は怖いこともある」というyokoちゃんの感性が好き。私の「怖い」は、yokoちゃんとはことなるだろうけれど、私も怖いときがある。
確かに花は美しい。しかし、花は植物にとって第一義は生殖器である。その色や香り、甘い蜜などで虫や小鳥を誘うのは、己の繁殖活動のため。雄しべと雌しべが結合して子孫を残すために花が咲く。路傍に咲く清楚な白百合だろうと、雄しべと雌しべは交合する。それは美しくもあり怖くもある。
花は光輝く美しいものであり、生殖器をひろげて虫を誘い込むものである。
インドの街角で路上で「大地」と大書し、まわりを人々が取り囲んでいる写真。
「だれも私にカメラを向けていない。みな自分の眼で見つめてくる」という感想を藤原は書いていました。日本なら自分の眼で見つめることをせず、カメラのフラッシュがたかれただろう、と藤原はいう。インドの見渡せばカメラなき時代のショット。
たぶん、今、同じことをしたら、インドだろうとネパールだろうとたちまちスマートフォンが向けられ、即座にインスタグラムだかフェイスブックで世界中に発信されるだろうなあと思い、藤原が写し取ったネパールやインドの映像は、映像としてすぐれているだけでなく、時代の貴重な証言でもあるのだろうと思いました。
2011311の被災地写真やバリ島の花の写真など、私が見てこなかった藤原の写真を、時代に沿って、テーマにそって見て歩き、写真の持つ雄弁な物語を、会場外のスライドでも確認しました。
アメリカ撮影旅行。アメリカのキッチュな文化
アジア
イスタンブール
香港。雨傘運動に寄せられた「レノンウォール」に貼られたメモの写真。
山口百恵らは不可でしたが、瀬戸内寂聴の写真はOKでした。寂聴との往復書簡も展示されていました。生と死をみつめる視線にきっと共感しあうものがあ
ったのでしょうね。
現代の日本。電車の中の若者
図録の「写真に添えられたことば」まだ全部読んでいませんが、おいおいと。
藤原が東京芸術大学油絵科を中退したことは知っていましたが、その後も絵を描き続けていたことは知りませんでした。油絵を並べたブースもあり、画業も知ることができました。
展覧会のテーマタイトル「祈り」。藤原自身が「写真を撮ることが私の祈りであった」ということはよくわかりました。
ガンジス川ほとりでの火葬。
藤原はその火を「人間が燃え尽きるまで、その明かりはせいぜい60ワット3時間」と表現する。
遺体を川で清める
ガンジス川。焼け残った父親の背骨を川の中に遠投する喪主の若い息子。藤原は「スポーツに取り組むように投げた」と書く。死は特別なことではなく、日常のヒトこまであり、明日は明日の日常がつづく。
ガンジス川のほとり
写真を撮る行為が藤原にとって「祈り」であるなら、私がその写真を見てあるくのも「祈り」であろうと思う。
<つづく>