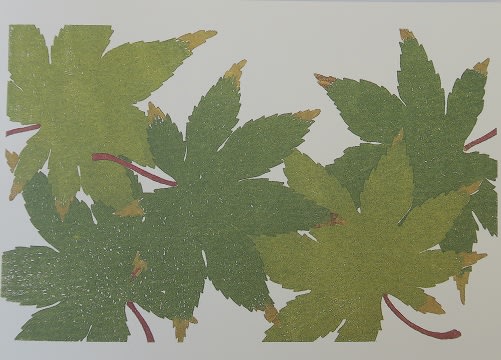田島弥平旧宅
20151118
ぽかぽか春庭日常茶飯事典>2015十五夜満月日記11月(1)絹産業近代化遺産・田島弥平旧宅
女子校のクラスメートやっちゃん。高校教員を定年退職した後は、悠々自適の暮らしを続けています。午前中は、大学馬術部をボランティア指導。午後は昼寝や読書。「家の中を片づける時間はないから、足の踏み場もないんだ」と、言います。我が家と同じ。我が家と違うのは、やっちゃんの家は、やっちゃんが自分で基礎工事をして、棟上げだけ大工さんにちょこっと手伝ってもらったけれど、内装も含めて文字通り手作りした家だ、ということです。
やっちゃんは、昨年は2度、これまでになかったほどの病気をしたので、この先の人生、友達とのつきあいも旅行もやりたいことを全部やってしまおう、という気持ちになったのですって。私とは「東欧自転車旅行をする」「日本全国キャンピングカー旅行をする」という約束をしました。来年早々に「ミャンマー旅行する」という約束、やっちゃんは早速ヤンゴン往復航空券の予約をすると言っていました。
私が「まだ世界遺産の富岡製糸場を見学していない」と言ったら、やっちゃんが案内してくれることになりました。車で「富岡製糸場と群馬絹産業遺跡群」を一回りし、おまけとして、上州名産こんにゃく工場の見学と無料こんにゃくバイキング。食べ放題でもこんにゃくやシラタキだったら、カロリー取り過ぎの心配もない、第一に無料というのがうれしい。
群馬県で生まれ育った者にとって「富岡製糸」は、郷土史が誇る近代化遺産でしたが、娘息子と16年前に甘楽町に一泊旅行したときは、富岡製糸場はまだ「操業を停止した古い工場」にすぎず、富岡の町も「過疎化が進んできた田舎町」でした。
甘楽町や富岡市、どんなふうに変わっていることでしょう。
高崎線本庄駅、はじめて降りました。やっちゃんの指示通りに駅前交番の脇で待っている間、やっちゃんの旅程計画を確認。
やっちゃんの案内計画では。
①10:30高崎線本庄駅で下車し、駅前交番の前でやっちゃんの車を待つ。
②群馬絹産業遺跡群の中の、養蚕農家遺跡(伊勢崎市境島村)を見学。
③藤岡市高山の養蚕学校「高山社跡」見学
④富岡製糸場見学
⑤こんにゃく工場見学とこんにゃくバイキング試食
⑥夕食とりながらヤンゴン旅行計画
と、盛りだくさん。全部まわり切れなかったら、次回のお楽しみ、ということにして出発です。
やっちゃんの車に同乗して、まず、群馬絹産業遺跡群のうち、田島弥平旧居へ。
世界遺産のひとつになったので、案内所なども整備されています。案内所は、島小学校(伊勢崎市立境島小学校)の隣にありました。
島小学校は、斎藤喜博先生による総合教育が有名になり、全国から授業参観が押し寄せた、いわば「群馬教育のメッカ」のような小学校でした。その小学校も、児童数は現在10名となり、来年は統廃合されるそうです。
やっちゃんと島小の前で記念写真を撮りました。
案内所へ行き、ビデオで田島弥平の生涯と事跡について学習しました。
「弥平」は代々の受け継ぎ名前で、明治初期に養蚕事業を行ったのは、田島邦寧(くにやす)1822(文政5)-1898(明治31)です。
蚕室の換気窓(櫓=やぐら)を備えた農家、清涼育という飼育法を考案し『養蚕新論』を著して養蚕の改良に努めました。
櫓は、二階蚕室の屋根の上に空調のための換気小屋根をつけたものを言いますが、さまざまな形の櫓がありました。

田島弥平旧宅(屋号:遠山近水邨舎)1863(文久3)築造

江戸末期から明治にかけて、群馬県は「労農」と称される篤農家(農業改良研究者)を輩出しました。群馬の子供達が小学校で暗記する『上毛カルタ』でも、「ろ」「ローノー、フナツデンジヘー労農船津伝治平」は「い」「伊香保温泉日本の名湯」の次ぎに覚える札です。しかし、田島弥平はカルタになっていませんので、私が田島弥平の名を知ったのは、2003年に読んだ丑木幸男『蚕の村の洋行日記―上州蚕種業者・明治初年の欧羅巴体験(1995)』によってです。
田島弥平(邦寧)は、1879(明治13)年、56歳のとき、蚕種輸出推進のために欧米旅行を行っており、『伊太利国未蘭在蚕種売捌日誌』を書き残しています。
私は、「日本事情」という教科を担当した時期に、日本と諸外国の交流をテーマに授業を実施していました。近代化の時期に、欧米から日本にやってきた御雇外国人の事跡と幕末から明治初期に欧米に洋行した日本人の記録について、自分もまなびながら留学生に交流史の発表をさせていたのです。
田島弥平を知ったのも、このころでした。
やっちゃんといっしょの大人のえんそく、大人の社会科見学からの帰宅後、久しぶりに『蚕の村の洋行日記』を本棚から引っ張り出して、著者の丑木幸男先生の経歴欄を見ました。先生は、私とやっちゃんが卒業した女子高校の教諭をしていた方だったことがわかりました。

私たちが卒業したあとに赴任されたのだろうと思いますが、もし丑木先生に日本史を教わっていたら、私は日本文学日本語学を専攻せずに、「群馬県の近代史」なんぞを専攻していたのではないかと思います。残念。
私が日本史を教わった先生は、高校定年後は「土屋文明記念文学館」に勤務されたということなので、文学寄りの方だったのだろうと思います。
案内所では、解説員の松村辰博さんが、たいへんていねいに詳しく説明してくださいました。島村の田島姓の人々と渋沢栄一の渋澤一族との関わりについても、私の質問したことに詳しく解説していただきました。
とてもよい解説なので、ついつい「次のところに回る予定がありますので、もう解説はけっこうです」と言い出せないまま、弥平と蚕について、いろいろ教わりました。
弥平旧宅の周辺には、櫓を備えた農家が十数棟も残されているというので、やっちゃんと案内所のレンタル自転車(無料)で回ることにしました。
どの家も、間口9間~12間、奥行き5間、という大きな農家。今はもう農業や養蚕をやっていない家もありましたが、たとえば、医院の家も、昔ながらの家をそのまま残して開業していました。
田島医院

主立った家には、進水館、栄盛館、有隣館、對青廬などの館名がついていて、案内板が出ていました。


でも、たくさんの大きな家があったので、帰宅して写真を見たら、どれがどの家だったか、わからなくなりました。
有隣館:1968(明治元)年築 写真を撮るやっちゃん。左はしにある自転車2台で回りました。

對青廬:1966(慶応2)築



進水館:幕末頃の築


群馬県は、車がないと移動が不便な土地柄。車1台あたりの使用人数は、1.14人(全国第1位)、つまり、人口の数と車の数がほぼいっしょ。やっちゃんも自宅から大学馬術部への行き帰りは車です。久しぶりに自転車に乗るというやっちゃんに対し、私は東京都内どこに行くのも地下鉄がほとんどで、自宅近所の交通手段へは自転車。自転車に毎日乗っています。
秋の日差しさんさんと注ぐ田園地帯を自転車で走るのは、とても気持ちよくて、利根川の川風もまだ冷たいほどではなく、快適なサイクリングでした。
利根川、島村の土手で

<つづく>