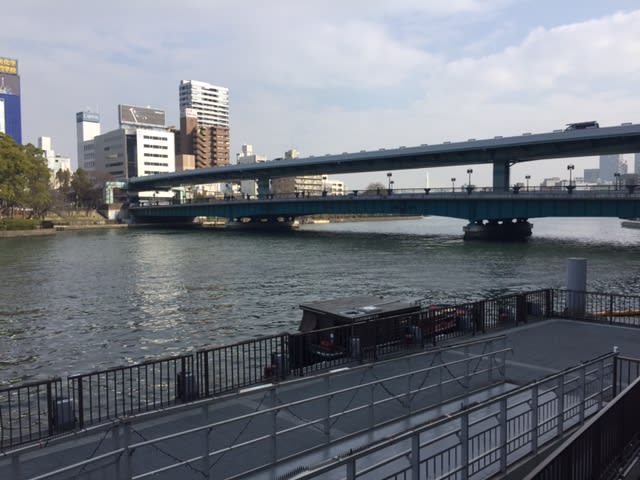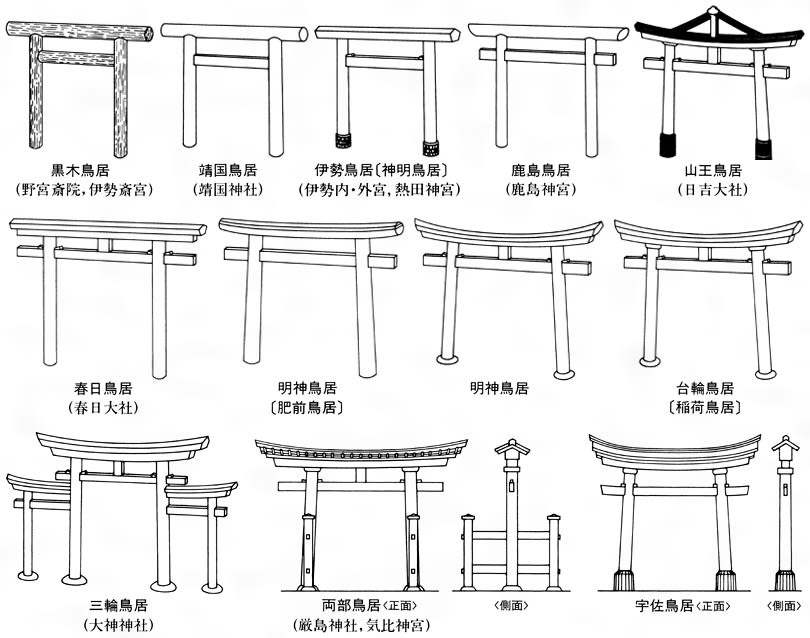名匠といわれる人、老舗といわれる店が今の時代とくに苦戦している。それも苦戦を強いられて久しい。
その一つがオーダーメイドの紳士服である。紳士服は江戸時代の終わりごろヨーロッパから神戸に入り、日本全国に広まっていった言われている。当時は機械がまだない時代なのですべて手縫いで作られていた。その手縫い技術は、いまも脈々と受け継がれている。
いまの時代、30万円出してスーツを買う人がいるのだろうか。と首を傾げたくなるが、この人が作る服でないとダメ。この仕立てでないとダメ。という心粋をもつ人たちが、まだまだたくさんいるという。でも、当然昔のバブル時のときに比べれば雲泥の差であろう。
紳士服をフルで手縫いすると、一針を5万回くらい通すことになるらしい。それくらい複雑でパーツが多いことになる。オーダーメイドは、いまさら記述することもないだろうが、生地選びから始まる。そして採寸。この採寸が出来上がりの良し悪しを決めるポイントだといわれている。
体型は、一人ひとりのすべて違う。丈、肩幅、腕の長さ、胸周り、胸の厚み、胴周り、腰周り、脚の長さに太さなどをしっかりと採寸する。そして左右の肩の位置が違う、腕の長さが違う、姿勢が違う、歩き方が違う。さらにそれに加えてお客様の好みが入ってくる。
これらの条件を入れて採寸、裁断、縫製をしていく。この技術をマスターするのは最低10年はかかると言われるほど難しい。仕上げる前に仮縫いという工程がある。この仮縫いは、お客さんに実際に着用してしてもらい、体にフィットしているか、どうかを確認する作業である。
この仮縫いのときに、肩の位置がずれてないか、胸に弛みが出てないか、腕にしわが寄ってないか、ボタン位置と丈のバランスがいいか、背中に生地がなじんでいるか、というほんと細部にわたってチェックする。そこでミリ単位で生地を摘んだり、長く短くしていく。
その仮縫いで補正した服をもう一度試着する。出来上がりまで少なくとも一ヶ月はかかる。
こんな手間隙かけて作る逸品が求められる時代ではないが、この服を着てくれる一人のお客さんを思い浮かべながら通す一針一針は実に重い。これも名匠逸品である。この精神は、いつの世にも生きる財産である。


その一つがオーダーメイドの紳士服である。紳士服は江戸時代の終わりごろヨーロッパから神戸に入り、日本全国に広まっていった言われている。当時は機械がまだない時代なのですべて手縫いで作られていた。その手縫い技術は、いまも脈々と受け継がれている。
いまの時代、30万円出してスーツを買う人がいるのだろうか。と首を傾げたくなるが、この人が作る服でないとダメ。この仕立てでないとダメ。という心粋をもつ人たちが、まだまだたくさんいるという。でも、当然昔のバブル時のときに比べれば雲泥の差であろう。
紳士服をフルで手縫いすると、一針を5万回くらい通すことになるらしい。それくらい複雑でパーツが多いことになる。オーダーメイドは、いまさら記述することもないだろうが、生地選びから始まる。そして採寸。この採寸が出来上がりの良し悪しを決めるポイントだといわれている。
体型は、一人ひとりのすべて違う。丈、肩幅、腕の長さ、胸周り、胸の厚み、胴周り、腰周り、脚の長さに太さなどをしっかりと採寸する。そして左右の肩の位置が違う、腕の長さが違う、姿勢が違う、歩き方が違う。さらにそれに加えてお客様の好みが入ってくる。
これらの条件を入れて採寸、裁断、縫製をしていく。この技術をマスターするのは最低10年はかかると言われるほど難しい。仕上げる前に仮縫いという工程がある。この仮縫いは、お客さんに実際に着用してしてもらい、体にフィットしているか、どうかを確認する作業である。
この仮縫いのときに、肩の位置がずれてないか、胸に弛みが出てないか、腕にしわが寄ってないか、ボタン位置と丈のバランスがいいか、背中に生地がなじんでいるか、というほんと細部にわたってチェックする。そこでミリ単位で生地を摘んだり、長く短くしていく。
その仮縫いで補正した服をもう一度試着する。出来上がりまで少なくとも一ヶ月はかかる。
こんな手間隙かけて作る逸品が求められる時代ではないが、この服を着てくれる一人のお客さんを思い浮かべながら通す一針一針は実に重い。これも名匠逸品である。この精神は、いつの世にも生きる財産である。