
「ある時 価値は反転する」
いい手だなと心が動かされる時がある。それはもの凄く派手な一手というばかりではない。むしろ何でもないような一手。実際に盤上に現れた手そのものに対してではなく、普通にみえるはずの手が「指されなかった」ことへの驚きというものがある。
「えっ、金逃げなくていいんですか?」
それは序盤ではまず絶対に現れないような一手だ。
「歩で金を取られてはいけない」
将棋を学ぶ時、一番最初に教えられることではないか。
それなのに……。
自分の先入観を打破するような手が現れた瞬間、「いい手だな」と感動しながら驚いてしまうのだ。
・金を粗末に扱うこと
・手を抜くこと
・人の言うことを聞かないこと
最初にみんな「よくないこと」だと教わったこと。それが「よい手」になる局面もある。
覚えてきたことを捨てなければ、それより先には進めないことがある。(なんて難しく、面白いのだろう……)
「終盤は駒の損得より速度」
と言う。だけど、終盤だって金は大事だろう。いつ、その格言は有効になるのか。
「歩で金を取られてはいけない」
勿論それは序盤の話である。
金取りを手抜くような手は、終盤ではよくある手だ。
「時は金なり」
終盤ではその言葉はより重い。金一枚も大きいが、一手利かされることも同じくらいに大きい。
~取らせてさばく手を覚えよう!
中飛車の上に自分の金がいてその頭を歩で叩かれている。飛車の斜めしたには馬がいて飛車に当たっている。振り飛車を指しているとそういう状況はよくあるのではないだろうか。攻められていてとても嫌な感じがする。できるだけ損をしたくない。被害を最小限に抑えたい。そのようなマインドになりやすいのではないだろうか。だけど、自陣ばかりみていてはいけないし、「さばく」という強い心を失ってはならない。相手の理想は、金を乱して飛車を取りたいのだ。(歩で利かして攻めを加速したい)無茶苦茶攻められているようだが、飛車と金を両方同時に取ることはできない。ある意味では攻撃が重複しているという視点を持つことが大事だ。歩を打って金を取るには2手費やすが、飛車取りに馬を動かした手も含めると3手を費やしている計算になる。「時は金なり」という感覚からすると、手抜きは選択肢の1つとなる。0手で利かされるよりも、3手かけて金を取ってもらう方がいいのではないか? そういう発想を持つべきだ。手抜くことによって生まれる一手で、敵陣に自分の有効な手を探す。金を取らせ、同じく飛車と前進する一手が手順に馬の当たりから逃れる。その時、飛車の横利きにもう一枚の敵の馬(77馬)がいるではないか。これはおあつらえむきだ!
「飛車でも金でも好きな方をどうぞ」
そうした大胆なさばきを身につけられれば、振り飛車はもっともっと楽しくなるのではないだろうか。















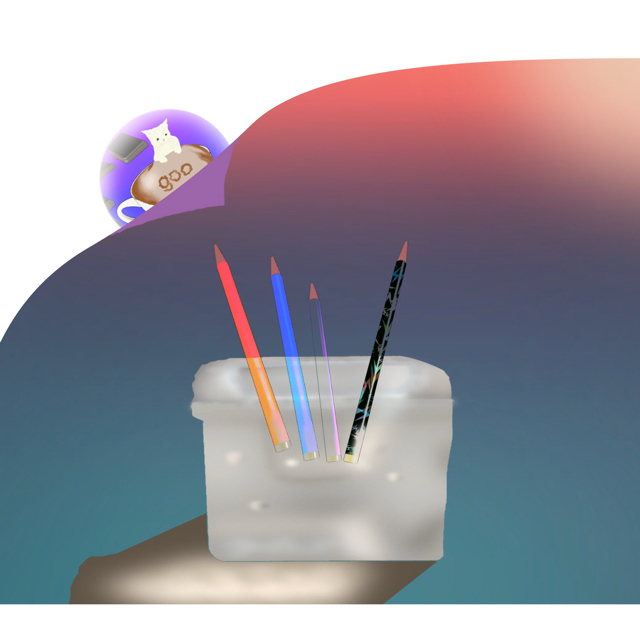

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます