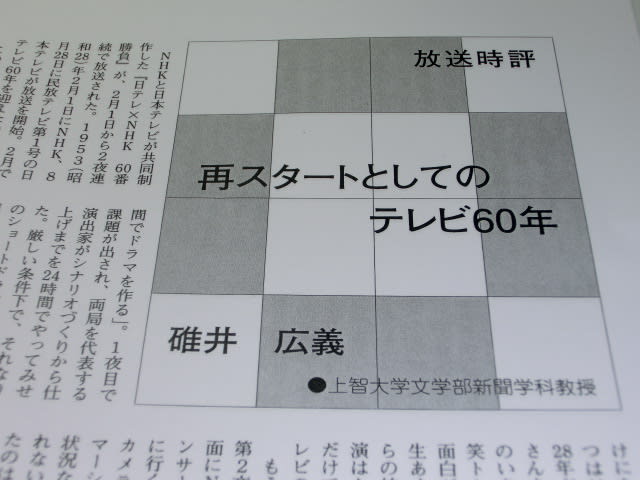「月刊民放」3月号の放送時評。
今回は、テレビ60年をテーマに書いています。
再スタートとしてのテレビ60年
NHKと日本テレビが共同制作した『TV60 日テレ×NHK 60番勝負』が、2月1日から2夜連続で放送された。1953(昭和28)年2月1日にNHK、8月28日に民放テレビ第1号の日本テレビが放送を開始。2月でテレビ60年だ。
この特番の目玉企画は「24時間でドラマを作る」。1夜目で課題が出され、両局を代表する演出家がシナリオ作りから仕上げまでを24時間でやってみせた。厳しい条件下で、それなりのショートドラマを作った制作陣には敬意を表すが、当然のことながらやや寒い内容だった。
それよりも、見ていて釘づけになった場面が2つある。1つはNHKが放送した第1夜、28年ぶりの出演だという明石家さんまがスタジオに現れ、過去のいきさつをネタに展開した爆笑トークだ。出演した「クイズ面白ゼミナール」で、さんまが生あくびをしていたと視聴者からの抗議が殺到。以降、本格出演はなかったというのだ。裏話だけでなく、当時の視聴者とテレビの関係性が興味深かった。
もう1つの釘づけシーンは第2夜の冒頭、日本テレビの画面にNHKの有働由美子アナウンサーが登場した時だ。CMに行くタイミングで有働アナがカメラに向かって、「はい、コマーシャル!」とやった。この状況なら当たり前の演出かもしれないが、見ていてドキドキしたのは事実だ。
この2つの場面の面白さを支えていたのは、まず生放送というスタイルだろう。わが家とは別空間であるはずのスタジオの空気や時間を、画面を通じて共有しているという感覚。つながっているという気分である。次に、NHKにいるはずのないさんま、日本テレビで見るはずのない有働アナを目撃したという驚きだ。テレビという日常の中に異分子が混入したことによる非日常性が見る側を興奮させた。人はそこにあるはずのないもの、見るはずのないものに遭遇したら目が離せなくなるのだ。
60年前の草創期、現在とは比べようもないレベルの画質や音質だったにも関わらず、テレビが見る人たちを惹きつけた。それはスポーツ中継であれバラエティーであれ、何が起きるか(飛び出すか)わからない生放送による特別な時間と、テレビでなければ見られないものを目撃する特別な体験だったからではないか。そして、こうしたテレビの力は現在も失われてはいないし、逆にテレビ60年をきっかけに、原点に返るという意味で再考に値するのではないか。この記念特番を見ながら、そんなことを思った。
もちろん、現在のテレビはのんきに還暦を祝っていられる状況ではない。ネットの台頭。視聴者のテレビ離れ。広告収入の減少。加えて原発事故をめぐって広まったテレビ報道への不信感もある。しかし、もしもテレビが劣化していると言うなら、それはテレビそのものではなく、テレビに関わる人たちの劣化かもしれないのだ。あえて青臭いことを言えば、テレビに関わる人間の志の問題である。
ここで思い浮かぶのが、1974年の秋から翌年3月まで放送された、フジテレビのドラマ『6羽のかもめ』のことだ。その最終回「さらばテレビジョン」の劇中劇で、政府は国民の知的レベルを下げることを理由に(セリフでは「これ以上の白痴化を防ぐために」)、国民に対してテレビ禁止令を出す。テレビ局は全て廃止。各家庭のテレビは没収。禁酒法時代の酒と同じ扱いとなるという設定だ。ドラマの終盤、山崎努演じる放送作家が酒に酔った勢いでカメラに向かって自分の思いをぶつける。あの伝説の名セリフが飛び出すシーンだ。脚本は倉本聰さん。
「だがな一つだけ言っとくことがある。(カメラの方を指さす)あんた!テレビの仕事をしていたくせに、本気でテレビを愛さなかったあんた!(別を指さす)あんた!――テレビを金儲けとしてしか考えなかったあんた!(指さす)あんた!よくすることを考えもせず偉そうに批判ばかりしていたあんた!あんた!! あんたたちにこれだけは言っとくぞ!何年たってもあんたたちはテレビを決してなつかしんではいけない。あの頃はよかった、今にして思えばあの頃テレビは面白かったなどと、後になってそういうことだけは言うな。お前らにそれを言う資格はない。なつかしむ資格のあるものは、あの頃懸命にあの情況の中で、テレビを愛し、闘ったことのある奴。それから視聴者――愉しんでいた人たち」
倉本さんが、ドラマの中のドラマという二重構造に仕込んで投げつけた時限爆弾は、テレビ60年を迎えた現在も、そのカウントダウンを続けている。
(月刊民放 2013年3月号)