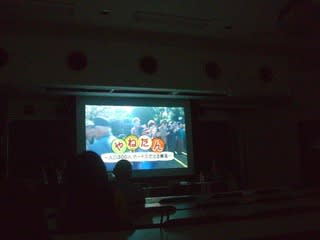昨日(17日)、「J-CASTニュース」に興味深い記事が掲載された。
14日(火)の19時台、民放の視聴率が軒並み1ケタだったというのだ。
そのことを“発信”したのが局P(放送局のプロデューサー)だった、という点も面白い。
タイトル:
「民放の19時台視聴率が1ケタになった」 テレ朝プロデューサーの「ツイッター」に「当然」の声
テレビ朝日の藤井智久ゼネラルプロデューサーが「ついに民放全局の視聴率が1ケタになった」とツイッターで呟いているとネットで話題になっている。
1ケタになったのは19時台全ての番組。もともと19時台はゴールデンタイムの入り口で、視聴率や広告収入が見込めたドル箱。
しかし、10年ほど前から不振が続き、メインターゲットとしていた小学生から高校生がテレビから離れてしまったという。
「見たい番組がない」など大量のリツィート
藤井ゼネラルプロデューサーは2011年6月15日、ツイッターで「ついに昨日、19時台の民放は全局、視聴率が1ケタになった(関東地区)」と呟いた。
昨日というのは14日(火)のことで、新聞のテレビ欄を見ると「泉ピン子宮古島に来襲」「AKBVS戦隊ヒーロー」「熟女4人が下町電車旅」などの番組が並んでいる。
この呟きがネットで大きな反響を呼んでいて、
「正直、見たい番組が、ない…TV 本当にもういらないかも・・・」
「5年後にゴールデンが全局一ケタでも驚きもしない」
などと「当然」と受けとめるリツイートが大量に寄せられている。
放送評論家の松尾羊一さんによれば、昔から19時台はゴールデンタイムの入り口として、まずは小学生から高校生を集める番組制作が行われた。
20時台になれば会社から家族が戻り、家事も一段落。家族全員でテレビを見ながら団欒する、という流れがあった。
しかし、携帯電話やゲーム、パソコンなど普及によって19時台の視聴者は10年前から急速にテレビ離れしていった。
復活のヒントは池上彰に学べ
視聴率が下がると制作費が削られるため魅力的な番組が減るスパイラルに陥り、起死回生策としてマンガやゲームでヒットした作品を持ってきたりもしたが、
「他のメディアでヒットした作品におもねても、テレビで成功するわけではない。若い人は感覚が鋭いため納得のいかないものは見ない」
さらに、番組が一部の人しか興味を示さないような狭い内容になってきた。こうしたことが視聴率が取れなくなった原因だと松尾さんは説明する。
もう19時台の視聴率復活は難しいのかというと、復活のヒントはあるのだそうだ。
実は、19時台で高視聴率を記録した番組があり、それはテレビ朝日系で08年から19時台に放送した池上彰さん司会の「学べる!!ニュースショー!」。
この番組はティーンエイジャーが主な視聴者で大うけだった。10年からは放送が8時台に移り「そうだったのか!池上彰の学べるニュース」に番組名が変更になった。
「見てわかりやすいし、勉強になるだけでなく楽しめる。この応用としてドラマやクイズ、バラエティー番組を制作する。そこに若い人達のニーズがあるのではないかと思います」
そう松尾さんはテレビ業界に対し提言している。
(J-CASTニュース 2011.06.17)
・・・・記事を読んでの最初の感想は、「そうか、これって初めてなんだ」というもの。
てっきり、ここ数年の中で、「民放全局の19時台視聴率が1ケタ」という事態を経験していると思っていた。
「ついに・・・」と藤井Pはつぶやいたそうだが、逆に、「よくここまで、そうならずに来たもんだなあ」と感じる。
申しわけないけど、記事にあるようなラインナップが続くなら、「19時台横並び1ケタ」はこれからも続発するはず。
松尾先生(と私は呼んでいます)の提言にも、しっかり耳を傾けるべきだと思います。