鹿児島で和裁士数名の研究会
「きつけ塾いちき」の和裁担当者と、これまできものを縫っていただいいていたベテラン和裁士が鹿児島の和裁教室の先生のお宅に伺います。
「半返しの遠山」としても知られている遠山先生の教室です。
伺う宮崎の和裁士も、京都の和裁教室で教える立場にあった方で、お勉強できるところがあればどこにでも行く研究熱心なベテラン和裁士。
今回、お勉強会の機会と場所を快くお受け頂いて、実現の運びとなりました。
どんなお勉強会になるか楽しみで、いまから私もワクワクして参加させていただきます。
技を盗むのが先方への礼儀
日頃、「和裁をお勉強したいのですが…」という電話での問合せに、「中途半端な気持ちなら、時間の無駄だからやめておきなさい。」という遠山先生。
その先生が「きつけ塾いちき」のために、朝から夕方まで一日空けて頂けるとのこと。ありがたいことです。
遠山流独特の和裁の流儀。
極意を盗むのが先方に対する礼儀…。堪能してまいりたいと思います。
遠山和裁着付け教室⇚クリック

 ●
● ●
●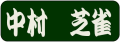 ●
●
 ●
●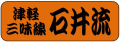 ●
● ●
●
 ●
● ●
●
まず、補整を作っていきます。
鹿児島の「花嫁着付け講座」が本格的に始まりました。
まず、着付けにとって肝心な「補整の作成」から始まります。
胸と腰とお尻の三点セット。それにピースもいろいろ作っていきます。
面倒だけれど、クリアーしたい最初の関門です。
自分で補整を作っていくからこそ、足りない部分が出てきたとき、すぐに対応出来るわけです。
次に「掛下」の帯結びです。
「掛下」の帯結びは文庫。
一般の文庫とは大きさと表情が少し異なります。
「手が覚える」と申しますが、くり返しお稽古しながらお稽古が続きます。
先日、「附下、留袖着付けの専門コース」の資格試験に合格された梅木さんは、ひきつづき「花嫁着付け」をお勉強されています。
「花嫁着付け」を受講したら、来年の成人式に向けて「振袖の着付け」も受講される予定です。
各種の着付け技術は共通する部分が多いもの。
今後この生徒さんの技術は、飛躍的に向上すると思われます。
プロ技術の階段を駆け上がっていきましょう。
下の写真は、掛下の文庫(受講生の作品です)

 ●
● ●
●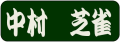 ●
●
 ●
●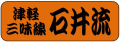 ●
● ●
●
 ●
● ●
●
玄宗皇帝や外国のお話も交えながら
学院長による「きもののTPOのお勉強会」は、きものの仕来りや決まり事などについての講義です。
十二単の紹介で海外に出かけていた頃の、外国の正装の決まり事についてのお話などもされ、楽しい講義になりました。
第一礼装の黒留袖などのお話では、中国の玄宗皇帝と楊貴妃のお話をされながら、「比翼の衿」の謂れなど、興味深く話されていました。
時代風俗衣裳の研究家として時代物の研究をしている市来学院長ならではの講義に、参加した受講生は質問などをして、有意義な時間を過ごされていたようです。
今回参加した受講生は、美容師の皆さまやメークアップアーティスト、他の教室の先生もいらして、お仕事に必要な知識を得ようと、真剣に聞かれていました。

 ●
● ●
●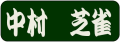 ●
●
 ●
●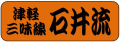 ●
● ●
●
 ●
● ●
●
きものの決まり事を学ぶ事は「きもの文化継承への道」
「きつけ塾いちき」は、最近頓に「きもの文化の崩壊」が顕著になっていると考えています。
例えば、貸衣裳の振袖の着付けを見た親御さんから次のようなクレームがよくあるそうです。
「帯から上の背縫いは身体の中心にあるが、お尻から裾にかけての背縫いがずれている。弁償すべきだ…」。考えられないクレームです。
着付けを知らないからおっしゃるのですが、それらにちゃんとお応えできる「担当者?」がいなくなっていることは深刻な現象です。
また、振袖でおトイレに行くときの方法を書いたきものの出版物で次のような事を平気で書いている冊子が多いことです。
いわく「振袖でおトイレに行くときには、邪魔になる袖を帯締めに挟んで…云々…」、こんなことをしたら振袖は着崩れるに決まっています。
なんという無謀な著者でしょうか。こんな「常識本?」が何冊も出版され、まかり通っているのです。
きものを専門にしている中でさえこの有様ですから、何とかしないと、などと焦りさえ感じます。
私たちは原点に帰って、「周りからきものの常識を知らしめていこう」と、従来から行なってきた「きもののTPOのお勉強会」を鹿児島でも始めました。
出来るだけ多くの人に、「きものの常識」や「着付けの常識」をしっかり学んで頂き、傾斜しつつある「きものの間違いの修正」に役立てたいと思っています。
きものの歴史の中で、決まりごとは少しずつ変わっていくものですが、昔から伝わる素晴らしい伝統を、利益のみをあげる…「為にする拝金主義」から守りたいものです。


 ●
● ●
●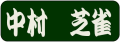 ●
●
 ●
●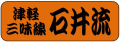 ●
● ●
●
 ●
● ●
●
舞踊・振袖着付けのプロフェッショナルを…
福岡で毎月行われている、「舞踊と振袖の着付け特別専門講座」二月の日程は、24日(水)から三日間です。
日程の内訳は、2月24日(水)と25日(木)の二日間は、早良区の「ももち文化センター」で、26日(金)は小倉新幹線口の「KMMビル」でそれぞれ開催されます。
それぞれの受講生の技術の程度に合わせて学んで頂くことはもちろんですが、本年度は特に、学んでいる受講生のみなさんが、プロとしての役割を果たせる実践的な実力を身に付けて頂きます。
楽しく学ぶこと、目的をもって学ぶこと、真剣に学ぶこと、仲間を思いやる心で学んでいきましょう。
2月の日程 をクリックしてください。
会場は超満席、拍手と大向うが…
2月14日(日)に、延岡向洋ライオンズクラブ主催「舞踊と歌謡とハワイアンの集い」が、延岡総合文化センターで行われました。
舞踊の部門で参加した「花柳流澄千瑠会」は、四演目で出演して、会場からは盛んな拍手と、「待ってました、スミチル、日本一!」などの大向うまで頂いていました。
この日、日本舞踊の他流派の皆さまも熱演されていました。
「きつけ塾いちき」は三名の衣裳方が着付けに伺い、「着流しに粋筋の貝ノ口」「はしょり着付けに新劇調のお太鼓結び」「袴の着付け」「裾引きの着付けに江戸前の柳結び」などを着せ付けさせて頂きました。
花柳流の皆さまお疲れさまでした。
いつもご用命いただきありがとうございます。
35年間で作り上げてきた、「着付け」と「着せ付け」の教室
SINCE1980。昨年、創業から35年周年を迎えました。
「次世代に、きもの文化を継承する」事が、私たち着付けに関わる者の使命です。
これまでに、「自分のきものを着れるようになりたい」という2000名近くの皆さまに、着付けをお教えしてまいりました。
また、私たちの教室には、「時代風俗衣裳」の着付けをお教えするというもう一つの歴史を積み上げてまいりました。
それは、遠く「卑弥呼の時代の貫頭衣(かんとうい)から、現代までの衣裳の歴史」を学び、「平安時代からの現代までの日本の衣裳の着付け」をお教えしてきたという歴史です。
この「時代風俗衣裳の研究」を通じて、「着せ付けという独自の分野」を切り開いてまいりました。
そんな中で生まれたのが、「十二単の着せ付け」、「花嫁の着せ付け」、「日本舞踊の着せ付け」、そして「振袖や正装の着せ付け」だったわけです。
次世代へ、振袖と舞踊着せ付けのプロフェッショナルを
これらの技術は、多くの皆さまに喜んでいただき、多くのご支持を頂いてまいりました。
現在は、九州の「着せ付けに関心のある一般のみなさん」はもちろんですが、「着付け教室の先生や学院長」、「美容師や美容院のオーナー」、「日本舞踊の名取や師範の先生方」、「貸衣裳の着せ付け師」、「呉服店の着せ付け担当者」、「若手の人形師」など、いろいろな皆さまが垣根を越えてお勉強にお越しになっています。
プロの皆さまが、ともに最高の技術を目指して研究している「講座」になっているわけです。
「きつけ塾いちき」は35周年を機に、この一年を「次世代に伝える着せ付けのプロフェッショナル養成」を大きな柱にして参りたいと思います。
着せ付けに関心のある方は、経験・未経験関係なく、お問い合わせください。
お待ちしています。 お問合せは、090-4489-9745 いちき まで
 ●
● ●
●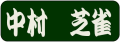 ●
●
 ●
●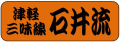 ●
● ●
●
 ●
● ●
●
「きつけ塾いちき」の衣裳方がお手伝い
延岡向洋ライオンズクラブ主催「舞踊と歌謡とハワイアンの集い」が、2月14日(日)に、延岡総合文化センターで行われます。
「きつけ塾いちき」の衣裳方は、花柳澄千瑠社中の着付けをさせて頂きます。
花柳澄千瑠会は、長年お付き合いをさせて頂いている皆さんです。
前日の13日(土)はリハーサル、14日(日)の本番は午前11時の開演となっています。
当日の入場料金は1,500円です。
関心のある方は是非お出かけ下さいませ。
これまでの澄千瑠会(Yahoo検索)

 ●
● ●
●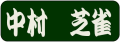 ●
●
 ●
●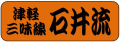 ●
● ●
●
 ●
● ●
●



















