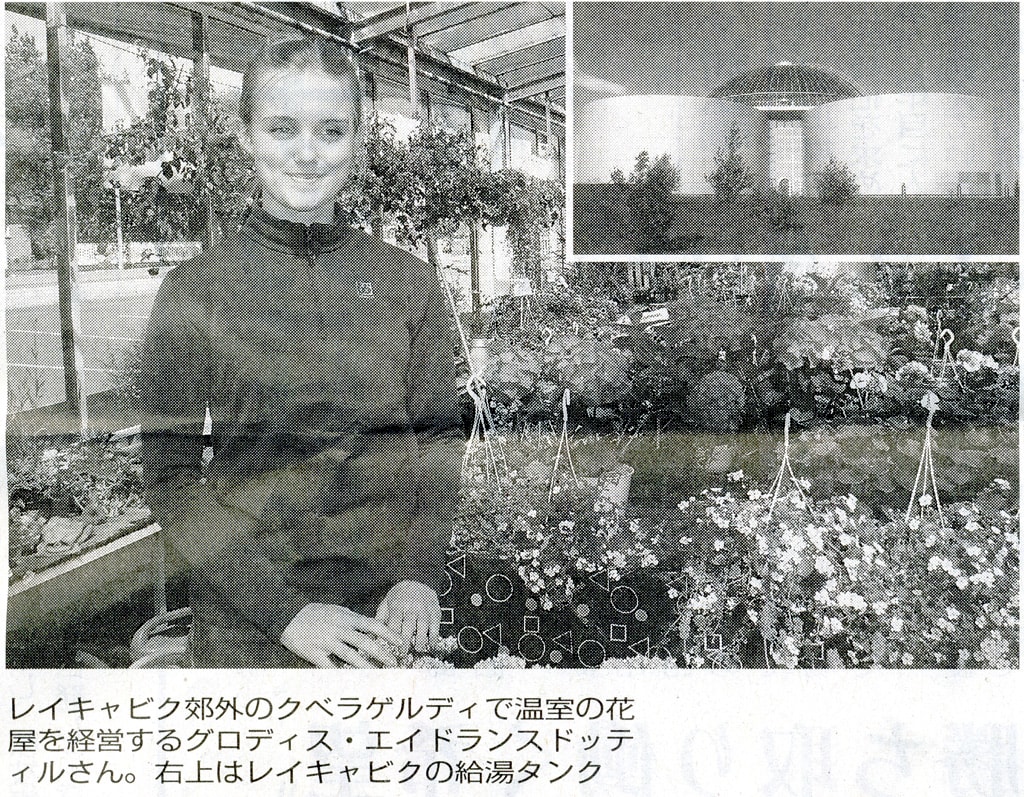大手メディアでなく「赤旗」がスクープ連発はなぜ?
FMラジオ番組 小木曽編集局長語る
「九州電力の『やらせメール』問題。さらに、佐賀県玄海町の町長の弟さんが社長をつとめる建設会社が九電から約54億円もの工事を受注していた事実…。これらのスクープを次々とモノにしたのは、いわゆる大手メディアと呼ばれる新聞社やテレビ局でもなく、日本共産党の機関紙『赤旗』だった!」
こんな紹介で、19日夜、FMラジオJ―WAVEのニュース番組「JAM THE WORLD」に、小木曽陽司・赤旗編集局長が登場。テーマはずばり「『しんぶん赤旗』とは?」。
ナビゲーター(進行役)の津田大介さん(ジャーナリスト)とリポーター高橋杏美さんとのあいだで、かわされたトークは―。

「赤旗」の役割 なぜ日刊紙必要か
中学時代に「しんぶん赤旗」を読んで、それが「物書き」になるきっかけになったという津田さん。「そういった『赤旗』がいま経営難になっているというのは非常に気になる。いろんなスクープをモノにしているんだけれども、そういうこと自体が知られていない。どういうメディアかお話をうかがえれば」
高橋 単純に経営が厳しいならば他の政党のように、(機関紙は)週1回とか、隔週とか、月1回とかの発行にしたらいいのかなとも思うんですが。
小木曽 週1回という点でいうと、うちには「赤旗」日曜版という独立した週刊新聞があります。100万部を超える部数を持っています。
ただ日刊紙についていいますと、単純な経営問題ではないんです。今度の「やらせメール」のようにタイムリーで、パンチの効いたスクープが威力を発揮できるのは日刊紙だからです。世界と日本は日々激しく動いているんですけれど、やはり社会を変えようという立場からそれを伝える「赤旗」日刊紙はどうしても必要だと思っているのです。
率直に言って今のマスメディアの状況の多くは「真実を伝える」、「権力を監視する」、というジャーナリズムの本来の使命を果たしているか少し疑問なところがあるんです。
そのもとでタブーなく真実を伝える「赤旗」日刊紙の役割は、共産党にとってはもちろんですが、日本社会にとっても必要じゃないかと思ってるんです。
やらせメール 「赤旗」に情報なぜ
話題は、九電の「やらせメール」問題に。津田さんは「これは日本の原子力行政のこれからに影響しかねない影響力をもつスクープだったと思う」とのべ、いきさつを詳しく聞きました。
津田 (他紙は)電力会社に遠慮して報じなかったのか、それとも完全に「赤旗」のスクープだったのか、どちらなんでしょうか?
小木曽 いくつかの新聞は情報は事前に入手して、九州電力にも確認を取っていたらしいんです。もちろん(九電側は)否定しましたけれど。しかし実際に記事にしてスクープしたのは「赤旗」だけでした。7月2日付の1面トップで「国主催の説明会 九電が“やらせ”メール」という大見出しで報じた。玄海原発の再稼働をめぐる説明会の正当性が問われる問題でした。ところがこれだけの大問題を他紙が追ってこなかったんですね。これはちょっとびっくりしました。
大手メディアがとりあげたのは、共産党の笠井亮議員の国会での追及を受け、九電の社長が謝罪した6日のことでした。
津田 この事実をつかんだのはいつだったんでしょうか?
小木曽 国による(佐賀県民への)説明会の直前に関係会社の内部資料と、関係者の証言を得ました。綿密な取材を重ねて、6月30日には九電の広報担当者に確認をしました。九電は「いっさいしておりません」という回答だったのですが、われわれは事実関係に確信を持っていましたので、報道に踏み切ったというのが経過です。
高橋 なぜ「赤旗」にそうした情報が集まってきたんですか?
小木曽 直接には福岡の共産党事務所に情報が寄せられたんです。情報を寄せられた方は、職場のなかで「九電はここまでやるのか」と話題になって、こんな行為は自分の会社のためにならないと意を決した。知人に相談したところ、共産党の事務所を紹介してくれたということです。いつでも権力と対峙(たいじ)して不正を追及してきた共産党への信頼があったからこそ、こういう内部告発があったのだと思っています。
東電会見 鋭い質問どのように
津田 「赤旗」というと最近印象的だったのが、原発事故が起こった当初、(東京電力の)記者会見の中継をネットで見ていて、鋭い質問をしていたのがフリーのジャーナリストや、海外メディアの特派員、もしくは「赤旗」の記者だった。東電側にとって厳しい質問をバシバシしていたと思うんですが、ああいった質問は、編集局長が方向性を指示されているんですか?
小木曽 あの質問に関していうと、原発担当の記者たちがいろいろ議論して会見にのぞんで質問したと聞きました。話題になったのが、3月26日の記者会見です。赤旗記者が、電源が失われた場合どうするのかを、国会で共産党の議員が質問していたのに、なぜ想定しなかったのかと質問をしたんです。東電の側からきちんとした答えがなくて、記者が何度も聞き返す。今度はフリーのジャーナリストも一緒になって答えてくださいと声をかける。いつもとちがった緊迫した記者会見になり、ネットで「赤旗GJ(グッド・ジョブ)」と話題になったようですね。
津田 「赤旗」とか共産党というのは、孤高の存在というか、あまりフリーの人との連携もしない印象があるんですけど、いまそういう新しい連携みたいな可能性もみえてきたんですかね。
小木曽 直接連携とっているわけではないのですが、やはり真実を追究するという点では一緒ですから、おのずとそういうことになるのではないでしょうか。
経営危機 どう打開するのか
後半は、「赤旗」日刊紙の“経営難”について、津田さんや高橋さんが、「赤旗」の最高部数は? 広告収入は? など率直に質問。小木曽氏は、発行部数では1970年代末から80年代はじめに日刊紙で60万部を維持していたこと、収入の大半を機関紙の売り上げが占め、部数減により日刊紙の経営が困難になっていることなどを丁寧に説明しました。
津田 (「赤旗」はこの間)大手メディアでは伝えられていないスクープの記事なんかも、出していたと思うんですが、そういったものの(部数増への)効果はなかったんですか。
小木曽 その時々に、紙面の価値を高めたり、政治を動かしたりするんですが、スクープを1回やったら、これだけの部数が増えるなどという、単純なものではないんですね。党の機関紙ですから、党員が増えてしっかりしないと、なかなか増えないというのはあるのですよ。
ただ私は、共産党はそれを乗り越える力をもっていると確信しています。いま日刊紙発行の危機を党員のみなさんや読者のみなさんに率直に訴えているんですけれど、この危機をなんとしても乗り切らないといけないと応えてくれる動きがずっと広がっています。
国民の探求に応える紙面を
津田氏は、インターネットや、デジタルなどで、ほかのメディアとの連携をふくめた展開を提唱。小木曽氏は、「研究しますので、ぜひお知恵を」と応じました。津田氏から、今後、読者獲得のためにはどんなことを考えているのかと問われ、次のようにのべました。
小木曽 やはり一番思うのは、今度の大震災・原発災害を契機にして、いま多くの国民がなにが真実だったのか、真実をみきわめたいという気持ち、日本は一体どういう国なんだということを知りたいという探求を始めていると思うのです。「赤旗」はそういうことに正面から応えられるような紙面を届けたいと思っています。
「しんぶん赤旗」日刊紙 2011年7月21日付掲載
民間のラジオ番組が赤旗の編集局長にインタビューする特集するってすごい世の中になりましたねえ!
小木曽さんが言っているように、激動する世の中、タイムリーに運動と世論、スクープなどを伝えて行く為には「日刊紙」は不可欠です。
それにしても、共産党なら大丈夫と内部告発をしてきたって事は嬉しいことですね。こんなことは、今回の原発問題に限らず、過去に幾度となく経験していることです。
ただし、スクープを一回やったからと言ってそれで単純に新聞が増えるってもんじゃないとリアルに見ています。
党員が増えてしっかししていないとなかなか増えないと・・・。
しかし、共産党はそれを乗り越える力を持っていると。そうです、それは綱領の力です。
「ペンは剣より強し」と言われたものです。今の時期、「しんぶん赤旗」の読者を増やすことが求められていますし、その条件はあるのではないでしょうか。
FMラジオ番組 小木曽編集局長語る
「九州電力の『やらせメール』問題。さらに、佐賀県玄海町の町長の弟さんが社長をつとめる建設会社が九電から約54億円もの工事を受注していた事実…。これらのスクープを次々とモノにしたのは、いわゆる大手メディアと呼ばれる新聞社やテレビ局でもなく、日本共産党の機関紙『赤旗』だった!」
こんな紹介で、19日夜、FMラジオJ―WAVEのニュース番組「JAM THE WORLD」に、小木曽陽司・赤旗編集局長が登場。テーマはずばり「『しんぶん赤旗』とは?」。
ナビゲーター(進行役)の津田大介さん(ジャーナリスト)とリポーター高橋杏美さんとのあいだで、かわされたトークは―。

「赤旗」の役割 なぜ日刊紙必要か
中学時代に「しんぶん赤旗」を読んで、それが「物書き」になるきっかけになったという津田さん。「そういった『赤旗』がいま経営難になっているというのは非常に気になる。いろんなスクープをモノにしているんだけれども、そういうこと自体が知られていない。どういうメディアかお話をうかがえれば」
高橋 単純に経営が厳しいならば他の政党のように、(機関紙は)週1回とか、隔週とか、月1回とかの発行にしたらいいのかなとも思うんですが。
小木曽 週1回という点でいうと、うちには「赤旗」日曜版という独立した週刊新聞があります。100万部を超える部数を持っています。
ただ日刊紙についていいますと、単純な経営問題ではないんです。今度の「やらせメール」のようにタイムリーで、パンチの効いたスクープが威力を発揮できるのは日刊紙だからです。世界と日本は日々激しく動いているんですけれど、やはり社会を変えようという立場からそれを伝える「赤旗」日刊紙はどうしても必要だと思っているのです。
率直に言って今のマスメディアの状況の多くは「真実を伝える」、「権力を監視する」、というジャーナリズムの本来の使命を果たしているか少し疑問なところがあるんです。
そのもとでタブーなく真実を伝える「赤旗」日刊紙の役割は、共産党にとってはもちろんですが、日本社会にとっても必要じゃないかと思ってるんです。
やらせメール 「赤旗」に情報なぜ
話題は、九電の「やらせメール」問題に。津田さんは「これは日本の原子力行政のこれからに影響しかねない影響力をもつスクープだったと思う」とのべ、いきさつを詳しく聞きました。
津田 (他紙は)電力会社に遠慮して報じなかったのか、それとも完全に「赤旗」のスクープだったのか、どちらなんでしょうか?
小木曽 いくつかの新聞は情報は事前に入手して、九州電力にも確認を取っていたらしいんです。もちろん(九電側は)否定しましたけれど。しかし実際に記事にしてスクープしたのは「赤旗」だけでした。7月2日付の1面トップで「国主催の説明会 九電が“やらせ”メール」という大見出しで報じた。玄海原発の再稼働をめぐる説明会の正当性が問われる問題でした。ところがこれだけの大問題を他紙が追ってこなかったんですね。これはちょっとびっくりしました。
大手メディアがとりあげたのは、共産党の笠井亮議員の国会での追及を受け、九電の社長が謝罪した6日のことでした。
津田 この事実をつかんだのはいつだったんでしょうか?
小木曽 国による(佐賀県民への)説明会の直前に関係会社の内部資料と、関係者の証言を得ました。綿密な取材を重ねて、6月30日には九電の広報担当者に確認をしました。九電は「いっさいしておりません」という回答だったのですが、われわれは事実関係に確信を持っていましたので、報道に踏み切ったというのが経過です。
高橋 なぜ「赤旗」にそうした情報が集まってきたんですか?
小木曽 直接には福岡の共産党事務所に情報が寄せられたんです。情報を寄せられた方は、職場のなかで「九電はここまでやるのか」と話題になって、こんな行為は自分の会社のためにならないと意を決した。知人に相談したところ、共産党の事務所を紹介してくれたということです。いつでも権力と対峙(たいじ)して不正を追及してきた共産党への信頼があったからこそ、こういう内部告発があったのだと思っています。
東電会見 鋭い質問どのように
津田 「赤旗」というと最近印象的だったのが、原発事故が起こった当初、(東京電力の)記者会見の中継をネットで見ていて、鋭い質問をしていたのがフリーのジャーナリストや、海外メディアの特派員、もしくは「赤旗」の記者だった。東電側にとって厳しい質問をバシバシしていたと思うんですが、ああいった質問は、編集局長が方向性を指示されているんですか?
小木曽 あの質問に関していうと、原発担当の記者たちがいろいろ議論して会見にのぞんで質問したと聞きました。話題になったのが、3月26日の記者会見です。赤旗記者が、電源が失われた場合どうするのかを、国会で共産党の議員が質問していたのに、なぜ想定しなかったのかと質問をしたんです。東電の側からきちんとした答えがなくて、記者が何度も聞き返す。今度はフリーのジャーナリストも一緒になって答えてくださいと声をかける。いつもとちがった緊迫した記者会見になり、ネットで「赤旗GJ(グッド・ジョブ)」と話題になったようですね。
津田 「赤旗」とか共産党というのは、孤高の存在というか、あまりフリーの人との連携もしない印象があるんですけど、いまそういう新しい連携みたいな可能性もみえてきたんですかね。
小木曽 直接連携とっているわけではないのですが、やはり真実を追究するという点では一緒ですから、おのずとそういうことになるのではないでしょうか。
経営危機 どう打開するのか
後半は、「赤旗」日刊紙の“経営難”について、津田さんや高橋さんが、「赤旗」の最高部数は? 広告収入は? など率直に質問。小木曽氏は、発行部数では1970年代末から80年代はじめに日刊紙で60万部を維持していたこと、収入の大半を機関紙の売り上げが占め、部数減により日刊紙の経営が困難になっていることなどを丁寧に説明しました。
津田 (「赤旗」はこの間)大手メディアでは伝えられていないスクープの記事なんかも、出していたと思うんですが、そういったものの(部数増への)効果はなかったんですか。
小木曽 その時々に、紙面の価値を高めたり、政治を動かしたりするんですが、スクープを1回やったら、これだけの部数が増えるなどという、単純なものではないんですね。党の機関紙ですから、党員が増えてしっかりしないと、なかなか増えないというのはあるのですよ。
ただ私は、共産党はそれを乗り越える力をもっていると確信しています。いま日刊紙発行の危機を党員のみなさんや読者のみなさんに率直に訴えているんですけれど、この危機をなんとしても乗り切らないといけないと応えてくれる動きがずっと広がっています。
国民の探求に応える紙面を
津田氏は、インターネットや、デジタルなどで、ほかのメディアとの連携をふくめた展開を提唱。小木曽氏は、「研究しますので、ぜひお知恵を」と応じました。津田氏から、今後、読者獲得のためにはどんなことを考えているのかと問われ、次のようにのべました。
小木曽 やはり一番思うのは、今度の大震災・原発災害を契機にして、いま多くの国民がなにが真実だったのか、真実をみきわめたいという気持ち、日本は一体どういう国なんだということを知りたいという探求を始めていると思うのです。「赤旗」はそういうことに正面から応えられるような紙面を届けたいと思っています。
「しんぶん赤旗」日刊紙 2011年7月21日付掲載
民間のラジオ番組が赤旗の編集局長にインタビューする特集するってすごい世の中になりましたねえ!
小木曽さんが言っているように、激動する世の中、タイムリーに運動と世論、スクープなどを伝えて行く為には「日刊紙」は不可欠です。
それにしても、共産党なら大丈夫と内部告発をしてきたって事は嬉しいことですね。こんなことは、今回の原発問題に限らず、過去に幾度となく経験していることです。
ただし、スクープを一回やったからと言ってそれで単純に新聞が増えるってもんじゃないとリアルに見ています。
党員が増えてしっかししていないとなかなか増えないと・・・。
しかし、共産党はそれを乗り越える力を持っていると。そうです、それは綱領の力です。
「ペンは剣より強し」と言われたものです。今の時期、「しんぶん赤旗」の読者を増やすことが求められていますし、その条件はあるのではないでしょうか。