



| まだ蕾の 沈丁花 がテラスを取り囲み、 テラスの一角の餌場は、 本館と同じ赤瓦の屋根を付けていた。 そこに群がっていた小雀たちは、 針で突ついたような啼音を立てて、 近付く本多と慶子の姿を見るなり翔った。 【三島由紀夫著 「暁の寺」~豊饒の海第3巻】 |
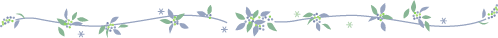
 日の出前の空は、
日の出前の空は、薄紫色のこんな優しい空に。
この空と同様、随分、
寒気の緩んだ朝となりました。
何でも3月中旬の気候とか。
そんな春の兆しを感じた
今朝、「匂い菫」 がいよいよ
首をもたげて 来ました。
【注 : 茎立(くくたち)】
一方、本当に長い事独り旅を
続けていた菫は、安心したように、ひっそりとその役目を終え・・。
長い事、お疲れ様!
ここにも菫たちのドラマがあるようですね。

 さて、今日の写真。
さて、今日の写真。昨日の公園のものです。
私の住んでいる山側は、
まだまだ開花していませんが、
こちら平野部の公園では
1輪、2輪と・・綻びつつ
あるようです。
今日などは暖かいですから、
一気に花開くかも知れませんね。
そうそう、そこでは沈丁花も
沢山の花芽を付け・・。
丁度、上記の引用文
そのままの光景が
繰り広げられていたものです。
それにしても小さな雀の事を
「小雀(こがら)」~なんて。
この年になって又、
1つ言葉を覚えました。
そんなこんなで・・。
一昨日に引き続き、今日も梅の事を。
昔の人が、いかに梅を愛していたかという事は、
先日の 【梅に鶯】 でも十分、感じ取れます。
もう1つ、学問の神様、菅原道真の 「飛梅伝説」 も、
あまりにも有名ですね。
前回の村上天皇と同様、道真も又、
梅をこよなく愛したと言います。
それは、大宰府に左遷される時、大切にしていた庭の梅の木に、
次のような別れの歌を贈った事でも分かりますね。
「東風吹かば匂ひおこせよ梅の花
あるじなしとて春を忘るな」
その梅が道真を慕って、遥か大宰府まで飛んで
行ったというのが、この伝説のいわれです。
何と言う壮大なロマンでしょう。
四季があるからこそ培われた
日本人の繊細な感性、素晴らしいですね。
季節は移ろい、厳寒の冬も必ず去って行きます。
先人は、他の花に先駆けて咲くこの梅の花に、
勇気と希望を貰った事でしょう。
今年は桜の花も、
例年とは違った目で眺める事が出来そうです。









