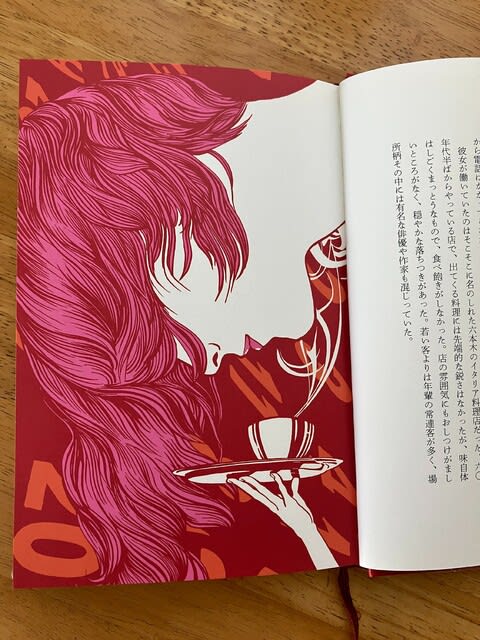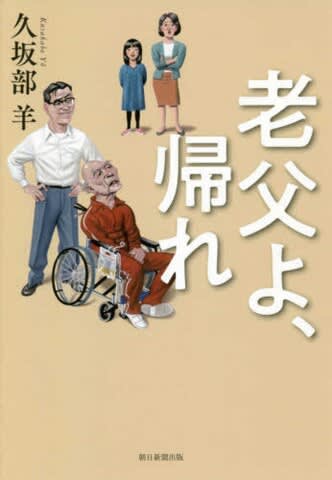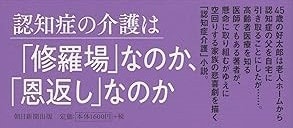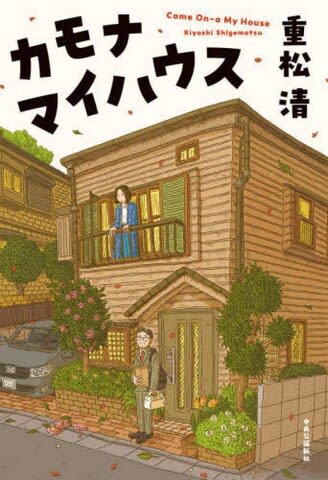夏川草介さんの『スピノザの診察室』
「神様のカルテ」に近い作品だろうと、図書室の書棚に鎮座していたからすぐに借りたわ。
主人公の雄町哲郎医師の飄々とした姿に見え隠れするある種の諦念、虚無感が見られることが
すごく印象的で。
それこそ将来を嘱望された凄腕医師で、患者からは慕われ、同僚からは医師として一目置かれ、
大学の准教授からもいまだにアドバイスを求められというスーパードクターな医師なのにね。
スーパードクターがそのままのスーパーぶりで行動していたら鼻持ちならないもの。それが。

雄町哲郎は京都の町中の地域病院で働く内科医である。三十代の後半に差し掛かった時、
最愛の妹が若くしてこの世を去り、 一人残された甥の龍之介と暮らすためにその職を得たが、
かつては大学病院で数々の難手術を成功させ、将来を嘱望された凄腕医師だった。
五橋看護師いうところの
「ここの仕事は、難しい病気を治すことじゃなくて、治らない病気にどうやって付き合って
いくかってことだから、もともとわかりにくいことをやっているの」
そんな京都の町中の原田病院に勤務するそれぞれ個性豊かな同僚医師の面々は、
理事長の原田百三のもと、鍋島外科医 秋鹿淳之介精神科医 中将亜矢外科医。
そして大学病院の花垣准教授 消化器内科医 研修医南茉莉(まつり)
物語の縦軸がこれらの医師との関係なら、横軸は雄町哲郎医師の患者との関係。
終末を迎えた患者との会話に雄町の信念がくっきりと見えて、私も患者として
雄町医師に診ていただきたいな、なんてことを思ったわけ。
物語に登場するそれぞれの患者に雄町が掛けた言葉の抜き書き。
どの言葉も雄町の根底にある信念や人間味があふれ出ていてしんとする。
坂崎幸雄 胃がん 癌性疼痛に 自宅療養
”こらあ、きついもんでんな、先生”
”そろそろ幕引きですわ。薬、増やしてくれはりますか”
”薬を増やします”
坂崎がほっとしたようにうなずいた。
うなずいてから妻の方に、震える顔を向け、小さく笑ってみせた。
(亡くなった日、雄町は)戸口に向き直って一礼する。
―お疲れさまでした。
矢野きくえ 90歳
「食べたほうがええかねぇ、先生」
「いや無理はしなくてもいいでしょう、きくえさん。人間、食べたくない日だってあります。
ただ、おじいちゃんのお迎えはまだかな」
「そら残念や。先生は、こんなおばあちゃんにも、まだまだいろんな治療をするんか?」
「動ける人には、それなりに力を尽くすというのが私の方針です」
「動けんようになったら?」
「そのときは」
「静かにおじいちゃんを待ちますか」
今川陶子 膵癌 抗がん剤を使用せず自宅療養
「六道まいりも始まりました。主人が迎えに来てはるみたいですわ」
「毎年毎年、主人を送り返すのも寂しいもんですさかい、今年はついて行ってもええかと
思うてます。さすがにもうがんばれやしません」
「(略)がんばらなくても良いのです。ただ、あまり急いでもいけません」
「あっちの世界への道は基本的に一方通行です。(略)
せっかくこちらにいるのですから、あまり急ぐのも、もったいないと思います」
黒木勘蔵 脳梗塞 自宅 骨董屋息子が介護
「『親父がはよ逝ってくれへんと面倒見る俺の方も大変や』なんて、いつもの軽口きいてた
くらいなんですわ・・・・、それがほんまに逝ってしまうなんて・・・・」
「それで良かったんですよ」
「息子さんがいつも通りに振舞っていた。おかげで、勘蔵さんはいつも通りの安心した
眠りの中で逝ったのでしょう」
「日々の介護はとても大変だったと思います。本当にお疲れさまでした」
「そないに言うてくれますか、先生は」「先生、ほんまおおきに・・・・」
中でも最も印象に残った患者が
辻新次郎72歳 アルコール性肝硬変 食道静脈瘤破裂
内服治療だけでは限界があり、今後、定期的な内視鏡検査と追加治療が必要、
と言われているのに「身の丈に合った薬だけもろうて、それで悪くなったら、
相方のところに逝こうと思うてる」と、経済状況が許さない治療を拒否する。
「このままにしといてくれへんんか、先生」
深い諦観があったが、暗い絶望は見えなかった。
人生の終着駅で、あの世行きの列車の到着をのんびりと待っているような、
のどかな旅人の風情であった。
辻は恐れていたようにひとり自宅で静脈瘤破裂のために亡くなる。
期限切れの免許証の裏に追加された大きな文字「おおきに、先生」
”先生のとこやったら、俺は安心して逝けそうな気がするんですわ” 声だけが降ってくる。
検視に立ち会った巡査が言う。
「財布の中にそんなあったかい言葉を抱えたまま、死んでいけるってのは、結構幸せな
ことなんじゃないかと思います。勝手な話ですが、うらやましいくらいだ」
「おおきに、先生、か。いい言葉ですな」
「本当に、うらやましいくらいだ」
私も巡査と同じような心持になって、辻新次郎さんの姿が見えて泣けてきそうになった。

雄町先生は、なかなかに難しいことをいとも簡単に話す。
「たとえ病が治らなくても、仮に残された時間が短くても、人は幸せに過ごすことができる。
…そのために自分ができることは何かと、私はずっと考えているんだ」
「人の幸せはどこから来るのか・・・」
私たちにできることは、「暗闇で凍える隣人に、外套をかけてあげることなんだよ」
そんなことを言う。できるのか、そんなこと難しいわ、できないわ、凡人の私には。
京都の銘菓 「長五郎餅」「阿闍梨餅」「矢来餅」がなかなかいいお仕事するの。
きっと続編が刊行されるはずと期待している。
原田病院の個性あふれる医師たちについてももっと知りたいのよ。

 「カフネ」阿部暁子(講談社)
「カフネ」阿部暁子(講談社) 「スモールワールズ」一穂ミチ(講談社)
「スモールワールズ」一穂ミチ(講談社) 「百年の孤独」ガブリエル・ガルシア=マルケス(新潮社)
「百年の孤独」ガブリエル・ガルシア=マルケス(新潮社) 「宙わたる教室」伊与原新(文藝春秋)
「宙わたる教室」伊与原新(文藝春秋) 「spring」恩田陸(筑摩書房)
「spring」恩田陸(筑摩書房)












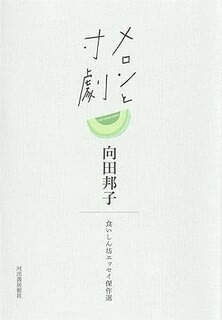











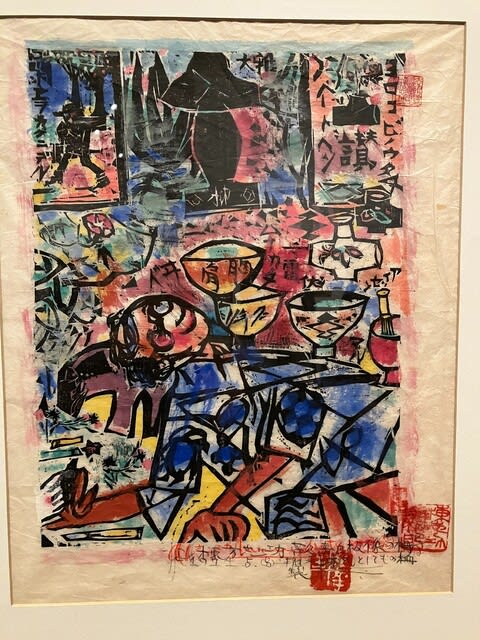









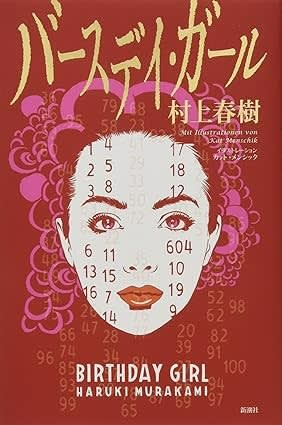 帯が付くと
帯が付くと