小沢さんは、余り表に出て来なくて、しかもとても饒舌とも言えませんから、世間ではキャラクターが分かりにくくて、それがまた悪役イメージを増幅させているようなところがあります。それでも、時折、漏れ聞こえてくる発言を拾ってみると、ちょっとびっくりするような異形を垣間見せます。その一つは、先日、小沢一郎政治塾で、昭和初期の旧・日本軍について、「捕虜になった途端に軍事機密も全部話すなど、全く秩序のない烏合の衆に化したと記載がある。帝国陸海軍の規律が、天皇陛下の名を借りて、抑え付けられた結果だ」という見方を披露したことです。国民を代表する与党の代議士でありながら、先日は、中国の要人のわがままを聞いて、あろうことか天皇陛下を顎で使うかのような、皇室伝統(天皇制と言えばサヨク用語になってしまうので、言い換えることにしています)を尊重しない不遜さで世間を驚かせたことが記憶に新しい通り、この人の精神構造は、一般の日本人のそれとはかなりかけ離れているようです。
折りしも、「日本兵捕虜は何をしゃべったか」(山本武利著)という本を読んだばかりで、感銘を新たにしていたので、小沢さんの発言が余計に引っかかりました。
さて、この本で、著者は、アメリカ国立公文書館にある日本兵捕虜関係の資料を丹念に掘り起こし、アメリカが、太平洋の戦域において6千人もの日系二世の情報兵を動員し(白人の数は僅かに7百人)、捕虜や遺棄文書から貴重な情報を獲得して、すぐさま前線にフィードバックし、自軍の作戦に役立てるというサイクルを、実にシステマティックに実行していたことを実証しています。太平洋戦争の帰趨は、軍事力や経済力といったハード面での彼我の格差によって決定したのは事実ですが、他方、諜報戦や情報戦といったソフト面での巧拙もまた日本の敗戦を加速したこと、しかもアメリカが情報戦において日本に勝っていたのは、電波技術の優劣や暗号解読の努力もさることながら、前線での軍機漏洩という単純で即物的な情報の束に裏打ちされていたという事実を知るに及んで、愕然とさせられます。
こうした恥ずべき事態に至った日本兵捕虜の行動様式に関して、アメリカ人が摩訶不思議でなかなか理解できなかったこととして挙げているのは、先ず第一に、日本兵が、作戦や部隊の編成・兵力・布陣や戦意などの機密情報を事細かに日記や日誌や手紙に書き記している上に、それらを作戦命令や作戦地図や部隊配置図などとともに戦場に携えていたこと(そのため戦場の死傷者や捕虜から膨大な情報が流出したこと)、第二に、日本兵は、捕虜となった当初こそ警戒し黙秘したり出鱈目を喋るのですが、やがて殺害されないことが分かり、更に食事や待遇が良いことに驚き、感謝の念を抱き始めると、アメリカ側の厚意に報いるかのように、自軍の情報を知る限り洗いざらい喋り、携帯する文書類に解説や分析まで付け加え、更にプロパガンダやスパイ活動への協力すら申し出たということでした。小沢さんの言い方によると、秩序のない烏合の衆に成り下がったということになりますが、これは一体どうしたことでしょう。
多数の日本兵捕虜の対応をしたあるアメリカの情報将校は、捕虜の訊問を積み重ねる中で、日本兵に情報守秘の姿勢が欠如しているのは、軍隊で受けた教育のせいではないかと結論づけています。ご存知の通り、日本兵は「戦陣訓」として「生きて虜囚の辱めを受けず、死して罪禍の汚名を残すことなかれ」といった武士道イデオロギーを叩き込まれました。確かに捕虜になって自殺を試みた人も中にはいたようですが(それもまた、自殺ゼロのアメリカには驚きだったようですが)、実際には殆どの日本兵は、人間の本性として簡単には自殺することが出来ず、さりとて軍からは、捕虜となれば自殺せよと教え込まれても、それ以上には軍人としての対処の仕方を教えられていませんでした。一方で、降伏は自身のみならず親兄弟など家族にとっても恥辱であるということだけは散々叩き込まれ、捕虜となることは、故郷ひいては祖国日本から排除されて(実際に「軍の辞書」には「捕虜」の文字がなく、全て戦死と見なされた)、日本への帰国の途が閉ざされることをも意味していました。その結果、捕虜となった日本兵は、むしろ死亡したと両親らに思われることを望み、日本への帰国を諦めるばかりか、帰国を望もうとせず、日本以外(それが敵国であろうとも)で生き延びる道を考え始め、最終的に外国に移住することを希望するほどだったというわけです。このあたりの事情は、日本兵捕虜が本名を決して名乗らず、もし捕虜になった事実が故郷や祖国に知れると、両親や家族が世間から不名誉な扱いを受けるのではないかということを最も恐れたというエピソードからも、察することが出来ます。
戦時中は、そういった極めて異常な精神状態に置かれていたにも係わらず、捕虜の調書から、日本兵に精神障害が少ないことも、アメリカからは驚きの念をもって迎えられました。ベトナムからの帰還兵についてもよく言われたことですが、アメリカ兵の約30%は何らかの神経病を患い、本国で治療を受ける必要があるらしいのですが、日本軍の病院の精神科は閑散としていたというのです。このことから、あるアメリカの捕虜収容所の将校は、日本兵が、命令依存の習慣や強制に慣らされて、つまるところ人間性を放棄し、精神の自殺を行っていたからこそ、精神的病気に至らなかったのではないかと分析しています。ちょっと極端ではありますが、アメリカ人の個人主義に対して、日本の集団主義と、よく対比して言われるのは、私としても、日本人が自我を半分捨てて集団の意思に委ねている(自我の半分が溶けて集団の意思と同一化している)のではないかと思っており、そうした現代の日本にも繋がるような国民性のありようとして、なかなか興味深く感じました。
実は、日本人の守秘性については、織田信長の時代に、ルイス・フロイスが、日本人の礼節を厳格に重んじる特性をほめそやす一方で、生来秘密を守ることができず信用のおけぬ国民だとも述べているそうで、かなり根深いものがありそうです。
この本で最も印象深いメッセージは、以上を踏まえ、日本兵捕虜から得た情報を最大限活用したのが、誰あろう南西太平洋方面の連合国軍総司令官だったマッカーサーで、アメリカ(GHQ)は、こうした戦時中の日本兵捕虜への対応によって、占領後の日本ならびに日本人への対応のノウハウを学んだのではないかという指摘でした。確かにGHQによる日本占領は、日本人の全てを捕虜にしたようなものです。だからこそアメリカは、日本兵捕虜への待遇と同じように、降伏後の餓死寸前の日本人に対して、極めて寛大に食料や医薬品や衣料を供給し、天皇陛下の戦争責任を追及しようとせず(日本兵捕虜は殆ど例外なく天皇陛下への崇拝の気持ちを抱き、天皇陛下に訊問が及ぶと強い反発を示したそうです)、結果、占領軍に対して感謝の念を催さしめ、日本人を懐柔し得たのでしょう。
新書で軽く読み飛ばせる本ですが、戦中そして終戦直後だけではなく、今もなお連綿と続く、日本人の業のようなものを感じさせられ、ずしりと心に重く響く内容をもった本でした。
折りしも、「日本兵捕虜は何をしゃべったか」(山本武利著)という本を読んだばかりで、感銘を新たにしていたので、小沢さんの発言が余計に引っかかりました。
さて、この本で、著者は、アメリカ国立公文書館にある日本兵捕虜関係の資料を丹念に掘り起こし、アメリカが、太平洋の戦域において6千人もの日系二世の情報兵を動員し(白人の数は僅かに7百人)、捕虜や遺棄文書から貴重な情報を獲得して、すぐさま前線にフィードバックし、自軍の作戦に役立てるというサイクルを、実にシステマティックに実行していたことを実証しています。太平洋戦争の帰趨は、軍事力や経済力といったハード面での彼我の格差によって決定したのは事実ですが、他方、諜報戦や情報戦といったソフト面での巧拙もまた日本の敗戦を加速したこと、しかもアメリカが情報戦において日本に勝っていたのは、電波技術の優劣や暗号解読の努力もさることながら、前線での軍機漏洩という単純で即物的な情報の束に裏打ちされていたという事実を知るに及んで、愕然とさせられます。
こうした恥ずべき事態に至った日本兵捕虜の行動様式に関して、アメリカ人が摩訶不思議でなかなか理解できなかったこととして挙げているのは、先ず第一に、日本兵が、作戦や部隊の編成・兵力・布陣や戦意などの機密情報を事細かに日記や日誌や手紙に書き記している上に、それらを作戦命令や作戦地図や部隊配置図などとともに戦場に携えていたこと(そのため戦場の死傷者や捕虜から膨大な情報が流出したこと)、第二に、日本兵は、捕虜となった当初こそ警戒し黙秘したり出鱈目を喋るのですが、やがて殺害されないことが分かり、更に食事や待遇が良いことに驚き、感謝の念を抱き始めると、アメリカ側の厚意に報いるかのように、自軍の情報を知る限り洗いざらい喋り、携帯する文書類に解説や分析まで付け加え、更にプロパガンダやスパイ活動への協力すら申し出たということでした。小沢さんの言い方によると、秩序のない烏合の衆に成り下がったということになりますが、これは一体どうしたことでしょう。
多数の日本兵捕虜の対応をしたあるアメリカの情報将校は、捕虜の訊問を積み重ねる中で、日本兵に情報守秘の姿勢が欠如しているのは、軍隊で受けた教育のせいではないかと結論づけています。ご存知の通り、日本兵は「戦陣訓」として「生きて虜囚の辱めを受けず、死して罪禍の汚名を残すことなかれ」といった武士道イデオロギーを叩き込まれました。確かに捕虜になって自殺を試みた人も中にはいたようですが(それもまた、自殺ゼロのアメリカには驚きだったようですが)、実際には殆どの日本兵は、人間の本性として簡単には自殺することが出来ず、さりとて軍からは、捕虜となれば自殺せよと教え込まれても、それ以上には軍人としての対処の仕方を教えられていませんでした。一方で、降伏は自身のみならず親兄弟など家族にとっても恥辱であるということだけは散々叩き込まれ、捕虜となることは、故郷ひいては祖国日本から排除されて(実際に「軍の辞書」には「捕虜」の文字がなく、全て戦死と見なされた)、日本への帰国の途が閉ざされることをも意味していました。その結果、捕虜となった日本兵は、むしろ死亡したと両親らに思われることを望み、日本への帰国を諦めるばかりか、帰国を望もうとせず、日本以外(それが敵国であろうとも)で生き延びる道を考え始め、最終的に外国に移住することを希望するほどだったというわけです。このあたりの事情は、日本兵捕虜が本名を決して名乗らず、もし捕虜になった事実が故郷や祖国に知れると、両親や家族が世間から不名誉な扱いを受けるのではないかということを最も恐れたというエピソードからも、察することが出来ます。
戦時中は、そういった極めて異常な精神状態に置かれていたにも係わらず、捕虜の調書から、日本兵に精神障害が少ないことも、アメリカからは驚きの念をもって迎えられました。ベトナムからの帰還兵についてもよく言われたことですが、アメリカ兵の約30%は何らかの神経病を患い、本国で治療を受ける必要があるらしいのですが、日本軍の病院の精神科は閑散としていたというのです。このことから、あるアメリカの捕虜収容所の将校は、日本兵が、命令依存の習慣や強制に慣らされて、つまるところ人間性を放棄し、精神の自殺を行っていたからこそ、精神的病気に至らなかったのではないかと分析しています。ちょっと極端ではありますが、アメリカ人の個人主義に対して、日本の集団主義と、よく対比して言われるのは、私としても、日本人が自我を半分捨てて集団の意思に委ねている(自我の半分が溶けて集団の意思と同一化している)のではないかと思っており、そうした現代の日本にも繋がるような国民性のありようとして、なかなか興味深く感じました。
実は、日本人の守秘性については、織田信長の時代に、ルイス・フロイスが、日本人の礼節を厳格に重んじる特性をほめそやす一方で、生来秘密を守ることができず信用のおけぬ国民だとも述べているそうで、かなり根深いものがありそうです。
この本で最も印象深いメッセージは、以上を踏まえ、日本兵捕虜から得た情報を最大限活用したのが、誰あろう南西太平洋方面の連合国軍総司令官だったマッカーサーで、アメリカ(GHQ)は、こうした戦時中の日本兵捕虜への対応によって、占領後の日本ならびに日本人への対応のノウハウを学んだのではないかという指摘でした。確かにGHQによる日本占領は、日本人の全てを捕虜にしたようなものです。だからこそアメリカは、日本兵捕虜への待遇と同じように、降伏後の餓死寸前の日本人に対して、極めて寛大に食料や医薬品や衣料を供給し、天皇陛下の戦争責任を追及しようとせず(日本兵捕虜は殆ど例外なく天皇陛下への崇拝の気持ちを抱き、天皇陛下に訊問が及ぶと強い反発を示したそうです)、結果、占領軍に対して感謝の念を催さしめ、日本人を懐柔し得たのでしょう。
新書で軽く読み飛ばせる本ですが、戦中そして終戦直後だけではなく、今もなお連綿と続く、日本人の業のようなものを感じさせられ、ずしりと心に重く響く内容をもった本でした。














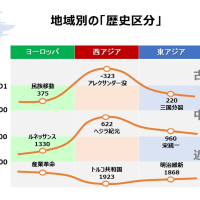




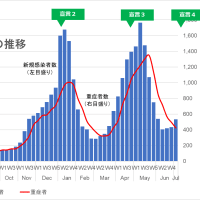






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます