前回は、集団で異常な夢を見ていただけのことではないかと書きました。確かに、大いなる共同幻想であったことは間違いありません。今では、勝算のない無謀な戦争に突入したというのがほぼ定説ですし、当時においても、開戦直前の夏、国家主導で総力戦研究所という組織に軍人・文官・民間から36名の若手エリートを集め、「日米もし戦わば」の命題のもとに数ヶ月にわたって行わせたシミュレーションによれば、奇襲攻撃で緒戦は勝利するが、物量において劣勢な日本に勝機はなく、長期戦となって敗戦に至る…という、驚くほど史実に近い結論に至っていたことが「昭和16年夏の敗戦」(猪瀬直樹著)の中で明らかにされています。
一方で、一種の全体主義国家で国民の誰もが窮乏をものともせず総力戦を覚悟し得る日本(いわばハリネズミ)と、民主主義国家で個人主義が根強く、戦争への関与には世論の批判もあって限定的とならざるを得ないアメリカ(いわば巨象)とでは、戦争に割ける国力の単純比較は難しい(実際に太平洋戦線において物量にモノを言わせ戦力が逆転し始めたのは中盤以降のことで、緒戦の躓きがあったればこそ)。しかもアメリカは、大西洋と太平洋とに戦力を二分され、更に西南太平洋にアメリカ軍を引き付けて戦う日本の戦法に従って、地の利がないのも明らかでした。「太平洋戦争は無謀な戦争だったのか」(ジェームズ・ウッド著)の中で、このアメリカの歴史学者は、開戦へと日本を導いた決断は必ずしも非合理的とは言えず、むしろ追い込まれた状況下で考え抜かれたベストのタイミングだったこと、その後いくつかの戦局でもっと巧妙な戦い方が出来たはずであることを検証し、壊滅的な敗北を免れることは可能だったのではないかと述べています。もとより当時の一般の人々は大した情報を持っていたわけではなく、戦争はデータだけではなく、やってみなければ分からないところがあると主張する人がいてもおかしくない状況だったのでしょう。
歴史は、将来に活かしてこそ歴史としての意味がありますが、現代の目で裁くべきではないと思ってきました。結果を知る現代人の目線は所詮は後知恵に過ぎないからで、当時の人たちが必ずしも必要十分な判断材料をもっていたわけではない中で下した意思決定には一定の敬意を払ってしかるべきでしょう。また、大きな事件の後は価値観が大きく変容を来たすこともあり、そもそも同じ土俵で議論すること自体が困難なこともよくあることです。たとえば、本来、喧嘩は両成敗であり、戦争は外交の延長に位置づけられ、「戦争は他の手段をもってする政治の継続にほかならない」(クラウゼビッツ)のが伝統的な考え方ですが、第一次大戦を機に、侵略戦争を新たに定義し、戦争責任を追及するといったように、戦争や平和に対する考え方は変りつつあり、戦間期はその過渡期にありました。逆に言うと新旧混交の時代であり、現代と比較すれば、空気はかなり異なっていたことでしょう。自由や民主主義に対する見方に至っては、現代とは格段に違っていたことでしょうし、戦後の民主教育の名のもとに、左翼的思想が私たちの戦争観を歪めてきました。
前回引用した「日本のいちばん長い夏」(半藤一利編)における座談会をきっかけとして、同じ作者が、昭和20年8月14日の正午から翌15日の正午までの24時間における主だった政策決定者の行動を時系列的に追いかけたドキュメンタリー「日本のいちばん長い日」(半藤一利著)を読むと、開闢以来負けたことがなかった日本の「敗北」を巡って、政権を取り巻く人々の心が大いに揺れていたことが分かります。それはまさに戦争観、更には国家観や人生観のせめぎ合いでもあったでしょう。私たちはともすれば海軍提督三部作(「米内光政」「山本五十六」「井上成美」いずれも阿川弘之著)に代表されるように、開明派の海軍に対する固陋頑迷な主戦派の陸軍という単純な図式で捉えがちで、現に終戦工作においても、和平を説く鈴木首相・海相・外相が、飽くまで徹底抗戦にこだわる陸相をなだめる構図ですが、ここでのキーマンである阿南陸軍大臣が、なかなかに印象深い人物として描かれています。
ポツダム宣言受諾にあたって、阿南大臣は、「無条件」ではなく、①保障占領は出来るだけ小範囲で短期間に、②武装解除と③戦犯処置は日本人の手に任せること、という三つの条件に拘ってなかなか譲ろうとしなかったのは、軍人たる部下のプライドを気遣ったものだろうと想像されます。終戦の詔勅(玉音放送)の文言を閣議で協議した際、当初、「戦勢日に非なり」とネガティブに表現されていた戦局見通しを、阿南大臣は決して認めようとせず、「戦局必ずしも好転せず」に変えるべしと最後まで譲らなかったのは、大本営の情報操作を最後まで徹底すると言うより、戦場で艱難辛苦に耐えつつ、まさに降伏を受け入れる直前まで戦い続ける兵士たちの気持ちを慮ったものだろうと想像されます。阿南大将のもとに陸軍は一つにまとまり、阿南さんの心一つでどうにでもなる態勢だと言われながら、陸軍大臣の職を辞することなく、終戦の覚悟を決めた鈴木首相を支え続け、威風堂々、陸軍としての立場は主張しつつ、部下の暴走(クーデター)は決して許さず、承詔必謹の方針を貫いて、最後はひとりで責任を取って自決されました。自決の数時間前に陸軍省・軍事課長に「若い立派な軍人をなんとか生き残るようにしてもらいたい」「軍がなくても日本の国は大丈夫、滅びるものか」と言い残し、その軍事課長は、戦後、復員兵の手配に尽力したといいます。皇国不滅を信じて徹底抗戦にはやる軍隊を統率し、無条件降伏という軍人として最大の屈辱を受け入れさせるのは、私たちには想像し得ない難しさがあったろうことを思うと、ここに軍人の一つの鑑を見る思いです。終戦当時の首相と陸相である鈴木貫太郎と阿南惟幾は、昭和4年夏から8年夏までの4年間、侍従長と侍従武官として昭和天皇のおそばにつかえ、三人が互いによく知る仲だったというのが歴史の妙だというようなことを、半藤一利さんは「~夏」の方で述べておられますが、歴史は、時にこうした気まぐれを潜ませるものなのですね。
戦後世代の私たちにとって、8月15日をいくら「終戦」記念日と呼んだところで、「敗戦」がア・プリオリなわけですが、それまで「敗戦」の二文字を知らなかった人たちが、「無条件降伏」を決断し、日本国及び日本人の運命に重大な危機を及ぼしかねない「敗戦」を受け入れることの重みを、僅かながらも垣間見て、「戦争」を見る視点がちょっと変った私でした。
一方で、一種の全体主義国家で国民の誰もが窮乏をものともせず総力戦を覚悟し得る日本(いわばハリネズミ)と、民主主義国家で個人主義が根強く、戦争への関与には世論の批判もあって限定的とならざるを得ないアメリカ(いわば巨象)とでは、戦争に割ける国力の単純比較は難しい(実際に太平洋戦線において物量にモノを言わせ戦力が逆転し始めたのは中盤以降のことで、緒戦の躓きがあったればこそ)。しかもアメリカは、大西洋と太平洋とに戦力を二分され、更に西南太平洋にアメリカ軍を引き付けて戦う日本の戦法に従って、地の利がないのも明らかでした。「太平洋戦争は無謀な戦争だったのか」(ジェームズ・ウッド著)の中で、このアメリカの歴史学者は、開戦へと日本を導いた決断は必ずしも非合理的とは言えず、むしろ追い込まれた状況下で考え抜かれたベストのタイミングだったこと、その後いくつかの戦局でもっと巧妙な戦い方が出来たはずであることを検証し、壊滅的な敗北を免れることは可能だったのではないかと述べています。もとより当時の一般の人々は大した情報を持っていたわけではなく、戦争はデータだけではなく、やってみなければ分からないところがあると主張する人がいてもおかしくない状況だったのでしょう。
歴史は、将来に活かしてこそ歴史としての意味がありますが、現代の目で裁くべきではないと思ってきました。結果を知る現代人の目線は所詮は後知恵に過ぎないからで、当時の人たちが必ずしも必要十分な判断材料をもっていたわけではない中で下した意思決定には一定の敬意を払ってしかるべきでしょう。また、大きな事件の後は価値観が大きく変容を来たすこともあり、そもそも同じ土俵で議論すること自体が困難なこともよくあることです。たとえば、本来、喧嘩は両成敗であり、戦争は外交の延長に位置づけられ、「戦争は他の手段をもってする政治の継続にほかならない」(クラウゼビッツ)のが伝統的な考え方ですが、第一次大戦を機に、侵略戦争を新たに定義し、戦争責任を追及するといったように、戦争や平和に対する考え方は変りつつあり、戦間期はその過渡期にありました。逆に言うと新旧混交の時代であり、現代と比較すれば、空気はかなり異なっていたことでしょう。自由や民主主義に対する見方に至っては、現代とは格段に違っていたことでしょうし、戦後の民主教育の名のもとに、左翼的思想が私たちの戦争観を歪めてきました。
前回引用した「日本のいちばん長い夏」(半藤一利編)における座談会をきっかけとして、同じ作者が、昭和20年8月14日の正午から翌15日の正午までの24時間における主だった政策決定者の行動を時系列的に追いかけたドキュメンタリー「日本のいちばん長い日」(半藤一利著)を読むと、開闢以来負けたことがなかった日本の「敗北」を巡って、政権を取り巻く人々の心が大いに揺れていたことが分かります。それはまさに戦争観、更には国家観や人生観のせめぎ合いでもあったでしょう。私たちはともすれば海軍提督三部作(「米内光政」「山本五十六」「井上成美」いずれも阿川弘之著)に代表されるように、開明派の海軍に対する固陋頑迷な主戦派の陸軍という単純な図式で捉えがちで、現に終戦工作においても、和平を説く鈴木首相・海相・外相が、飽くまで徹底抗戦にこだわる陸相をなだめる構図ですが、ここでのキーマンである阿南陸軍大臣が、なかなかに印象深い人物として描かれています。
ポツダム宣言受諾にあたって、阿南大臣は、「無条件」ではなく、①保障占領は出来るだけ小範囲で短期間に、②武装解除と③戦犯処置は日本人の手に任せること、という三つの条件に拘ってなかなか譲ろうとしなかったのは、軍人たる部下のプライドを気遣ったものだろうと想像されます。終戦の詔勅(玉音放送)の文言を閣議で協議した際、当初、「戦勢日に非なり」とネガティブに表現されていた戦局見通しを、阿南大臣は決して認めようとせず、「戦局必ずしも好転せず」に変えるべしと最後まで譲らなかったのは、大本営の情報操作を最後まで徹底すると言うより、戦場で艱難辛苦に耐えつつ、まさに降伏を受け入れる直前まで戦い続ける兵士たちの気持ちを慮ったものだろうと想像されます。阿南大将のもとに陸軍は一つにまとまり、阿南さんの心一つでどうにでもなる態勢だと言われながら、陸軍大臣の職を辞することなく、終戦の覚悟を決めた鈴木首相を支え続け、威風堂々、陸軍としての立場は主張しつつ、部下の暴走(クーデター)は決して許さず、承詔必謹の方針を貫いて、最後はひとりで責任を取って自決されました。自決の数時間前に陸軍省・軍事課長に「若い立派な軍人をなんとか生き残るようにしてもらいたい」「軍がなくても日本の国は大丈夫、滅びるものか」と言い残し、その軍事課長は、戦後、復員兵の手配に尽力したといいます。皇国不滅を信じて徹底抗戦にはやる軍隊を統率し、無条件降伏という軍人として最大の屈辱を受け入れさせるのは、私たちには想像し得ない難しさがあったろうことを思うと、ここに軍人の一つの鑑を見る思いです。終戦当時の首相と陸相である鈴木貫太郎と阿南惟幾は、昭和4年夏から8年夏までの4年間、侍従長と侍従武官として昭和天皇のおそばにつかえ、三人が互いによく知る仲だったというのが歴史の妙だというようなことを、半藤一利さんは「~夏」の方で述べておられますが、歴史は、時にこうした気まぐれを潜ませるものなのですね。
戦後世代の私たちにとって、8月15日をいくら「終戦」記念日と呼んだところで、「敗戦」がア・プリオリなわけですが、それまで「敗戦」の二文字を知らなかった人たちが、「無条件降伏」を決断し、日本国及び日本人の運命に重大な危機を及ぼしかねない「敗戦」を受け入れることの重みを、僅かながらも垣間見て、「戦争」を見る視点がちょっと変った私でした。














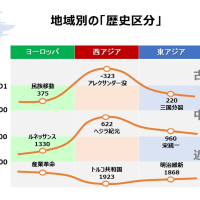




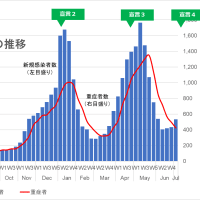






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます