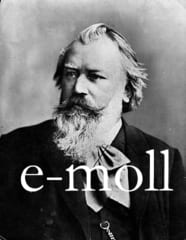
今更ながら・・・されど、
とても大事なことと、ふと思われましたのは、
(これは音楽をしながら、常日頃、思うところあるのですが)
クラシック音楽において、
様々な楽曲・さらには多くの人に知られる
「名曲」なるレパートリーも少なからずあります。
そして、
名曲にしろ、あるいはそうでない曲にしろ、
ある音楽の持っている「調性感」というものが、
その曲以外の音楽においても、
その調性が聴こえ、それが各々の知っていた別の曲の「調性感」と一致することで
その瞬間・今そこにある音楽のイメージが増幅され、
その音楽に対する大きな近親感・充実感を
得られることが出来るのではないか!?
と思う次第なのです。
例えば、今しがた
ブラームス作曲のある曲を勉強していたところ、
「ホ短調e-moll」という調性が現れて、ふと私の脳裏をよぎったのは、
「あ・・・4番の《交響曲》がホ短調だ・・・!!」
という思い。
ブラームスにおけるこの調性のイメージが彷彿され、
なんだかその音楽を「掴めた」!?かのような
感触を得る契機となったのです・・・
このような感触は、
現場の楽曲に現れる調性と、
他の楽曲との関連が見付かったときに味わう
少なからぬ満足感、と言う事もできましょうか。
ちょっと試しに、
ブラームスの「ホ短調e-moll」について
さらにイメージを膨らませてみますと・・・
思い浮かぶのは、
最後のピアノ独奏曲集《op.119》の最初の曲が、
「ホ短調」だったはずです。
不協和音ばかりの、なんとも切なく物悲しい音楽で
あったことが思い出されます・・・
上記の《交響曲 第4番》にしても、
1楽章の、あの切ないメロディー・・・
終楽章の「パッサカリア」は、とうとう「ホ短調」のまま
終わりを迎える・・・まるで救い無き音楽・・・!?
確か、この曲の初演に際しては、
世間からはあまり評価を得られず、
21世紀の今日の我々にとっては「名曲」といわれるこの音楽が
当時は、作曲家の失望のうちに世に出回ったという
なんとも悲しいブラームスの孤高の晩年の姿・・・
というエピソードも、思い出されます・・・
ちょっとブラームスを離れることを許されるならば、
J.S.バッハ作曲の不朽の名作《マタイ受難曲》の冒頭は、
この「ホ短調e-moll」で始まります・・・

通奏低音の、長い長い主音「ミ(E)」が奏でられながら、
それが初めて動き出す上昇の順次進行に
心を・魂を揺さぶられるかのような思いを抱くのは
きっと誰しも同じではないでしょうか・・・!?
ピアノ弾きの自分としては、
ベートーヴェンの《ピアノソナタ》においては、
《第27番 op.90》が「ホ短調」であることも
ちょっと触れておきたくもあります。
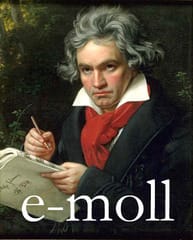
後期ベートーヴェンの作品群へと進む前夜の、
緩急相携えた2楽章からなる珠玉の名曲と思われます。
というわけで、
「ホ短調e-moll」ひとつを取っても、
(まだまだ一杯思い出せない
この調の具体例・イメージがある気がして
我ながら情けない気もしてしまいますが!!)
少なからぬ、多くの楽曲・それに付随するイメージを
列挙させることが出来るのではないか、
と思われます。
クラシック音楽の
きら星のごとく輝く名曲の数々、
それぞれの固有のイメージを有する「調性感」は、
知れば知るほど、
他の音楽との連帯感を有するチャンスが生まれ、
様々な音楽を掴み・愉しむ満足感を得られる可能性が
どんどん拡がってゆくのかもしれません。
是非とも、
「調性」というものに意識を持って、
色々な音楽に触れてみてはいかがでしょうか。
♪
とても大事なことと、ふと思われましたのは、
(これは音楽をしながら、常日頃、思うところあるのですが)
クラシック音楽において、
様々な楽曲・さらには多くの人に知られる
「名曲」なるレパートリーも少なからずあります。
そして、
名曲にしろ、あるいはそうでない曲にしろ、
ある音楽の持っている「調性感」というものが、
その曲以外の音楽においても、
その調性が聴こえ、それが各々の知っていた別の曲の「調性感」と一致することで
その瞬間・今そこにある音楽のイメージが増幅され、
その音楽に対する大きな近親感・充実感を
得られることが出来るのではないか!?
と思う次第なのです。
例えば、今しがた
ブラームス作曲のある曲を勉強していたところ、
「ホ短調e-moll」という調性が現れて、ふと私の脳裏をよぎったのは、
「あ・・・4番の《交響曲》がホ短調だ・・・!!」
という思い。
ブラームスにおけるこの調性のイメージが彷彿され、
なんだかその音楽を「掴めた」!?かのような
感触を得る契機となったのです・・・
このような感触は、
現場の楽曲に現れる調性と、
他の楽曲との関連が見付かったときに味わう
少なからぬ満足感、と言う事もできましょうか。
ちょっと試しに、
ブラームスの「ホ短調e-moll」について
さらにイメージを膨らませてみますと・・・
思い浮かぶのは、
最後のピアノ独奏曲集《op.119》の最初の曲が、
「ホ短調」だったはずです。
不協和音ばかりの、なんとも切なく物悲しい音楽で
あったことが思い出されます・・・
上記の《交響曲 第4番》にしても、
1楽章の、あの切ないメロディー・・・
終楽章の「パッサカリア」は、とうとう「ホ短調」のまま
終わりを迎える・・・まるで救い無き音楽・・・!?
確か、この曲の初演に際しては、
世間からはあまり評価を得られず、
21世紀の今日の我々にとっては「名曲」といわれるこの音楽が
当時は、作曲家の失望のうちに世に出回ったという
なんとも悲しいブラームスの孤高の晩年の姿・・・
というエピソードも、思い出されます・・・
ちょっとブラームスを離れることを許されるならば、
J.S.バッハ作曲の不朽の名作《マタイ受難曲》の冒頭は、
この「ホ短調e-moll」で始まります・・・

通奏低音の、長い長い主音「ミ(E)」が奏でられながら、
それが初めて動き出す上昇の順次進行に
心を・魂を揺さぶられるかのような思いを抱くのは
きっと誰しも同じではないでしょうか・・・!?
ピアノ弾きの自分としては、
ベートーヴェンの《ピアノソナタ》においては、
《第27番 op.90》が「ホ短調」であることも
ちょっと触れておきたくもあります。
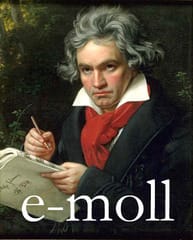
後期ベートーヴェンの作品群へと進む前夜の、
緩急相携えた2楽章からなる珠玉の名曲と思われます。
というわけで、
「ホ短調e-moll」ひとつを取っても、
(まだまだ一杯思い出せない
この調の具体例・イメージがある気がして
我ながら情けない気もしてしまいますが!!)
少なからぬ、多くの楽曲・それに付随するイメージを
列挙させることが出来るのではないか、
と思われます。
クラシック音楽の
きら星のごとく輝く名曲の数々、
それぞれの固有のイメージを有する「調性感」は、
知れば知るほど、
他の音楽との連帯感を有するチャンスが生まれ、
様々な音楽を掴み・愉しむ満足感を得られる可能性が
どんどん拡がってゆくのかもしれません。
是非とも、
「調性」というものに意識を持って、
色々な音楽に触れてみてはいかがでしょうか。
♪




















