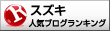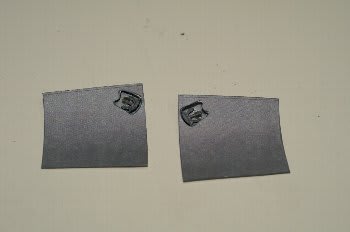朝から快晴。気分がいい。
急にカブに乗って琵琶湖方面に走りたくなった。
カブもこの頃、京都市内の近場ばっかりなのでうっぷんがたまって
いる。たまにはスカッと走りたがっていると思う。
とはいっても、いつもと同じくゆったりとことこ。ぷひぷひ。

大原越えのいつもの道。
途中の還来神社へ立ち寄り。
還来神社(もどろきじんじゃ)。
大津の歴史辞典より↓
藤原百川(ももかわ)の娘・旅子(たびこ)の霊をまつる。旅子は
この地に生まれ、のち桓武天皇の夫人となる。彼女の死後、その遺言
によって生まれ故郷の梛(なぎ)の木の下に埋葬された。
同社には神木椰の古木が残る。
社名も彼女が再び故郷に還って来たことに由来する。
社務所にあった由来書には、兵乱に旅行に無事故郷へ還らんことの
祈願を籠め、参詣者少なかなざりし・・・と書いてある。
そういえば、父が戦争に行ったときに、母が家から近所の人達と、
1日かけてここまで歩いて参詣しにきたという話を聞いたことがある。

心を込めて、二拝二拍手一拝

本日の目的地。
ここの菜の花と比良山系を見ると、すがすがしい気分になれる。

土手にバイクが停めてある。
まあ、絵になったので良いか。

負けじと自分のカブも写真に収めておいた。
ハンドルカバーは意外に便利だと思う。琵琶湖大橋を渡るときに、
20円を支払うのであるが、財布からいちいち出すのが面倒。
ハンドルカバーの中に20円を放り込んでおけば楽に支払えることが
わかった。

琵琶湖に来たついでに、いつもの近江八幡へ。
日牟禮八幡宮(ひむれはちまんぐう)にカブを停めて近辺をうろちょろ。
毎年3月14日、15日に近い土日に左義長祭(さぎちょうまつり)が行わ
れるので、松明とかが準備されていた。

御祭神
譽田別尊(ほむだわけのみこと)、息長足姫尊(おきながたらしひめのみこと)、
比賣神(ひめがみ)


立派な楼門の中に、木でできた狛犬が鎮座している。

神楽殿も歴史を感じる。
毎年薪能が演じられるとのこと。

本殿。
心を込めて、二拝二拍手一拝。


かわらミュージアム近くのみ散策。
季節柄、観光客はほとんど見かけない。しーんと静まり返っていい感じだった。
カブで走るとまだ寒い。
大原あたりは6度から7度。
啓蟄の日だが、虫はまだ土の中。
この頃、ウインカーを点けるのが遅い車が多い。交差点でも発進するときに
点けるヘタクソがいる。急に左折、どひゃー・・である。
カブに乗っていてそんな車に遭遇すると往生する。
啓蟄で眠っていた腹の虫が這い出しそう。
急にカブに乗って琵琶湖方面に走りたくなった。
カブもこの頃、京都市内の近場ばっかりなのでうっぷんがたまって
いる。たまにはスカッと走りたがっていると思う。
とはいっても、いつもと同じくゆったりとことこ。ぷひぷひ。

大原越えのいつもの道。
途中の還来神社へ立ち寄り。
還来神社(もどろきじんじゃ)。
大津の歴史辞典より↓
藤原百川(ももかわ)の娘・旅子(たびこ)の霊をまつる。旅子は
この地に生まれ、のち桓武天皇の夫人となる。彼女の死後、その遺言
によって生まれ故郷の梛(なぎ)の木の下に埋葬された。
同社には神木椰の古木が残る。
社名も彼女が再び故郷に還って来たことに由来する。
社務所にあった由来書には、兵乱に旅行に無事故郷へ還らんことの
祈願を籠め、参詣者少なかなざりし・・・と書いてある。
そういえば、父が戦争に行ったときに、母が家から近所の人達と、
1日かけてここまで歩いて参詣しにきたという話を聞いたことがある。

心を込めて、二拝二拍手一拝

本日の目的地。
ここの菜の花と比良山系を見ると、すがすがしい気分になれる。

土手にバイクが停めてある。
まあ、絵になったので良いか。

負けじと自分のカブも写真に収めておいた。
ハンドルカバーは意外に便利だと思う。琵琶湖大橋を渡るときに、
20円を支払うのであるが、財布からいちいち出すのが面倒。
ハンドルカバーの中に20円を放り込んでおけば楽に支払えることが
わかった。

琵琶湖に来たついでに、いつもの近江八幡へ。
日牟禮八幡宮(ひむれはちまんぐう)にカブを停めて近辺をうろちょろ。
毎年3月14日、15日に近い土日に左義長祭(さぎちょうまつり)が行わ
れるので、松明とかが準備されていた。

御祭神
譽田別尊(ほむだわけのみこと)、息長足姫尊(おきながたらしひめのみこと)、
比賣神(ひめがみ)


立派な楼門の中に、木でできた狛犬が鎮座している。

神楽殿も歴史を感じる。
毎年薪能が演じられるとのこと。

本殿。
心を込めて、二拝二拍手一拝。


かわらミュージアム近くのみ散策。
季節柄、観光客はほとんど見かけない。しーんと静まり返っていい感じだった。
カブで走るとまだ寒い。
大原あたりは6度から7度。
啓蟄の日だが、虫はまだ土の中。
この頃、ウインカーを点けるのが遅い車が多い。交差点でも発進するときに
点けるヘタクソがいる。急に左折、どひゃー・・である。
カブに乗っていてそんな車に遭遇すると往生する。
啓蟄で眠っていた腹の虫が這い出しそう。