東海道を行き来する参勤交代の大名は、移動する行程や日程、移動
経路などが幕府により厳しく取り決められていた。
宮と桑名の間ではこの七里の渡しを使うか、佐屋街道を行き三里を舟
渡しで行くかの二択で有ったが、距離の短い佐屋廻りを選ぶ西国大名
が多かったと伝えられている。
船旅は時に長時間を要すことも有り、日程が決められている大名に
は、その後の影響を考えると都合が悪く、何より船酔いの心配も有り
苦痛であったようだ。


宮から現在の渡しJRで桑名に移動、国営木曽三川公園として整備の
進む七里の渡し跡を見て、ここからは陸路での東海道を四日市に向けた
歩みが再び始まる。
船着き場から南に延びる旧道は、城下町特有の枡形を多用した道らし
いが、ベージュのカラー舗装が施された道なので、それを辿れば間違え
ることはなさそうだ。


街道を南に向け八間通りの広い道を横切り、暫く行くと右手に銅鳥居
が見えてきた。青銅の大きな春日神社の鳥居で、寛文7(1667)年七代
目桑名藩主・松平定重が寄進した。
当時の慶長金で250両との記録があり、県有形文化財に指定されている。
高さ6.9m、笠木長さ8.1m、柱廻り57.5㎝、鋳物業として栄えた町のシン
ボル的な存在だ。
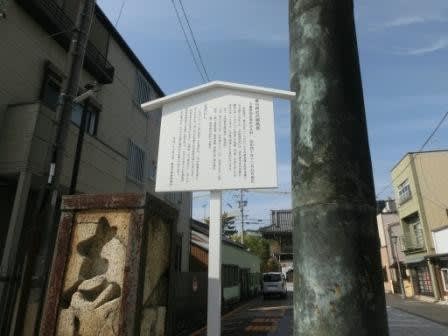

その脚の横に「しるべいし(迷い児石)」が立っている。
子供が迷子になると、子の特徴などを書いた紙を左側面(たずぬるかた)
に貼り、それに心当たりがあると右側面(おしゆるかた)に、子供が居
た場所などを書いて貼るのだそうだ。
こう言った石は多度大社の鳥居の横にも、また岡山城下の中心・京橋
の袂にも残されている。通信手段の乏しい当時では有効なツールとして
各所で使われていたようだ。(続)

 にほんブログ村
にほんブログ村
経路などが幕府により厳しく取り決められていた。
宮と桑名の間ではこの七里の渡しを使うか、佐屋街道を行き三里を舟
渡しで行くかの二択で有ったが、距離の短い佐屋廻りを選ぶ西国大名
が多かったと伝えられている。
船旅は時に長時間を要すことも有り、日程が決められている大名に
は、その後の影響を考えると都合が悪く、何より船酔いの心配も有り
苦痛であったようだ。


宮から現在の渡しJRで桑名に移動、国営木曽三川公園として整備の
進む七里の渡し跡を見て、ここからは陸路での東海道を四日市に向けた
歩みが再び始まる。
船着き場から南に延びる旧道は、城下町特有の枡形を多用した道らし
いが、ベージュのカラー舗装が施された道なので、それを辿れば間違え
ることはなさそうだ。


街道を南に向け八間通りの広い道を横切り、暫く行くと右手に銅鳥居
が見えてきた。青銅の大きな春日神社の鳥居で、寛文7(1667)年七代
目桑名藩主・松平定重が寄進した。
当時の慶長金で250両との記録があり、県有形文化財に指定されている。
高さ6.9m、笠木長さ8.1m、柱廻り57.5㎝、鋳物業として栄えた町のシン
ボル的な存在だ。
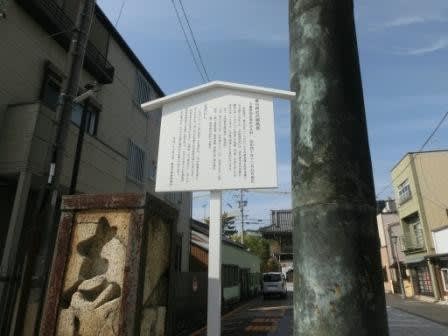

その脚の横に「しるべいし(迷い児石)」が立っている。
子供が迷子になると、子の特徴などを書いた紙を左側面(たずぬるかた)
に貼り、それに心当たりがあると右側面(おしゆるかた)に、子供が居
た場所などを書いて貼るのだそうだ。
こう言った石は多度大社の鳥居の横にも、また岡山城下の中心・京橋
の袂にも残されている。通信手段の乏しい当時では有効なツールとして
各所で使われていたようだ。(続)




























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます