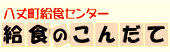みなさま、こんにちは!海風おねいさんです。
爽やかな秋のようなお天気の八丈島です。
年末年始と悪天が続いてましたので、今日の日曜日は、
あぁ、岩海苔かハンバ海苔でも摘み採りに行きたい陽気ですねぇ。
八丈島の特産物である岩海苔類は、これからが旬ですが、
こちらは後日またご紹介するとして、
今日は「小豆」(あずき)と「ささげ」のお話です。
 本年より、食品の豆知識も少しずつご紹介してまいります。
本年より、食品の豆知識も少しずつご紹介してまいります。

「あさぬま」で販売しているモアセレクトの「ささげ」と「小豆」です。
この違い、みなさま、ご存知でしたか?
よくご覧くださいね。あなたの地方のお赤飯には、どちらの豆が使われてます?
おねいさんのお赤飯には、左の「ささげ」が多い気がします。
お汁粉はどうですか?そんなこと考えたこともなかった?

豆の種類の一覧表です。


左:ささげ 右:小豆
右の小豆は目(白い所、ヘソとも言います)が白1色ですが、
ささげは目の周りに黒い輪模様があります。
左のささげは関東以南で栽培されてますが、今では栽培が減少傾向とのことです。
モアセレクトのささげは中国産でした。
ささげには大粒と小粒がありますが、通常ささげといわれるのは小粒の方。
赤飯には、北海道では小豆(あずき)を使うそうです。
これが関東になると、ささげ(大角豆)を使うのが多いらしい。
何故でしょう?
小豆は煮た時に皮が破れやすいため、「腹切れする豆は切腹に通じる」として、
武士の間で嫌われ、一方ささげは煮ても皮が破れず煮崩れしないことに由来して、
関東ではささげを使うのが一般的となったとか。
ちなみに、小豆の大粒の物で大納言がありますが、
大納言は大粒で煮崩れしにくいことから、甘納豆や小倉餡として使われてます。
「大納言」の名は、煮ても皮が腹切れしにくいことから、
切腹の習慣がない公卿の官位である「大納言」と名付けられたそうです。
以前におねいさんが雑誌BE-PALの八丈島記事のお手伝いをしたときに、
ムロアジの開きを作りました。
このアジの開きも、腹を切るのは縁起が悪いとして、関東は腹開きを嫌い
以前は背開きが主流であったのです。
関東には、武家の縁起担ぎの風習の名残がけっこうあるのですね。
話飛びましたが、みなさまは、鏡開きにはお汁粉を召し上がりましたか?
10日までお供えのお餅を飾っておき、11日にお餅を割ってお雑煮などを作る
「鏡開き」も元々は武家社会の風習でした。
「二十日に鏡を祝うは、初顔祝うという詞の縁をとるなり」とし、
ハッカが刃柄と通じるところから、元来は20日に行なわれてきたものです。
徳川三代将軍家光が4月20日に亡くなった後は、
この日を忌日として避けて11日になったといわれています。
しかし、今でも20日に鏡開きをする地方も多いのです。
11日にはお雑煮を食べ、20日にお汁粉を食べる地方もあるようです。
おねいさんも今年はこれに習い、11日にはお雑煮を食べました。
20日にお汁粉を食べようと、(冷凍するつもりで)早めに小豆を煮ていたら、
深夜、ネットでの調べものに夢中になって、見事、小豆を焦がしました。
煮物中のネットは厳禁です。今年第一弾の教訓です。
それで煮た小豆の画像がありません。お許しください。
20日までにまた煮て必ずリベンジしま~す!
※尚、この記事中の「小豆」と「ささげ」に関する豆知識は、
以前にめずらしい「そうめんかぼちゃ」をお送りくださった
北海道で農業を営むよしくんから教えていただき、画像もお借りしました。
よしくん、わかりやすい説明をありがとうございました。
爽やかな秋のようなお天気の八丈島です。

年末年始と悪天が続いてましたので、今日の日曜日は、
あぁ、岩海苔かハンバ海苔でも摘み採りに行きたい陽気ですねぇ。
八丈島の特産物である岩海苔類は、これからが旬ですが、
こちらは後日またご紹介するとして、
今日は「小豆」(あずき)と「ささげ」のお話です。
 本年より、食品の豆知識も少しずつご紹介してまいります。
本年より、食品の豆知識も少しずつご紹介してまいります。
「あさぬま」で販売しているモアセレクトの「ささげ」と「小豆」です。
この違い、みなさま、ご存知でしたか?
よくご覧くださいね。あなたの地方のお赤飯には、どちらの豆が使われてます?
おねいさんのお赤飯には、左の「ささげ」が多い気がします。
お汁粉はどうですか?そんなこと考えたこともなかった?

豆の種類の一覧表です。


左:ささげ 右:小豆
右の小豆は目(白い所、ヘソとも言います)が白1色ですが、
ささげは目の周りに黒い輪模様があります。
左のささげは関東以南で栽培されてますが、今では栽培が減少傾向とのことです。
モアセレクトのささげは中国産でした。
ささげには大粒と小粒がありますが、通常ささげといわれるのは小粒の方。
赤飯には、北海道では小豆(あずき)を使うそうです。
これが関東になると、ささげ(大角豆)を使うのが多いらしい。
何故でしょう?
小豆は煮た時に皮が破れやすいため、「腹切れする豆は切腹に通じる」として、
武士の間で嫌われ、一方ささげは煮ても皮が破れず煮崩れしないことに由来して、
関東ではささげを使うのが一般的となったとか。
ちなみに、小豆の大粒の物で大納言がありますが、
大納言は大粒で煮崩れしにくいことから、甘納豆や小倉餡として使われてます。
「大納言」の名は、煮ても皮が腹切れしにくいことから、
切腹の習慣がない公卿の官位である「大納言」と名付けられたそうです。
以前におねいさんが雑誌BE-PALの八丈島記事のお手伝いをしたときに、
ムロアジの開きを作りました。
このアジの開きも、腹を切るのは縁起が悪いとして、関東は腹開きを嫌い
以前は背開きが主流であったのです。
関東には、武家の縁起担ぎの風習の名残がけっこうあるのですね。
話飛びましたが、みなさまは、鏡開きにはお汁粉を召し上がりましたか?
10日までお供えのお餅を飾っておき、11日にお餅を割ってお雑煮などを作る
「鏡開き」も元々は武家社会の風習でした。
「二十日に鏡を祝うは、初顔祝うという詞の縁をとるなり」とし、
ハッカが刃柄と通じるところから、元来は20日に行なわれてきたものです。
徳川三代将軍家光が4月20日に亡くなった後は、
この日を忌日として避けて11日になったといわれています。
しかし、今でも20日に鏡開きをする地方も多いのです。
11日にはお雑煮を食べ、20日にお汁粉を食べる地方もあるようです。
おねいさんも今年はこれに習い、11日にはお雑煮を食べました。
20日にお汁粉を食べようと、(冷凍するつもりで)早めに小豆を煮ていたら、
深夜、ネットでの調べものに夢中になって、見事、小豆を焦がしました。

煮物中のネットは厳禁です。今年第一弾の教訓です。

それで煮た小豆の画像がありません。お許しください。
20日までにまた煮て必ずリベンジしま~す!

※尚、この記事中の「小豆」と「ささげ」に関する豆知識は、
以前にめずらしい「そうめんかぼちゃ」をお送りくださった
北海道で農業を営むよしくんから教えていただき、画像もお借りしました。
よしくん、わかりやすい説明をありがとうございました。