送信メールが、さっぱり送れなくなった。受信は平気なのに。
劇団IT部に問い合わせると、迷惑メール規制に伴うエラーだという。なるほど、最近FAXで何度かそんなのが来てました。
 さっそく設定を変えたら、簡単に直りました。
さっそく設定を変えたら、簡単に直りました。
昨日は昼過ぎから、某損害保険会社の本社にて講習を受けてきました。
役者の中には、銀行員、葬儀屋さん、板前さんなど前職からの転身組がいますが(ちなみに例は東演以外も含む)、僕も20代の頃、個人的に損保の資格を取っていて、制作になった今もそれを生かせるところには生かしています。
例えば海外ツアーや国内ツアーの保険(いわゆる傷害保険)、東演は劇場を有しているので、その保険(火災保険及び賠償責任保険)、月光など小規模公演に活躍するワゴン車は自動車保険・・・てな具合に。
劇団におけるリスク回避のために、微力ながら貢献させていただいております。
益々多様化する社会の中で、制作者の仕事の中に「リスクマネジメント」は今や当然の業務となっています。まぁ、一言で片づくほど簡単なモノではないけれど…。
ネットの普及による顧客データなどの管理=プライバシーポリシーなんかは一番解りやすい仕事の一つと言えるでしょう。
テレビからはノロウイルス席巻のニュース。
思えば、12/6付ブログの“風邪”は、そのあと多くの人から全面的に断定されましたが、確かにあれは「ノロ」でした。
劇団や俳優達のリスクも大事だが、まずは自分を何とかせい!ってことか。。。
忘年会の重なるシーズンだしね
 かくいう今日も2件重なっている。。。
かくいう今日も2件重なっている。。。
やはり先約優先だよな。
あ、ノロから復活しかけた時、まだ足もとが覚束なかったのか、右足首を捻挫した。5日ほどたつが、まだ痛い。いや右を庇ううち左足が…と思って、右にも重心かけると痛みが再発。。。
まさしく、転ばぬ先の杖。
リスクマネジメントが大切ってこと?
劇団IT部に問い合わせると、迷惑メール規制に伴うエラーだという。なるほど、最近FAXで何度かそんなのが来てました。
 さっそく設定を変えたら、簡単に直りました。
さっそく設定を変えたら、簡単に直りました。昨日は昼過ぎから、某損害保険会社の本社にて講習を受けてきました。
役者の中には、銀行員、葬儀屋さん、板前さんなど前職からの転身組がいますが(ちなみに例は東演以外も含む)、僕も20代の頃、個人的に損保の資格を取っていて、制作になった今もそれを生かせるところには生かしています。
例えば海外ツアーや国内ツアーの保険(いわゆる傷害保険)、東演は劇場を有しているので、その保険(火災保険及び賠償責任保険)、月光など小規模公演に活躍するワゴン車は自動車保険・・・てな具合に。
劇団におけるリスク回避のために、微力ながら貢献させていただいております。
益々多様化する社会の中で、制作者の仕事の中に「リスクマネジメント」は今や当然の業務となっています。まぁ、一言で片づくほど簡単なモノではないけれど…。
ネットの普及による顧客データなどの管理=プライバシーポリシーなんかは一番解りやすい仕事の一つと言えるでしょう。
テレビからはノロウイルス席巻のニュース。
思えば、12/6付ブログの“風邪”は、そのあと多くの人から全面的に断定されましたが、確かにあれは「ノロ」でした。
劇団や俳優達のリスクも大事だが、まずは自分を何とかせい!ってことか。。。
忘年会の重なるシーズンだしね

 かくいう今日も2件重なっている。。。
かくいう今日も2件重なっている。。。やはり先約優先だよな。
あ、ノロから復活しかけた時、まだ足もとが覚束なかったのか、右足首を捻挫した。5日ほどたつが、まだ痛い。いや右を庇ううち左足が…と思って、右にも重心かけると痛みが再発。。。

まさしく、転ばぬ先の杖。
リスクマネジメントが大切ってこと?










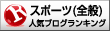



 結団式なんて云うとイカツいけれど、
結団式なんて云うとイカツいけれど、 余談だが、テーブルにはローストビーフにサンドイッチ、
余談だが、テーブルにはローストビーフにサンドイッチ、 )
)


 僕が「制作」を担当しはじめて
僕が「制作」を担当しはじめて



 」と。
」と。
 2/3(土)-4(日)
2/3(土)-4(日)















