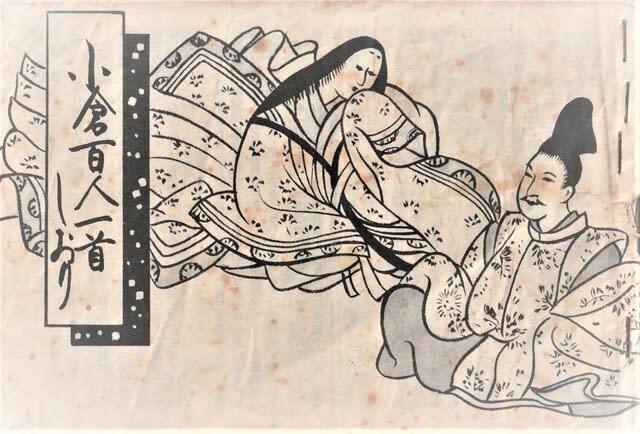「爺さんの備忘録的花図鑑」
「ハ」
◯バーベナ(美女桜) ⇨ 2024.0517
◯バイカウツギ(梅花空木) ⇨ 2021.05.27
◯バイカオウレン(梅花黄蓮) ⇨ 2022.03.04
◯バイモ(貝母) ⇨ 2025.04.05
◯ハクサンイチゲ(白山一花) ⇨ 2022.03.09
◯ハクサンチドリ(白山千鳥) ⇨ 2024.11.26
◯ハクサンフウロ(白山風露) ⇨ 2022.03.10
◯ハクモクレン(白木蓮) ⇨ 2021.03.10
◯ハコネウツギ(箱根空木) ⇨ 2021.05.13
◯バコパ ⇨ 2020.05.14
◯ハゼラン(爆蘭) ⇨ 2024.10.31
◯ハナイカダ(花筏) ⇨ 2022.03.11
◯ハナウド(花独活) ⇨ 2022.05.22
◯ハナカイドウ(花海棠) ⇨ 2022.12.17
◯ハナズオウ(花蘇芳) ⇨ 2022.04.03
◯ハナトラノオ(花虎ノ尾) ⇨ 2020.08.10
◯ハナニラ(花韮) ⇨ 2023.03.27
◯ハナネコノメソウ(花猫の目草) ⇨ 2022.03.03
◯ハナミズキ(花水木) ⇨ 2022.04.15
◯ハハコグサ(母子草) ⇨ 2020.05.10
◯ハバヤマボクチ(葉場山火口) ⇨ 2022.12.13
◯ハンゲショウ(半夏生・半化粧) ⇨ 2021.07.11