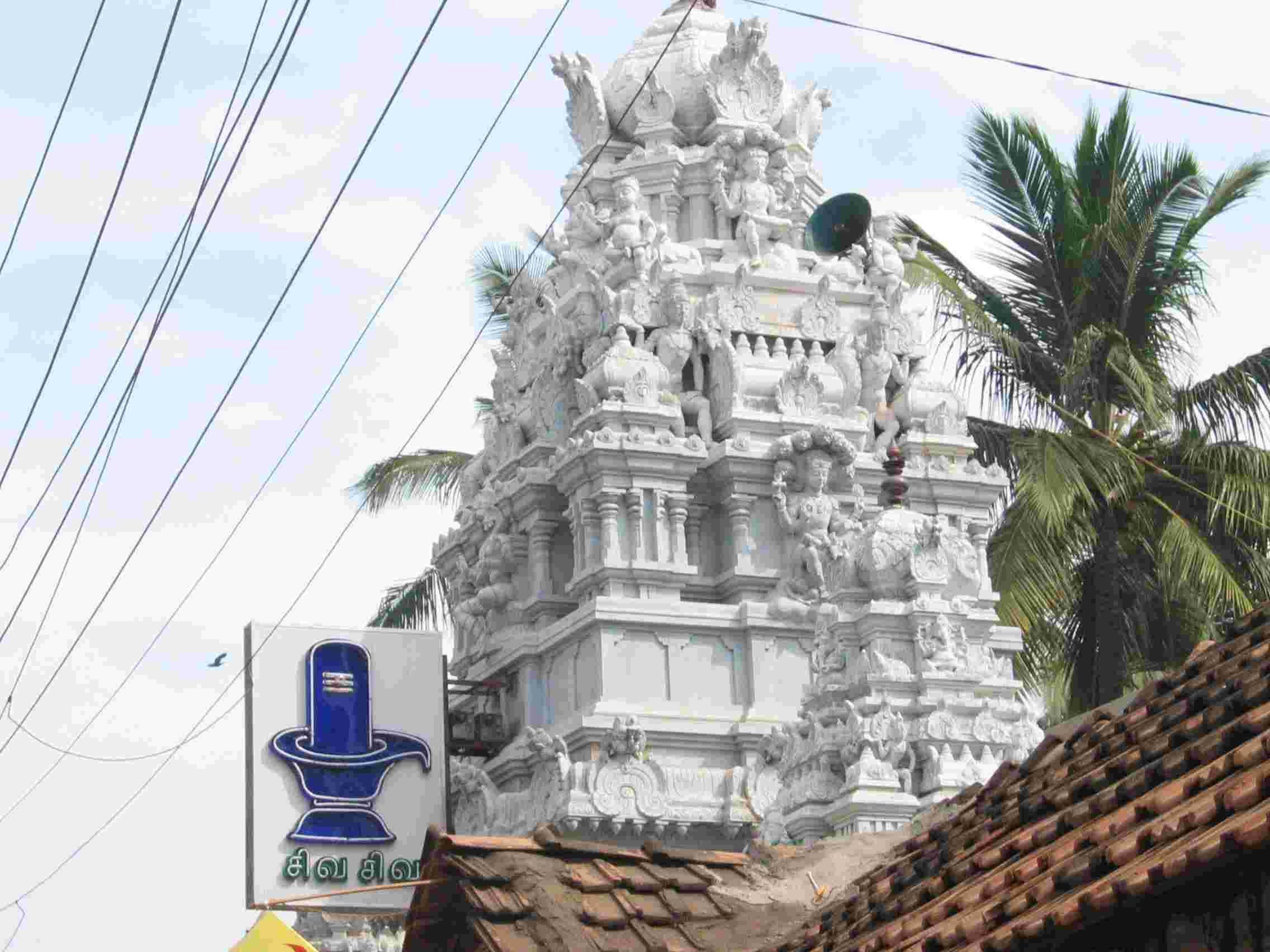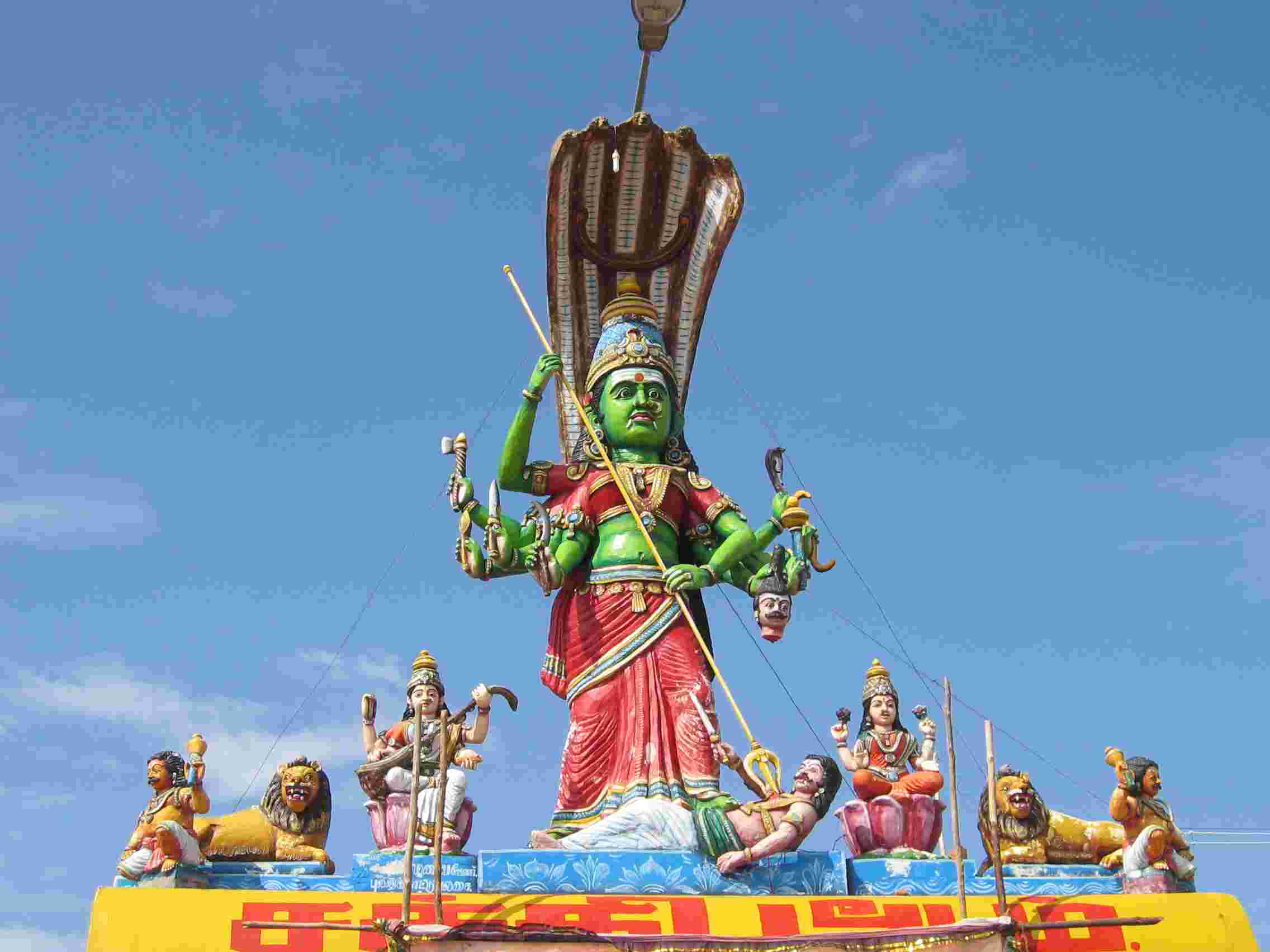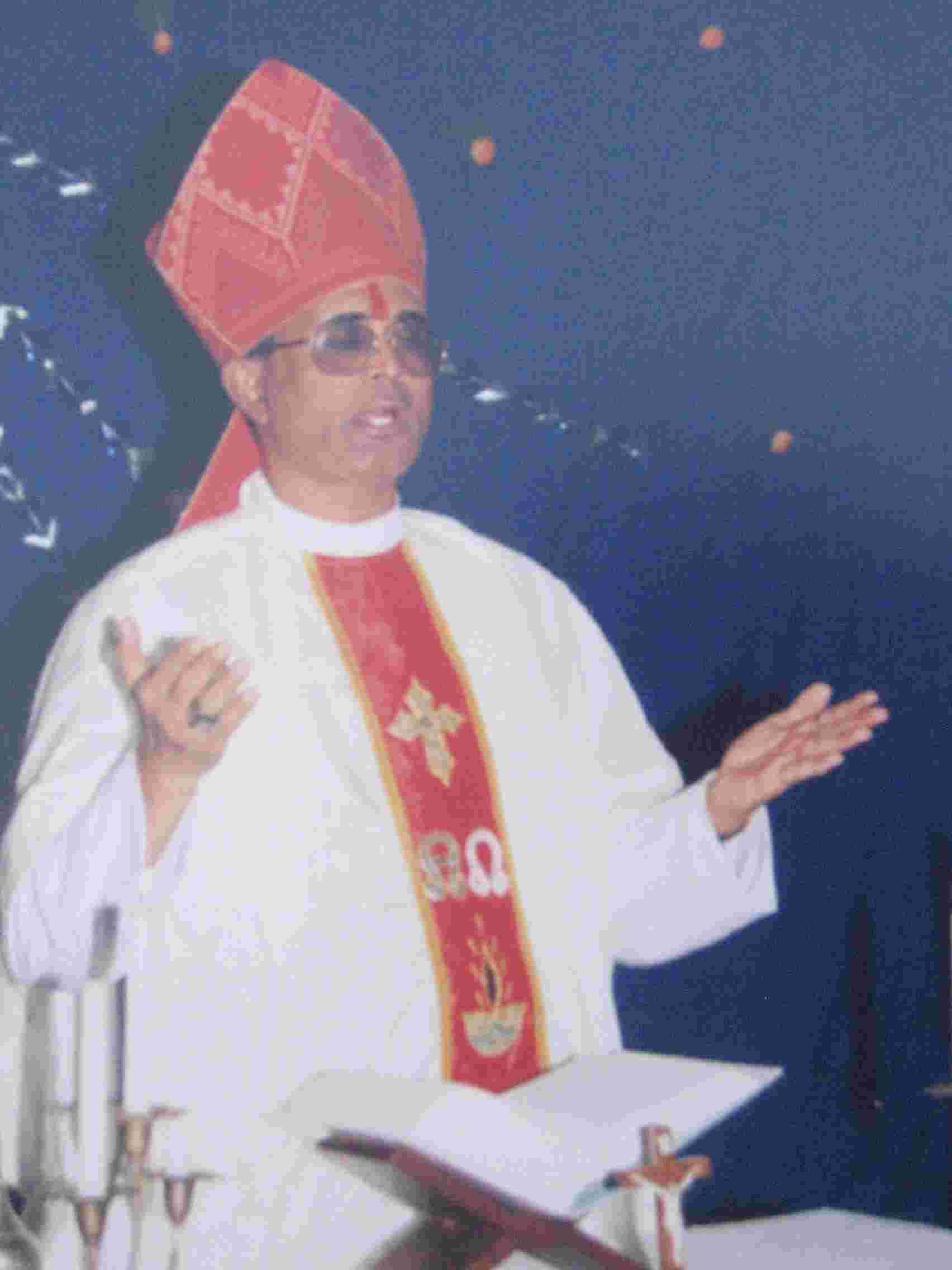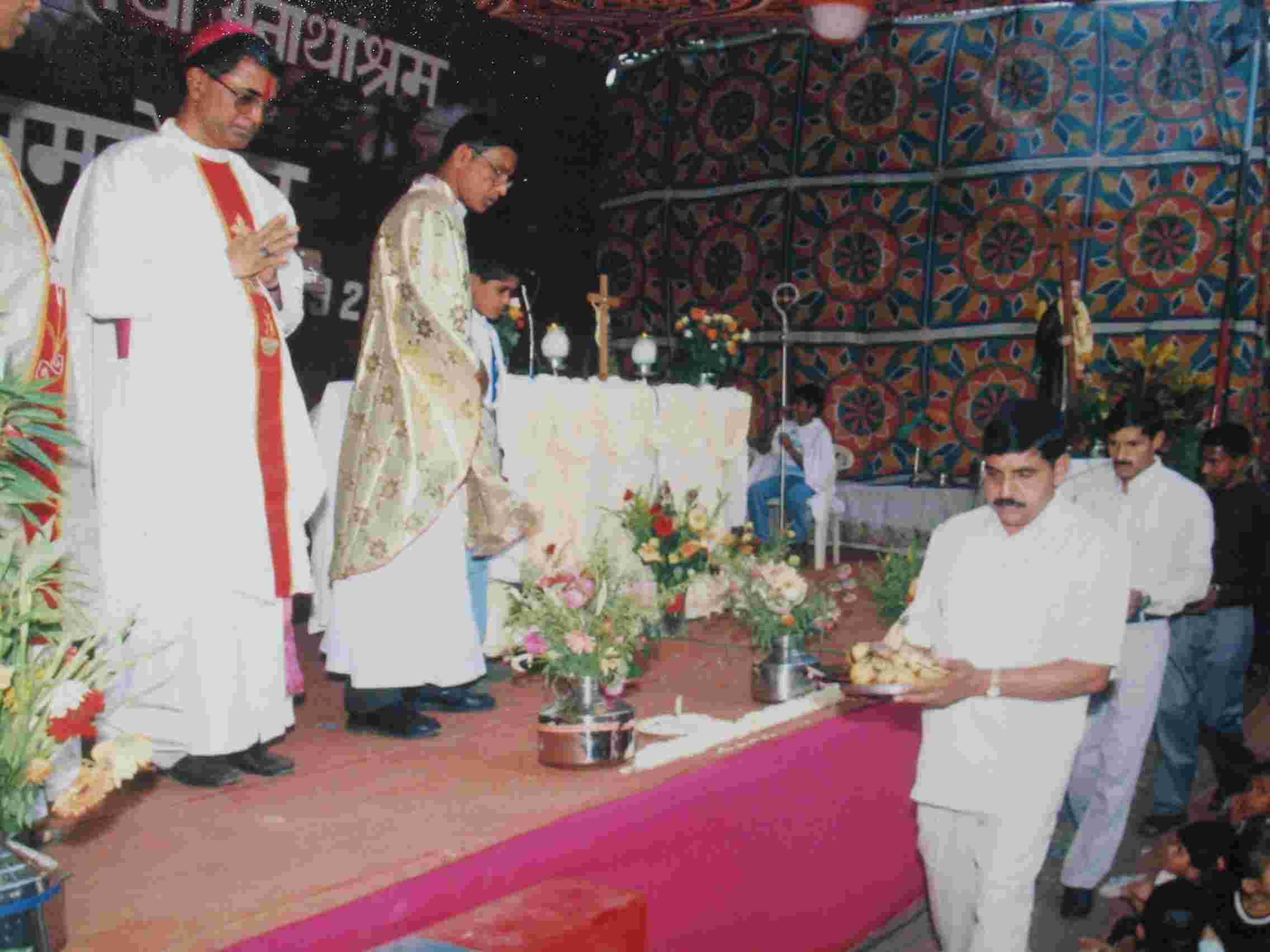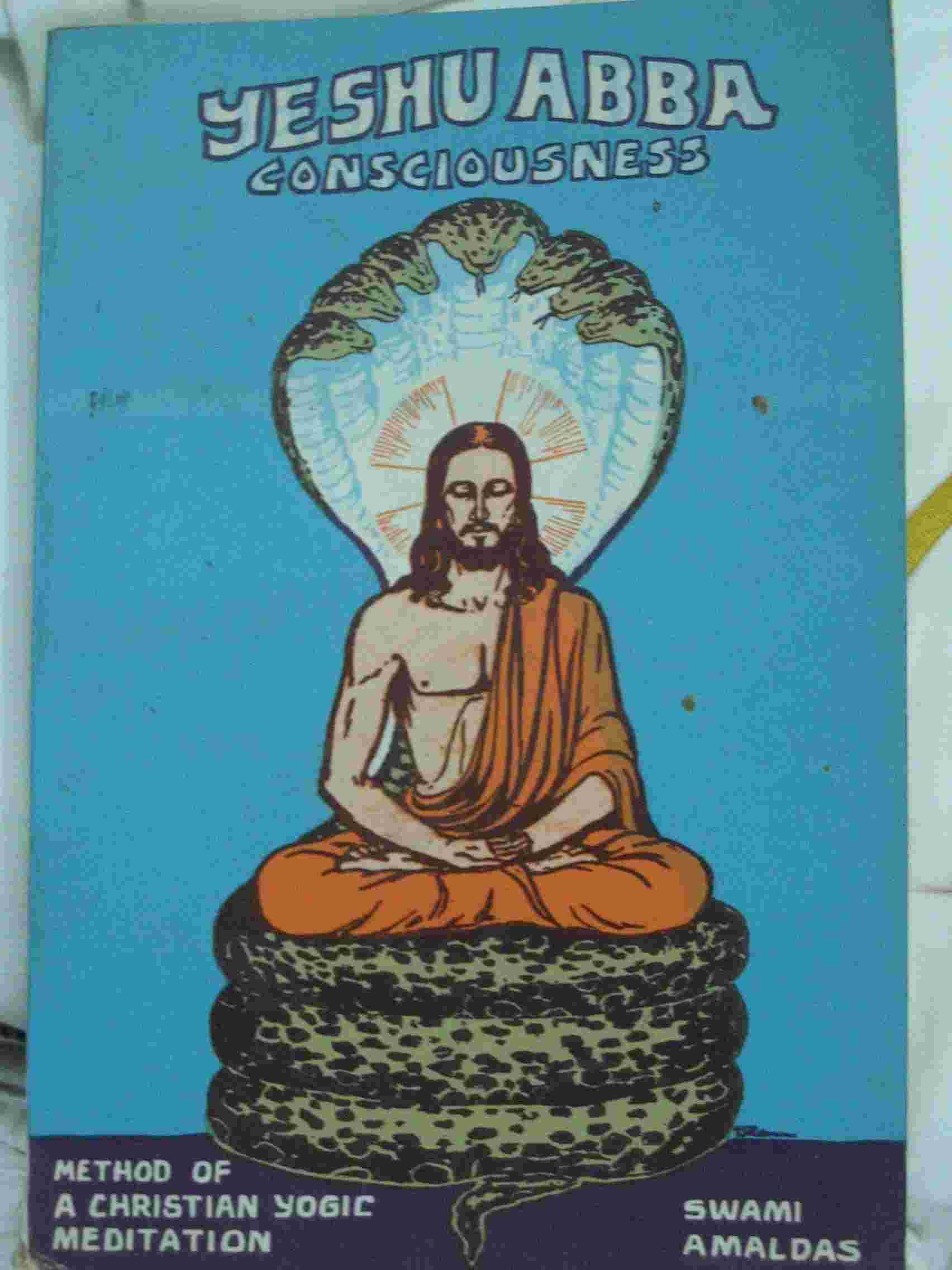アヴェ・マリア!
【質問】
第二バチカン公会議はどこが特別なのですか。第二バチカン公会議が単なる司牧的公会議だった、とはどういう意味ですか。第二バチカン公会議は、同時に教義的でもあり司牧的だったのではないですか。
【答え】
第二バチカン公会議は、教皇ヨハネ二十三世によって1962年10月11日に開催され、(ヨハネ二十三世は翌年なくなったので)後継者のパウロ六世が公会議を継続し、1965年12月8日に閉会しました。第二バチカン公会議は、カトリック教会における第21回公会議でした。全教会史の中で参加した司教様(教父)たちの数が最も多く、2000余名を数えます。
第二バチカン公会議は、信仰に関する問題を定義することを避け、教会生活のために司牧的指針を与えることをその目的としました。そのため不可謬権を行使した教義定義決定をしませんでした。そこで第二バチカン公会議の諸文書は必ずしも不可謬であるとは限りません。公会議を開催した教皇様たちは、公会議中「司牧的」であることを強調しました。
【公会議の通常の目的は?】
第一バチカン公会議招集の大勅令(Bulla)である「エテルニ・パトリス(Aeterni Patris)」で、ピオ九世は「時代の極めて重大な混乱と私たちの聖なる宗教と市民社会の災難においてとりわけ」公会議が招集され、信仰の教義を定義し、広がる誤謬を排斥し、カトリックの教えを擁護し、教会の規律を保全し高め、人民の弛緩した道徳を強めるために開催されると言っています。特に最初の7つの公会議は、異端の根絶のために開催されましたし、公会議は常にその当時の悪を断罪するために開催されてきました。
(ピオ九世の大勅書のイタリア語訳の一部)
Ne gli stessi Sommi Pontefici tralasciarono, quando lo giudicarono opportuno, in modo particolare nelle gravissime perturbazioni dei tempi e nelle calamita della nostra santissima Religione e della civile societa, di convocare Concilii generali, al fine di confrontare i propri consigli con quelli dei Vescovi di tutto il mondo cattolico: dei Vescovi che "lo Spirito Santo pose a reggere la Chiesa di Dio", cosi che con le forze riunite si adottassero sapientemente e provvidamente tutte quelle disposizioni che possono giovare principalmente a definire i dogmi, a condannare gli sparsi errori, a propugnare, a illustrare e a svolgere la dottrina cattolica, a mantenere e a rafforzare la disciplina ecclesiastica, a correggere i corrotti costumi dei popoli.
【第二バチカン公会議以前には「司牧的」公会議はなかったのか?】
カトリック教会の全ての公会議は司牧的でした。しかし第二バチカン公会議以前の20の公会議では、教義を定義決定し、誤謬を明らかにし、カトリックの教えを擁護し、規律や道徳の弛緩に対して闘いながら、司牧的であろうとしました。第二バチカン公会議の独特な特徴は、新しいやり方で司牧的であろうとしたことです。つまり、
教義定義をすることを拒み・誤謬を排斥することを避けて・カトリックの教えを護教的に提示しないことによって、「司牧的」であろうとしたことです。
【第二バチカン公会議は教義的な公文書を発表しているのではないか】
第二バチカン公会議は16の文書を発布しました。つまり7つの教令と3つの宣言と4つの憲章です。これらのうち『教会憲章』と『神の啓示に関する教義憲章』は「教義憲章」(Dogmatic constitutions)と呼ばれています。この意味は、
教義(ドグマ)に関する内容を取り扱っている憲章という意味で、教義決定をしたという意味でも不可謬であるという意味でもありません。何故なら、第二バチカン公会議は、不可謬のやり方で教義を決定することを避けたからです。
パウロ6世は、第二バチカン公会議数週間後の1966年1月12日に、一般謁見で公会議が不可謬の印を伴うドグマの全ての特別宣言を避けたことをこう説明しています。
「
公会議は教会の教導職の不可謬権を行使した荘厳な教義決定的な定義を避けましたが、このような公会議が与える教えのもつ権威すなわち神学的資格は何かと疑問に思う人々もあります。その答えを私たちはよく知っています。1964年3月6日の公会議の宣言を思い出しましょう。これは、1964年11月16日にも繰り返されました。すなわち、公会議の司牧的性格を鑑み、
公会議は不可謬の印を伴うドグマの全ての特別宣言を避けました。しかし公会議は、通常教権の権威を伴う教えを提供し、それはそれぞれの文章の本性と目的とに合わせて公会議の心にのっとって従順に受け入れられなければなりません。」
(
DC, 1964, no 1466, col. 420)
"There are those who ask what authority, what theological qualification, the Council intended to give to its teachings, knowing that it avoided issuing solemn dogmatic definitions backed by the Church's infallible teaching authority. The answer is known by those who remember the conciliar declaration of March 6, 1964, repeated on November 16, 1964. In view of the pastoral nature of the Council, it avoided proclaiming in an extraordinary manner any dogmas carrying the mark of infallibility but has strengthened its teaching with the authority of the supreme ordinary Magisterium; this ordinary and truly authentic Magisterium must be accepted with docility and sincerity by all faithful, according to the spirit of the Council, concerning the nature and the goal of each document."
● パウロ六世は、第二バチカン公会議議長であったティスラン枢機卿へつぎのように公式通達をし、第二バチカン公会議が、過去すでに宣言され、あるいは定義された(declarata vel definita)教義を、ただ単に示す(exponatur)だけなのだと言う。第二バチカン公会議が荘厳宣言を避け、新しい教義決定もしないと言っています。
「これらの草案を新しくすることで、この公会議の司牧的な性格を大事にしました。信仰に関する確かで不変の教義は、教会の最高教導職によって、そして先立つ数々の公会議、特にトリエント公会議と第1バチカン公会議によって宣言されあるいは定義されました。この教義には忠実に服従しなければならず、また、この教義が現代に相応しいやり方で示され、現代人が容易に真理を抱き入れキリストによって私たちのために与えられた救いが受け入れられるようにされなければなりません。」
(ラテン語原文Acta Synodalia Sacrosancti Concilii oecumenici Vaticani II, Typis polyglottis Vaticanis, Vol. II, Pars I, 1971, p. 11.
トマス小野田神父訳)
"When revising the schemas, we were careful to highlight the pastoral character of this Council. It is indeed necessary that the certain and immutable doctrine of the faith, which has been declared or defined by the supreme magisterium of the Church and by the previous Ecumenical Councils, especially the Council of Trent and the First Council of the Vatican, and to which we must faithfully submit ourselves, be exposed in a manner that corresponds to our time, and that today's men have an easier access to the truths which must be embrassed and to the salvation to be received which Christ has obtained for us."
(In Sel de la Terre, n. 35, p.36)
パウロ六世教皇は1975年8月6日の一般謁見でこう言っています。
「
その他の公会議とは違って、この公会議は直接に教義決定のものではなく、規律と司牧に関するものでした。」
Paul VI, General Audience, August 6, 1975
"Differing from other Councils, this one was not directly dogmatic, but disciplinary and pastoral."
ラッツィンガー枢機卿(当時、現在ベネディクト十六世教皇)は、チリのサンチアゴで、チリの司教評議会に1988年7月13日にこう言っています。
「ルフェーブル大司教に反対して第二バチカン公会議を有効であり[ママ]教会を建設するものとして守ることは必要な仕事です。確かに、第二バチカン公会議を孤立化する狭いメンタリティーがありますが、それがこの反対を挑発したのです。その多くの例があり、それは第二バチカン公会議以後全てが変わってしまった、そして公会議以前のものは全く価値がないか、あるいは良くても第二バチカン公会議の光のもとにしか価値がないという印象を与えています。第二バチカン公会議は、教会の生ける全聖伝の一部としてではなく、単に聖伝の終わりとして、ゼロからの新しい始まりとして取り扱われてきました。
真理は、この公会議はいかなる教義をも決定したわけではありません。そして故意に、単なる司牧公会議としての慎ましいレベルに止まることを選んだのです。しかしながら、多くの人々はこれをそれ自身で、その他の全ての(公会議の)重要さを取り除くある種の超教義(スーパードグマ)であるかのように取り扱っています。
Cardinal Ratzinger, Address to the Chilean Episcopal Conference, Il Sabato 1988
"It is a necessary task to defend the Second Vatican Council against Msgr. Lefebvre, as valid, and as binding upon the Church. Certainly there is a mentality of narrow views that isolate Vatican II and which has provoked this opposition. There are many accounts of it which give the impression that, from Vatican II onward, everything has been changed, and that what preceded it has no value or, at best, has value only in the light of Vatican II.
"The Second Vatican Council has not been treated as a part of the entire living Tradition of the Church, but as an end of Tradition, a new start from zero. The truth is that this particular Council defined no dogma at all, and deliberately chose to remain on a modest level, as a merely pastoral council; and yet many treat it as though it had made itself into a sort of superdogma which takes away the importance of all the rest.
【第二バチカン公会議の「司牧性」の特徴とは?】
カトリック教会の全ての公会議は、その時代時代に応じて、その時代に広がっていた誤謬を断罪・排斥し、その時期に流行の規律の弛緩に対して制裁を与え、教会の敵に反対して警告を与えていました。その「時代に応じて」とは、その時代の悪により良く抵抗したということであって、この世と迎合したという意味ではありません。天主に嘉されるために、その時代にあるこの世の悪と戦って打ち勝ったという意味です。たとえば、聖職売買、腐敗、異端、離教などです。
しかしヨハネ二十三世は第二バチカン公会議の第1の直接の目的についてこう言いました。
「公会議の第一の直接の目的は、この世に天主の教会を提示することである」(1960年2月14日)
パウロ六世は、回勅「
エクレジアム・スアム」(79)で、教会は悪を断罪するのではなく、この世と対話をすると言っています。
78. Clearly, relationships between the Church and the world can be effective in a great variety of ways. The Church could perhaps justifiably reduce such contacts to a minimum, on the plea that it wishes to isolate itself from secular society. It might content itself with conducting an inquiry into the evils current in secular society, condemning them publicly, and fighting a crusade against them. On the other hand, it might approach secular society with a view to exercising a preponderant influence over it, and subjecting it to a theocratic power; and so on.
But it seems to Us that the sort of relationship for the Church to establish with the world should be more in the nature of a dialogue, though theoretically other methods are not excluded.