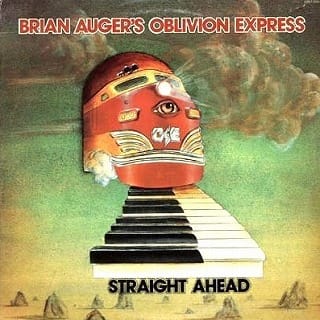■Schizoid Man / King Crimson (Virgin = CD)
自分の好きな歌や演奏だけを集めたテープやCDを作った経験は、音楽愛好者ならば必ずやあるはずです。
それは様々なミュージャンや歌手のオムニバスである場合と同じく、楽曲単位というか、ひとつの歌や演奏を様々なバージョン&テイクで集めて聴くという行為にも繋がるわけですから、本日ご紹介は、なんとっ!?!
今に至るもキング・クリムゾンの代名詞となっている「21st Century Schizoid Man / 21世紀の精神異常者」だけを集めた偏執者向けのCDで、もちろん1969年のオリジナルバージョンから1974年のライプ音源までという、キング・クリムゾンが最も「キング・クリムゾンらしかった」時期の5トラックを収録しています。
01 1969年オリジナルバージョンの短縮編集版
02 1969年オリジナルバージョン (「クリムゾン・キングの宮殿」より)
03 1969年5月6日のBBC音源 (発掘編集盤「エピタフ」より)
04 1972年2月11日のライプ音源 (「アースバウンド」より)
05 1974年6月28日のライプ音源
まずトラック「01」~「03」まではイアン・マクドナルド(sax,fl,key,vo,vib,etc.)、ロバート・フリップ(g,key)、グレッグ・レイク(el-b,vo)、マイケル・ジャイルズ(ds,per)、そして曲作りやステージの演出を担当する詩人のピート・シンフィールドによる公式デビュー時の音源です。
ただしトラック「01」は「02」のスタジオバージョンを短く編集したもので、おそらくは1976年頃に何故かイギリスで発売されていたシングル盤に収録のものでしょうか? 残念ながらサイケおやじは件のシングル盤を未聴なので、確かは事は言えませんが、「02」を存分に堪能した自分にとっては、物足りないことが否めません。
ですからキング・クリムゾン名義としては、現存する公式ライプソースの中で最も古いとされるトラック「03」が興味深いのは当然でしょう。
そして期待に違わず、激しく混濁しながら狂気と妄想の世界を強烈に構築していくバンドの演奏が唯一無二!
もはやサイケおやじの稚拙な筆など不要であり、まさに聴かずに死ねるかですよ。
気になる音質も、流石はBBCでのスタジオセッションですから、ブートで流出していた頃からの優良保証が、ここでは更なるリマスターで迫力が増していますし、メンバー各々担当パートの分離も素晴らしく、そこから噴出される強烈なアドリブとバンドアンサンブルのスリルはオリジナルバージョンを凌ぐ瞬間さえあると思います。
ですから公式ライプ音源としては「アースバウンド」でお馴染みの「04」が、ロバート・フリップ(g)、メル・コリンズ(sax,key)、ボズ・バレル(b,vo)、イアン・ウォーレス(ds,per) という暴力的なメンバーで演じられた事が賛否両論であったとしても、例によって終盤での緊張感あふれるキメのリフの意思統一作業があるかぎり、それぞれにバラバラだった演奏者が収斂していく様は痛快!
ちなみにこの「04」はアナログ盤時代は些かモコモコした音でしたが、ここに収められたリマスターバージョンはスッキリして聴き易く、それゆえに失われてしまった重量感との引き換え差異は十人十色のお好みでしょうか……。
個人的にはアナログ盤を支持したくなりますが、これはこれで楽しめる事は言うまでもありません。
さて、そこでオーラスのトラック「05」は、記載データを信ずれば、おそらくは一般流通として、このCDが発売された1996年夏の時点では、ここでしか聴けないというライプ音源でした。
メンバーはロバート・フリップ(g,key)、ジョン・ウェットン(b,vo)、ビル・ブラッフォード(ds,vo)、デイヴィッド・クロス(vln,key,vo) という4人組で、ファンの間ではメタル期と称されるほどの硬質な演奏が繰り広げられ、中でもドラムスとベースの突出した大暴れは、それまでのキング・クリムゾンというバンドイメージを壊しかねないほどのアンバランス感!?!?
そして反逆を許さずに抵抗するロバート・フリップとデイヴィッド・クロスの思惑違いが露呈したアドリブの応酬も、これまた大白熱!?!?
ですからグループの歴史の中のライプ音源としては、この時期が最も多くのファンに求められているものとして貴重極まりないのですが、現在では他にも様々なルートで出回っているようです。
ということで、やはり曲そのものの構成が凄いというしかありませんし、実演すれば緊張感が必須の怖さ満点! そんなものばかりを五連発で満喫出来るのは、自虐的幸福感の極みといって過言ではありません。
ただし、車の運転中には絶対に禁物ですよ。
思わず耳を集中させてしまう後には、軽い目眩さえ覚えますからねぇ~。
好きなものは本当は危険という、この世の倣いを痛感させられるのでした。