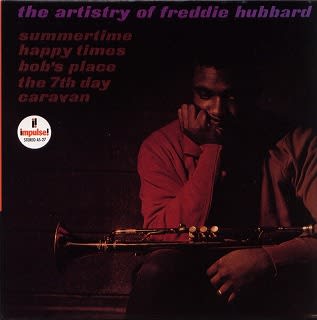■Max Roach 4 Plays Charlie Paker (Mercury)
モダンジャズの基本は全てチャーリー・パーカー(as) に帰結するというのは、歴史上の真実のひとつでしょう。ですから、多くのミュージシャンは「チャーリー・パーカーの楽曲」を演じることによって、ジャズの奥儀を極めんとするのでしょうか。
と、本日もまた、独断と偏見の書き出しではありますが、実際、私なんかはそうしたアルバムをノー文句で聴いてしまうんですねぇ。同系の企画盤としては「デューク・エリントン集」とか「セロニアス・モンク集」とかもあるんですが、一番「らしい」のは、やはり「チャーリー・パーカー集」だと思い込んでいるのです。
で、このアルバムもそのひとつとして、堂々のタイトルがつけられていますが、リーダーのマックス・ローチは全盛期チャーリー・パーカーのバンドではレギュラーを務めていたドラマーですから、説得力は十分!
その内容は当時のレギュラーバンドによる演奏ですが、メンツと時期が異なるセッションが収められ、まず1957年12月23日の録音はマックス・ローチ(ds) 以下、ケニー・ドーハム(tp)、ハンク・モブレー(ts)、ジョージ・モロウ(b) というお馴染みの面々♪ そして翌年4月11日のセッションになると、新鋭のジョージ・コールマン(ts)、実力派のネルソン・ボイド(b) がそれぞれ後任として交代参加しています。
A-1 Yardbird Suite (1957年12月23日録音)
チャーリー・パーカーのニックネームを「組曲」なんて大袈裟なタイトルにしていますが、その実態は有名スタンダード曲のコードを借りて改作した、ビバップ特有のものです。しかしここでも明らかなように、そのリラックスしたメロディ展開と曲構成は、エキセントリックだと先入観が強いビバップとは一線を隔していると感じますから、私は大好き♪
ここでの演奏も、そうした雰囲気を大切にしたゆったりテンポですが、マックス・ローチのドラミングは既にしてハードバップから離脱しつつある、所謂ポリリズムの萌芽があるようです。実際、終盤のドラムソロは実に躍動的ですよ。
またケニー・ドーハムやハンク・モブレーも、まったく自分達の個性に沿った安定感を聞かせてくれます。
A-2 Confirmation (1957年12月23日録音)
もちろんチャーリー・パーカーが作曲した幾何学的なメロディはビバップの聖典ですから、ここでのテンションの高い演奏は当たりまえだのクラッカー! アドリブ先発のケニー・ドーハムが必死のツッコミを聞かせれば、続くハンク・モブレーは悠々自適の「モブレー節」に専心しますが、ピアノレス編成でマック・ローチのドラミングに自由度が高い所為でしょうか、特にハンク・モブレーに微妙な浮遊感があって、妙な心持ちにさせられます。
そしてクライマックスではマックス・ローチの爆裂ドラムソロが堪能出来ます。その流れるように構築されるリズムとビートの嵐は、後のロックインストにも影響が大きいところでしょう。
A-3 Ko-Ko (1958年4月11日録音)
既に述べたように、この1958年のセッションではメンツが交代し、ジョージ・コールマンの参加が注目されるところでしょう。
曲はチャーリー・パーカーが自らのアドリブフレーズで作った、モダンジャズでは歴史的なリフなんですが、実は「アドリブ命」というのが、その真相!
ですからケニー・ドーハムが、「イブシ銀」なんてイメージをブッ飛ばす猛烈な勢いで疾走すれば、ジョージ・コールマンが恐るべき全力投球で、後に加わるマイルス・デイビスのバンドでのライブ演奏を彷彿とさせます。
しかし、このベースの居直ったような手抜きは??? 決して演奏スピードについていけないから? とは思いたくないのですが……。
まあ、そこのところを充分にフォローして大車輪のマック・ローチのドラムスが、劇的に強烈至極ですから、きっと意図的なんでしょうねぇ。結果オーライと納得するしかないのでしょうか……。
B-1 Billie's Bounce (1958年4月11日録音)
これまたモダンジャズの創成、ビバップの完成に大きく関与したチャーリー・パーカーが自作のブルース♪ その覚え易くて弾んだリフだけで最高の気分になりますねぇ。ジャズが好きになって良かったと思える瞬間が楽しめます。
ここでの演奏も、当然ながら躍動的なマックス・ローチのドラムスに煽られ、まずはジョージ・コールマンが全く正統派のアドリブを聞かせてくれますが、おぉ、ハンク・モブレーに似ていますねぇ~~~♪ ただし、本家に特徴的な「タメとモタレ」は当然ながら表現しきれず、まろやかでパワフルな黒っぽさだけを自分流儀で演じていますが、それでも高得点でしょう。
またケニー・ドーハムのクールなブルースフィーリングは、後の大名盤「Quite Kenny (New Jazz)」へとダイレクトに繋がる名演だと思います。
演奏はこの後、ネルソン・ボイドの堅実なウォーキングベースのソロとなって、その背後ではマックス・ローチが変幻自在な4ビート♪ そしてテンションの高いドラムソロへと繋がるのは、全くの美しき流れで、もう、たまりませんねっ♪♪♪
B-2 Arres-Vous (1957年12月23日録音)
フランス語みたいな曲タイトルになっていますが、これも聴けば納得というチャーリー・パーカーの有名オリジナル「Au Privave」ということで、アップテンポのハードバップが存分に楽しめます。
俺流を貫くハンク・モブレーに続いて登場するケニー・ドーハムが、特に良いですぇ~♪ もちろんマックス・ローチとの丁々発止も醍醐味です。
B-3 Parker's Mood (1958年4月11日録音)
そしてアルバムの締め括りは、もう、これしか無いのスロ~ブル~スのハードバップ的解釈が最高です。力強いペースとドラムスには、ある種の猥雑性が滲んでいますから、黒人モダンジャズのクールというカッコ良さが、存分に味わえるのです。
特にケニー・ドーハムが大名演ですよっ! ピアノが入っていない空間の自由度が、本当に何とも言えず、ジョージ・コールマンも素晴らしかぎり! マックス・ローチのテンションの高いブラシの妙技、またシンプルな音使いがジャストミートのネルソン・ポイドも、流石にレギュラーバンドとしての存在感を示していると思います。
ということで、単純な企画盤という感じから軽視される傾向の作品ですが、正統派モダンジャズとしては安心して聴ける1枚だと思います。中でもケニー・ドーハムの好調さは出色というか、所謂代名詞の「イブシ銀」よりは、クールな名演が聞かれますよ。
このあたりは、いろいろとあった1年、特に年末の哀しさから、どうしても安定感を求めてしまう今の自分の心境にはちょうど良い感じです。
思えば今年は5月頃からの仕事の多忙とゴタゴタでプログが中断に追い込まれたり、また有名人の突然死とか、世界的な不景気による閉塞感、政治の貧困や役人の独り善がり、そしてやるせない犯罪が多発した、本当に嫌な出来事ばかりが印象に残ります……。
そこで、せめて日頃の音楽鑑賞ぐらいは、楽しみと癒し優先でいきたいと思います。
本年は皆様のご厚情に支えられました。来る年もよろしくお願い致します。