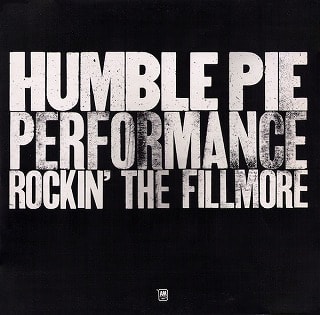■Humble Pie Performance Rockin' The Fillmore (A&M)
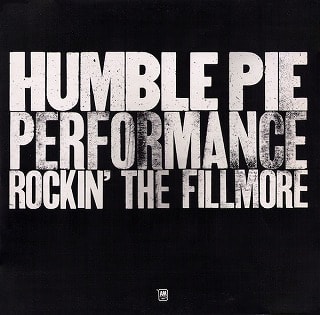
ロックの醍醐味のひとつがライプステージの熱狂にあるとすれば、演じていた歌手やバンドの大ブレイクに直結する事も度々なのが業界のひとつ慣わしですから、どのような事情があるにせよ、切り札的に作られるライプアルバムが人気アイテムとなるのはムペなるかな!?
例えば本日ご紹介の2枚組LPは、結成当時からスーパーグループと期待されながら、レコード会社の倒産や諸々の人間関係から煮詰まりかけていたハンプル・パイが1972年に出した起死回生の傑作盤です。
A-1 Four Day Creep
A-2 I'm Ready
A-3 Stone Cold Fever
B-1 I Walk On Gilded Splinters
C-1 Rolling Stone
D-1 Hallelujah I Love Her So
D-2 I Don't Need No Doctor
既に述べたようにハンプル・パイがスーパーグループ! と期待を集めたのは、本来は実力も業界では認められていたスモール・フェイセズとハードという、1968年当時最高のアイドルバンドで中心メンバーだったスティーヴ・マリオット(vo,g,key) とピーター・フランプトン(vo,g) がそこを脱退してまで組んだのですから、これは我国でもリアルタイムの洋楽マスコミでは相当な話題になっていたほどです。
そしてグレッグ・リドレー(b,vo)にジェリー・シャーリー(ds) という顔ぶれが揃っての公式デビューから翌年に発売されたシングル盤が傑作「あいつ c/w Wrist Job」だったのですが……。
首尾良く各方面で好評を得たのも束の間、ピーター・フランプトンの怪我やレコード会社の倒産によってマネージメントが縺れ、その流れの中で制作された2枚のアルバムも泣かず飛ばずでしたから、1970年に入ってアメリカのA&Mレコードと新たな契約に踏み切ったのも、心機一転というよりは、かなり切羽詰まった事情があったと言われています。
しかし如何にもアメリカ流儀の売り出し方として、頻繁なライプ巡業こなしながらのレコード制作&発売が、結果としてスモール・フェイセズもハードも果たせなかったアメリカでの大きな人気の獲得に繋がったのですから、グループの選択は正しかったわけです。
そして力強い2枚のアルバムを出した後、評判の高かったライプステージを決定打にするぺく作られたのが、この「パフォーマンス・ロッキン・ザ・フィルモア」と名付けられた、そのタイトルに偽り無しの大名盤!
1971年5月に今や伝説のフィルモアイーストで録られたそこにはハードで粘っこく、ソウルフルでロック魂に満ちた演奏がテンコ盛りに詰め込まれ、曲によってはLP片面全てを費やしたトラックがあるのは、如何にも当時のロックがその場のノリでやってしまうアドリブや盛り上げ方を重要視していた事の表れですし、また、そういう展開が出来なければ、これは一流のバンドと評価されない要因でもありました。
ですから、せっかくやった長尺演奏が退屈だったりしたら、それはもう自縄自縛の地獄と化すんですが、ご安心ください! ハンプル・パイは、たった4人で見事な熱演を披露しています。
なにしろ冒頭の「Four Day Creep」からして、これはアメリカの女性ブルース歌手として歴史に名を残すアイダ・コックスの十八番を見事なハードロックに仕立てるという、なかなか真に迫った熱演になっているんですが、特筆すべきは情熱優先主義に徹するスティーヴ・マリオットの黒いボーカルに対峙するピーター・フランプトンのギターが、実にメロディアスなフレーズの大洪水♪♪~♪
もう、最初に聴いた時から、こんなに歌心のあるアドリブソロって、本当は寝ないで考えたんじゃなかろうか……?? とサイケおやじは勘繰ったんですが、それこそがギタリストしてのピーター・フランプトンの持ち味なんですねぇ~♪
とにかくアルバム全篇を通して、それが溢れる泉の如く堪能出来るのですから、ハードロックギター好きには急所を鷲掴みにされたも同然でしょう。
一方、もうひとりの看板スタアたるスティーヴ・マリオットも負けじと奮戦! コテコテに粘っこく、火傷しそうに熱い歌いっぷりは言わずもがな、重心の低いサイド&リードギターはロックの本質を体現していますし、当時既に本格的な流行になっていたスワンプロック的なニュアンスも楽しめるのは、そこに由縁していると思います。
またドラムスとベースのゴリゴリ感も流石の一言で、実は有名すぎるR&Bヒットの「Hallelujah I Love Her So」、あるいはシカゴブルースの大定番「I'm Ready」や「Rolling Stone」が単なるブルースロックの焼き直しに陥っていないのは、グレッグ・リドレーとジェリー・シャーリーの個性派(?)コンビの頑張りにあるんじゃないでしょうかねぇ~♪
ですから、今に至るハンプル・パイと言えば、これが出ないと収まらない「I Don't Need No Doctor」が、実はレイ・チャールズの有名持ちネタである真相から遊離し、完全に自家薬籠中のオリジナルの如き人気を集めてしまったのも当然が必然です。
もう、このあたりはサイケおやじが稚拙な文章を弄するよりも、皆様には絶対に聴けずに死ねるか! そういう思い入れで楽しんでいただきたい名演なんですよっ!
それと長尺演奏の決定版として、これまた変形R&Bの「I Walk On Gilded Splinters」はメンバー相互間のアドリブ合戦とバンドしての意思の疎通が、なかなか危ういバランスの上で成立した奇蹟かもしれず、それゆえに紙一重のなんとやら……。
これまた、かなりの思い入れがないと、現代では聴き通すのが苦しくなる皆様もいらっしゃるはずですが、それは「ロック全盛期」の免罪符ってやつかもしれませんねぇ。告白すれば、なぁ~んて書いてしまったサイケおやじにしても、額に汗が滲むわけです。
しかし、その意味で純粋なバンドオリジナルの「Stone Cold Fever」が、妙にあっさりしているのは、この時期のハンブル・パイがひとつの限界に来ていたことの表れかと思います。
なにしろピーター・フラントンが、このアルバムの大成功を待たずしてグループを脱退したのも、闇雲にハード&ソウルフルな音楽性ばかりを全面に出す方針が人気の秘訣と知ったからと言われているとおり、本人はもっとメロディ優先の歌と演奏を希望していた事は、独立後に作られたリーダー盤を聴けは納得されるはずです。
ということで、これはロックのライプアルバム「ベストテン」は無理にしても、「ベスト50」には必ずや入るであろう名盤だと思います。
そして良く言われるように、ハンブル・パイとフリーは共に英国ロックのブルース&ソウル部門では「似た者同士」でありながら、決定的に異なる個性を持った稀有な存在であり、個人的にはフリーが豪胆ならば、ハンブル・パイは柔軟な姿勢があったように感じています。
ただし、それはピーター・フランプトンが在籍していた時までであって、後任としてデイヴ・クレムスンというロックジャズもイケるハードなギタリストが参加した事により、ハンブル・パイは尚更にドロドロした音楽性を硬派に演じていくのですから、逆に物分かりが良くなっていったフリーとの対比も、些か色あせてしまったように思います。
そこで絶対に忘れられないのが、やはり本日ご紹介のアルバム「パフォーマンス・ロッキン・ザ・フィルモア」でありまして、この傾向のロックを目指すバンドは日本も含めて世界中のグループが当時、お手本にしていたものです。
まさに聴いているうちに寒さもブッ飛ぶ、熱演盤!