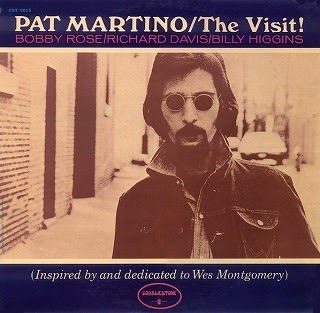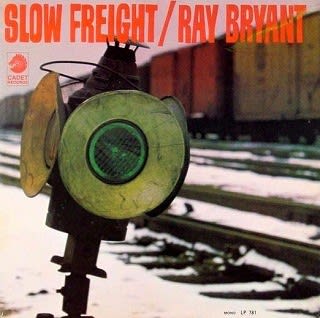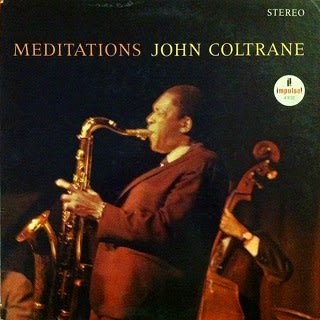■Gil Evans & Jaco Pastorius Live Under The Sky Tokyo '84 (Hi Hat = CD)
★Disc-1
01 Stone Free
02 Up From The Skies
03 Orange Was The Color Of Her Dress
04 Jaco Solo
05 Soul Intro / The Chicken
06 Here Comes de Honey Man / Eleven
07 Announce
★Disc-2
01 Jaco Solo / Goodbye Pork Pie Hat
02 Variations on the Misery / Jaco Solo
03 Dania
04 Announce
毎年、夏の風物詩とも言えるようになった野外フェスも、殊更1980年代のバブルが弾ける前あたりまではジャズの分野でも大盛況だった中にあって、1977年から始まった「ライブ・アンダー・ザ・スカイ」と称されたイベントは、大物ジャズ&フュージョンプレイヤーを豪華絢爛に招聘した事により、今や伝説となったライブギグも多く、例えば1977年と1979年の VSOP クインテットは知られ過ぎている感もありますが、本日掲載のCDで聴かれる、1984年のギル・エバンス・オーケストラと
ジャコ・パストリアスの共演ステージも、まさに様々な憶測や悪評も否定出来ない超・伝説、あるいは真・伝説!?
サイケおやじは幸運(?)にも、その現場に参集しておりましたので、当夜の印象を交えながら、この音源をご紹介させていただきます。
まず、何と言っても、
ギル・エバンスとジャコの共演という企画からして、発表された瞬間からの衝撃は大きく、特にジャコに関してはウェザー・リポートに加入してからの大ブレイク以降、その革新的とも言える斬新なエレクトリックベースのサウンドと演奏スタイルはジャズ者ばかりか、ロック&ソウルファンからも人気と注目を集めた存在でしたから、自身がリーダーとなったバンドでの来日公演も大成功していながら、この1984年当時は、ほとんど音信不通というか、あまり活動状況が伝えられていなかったわけで、今となっては、その頃のジャコは悪いクスリや大酒鯨飲等々から、心身共に不安定さを増し、その周囲からはミュージシャン仲間が去っていたという孤立状態だったそうですから、さもありなんと言えば、それまで……。
しかし、リアルタイムじゃ~、そんな内幕なんかは一般の音楽好きには知らされていなかったのですから、ビックバンドでの音楽構築に拘りつつ、大きな成果を残していたジャコがギル・エバンス率いるオーケストラに特参する企画は、まさに夢の中の正夢!?
サイケおやじにしても、ウェザー・リポートの来日公演以降、ジャコのライブには接する事が出来なかった事から、このステージは絶対に逃せないと覚悟を決め、万難を排してチケットをゲットしたわけですが……。
さて、当日の1984年7月28日、場所は東京よみうりランドの野外シアター・イーストに出向いてみると、リハーサルが長引いていたらしく、客入れが大幅に遅れている様子で、しかもやっと入場した時でさえ、ステージには囲いが設けられ、その中でリハーサルが続いていたという段取りの悪さは、そこから時折聞こえて来た奇声(?)や怒号(?)等々と共に、なんだか不穏な空気が感じられた記憶が残っているものの、それでもそんなリハーサルに音だけでも接する事が出来たラッキーな気分も確かにありましたですねぇ~~♪
ちなみにオーケストラの来日メンバーはギル・エヴァンス(key) 以下、ルー・ソロフ(tp)、マービン・ピーターソン(tp)、マイルス・エバンス(tp)、ジョージ・ルイス(tb)、クリス・ハンター(as)、ジョージ・アダムス(ts)、ハワード・ジョンソン(bs,tuba)、ピート・レヴィン(synthesizer)、ハイラム・ブロック(g)、マーク・イーガン(b)、アダム・ナスバウム(ds) という実力派揃いでしたから、ここにジャコが加わったらという、それは正しく未知との遭遇でしょう!?
そして待ってましたの開演は、ギル・エバンスがジミヘンをやらかす「Stone Free」と「Up from the Skies」の二連発!
ご存じのとおり、ギル・エバンスはジミヘンとの共演レコーディングを目論んでいながら、肝心のジミヘンが急逝した事により、その計画は頓挫したものの、体勢を立て直しての1974年に出したアルバム「ブレイズ・ジミ・ヘンドリックス(RCA)」の大成功によって世界中を驚嘆させて以降、ライブの現場でも度々ジミヘンの楽曲を演奏していた事は今日まで残された幾多の音源でも明らかですが、やっぱりリアルタイムの実演に接してみれば、そのゾクゾク感は格別!
とにかく何気ない始まりから、ググゥゥ~っと盛り上がって爆発する「Stone Free」ではクリス・ハンターが熱血のアルトサックスで泣き節アドリブを披露するんですが正直、デイヴィッド・サンボーンの代役みたいな存在という先入観があろうとも、これはこれでジャズの醍醐味でありましょう。
そしてハワード・ジョンソンのチューバのソロから、ハードフュージョンにどっぷり染まったハイラム・ブロックのギターソロが飛び出す頃には、本当にカッコイィ~~ジャズを聴いているという気分にさせられましたですねぇ~~~♪
またそこから自然に繋がっている「Up from the Skies」は、4ビートも入れたロックジャズになっていて、ここでもハイラム・ブロックが良い味出しまくりなんですが、お目当てのジャコは時折ステージに顔を出すというか、居並ぶメンバーのところへ行っては追っ払われるみたいな奇行が???
当然ながら、演奏ではマイク・イーガンがメインでベースを担当していたんですが、ちょっとでもジャコの姿が見えれば、それだけで観客は大騒ぎというハイボルテージな状況で、そんなこんなは、この音源にもしっかり記録されていますので、ご想像とご確認をお願いする次第です。
したがってチャーリー・ミンガスの古典「Orange Was The Color Of Her Dress」にもジャコの存在感は無いに等しく、それゆえに優雅な演奏が成立したのでしょうか、ジョージ・アダムスのシビレるテナーサックスが過激と和みのコントラストを見事に描いていたのは高得点でした。
あぁ~~、このサウンドこそ、ギル・エバンスの魔法ですよねぇ~~~♪
ですから、いよいよジャコが本格的に入ってのジコチュウにならなければ納得出来ない「Soul Intro / The Chicken」、またその前段としての「Jaco Solo」の煮え切らなさは、ますます観客をフラストレーションに誘ったが如き狂熱であり、告白すれば、その場のサイケおやじも燃えるジャズライブのルツボに落とされていたんですが……、それこそが生演奏に接する喜びであったに違いありません。
あぁぁ~、ルー・ソロフのトランペットとジョージ・ルイスのトロンボーンがモダンジャズの真髄に迫っていますっ!
ですから、続くジョージ・ガーシュイン作の有名ミュージカル曲「Here Comes de Honey Man」とギル・エバンスの十八番「Eleven」のメドレーが長~~い演奏になってはいても、ハイラム・ブロックのプログレ風味も交えたギター、ソニー・ロリンズ風の展開も披露するジョージ・アダムスのテナーサックス、ピート・レヴィンのシンセ、さらには荒っぽくてもビシっとキメるアダム・ナスバウムの力強いドラムスに爆裂するマービン・ピーターソンのトランペット等々、グッと惹きつけられるプレイは強烈至極ですよっ!
まさに、この音源のハイライトとも言うべき演奏だと思いますし、ここまでやられると、ジャコの存在、その好不調なんて、それほど問題にならないような気がするばかりなんですが、実際にジャコの出番なんて無くて、そのライブステージでも本人のベースの音はミックスで下げられていたような感じもありましたが、いかがなものでしょう。
しかしそれでもファンの熱狂は殊更ジャコ信者に物凄く、「Announce」で聴けるように、如何にもの手拍子で「サンサンナナビョ~~シ」が出てしまうあたりは、いやはやなんとも、それもニッポンの夏!?
ちなみに、この音源のソースは当時のNHK-BSで放送されたというクレジットがあって、サイケおやじも後に友人から頂戴したカセットコピーを聴いていたんですが、映像とかの完全版は、ど~なっているんでしょうかねぇ~~、とにかくここで解説放送されているのは、ジャズ評論家の児山紀芳先生であります。
で、そんなこんなの流れは、いよいよ Disc-2 で煮詰まり、「Jaco Solo / Goodbye Pork Pie Ha」ではツカミにあたるジャコのベースソロのマンネリ感というか、これまでの常套手段を聴けるだけで満足させられる事は確かですから、それでも「Goodbye Pork Pie Hat」でのクリス・ハンターの真摯な熱演には、ジャズを聴いているという喜びに震えてしまいますよ♪♪~♪
オーケストラサウンドの彩も素晴らしく、なかなかの名演じゃ~ないでしょうか。
これはジャコが後半、ほとんど音を出していなかった(?)結果かもしれません。
その意味でロックビートとモロジャズの4ビートが交錯する「Variations On The Misery / Jaco Solo」は混濁した痛快さが満点で、ジョージ・アダムスのテナーサックスやルー・ソロフのトランペットがアドリブの醍醐味を伝えてくれますし、リズム隊の伴奏というか、上手いバックアップは流石の証明なんですが、そ~なってみるとジャコの短いソロパフォーマンスが、なんだかなぁ……。
ついにはジャコ自作の「Dania」に入っても、グルーヴィなリズム的興奮にジャコ本人がノリ切れないというか、この不完全燃焼があっては、この日の伝説が悪評として残されたのも無理からん話と思います。
ただし、オーラスの「Announce」に記録されているとおり、サイケおやじを含むその夜の観客の熱狂は物凄く、実はそれこそが、このCD化された音源の最大意義だとしたら、伝説は伝説として、素直に後世へ残しておくのも悪い事ではないのでしょう。
ということで、あの夜から既に33年が過ぎ、ジャコもこの3年後には鬼籍に入ってしまったのですから、伝説の重みと深味は強くなるばかりとはいえ、やっぱり今となっては、ジャコの奇行というか、例のドロだらけでの演奏とか、ベースを掌の上で直立させてのバランス遊び等々、写真や映像で接するだけの事でも、その精神の危うさは押して知るべし……。
そんな紙一重の天才に会えただけでも、サイケおやじは納得して、この音源を聴いているのでした。