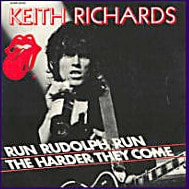今日は実家へ戻ろうと思ったのですが、どうせ家族は旅行へ行って留守だし、単身赴任でロンリーなお正月も、本当は楽しいというのが本音です。いや、負け惜しみではなくて♪
そして結局、仕事のあれこれに手を染めてしまった1日でした。まあ、神棚の掃除ぐらいはやりましたが。
ということで、本年の最後は美女ジャケで♪ 実は本年1月2日にもアップしたのですが、先日オークションで落札出来たアナログのブツが到着しましたので――
■Easy To Love / Roland Hanna (Atco)
美女ジャケットとして、大変に有名な1枚♪ もちろん彼女は、中身の演奏とは一切、関係がありません。
主役のローランド・ハナは黒人ながら、クラシック系のテクニックにも秀でたピアニストとして柔らかな歌心、ほどよい黒っぽさ、そして華麗なフレーズ展開が魅力の名手です。
しかもこのアルバムは、有名スタンダードを主体とした快演ばっかりですから、ジャケットに使われた美人モデルさんも本望でしょう♪
録音は1959年9月25日、メンバーはローランド・ハナ(p)、ベン・タッカー(b)、ロイ・バーンズ(ds) という正統派のビアノトリオです――
A-1 The Best Things In Life Are Free
A-2 Next Time You See Me
A-3 From This Day On
A-4 Like Someone In Love
B-1 Yesterdays
B-2 Farouk Thelonious
B-3 It Never Entered My Mind
B-4 Easy To Love
B-5 Night In Tunisia
まず、ド頭の「The Best Things In Life Are Free」が、いきなり美味しいメインです。歯切れの良いピアノタッチと明快な歌心、スイングしまくるアドリブ展開が実に爽快なんですねぇ~♪ またタイトル曲の「Easy To Love」も同系の素敵な演奏で、和みます。
サポートに撤するベースとドラムスも、なかなか手堅い好演で、ベン・タッカーは「Next Time You See Me」、そして「Farouk Thelonious」と2曲もオリジナルを提供し、存在感をアピールしています。もちろんロイ・バーンズのドラミングも素晴らしく、特にブラシでは良い味出しまくり♪ ブルースの「Next Time You See Me」ではトリオが一体となったグルーヴィな雰囲気を演出し、ちょいと硬派な「Farouk Thelonious」で軽妙なノリを生み出しているのです。
そして個人的に最も好きなのが「It Never Entered My Mind」のスローな味わいです。ローランド・ハナの綺麗なピアノタッチと素直なメロディ解釈が絶品! 完全なソロピアノからベースとドラムがスゥッと入ってくるところも、たまりません。こういう、きらびやかでありながら質素なところが、ローランド・ハナの魅力かもしれません。
ちなみにローランド・ハナはクラシックやジャズばかりでなく、非常に幅広い音楽性に裏打ちされた活動が基本姿勢らしく、スイング系ビックバンドから前衛派のセッションまで、分け隔てなく参加した録音が多数残っています。
そこで注目しておきたいのが、我国初の本格的ミュージカル映画「アスファルト・ガール」の音楽監督を務めたことです。この作品は1964年に大映で作られたのですが、主演女優の中田康子は大映の社長・永田雅一の愛人で、しかも東宝専属だったセクシーな美女♪ つまり彼女のゴキゲンをとるためにワガママを聞き入れて実現させた経緯があるのです。
残念ながら出来はイマイチなんですが、ローランド・ハナはサド・ジョーンズ(tp) やアルバート・ヒース(ds) と共に演奏部分には深く関わっていますので、DVD化を熱望しています。
ちなみに大映は、永田雅一のワンマン体制がこの頃から加速し、愛人・中田康子のワガママも影響したのか、時代の流れもあって経営が悪化して行ったのは歴史になっています。
まあ、これはローランド・ハナの責任ではありませんが、美女はやっぱり罪作りだなぁ……。と、このアルバムジャケットを見ると、何時も私は思ってしまいます。
ということで、本年もお世話になりました。毎日、独り善がりの戯言ばかりでしたが、皆様の暖かいコメントがあって、どうにか書き通せた感じです。
感謝しつつ、来年も頑張る所存です。
皆様には、素晴らしい新年を迎えられますよう、祈念しております。