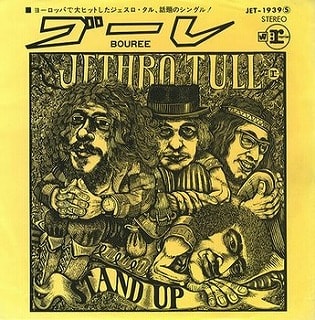■Minnows / Marc Benno (A&M)
1970年代前半のスワンプロックブームの中からはレオン・ラッセルやデラニー&ポニー等々のスタアも誕生していますが、同じサークルで活動していながら、ほとんど注目されなかったミュージシャンの方が、当然ながら大勢でした。
本日ご紹介のマーク・ベノもそのひとりとして、レコード会社はレオン・ラッセルの盟友的な売り方もしていたんですが、肝心の音楽性があまりにも地味……。
本国アメリカはもちろんのこと、我国でもリアルタイムで出されていたレコードが売れたなんて話は聞いたこともありません。
しかしマーク・ベノ本人でしか醸し出せない味わいは確固たるもので、その歌とギターはシブイ! その一言に集約されるでしょう。
特に掲載したアルバムは邦題が「雑魚」なんていう、ほとんどウレセンから遠く離れた世界に屹立する名盤で、やっていることはブルースやR&B、そしてゴスペルや民間伝承歌のゴッタ煮を白人的に解釈したという、これが泥沼系ロックの典型♪♪~♪
A-1 Franny
A-2 Put A Little Love In My Soul
A-3 Stones Cottage
A-4 Speak Your Mind
A-5 Back Down Home
B-1 Good Times
B-2 Baby I Love You
B-3 Baby Like You
B-4 Before I Go
B-5 Don't Let The Sun Go Down
上記演目は全てマーク・ベノ(vo,g,key) 本人が書いたものですから、所謂シンガーソングライターとしての存在感も強く、ですからクラレンス・ホワイト(g)、ジェシ・エド・デイヴィス(g)、ジェリー・マギー(g)、ボビー・ウォマック(g)、カール・レイドル(b)、ジェリー・シェフ(b)、ジム・ケルトナー(ds)、リタ・クーリッジ(vo)、クライディ・キング(vo) 等々、リアルタイムでスワンプロック最前線を形成していたメンツが力強いバックアップを演じているのも頼もしいかぎりです。
ちなみに発売されたのは1971年秋で、マーク・ベノにとっては単独リーダー盤の2作目にあたるのですが、録音はそれ以前の様々なセッションから少しずつ行われていたと言われていますから、ジャケットにも曲単位の詳細なメンバー構成は記載されていません。
しかしA面ド頭「Franny」のソウルフルにエグミの効いたサイドギターは、黒人ソウルの新感覚派として今も人気が衰えないボビー・ウォマックならではの匠の技に違いありません。もう、これだけで好きな人にはたまらない世界が現出し、もちろんサイケおやじもそのひとりですから、穏やかにして秘めた情熱が滲み出る歌と演奏には完全に虜になるのてす。
ただしマーク・ベノ本人の歌は決して熱血とか力みなんてものとは無縁ですし、ギターにしても長いアドリブソロは演じていません。逆に独り言のような歌唱がジワジワとファンキーな気分を作り出していく伴奏系ギターによって、実に濃厚な味わいとなり、それがこのアルバム全篇で楽しめるという趣向なのです。
しかも前述した助っ人の名手達が決して出しゃばることのない個性の表現とでも申しましょうか、単なる義務的なセッション演奏ではない自己主張が、マーク・ベノ本人の地味な感性と最高の相性になっているように思います。
それはグッと重心の低いグルーヴとエッジの効いたビートに支えられた「Put A Little Love In My Soul」や「Back Down Home」、正統派ブルースロックの「Stones Cottage」、シミジミ系ソウルパラードのお手本のような「Speak Your Mind」が収められたA面に特に顕著で、ソウルフルにしてハートウォームな女性コーラス隊の存在も良い感じ♪♪~♪
このあたりは本当に典型的なスワンプロックの見本市ですよ。
そしてB面に針を落とせば、当時の最新流行になりつつあったカントリロックをウエストコースト的に発展させた「Good Times」や「Don't Let The Sun Go Down」が、後のイーグルス人脈がやりそうな、実に良いムード♪♪~♪
また続く「Baby I Love You」はジム・モリソン在籍時最末期のドアーズのような、サイケデリックなブルースロックを分かり易くやってしまった演奏なんですが、後に仰天したのは、このアルバムセッションと同時期にマーク・ベノがドアーズのスタジオセッションに参加していた事実を知ったことです。
その所為でしょうか、これまた続くブルースロック「Baby Like You」のハート&ヘヴィな仕上がりが、さらにドアーズっぽく感じられるのですから、いやはやなんとも……。チープ&ディープなオルガンが曲者なんですよ。
おまけに全くイメージに合わない美メロのスローバラード「Before I Go」は、濃厚なメロトロンでも入っていれば、完全にプログレ!?!
いゃ~~、なんとなく青春映画の挿入歌という雰囲気さえ滲んでくるんですよねぇ。
もう、こんなん、「あり」ですかぁ~!?!
本当にマーク・ベノのスワンプロッカーというレッテルに疑問を感じてしまうほどです。
実は、これも後追いで聴いたレコードですが、マーク・ベノは1960年代にハリウッドでレオン・ラッセルとサイケデリックポップスのセッション録音を残しており、それはアサイラム・クワイア名義として2枚のLP等々に纏められているのですが、そこには所謂サージェントペパーズ系の万華鏡ロックが展開されていたのです。
ご存じのとおり、それは全く売れず、レオン・ラッセルはスタジオの仕事の傍らにスワンプロックの創成に携わり、マーク・ベノは失意の内に故郷のテキサスへ逼塞したという経緯が……。
しかし1970年、リタ・クーリッジのバックバンドにギタリストとして参加したことから再びレコード契約が成立し、この時期に作られたセカンドアルバムが「雑魚」ということで、決して単一指向のミュージシャンではないと思います。
それでも結果的に、このアルバムも売れたとは言えません。なんとか契約の上では3作目の「アンブッシュ」も発売されていますが、一説には無名時代のスティーヴィ・レイ・ヴォーンも参加したと言われる新作レコーディングは完全にオクラ入り……。以降、1979年まで消息不明となるのですから、現実は厳しいものです。
ただしその間に、この「雑魚」が隠れ名盤化した事実は、例えそれが我国のロック喫茶の中だけであったとしても、近年の再評価の対象になるのは喜ばしいことです。
またマーク・ベノ本人も1980年代末頃から再び表だった活動を再開し、ほとんど自主制作に近い形ではありますが、リーダー盤も作っていますし、確か数年前には来日公演も行われたと記憶しています。
まあ、正直にいえば、そのライプにも積極的に赴く覚悟が出来なかったサイケおやじですから、絶対に夢中になっているミュージシャンとは言えないのがマーク・ベノです。
それでも、このアルバムは別格!
聴くほどに味わいが深くなる大切な1枚なのでした。