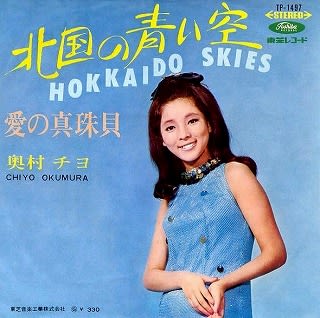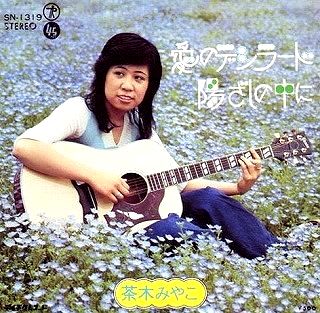■セーリング・ラブ / 松崎しげる (インビテーション / ビクター)
真夏の歌謡曲は決して女性アイドルだけのものじゃ~なくて、昔っから例えば橋幸夫、加山雄三、山下達郎等々、とにかく素敵なレコードがどっさり発売されてきました。
しかし、そういう季節商品は、それゆえに本人達の代表作には成り得ていないのも、深刻な事実かもしれません。
というのも、例えば本日掲載のシングル盤A面曲「セーリング・ラブ」は昭和54(1979)年に出た、これが歌っている松崎しげるの個性が存分に発揮された快楽のサマーソングでありながら、近年の夏場には全く顧みられないんですから、ちょっと気分はロンリーで、これを書いているというわけです。
ご存じのとおり、松崎しげるは我国屈指の実力派シンガーとして、昭和45(1970)年頃から幅広いジャンルの歌を聞かせ続けてきましたが、近年は特にテレビ出演時になると、代名詞ともなっている「愛のメモリー」ばっかりなんですよねぇ……。
もちろん十八番の歌い上げるスタイルは、そこで最高に発揮される事は分かっているんですが、もうひとつ忘れてならないのは、軽いフィーリングで歌い飛ばすようなソフトロックのグルーヴとでも申しましょうか、例えば初期のヒット曲「黄色い麦わら帽子」を聞かせて欲しいと思っているファンも多いはずです。
さて、そこでこの「セーリング・ラブ」は、如何にも当時の洋楽では流行最先端だったラテンフュージョンを大きく取り入れた快作で、具体的にはバリー・マニロウが前年からロングセラーにしていた大ヒット曲「Copacabana」を強く意識したものでしょう。
つまりド頭からノリまくった陽気なグルーヴが絶対の命であり、しかも鬱陶しさをリスナーに感じさせない歌唱力が求められるのですから、これを実力派の松崎しげる以外に誰が演じられるの!?
お叱りを覚悟で言わせていただければ、もしも夏男の括りで山下達郎が歌ったとすれば、妙にコブシが効いた仕上がりになっちまう気がしますし、西城秀樹じゃ~、汗ダラダラですからねぇ~~。
やっぱりここは松崎しげるのディナーショウ感覚というか、良い意味でのフロア人気が正解だと思うばかりです。
そして作詞:荒木とよひさ&作曲:馬飼野康二のヒットメーカーコンビが狙ったラテン歌謡の進化形を尚更にコンテンポラリーにしているのが、前田憲男、斉藤ノブ、植田芳暁、小笠原寛という4人連名のアレンジャー諸氏!
終始浮かれた調子のピアノとパーカッションが松崎しげるのボーカルと絶妙の対立構図を描き出せば、その熱気と涼風の心地良さには自然に腰が浮いてしまうはずですし、思わず一緒に歌いたくなるキメのフレーズも良い感じ♪♪~♪
あぁ~、これも昭和の夏だったんですよねぇ~~♪
ということで、なんとも行き詰ったムードから脱出する気配さえ、なかなか感じられない昨今の夏にこそ、松崎しげるには「セーリング・ラブ」を歌っていただきたいものです。
最後になりましたが、松崎しげるは左利きのギターも相当上手くて、昔はテレビでも時々やっていましたが、あのチューニングはど~しているんですかねぇ~~? 弦を上下逆さまに張り替えているとは見えなかったので、おそらくレギューで押さえ方を独自に作っていたんでしょうか?
それも最近、気になっているので、映像でしっかり確認したいなぁ~。