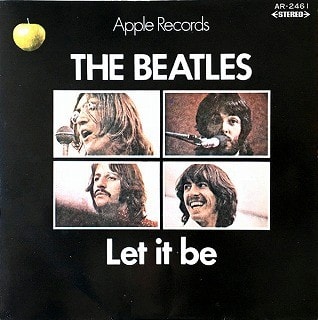ビートルズは歴史なので、今でこそ様々な資料が掘り起こされ、当時の一連の流れを眺める事が可能です。
しかし当時は、殊更日本では、そ~ゆ~情報に時間差があり、ポールの脱退&解散騒動は、一般紙でも報道されましたが、その頃のサイケおやじに分かっていたのは、ビートルズのメンバー同士の仲が悪くなっている程度の認識でした。
しかし……、映画「レット・イット・ビー」を観てしまった後になると、それは納得するしかない部分が確かにあったのです。
さらに、それよりも驚いたのは、新作アルバム「レット・イット・ビー」の評判が、特に評論家の先生方の間で、全く良くない事でありました。
それはもちろん当時、その製作に関するゴタゴタ諸々について、こちらが知らなかった所為もあるんですが、中でも個人的には気に入っていた「The Long And Winding Road」にポールが異を唱え、一部の音楽マスコミがボロクソに書いていた事は、ど~しても理解出来ませんでした。
それでも…… 暫くして、大きな要因はプロデューサーのフィル・スペクターが元々の素材を大改造してしまった所為と知れるのですが、その問題の「The Long And Winding Road」における、ポールに無断(?)で勝手にダビングされた大仰なストリングスパートのアレンジが、実はサイケおやじは大好きで、それが高じて、ついにはビートルズの曲をストリングスで演奏しているアルバムまで買ってしまったという、いやはなんともの告白をせねばなりません。
ですから、今でもフィル・スペクターは悪い事はしていないと信じているのですが、ただ確かに、アルバム「レット・イット・ビー」には、何とも言えない違和感がありました。
結論から言うとそれは、このアルバムは「ロックの音」がしていないっ!
と、いう事です。
もちろん、この結論は後付でサイケおやじが捻り出したものですが、最初に気が付いたのは、この作品の前に発表されたアルバム「アビー・ロード」との音の差異でした。
「アビー・ロード」には、何故あれほどまでの聴覚的快感があるのか?
それは曲が良い、曲の配列が良い、構成の妙がある等々の要因に加えて、音が見事にロックしていたからだと、サイケおやじは考えます。
そして、今にして想えば、それは「1970年代ロックの音」を先取りしていたと思うのです。
対して「レット・イット・ビー」はどうでしょう。
確かに膨らみと温かみのある音でした。しかし、そこからロックのエネルギーが感じられるでしょうか? あの細密に創りあげられた「サージェント・ペパーズ」でさえ、強烈なロックのエネルギーを放っていたというのに……。
もし……、フィル・スペクターが間違いを犯したとされるなら、サイケおやじは、この点だと思っています。
「其の拾参」でも少し触れた様に、フィル・スペクターのプロデュースの最大の特徴は厚みのある音作りです。それは演奏者の大量動員、例えばギターやピアノや打楽器等々のプレイヤーを複数集めて、一斉に演奏させる事や、出来上がったカラオケや録音したボーカルに過剰なエコーを施して生み出されるものですが、ひとつハズしてしまうと、本来迫力があるはずであった音がモコモコになってしまう、つまりエッジの無い音になってしまうのではないか?
と、思います。
その原因は、当時のレコード盤の状況にあり、フィル・スペクターが敢て、そういう手法で生み出した作品が最高の迫力で味わえるのが、モノラルの45回転シングル盤の世界でした。
特にフィル・スペクターが活動のベースにしていたアメリカでは、シングル盤のカッティング・レベルがとても高く、それは出力レベルの低い小さなレコード・プレイヤーやジューク・ボックスで使用されたり、あるいはAMラジオで放送されたりする事を前提にしたものでした。
ですから、それを基準にして作っていた所謂スペクター・サウンドは、当然33回転LPにも収録して当時から出回っていましたが、やはり回転スピードが遅いためにシングル盤と同じ迫力が再現出来ていませんでしたし、もちろんステレオ・バージョンも作られ、LPでは聴けましたが、矢鱈エコーばかりが強くて、これもダメ!?
以下はサイケおやじの完全なる独断と偏見です。
フィル・スペクターが全盛期に作り出していた楽曲の多くは、甘く切ないドリーミーな世界です。そういうものでは温かみがあり、膨らみがある音が合っていたからこそ、数多のヒットが生まれたのです。
ところがビートルズの出現により、彼の作り出していた音は時代遅れになりました。
それが何故かと言えば、ビートルズは所謂アメリカンポップス以前のアメリカの音、つまりチャック・ベリーやリトル・リチャード、そして初期エルビス・プレスリー等の粗野な音を持っていたからです。それがロックの音でした。さらにビートルズが新鮮だったのは、そうした音で、アメリカンポップスの香りが感じられる楽曲を歌い、演奏していた事でした。
もちろん、そこに自然な英国風の味付けが施されていたのは言うまでもありません。
ただし、これは彼等の勘違いから生まれたものだ、とサイケおやじは思っています。
それはビートルズが生まれ育ったイギリスのリバプールが、田舎であるにもかかわらず港町という事で、アメリカの流行歌のレコードが入荷し易く、多くの若者がロックンロールの洗礼を受けていた事と平行して、当時最新流行の音楽にも逸早く接する事が出来たという下地があったのですが、やはり情報不足は否めず、おそらく彼等は本格的にバンド活動を始めた60年代初期において、本場アメリカではロックンロールもアメリカンポップスも同時に流行っていると思っていたのではないでしょうか?
そして、その両者を上手く交ぜ合わせれば、素晴らしい音楽になるに違いない!?
アメリカでも成功するに違いないっ!
と、ある種の勘違いをしていたのでは……。
ところがリアルタイムのアメリカにおける芸能界の実情は、エルビス・プレスリーが兵役に取られていた事を筆頭に、チャック・ベリーはある事件でリタイア中、バディ・ホリーは飛行機事故で他界する等々、50年代に熱狂をまきおこしていたロックンロールは下火になり、代わって職業作家によって作られた楽曲を歌うアイドルの全盛時代になっていました。
で、その職業作家達、例えばその代表がバリー・マンやキャロル・キング、ニール・セダカ等で、フィル・スペクターも、その中に入っていたのですが、そ~ゆ~ソングライター達はロックンロールの8ビートに、それまでの主流だったジャズ系ポピュラーソングのコード進行に基づいたメロディーを乗せた楽曲を量産しておりました。
ただしそれは、ほとんどが白人ティーンエイジャーに向けたものですから、ロックンロールの毒気はシュガー・コーティングされた世界になっていました。
つまり、一番肝心の部分である、リズム的興奮が抜け落ちていたのです。
そこへ、ビートルズの出現です。
ビートルズの音楽は、その容姿共々に大人達からは顰蹙物でしたが、何故アメリカで受け入れられたかと言えば、黒人的でありながら黒人的ではなかったからだと思います。
その点は黒人的感覚で歌う白人歌手というエルビス・プレスリーのデビュー時もそうでしたし、また当時、ビートルズに唯一対抗出来たアメリカ産流行歌である黒人ポップスのモータウン・サウンドは、スペクター・サウンドの黒人的展開でした。
突き詰めれば、ここでサイケおやじが言及する「黒人的」とは、ビートを強調した強いリズム感覚、「黒人的では無い」とはジャズ系ポピュラーソングにおけるユダヤ人的感覚、あるいは北イギリス的感覚という白人的なメロディの導入です。
そして、この時点で「ロックンロール」は、今に続く「ロック」に変化したのだと、サイケおやじは妄想してしまうのですが、いかがなものでしょう。
結果として、フィル・スペクターは、その「ロックの音」に気がついていなかったと言うよりも、それでも頑なに自己の音世界に拘ったのではなかろうかと思います。このあたりは、スペクター的中華思想というか、彼の天才性の証明かもしれません。
そこで「レット・イット・ビー」ですが、「スペクターの音」は「Two Of Us」や「Across The Universe」、あるいは賛否両論あるにしろ「The Long And Winding Road」といった柔らさが持ち味の曲では、とても良く合っていると思います。
しかしながら、「One After 909」等々の屋上ライブで演奏された楽曲では、必ずしもそうではありません。
ここでは一応、既発曲であった「Get Back」が「スペクターの音」で収録されておりますが、それにしても、その味は薄めになっておりますし、より黒っぽい「Don't Let Me Down 」がアルバム「レット・イット・ビー」に入れられなかったのも、シングルB面はLPには収録しないという慣例に従った事ばかりでは無いと思うばかりです。
以上、サイケおやじが独断と偏見で思うところは申し述べました。
もちろん皆様からの、お叱りは覚悟しております。
ということで、アルバム「レット・イット・ビー」は「ロックの音」がしないという物足りなさを決定的に証明したかの様な事件が、1970年末に発生するのでした。
注:本稿は、2003年10月13日に拙サイト「サイケおやじ館」に掲載した文章を改稿したものです。