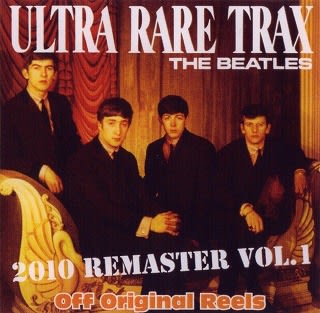■Ob-La-Di Ob-La-Da c/w While My Guital Gently Weeps
/ The Beatles (Apple/ 東芝)
リアルタイムの我国において、ビートルズの人気が頂点に達していたのは、おそらく昭和41(1966)年の来日公演の頃だったと思います。
しかし翌年になって、当時としては難解の極みだった「Strawberry Fields Forever」が出たことにより、何か一般的な人気が冷め始めたように思うのですが、如何なもんでしょう? 少なくともリアルタイムで少年時代のサイケおやじは、ついていけないものを感じていました。
また同じ頃、我国の芸能界はGSブームが爆発し、そこに登場していくる幾多のバンドは明らかにビートルズを筆頭とした「歌えるエレキバンド」を模倣していましたから、つまりは身近なアイドルに浮気してしまった大勢の女性ファンが、ビートルズ熱を冷ましてしまった一因ようです。
ちなみにその頃のラジオでも、やっぱりメインはGS曲で、ビートルズはあまり流れなくなったなぁ……、という感慨もあるのです。
しかし、そんなブームの諸行無常の中で、久々にビートルズが一般的に復活したのが、本日ご紹介のシングル曲「オ・ブラ・デイ・オ・ブラ・ダ」でした。
これは説明不要、ビートルズが1968年晩秋に出した2枚組LP「ザ・ビートルズ」に収録されていたわけですが、その通称「ホワイトアルバム」は我国でも翌年1月に発売されながら、なんと4千円という無慈悲な価格でしたから、中高生あたりには、その全てを自分の物として楽しむ事は不可能に近かったのです。
しかも当然ながらマスコミは、その内容の良さを喧伝していながら、それでもラジオの洋楽番組では特集として、件の新作アルバムから数曲を流すのがやっとという有様でした。
ちなみに当時は未だ国営FM放送でアルバムを丸ごと放送するなんていう、太っ腹な番組は無かったと思いますし、それは確か昭和44(1969)年春頃のスタートだったと記憶しています。
ですから、ますますビートルズの新譜に対する欲求不満は精神衛生からも全く厄介な存在として、これじゃ~、ビートルズの人気が落ちるのも、さもありなん……。
なぁ~んて、不遜な事を悔しい気分で思っていたのですが……。
そんな時期にラジオを中心にヒットし始めたのが、この「オ・ブラ・デイ・オ・ブラ・ダ」という、ウキウキと楽しい名曲でした。
うっ、これはビートルズのっ!?
当時のサイケおやじは、未だ「ホワイトアルバム」を全て聴いたことが無かったにも拘らず、ラジオで数回は接していた、このハッピーな歌が好きになっていましたから、てっきりビートルズかと思ったのですが……。
今日では、それはマーマレイドというイギリスのポップスグループが演じたカパーだろうという推測が当然でしょう。しかしサイケおやじの記憶では、幾つものカパーバージョンが同時多発的に流行っていたように思います。
中でも特に印象深いのが、我国GSの人気バンドだったカーナビーツの日本語バージョンでしたねぇ~♪ それが、デズモンドとモリーを太郎と花子に置き換えた、下段掲載のシングルです♪♪~♪
そして、そんな流行があれば、残るは絶対にビートルズのオリジナルバージョンですから、ついに昭和44(1969)年春、堂々のシングルカットが実現したのです。
しかも、このシングル盤は様々な意味合いから、今日でも話題の1枚なんですよ。
まず世界中で我国が先駆けた独自のシングルカットであることは、嬉しさの極みでしょう。なにしろ問題の「ホワイトアルバム」は高価な2枚組でしたからねぇ。
当然ながら、シングル用マスターなんてものは世界中に存在していませんでしたから、これは日本へ送られていたコピーマスターから制作した所為で、恐らくはリアルタイムで初めてのステレオミックスのシングル盤になっているはずです。
さらに我国では、これが初めての「アップル」レーベル使用の1枚!
そのあたりの事情は「Hey Jude」の項にも書きましたが、まさに記念すべきコレクターズアイテムになっていると思います。
肝心の楽曲そのものについては、仕上がりの楽しさとは裏腹に、今日では当時のビートルズの人間関係の悪さを象徴する1曲と認定されるほどで、実際、イントロから強い印象を残すピアノは、ポールから何回もダメ出しされたジョンが、マジギレしてのヤケッパチで弾いたもんだとか、ジョージやリンゴ、あるいは現場の制作スタップも含めて、ポールの横暴さには辟易していたという証言が山のように残されているんですから、この明るく前向きな歌とは裏腹な事情には、いやはやなんとも……。
また問題児のポールは、この曲の印象的な「オブ・ラ・デイ・オブ・ラ・ダ」というフレーズをジャマイカ人のセッションミュージシャンから盗作(?)したとか、いろんな問題行動もあるようですが、それにしても、これほどリスナーやファンを素直に楽しい気分へと導く歌もないでしょう。
流石はビートルズっ!
既に述べたように、「ホワイトアルバム」を買えなかったサイケおやじは、それゆえに他人から何を言われようと、ど~しても、このシングル盤をゲットしようと固い決意で入手したわけですが、手元にやってきたレコードへ針を落したのは、B面の「マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス / While My Guital Gently Weeps」の方が先でした。
というのも、A面の「オブ・ラ・デイ・オブ・ラ・ダ」は耳に馴染み過ぎるほど好きになっていましたが、もう一方の「マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス」はほとんど聴いた事が無く、しかし既に名曲名演という噂を耳にしていましたからねぇ~♪
これも今となっては説明不要だと思いますが、妙にアンニュイな気分にさせられる曲調とジャストミートしたジョージの音程が些か危ういボーカルの歌い回し、さらに素晴らしいアクセントというよりも、同等の主役を演じているエリック・クラプトンのギターソロ♪♪~♪
まさに泣いているギターの気分は、せつなさの極北でした。
ちなみに、ここでの参加ギタリストがエリック・クラプトンであるという真相は、何時の間にか知らされた情報ではありますが、既に当時は神様扱いだったギタリストがビートルズの助っ人を演じるというスーパーセッションには、震えるばかりです。
そしてミエミエの狙いが、ここまでズバッとストレートにキマッていながら、イヤミになっていないのは、万事が控えめだと思われていたジョージの人徳でしょうか。
とにかく「ホワイトアルバム」の収録作品中、ダントツの完成度を極めた名曲名演であることは否定出来ないでしょう。
そしてA面の何も考える必要の無い幸せ気分の歌とは正逆の、まさにB面に収録されるに相応しく、また勿体無い贅沢なシングル盤の構成には万歳三唱♪♪~♪
ということで、やはり「本命盤」とジャケットに堂々の記載があることに嘘偽りはありません。
時代的には永遠の名曲「Hey Jude」に続くシングルヒットとされる我だけの事情ではありますが、実は「オ・ブラ・デイ・オ・ブラ・ダ」の方がさらに世間には馴染んでいたように思います。
最近の暗い年末事情には、こういうノーテンキ直前のハッピーソングが求められるのかもしれませんね。