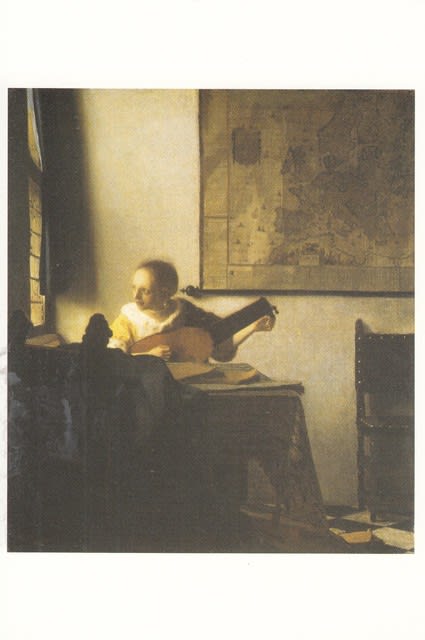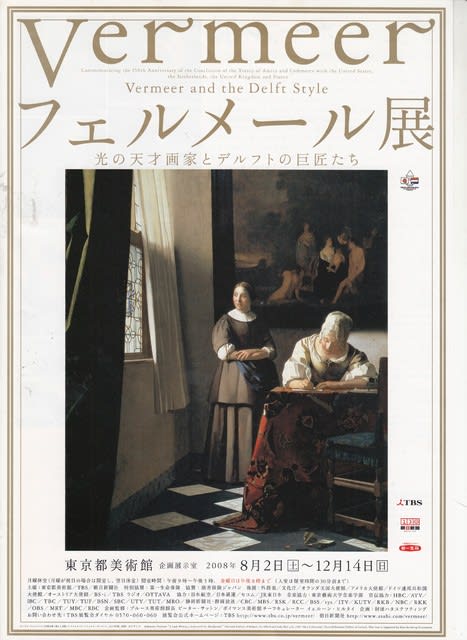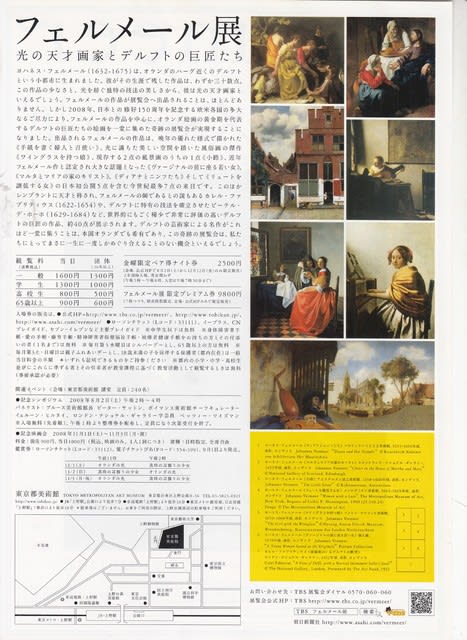日生劇場『生きる』、気温急降下の中、明日にしてしまうと7日連続でバスに乗ることになるので、なんとか今日無事に観劇してきました。ホリプロ主催の国産ミュージカル、黒澤明監督の映画を宮本亜門さんの演出でミュージカル化した作品。政府の緩和策にそって客席のソーシャルディスタンスは緩和され、生演奏でした。幕がおりたあとで観客のために演奏してくれる至福のひととき。オーケストラボックスに指揮者が立ち、生の音色が劇場に響く中に身を置くのは、1月の宝塚大劇場雪組公演以来かな。9カ月前のことになりますが、もっとはるか遠い日のことのような気がします。
30年間無遅刻無欠席で真面目に働き続けた市役所勤務の渡辺勘治が60歳で定年退職を迎えるまであと一年というとき、余命半年であることを知り、それまでの人生に反逆を企てて生きる喜びを知り、最後の半年間を生き抜いた物語。高校の卒業したあと勤めた地方銀行で定年退職を迎えた翌日胃がんで亡くなった方がいたことを思い出しました。戦争が終わって半年の日本が舞台。患者に真実を知らせることはタブーだった時代の物語。お金の使い方を知らないまま生きてきた彼が最後に自分はなにができるのかと自らに問いかけ成し遂げたのは市民の願いである公園をつくること。なぜ公園にこだわったのか。それは、妻を早くに亡くし、母親がいなくなったあと誰にも心を開かなくなった一人息子が笑顔を取り戻したのは一緒に公園に行った時だったから。その息子に真実を告げると入院させられてしまう、病院のベッドで死を待つのはいやだから公園ができたら知らせるつもりだった、自分には時間がない、このままでは死ねないと命の炎を燃やし、息子とすれ違ったまま公園再生のために命をかけて、開園式の前の日の夜出来上がった公園で倒れて最期の時を迎えた渡辺勘治。彼のそばには小説家がいました。最期の場面は描かれていなかったのですがお葬式の日、雪が舞い散る中をブランコをこぐ渡辺勘治をみんなが見守って幕。妹が亡くなった後勧められて映画をみたことがありますがそれから歳を重ねて、てんがいこどくとなった自分でみると沁みます。余命を知り、人のために動くことで生きる喜びを知った渡辺勘治。一日一日を生きる、それだけだと。
渡辺勘治はWキャストで鹿賀丈史さん。鹿賀さん、『レ・ミゼラブル』初演のバルジャン、ジャベール。この公演が始まってから70歳の誕生日を迎えられましたがさすがの歌声。願わくば市村正親さんもみたいですが無理でこうして一度だけでもなんとか観劇できてよかったです。死なないために次の土曜日は帝国劇場で『ローマの休日』、終演後シャンテでゆっくりしてしまうと最寄り駅からのバスの時間があぶなかったですが体はきつくても翌日休みの方が気持ちはゆったりと楽ちん。土曜日夜出ているか土曜日はゆっくりして日曜日の昼出るか、土曜日かな。
明日のことは誰にもわからないですね。一日一日を生きる。できることはそれだけ。今は今のためにある。豊かな老後を目指して生きているわけではない。老後のために今の時間があるわけではないとあらためて思ったのですがこんなこといっているとお金のない、みじめな老後が待っているだけですかね、死ぬまで働き続けなければならない見通しですが与えられた時間はわからない。神様から与えられた一度きりの人生の時間を生き抜くだけだということを渡辺勘治からおしえられました。あたたかい涙が流れた二時間でした。地方公演もあるので一人でも多くの方に今みてほしいと思いました。
日生劇場、ロビーに市村さんをはじめとするキャストのみなさんがコロナ対策への協力と注意を呼びかける映像が流れ続けていました。緊急連絡先登録用紙に記入して箱に投函しました。静かな劇場、スタッフの案内がいちだんと丁寧で恐縮するばかり。緩和策で少し賑やかになったかな。電車の中の広告がすきすきでコロナの影響は計り知れないなと思いました。こうして日比谷で劇場の幕が上がっている、それだけでほんとに尊い。



日比谷コテージには天使のあーちゃん(綺咲愛里さん)がいました。駆け足でパネル展の写真もなんとか撮ることができました。


東京宝塚劇場には次回の月組公演のパネルも。

電車の中でタブレット端末から投稿した記事を帰宅後パソコンで書き直しました。
ささやかなブログへの訪問、ありがとうございます。
30年間無遅刻無欠席で真面目に働き続けた市役所勤務の渡辺勘治が60歳で定年退職を迎えるまであと一年というとき、余命半年であることを知り、それまでの人生に反逆を企てて生きる喜びを知り、最後の半年間を生き抜いた物語。高校の卒業したあと勤めた地方銀行で定年退職を迎えた翌日胃がんで亡くなった方がいたことを思い出しました。戦争が終わって半年の日本が舞台。患者に真実を知らせることはタブーだった時代の物語。お金の使い方を知らないまま生きてきた彼が最後に自分はなにができるのかと自らに問いかけ成し遂げたのは市民の願いである公園をつくること。なぜ公園にこだわったのか。それは、妻を早くに亡くし、母親がいなくなったあと誰にも心を開かなくなった一人息子が笑顔を取り戻したのは一緒に公園に行った時だったから。その息子に真実を告げると入院させられてしまう、病院のベッドで死を待つのはいやだから公園ができたら知らせるつもりだった、自分には時間がない、このままでは死ねないと命の炎を燃やし、息子とすれ違ったまま公園再生のために命をかけて、開園式の前の日の夜出来上がった公園で倒れて最期の時を迎えた渡辺勘治。彼のそばには小説家がいました。最期の場面は描かれていなかったのですがお葬式の日、雪が舞い散る中をブランコをこぐ渡辺勘治をみんなが見守って幕。妹が亡くなった後勧められて映画をみたことがありますがそれから歳を重ねて、てんがいこどくとなった自分でみると沁みます。余命を知り、人のために動くことで生きる喜びを知った渡辺勘治。一日一日を生きる、それだけだと。
渡辺勘治はWキャストで鹿賀丈史さん。鹿賀さん、『レ・ミゼラブル』初演のバルジャン、ジャベール。この公演が始まってから70歳の誕生日を迎えられましたがさすがの歌声。願わくば市村正親さんもみたいですが無理でこうして一度だけでもなんとか観劇できてよかったです。死なないために次の土曜日は帝国劇場で『ローマの休日』、終演後シャンテでゆっくりしてしまうと最寄り駅からのバスの時間があぶなかったですが体はきつくても翌日休みの方が気持ちはゆったりと楽ちん。土曜日夜出ているか土曜日はゆっくりして日曜日の昼出るか、土曜日かな。
明日のことは誰にもわからないですね。一日一日を生きる。できることはそれだけ。今は今のためにある。豊かな老後を目指して生きているわけではない。老後のために今の時間があるわけではないとあらためて思ったのですがこんなこといっているとお金のない、みじめな老後が待っているだけですかね、死ぬまで働き続けなければならない見通しですが与えられた時間はわからない。神様から与えられた一度きりの人生の時間を生き抜くだけだということを渡辺勘治からおしえられました。あたたかい涙が流れた二時間でした。地方公演もあるので一人でも多くの方に今みてほしいと思いました。
日生劇場、ロビーに市村さんをはじめとするキャストのみなさんがコロナ対策への協力と注意を呼びかける映像が流れ続けていました。緊急連絡先登録用紙に記入して箱に投函しました。静かな劇場、スタッフの案内がいちだんと丁寧で恐縮するばかり。緩和策で少し賑やかになったかな。電車の中の広告がすきすきでコロナの影響は計り知れないなと思いました。こうして日比谷で劇場の幕が上がっている、それだけでほんとに尊い。



日比谷コテージには天使のあーちゃん(綺咲愛里さん)がいました。駆け足でパネル展の写真もなんとか撮ることができました。


東京宝塚劇場には次回の月組公演のパネルも。

電車の中でタブレット端末から投稿した記事を帰宅後パソコンで書き直しました。
ささやかなブログへの訪問、ありがとうございます。