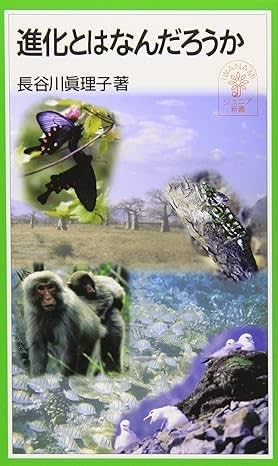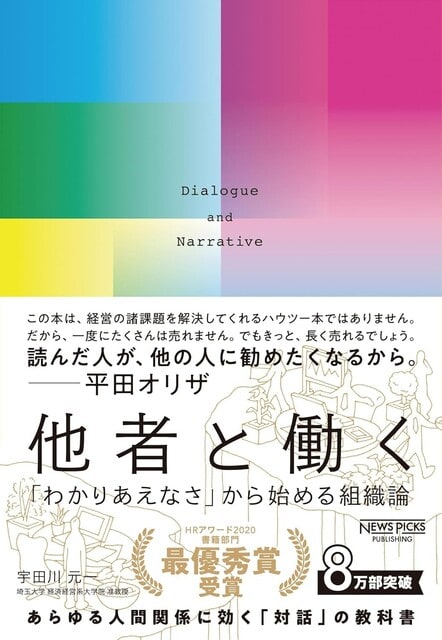参加している読書コミュニティでの「利他」をテーマとした課題図書の1冊。自分の認知の枠組みに新たな軸を与えてくれた1冊となりました。
筆者の贈与とは、「僕らが必要としているにもかかわらずお金で買うことのできないものおよびその移動」と定義します。身近なところでは、家族や友人、恋人との関係性などであるし、社会的には(補償金支払いの前提が無い)核廃棄物の処理場受け入れなどです。本書はその「贈与」の原理について、解きほぐすための「言葉」と「概念・思考」と併せて解明します。タイトルは「贈与」ですが、検討・記述範囲は広いです。平易に分かりやすく書かれてはいますが、内容は哲学そのもので意味深く、おそらく今時点では半分ぐらいしか理解できてないと感じる所です。
ただ、これまで深く考えることの無かった「贈与」というテーマについて考えることで、普段の自分の行動や取り巻く環境が違った角度で見えてくる新鮮さと驚きを味わえました。資本主義の真っただ中で生きることで、数値化、経済的価値、交換の発想が意識しないうちに染みついている多くの現代人に、お金で買えないものの存在、そしてその重要性(資本主義と矛盾するわけでもない)について気が付かせてくれます。(ただタイトルの「贈与でできている」は書きすぎで、サブタイトルの「『すきま』を埋める」ものとして贈与が正確)
「贈与」ということにここまで難しく考え抜かなくてはいけないのか?言葉遊びになってないか?と感じてしまう私も多分に感じながら、これからも本書を時折、読みかえすことになるでしょう。
2025年1月3日 読了
<印象に残った記述の抜粋>
・贈与を上げる人が嬉しいのは、贈与を受け取ってくれたということは、その相手がこちらと何らかの関係性、つまり「つながり」を持つことを受け入れたことを意味するから。
・親は自分の子供がその子供(孫)を愛するのを見て、自分の子供への愛の正当性を確認している。(pp..30-31)
・贈与はすでに受け取ったものに対する返礼(過去の負い目にもとづく)であり、受け取ることなく開始されることは無い。贈与は返礼として始まる。(pp..42-45)
・贈与の対抗は交換。交換するものが無い時、つながりや援助が必要
・贈与は、それが贈与と知られてはいけない。明示的に知らされる贈与は、見返りを求めない贈与から「交換」へ変わる。それは「呪い」(返礼義務の負い目)にもなる。
・(贈与における「受取人」の重要性)贈与は「受け取る」から始まる。受取人においては贈与は過去にある。贈与は差出人に倫理を要求し、受取人に知性を要求する。過去の中に埋もれた贈与を受け取ることのできた主体だけが、つまり贈与に気づくことができたしゅたいだけが再び未来に向かって贈与を差し出すことが出来る(pp..111-114)
・アンサングヒーロー:評価されることも褒められることもなく、人知れず社会の最悪を取り除く人。アンサングヒーローは、想像力を持つ人にしか見えない。アンサングヒーローの仕事にはインセンティブ(報酬)とサンクションが機能しない。アンサングヒーローは自分が差し出す贈与が気づかれなくても構わないと思うことができる。それどころか気がつかないままであってほしいとさえ思っている。なぜなら、受け取り人がそれが贈与だと気づかないと言う事は、社会が平和であることの何よりの証拠だから。自身の贈与によって最悪を未然に防げたからこそ、受け取り人がそれに気づかない。(pp..209‐213)
・贈与は僕らの前に、不合理なもの、つまりアノマリーと言う形で現れる。現代社会が採用しているゲームが等価交換を前提とし、市場経済と言うシステムを採用しているから。だからその中に存在している(商品じゃないもの)に、僕らは気づくことができる。だから贈与は市場経済の「隙間」に存在すると言える。市場、経済のシステムの中に存在する無数の「隙間」そのものが贈与。資本主義と言うシステム、市場経済と言うシステムが贈与をアノマリーたらしめる(pp..223‐224)
・ギブアンドテイク、winーwinの中から「仕事のやりがい」は生まれないのは、交換に目指したものだから。不当に受け取ってしまった。だから、このパスを次に繋げなければならない。誤配を受け取ってしまった。だから、これを正しい持ち主に手渡さなければならない。この自覚から始まる贈与の結果として、宛先から逆向きに「仕事のやりがい」や「生きる意味」が偶然帰ってくる。仕事のやりがいと生きる意味の獲得は、目的ではなく結果。目的はあくまでもパスをつなぐ使命を果たすこと。このような贈与によって、僕らはこの世界の「隙間」を埋めていく。この地道な作業を通して、僕らは健全な資本主義、手触りの暖かい資本主義を生きることができる。(pp..242-244)