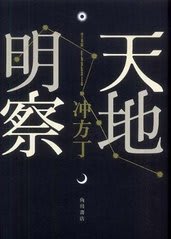ピカデリーサーカスと並んでロンドンのへそと言えるトラファルガー広場。その北辺には美の殿堂ナショナル・ギャラリーが堂々と構える。そしてそのナショナル・ギャラリーの裏にひっそりと佇むのがナショナル・ポートレート・ギャラリー。入り口は狭く、陽も殆ど当たらないが、中に一歩足を踏み入れると、イギリスの肖像画の歴史と伝統に圧倒される。16世紀のヘンリー八世やアン・ブーリンから現代のエリザベス女王や故ダイアナ妃やキャサリン妃に至るまで、皇族・政治家・学者・商人そして市井の人々に至るありとあらゆる人々の顔がある。肖像画の鑑賞ってこんなに面白んだと気づかされると同時に、年代別の配置はまさにイギリス史そのものである。
本書は、その英国における肖像画の歴史を追いながら、その歴史的背景を紹介する。タイトルは「肖像画で読み解くイギリス史」だが、むしろ「英国肖像画の歴史」という方が内容にはぴったりする。ナショナル・ポートレート・ギャラリーに行ったことのある人、これから行く予定のある人には必読、そのいずれでもなくても美術好きの人にも、自信を持っておすすめできる優れた本だ。
まず、時代時代の肖像画にまつわる物語が実に面白い。能面のように描かれるエリザベスI世の肖像画の秘密、18世紀イギリスのセレブであったメアリー・ロビンソン女史の波乱の一生と肖像画、作家サミュエル・ジョンソンの「変」な肖像画の背景など興味深いエピソードに満ちている。そして、洗練されていて、読みやすく、読者を惹きつける文章により、肖像画のモデルたちが生命を与えられたかのごとく生き生きと迫ってくる。
美術史の知識としても勉強になる。肖像写真の登場がラファエル前派に与えた影響、イギリスの肖像画の伝統を引き継いだのがアメリカ系のホイッスラーであり、サージェントであったこと。そして、サージェントがシェイクスピアの題材を使って描きつつ、物語には存在しない場面を描くことで作品と作者のオリジナリティを発揮したという指摘などには、「なるほど~」と唸らされた。
「だからもう、わたしたちもこのあたりでいいかげん、気づいてもいい頃だ。イギリスの無数の肖像画がこれまでずっと伝えつづけてきた、あるひとつのメッセージに。人と人の生きる世界には、いつかどこにも必ず、美がある。ただ、それだけのことに気づけたなら、わたしたちの日々もたちまち色鮮やかな断片と化していく。」(p255)と結ばれる本書は、肖像画の魅力を余すことなく伝えてくれる。本書を読んで、ナショナル・ポートレート・ギャラリーを再訪したくなった。