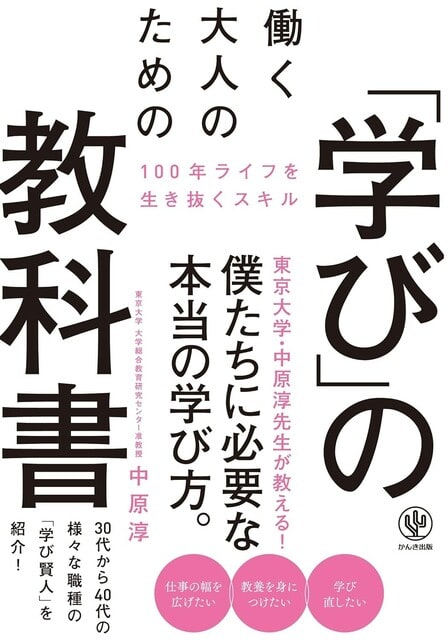自主読書会の課題図書として読んだ。「一汁一菜」をキーワードに、日本人の食事、生活についての筆者の思いが打ち込まれた一冊。
「栄養的に一汁一菜で本当に大丈夫?」「復古主義的過ぎないか?」と感じるところもあったが、食事の意味合いや重要性について、私自身、日常であまり意識していないことが、分かりやすく言語化されていた。改めて食について見直す機会になり、気づきの多い書である。
文化・伝統・自然としての食事の意味、「ハレ」と「ケ」の区別、家庭料理の重要性、家庭料理・チェーン店・料理店(レストラン)の機能の違い、箸・茶碗・お膳なので食器類の重要性などなど、子供の時からの今に至るまでの今までの食にまつわる自分史についても振返ることができる。
「一汁一菜」という表面的なアウトプットに目を奪われるのではなくて、その考え方・思想について理解し、日常に取り入れるところまで実践したい。一方で、時間の余裕無し・誘惑多しの現代社会においては、実践にはそれなりの意思が必要だろう。まずは、これまでの人生で単身赴任期間を除いて殆ど料理をしてこなかった自らの行動改革から始めるとするか。
(自分のための引用メモ)
・人間は食事によって生き、自然や社会、他の人々とつながってきたのです。食事はすべての始まり。生きることと料理する事はセットです。(p15)
・一汁一菜とは、ただの「和食献立のススメ」ではありません。一汁一菜と言う「システム」であり、「思想」であり、日本人としての「生き方」だと思います。(p16)
・人間の能力の1つ発達してきたものが、それぞれの風土の中で民族の知恵となりました。ですから、食材に触れて料理すると、意識せずともその背景にある自然と直線的につながっていることになるのです。(p21)
・私たちがものを食べる理由は、おいしいばかりが目的ではないことがわかります。情報的なおいしさと、普遍的なおいしさとは区別するべきものです。(p26)
・家庭料理を失った食文化は、薄っぺらいものです。家庭料理は人間の力です。(p31)
・日本には、「ハレ」と「ケ」と言う概念があります。ハレは特別な状態、祭り事。ケは日常です。日常の家庭料理は、いわば家の食事なのです。手をかけないで良い。そのケの料理に対して、ハレ晴れにはハレの料理があります。両者の違いは「人間のために作る料理」と「神様のために作る料理」と言う区別です。 (p32)
・人間にとって人生の大切な時期に手作りの良い食事と関わることが重要です。新しい家庭を築く始まりに、また、子供が大人になるまでの間の食事が特に大切だと思います。そして、自分自身を大切にしたいと思うなら、丁寧に生きることです。(p.45)
・料理することのない人生は、岡潔が「生存競争とは無明でしかない」とすることにも重なるのかもしれません。無明とは、仏教で言うと、人間の醜悪にして恐ろしい一面です。(p.46)
・家庭料理に関わる約束とは何でしょうか。食べることと生きることとのつながりを知り、一人一人が心の暖かさと感受性を持つもの。それは、人を幸せにする力と、自ら幸せになる力を育むものです。持続可能な家庭料理を目指した一汁一菜で良いと言う提案のその先にあるものは、秩序を取り戻した暮らしです。一人ひとりの生活に、家族としての意味を取り戻し、世代を超えて伝えるべき暮らしの形を作るのです。そしてまた、一汁一菜は、日本人を知り、和食を知るものでもあるのです。(p96)
・人間の暮らしで一番大切な事は、一生懸命生活することです。料理の上手、下手、器用、不器用、要領の良さでも悪さでもないと思います。一生懸命した事は1番純粋なことです。そして純粋である事は最も美しく、尊いことです。それは必ず子供たちの心に強く残るものだと信じています。(p.99)
・お料理と人間との間に、箸を揃えて、横に置くのは、自然と人間、お天道様から生まれた恵みと、人間との間に境を引いているのです。私たちは「いただきます」という言葉で結界を解いて、食事を始めるのだと考えられます。(p.139)
・よそ行きのものよりも、毎日使うものを優先して、大事にしてください。人間は道具に美しく磨かれることがあるのです。家族それぞれ、自分に自分のお茶碗や湯のみ、お箸と決められたものを「属人器」といいますが、日本を含む東アジアの一部だけのことらしいです。それによって、自分だけが使うものに強い愛着、心(愛情)を持つのです。 (p.170)
・お膳を勧めるのは、お膳の縁が、場の内側と外側を区別して、結界となるからです。(p178)