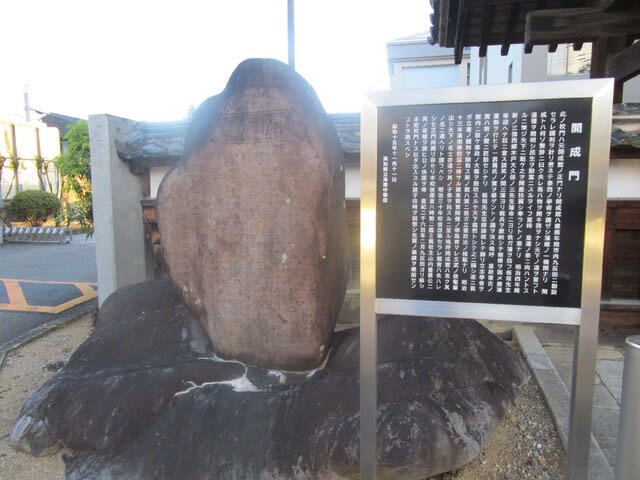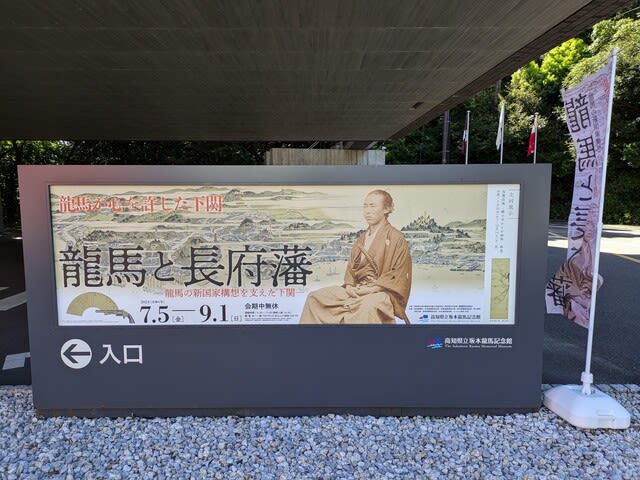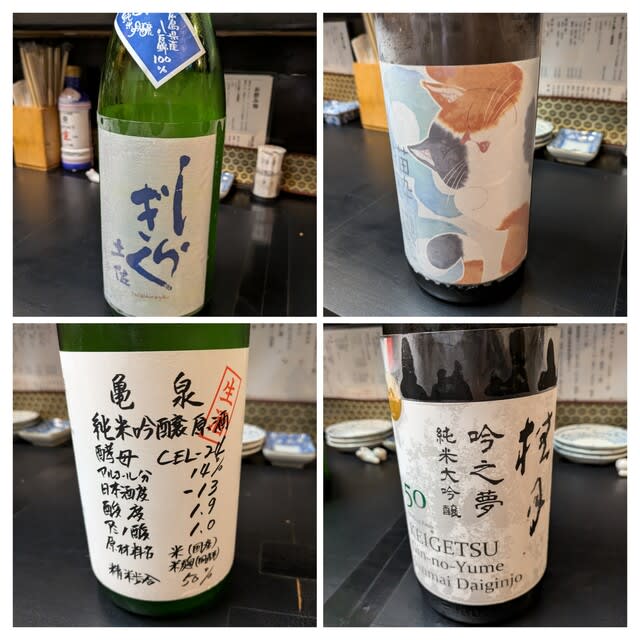3日目。帰京は翌日だが、朝一番の飛行機なので、この日が活動最終日。行先は悩みに悩んだ。仁淀川・久礼を経由して四万十川まで足を伸ばすのがもともとの計画だったが、暑さと各スポットの面白さで想定以上に体力消耗していて、往復200キロになるであろう四万十川への日帰りは、ただ行って帰ってくるだけのドライブになりそうな予感。四万十川は次回の訪問を誓って断念した。
ということで、この日は仁淀川と久礼を主要訪問地に設定し行動開始。
【仁淀川 沈下橋】
仁淀川は四万十川に劣らず、その透明度の高さで有名な川(水質日本一)だが、下流水域は高知市街から15キロほどしか離れていない。あえて高速道は使わず、国道を使って高知郊外の風景を楽しみながら西方向に向かった。途中、昔、甲子園を沸かせた伊野高校があったり、JR土讃線ととさ電(高知市街から伸びている路面電車)が国道を挟んで並行して敷設してある区間があったりで楽しかった。
仁淀川に出ると、川に沿って北上。この辺りは土佐和紙の産地であるようで、工房や博物館がある。中流域に達すると、写真や映像ではよく見かける沈下橋なるものがあった。水量が増した際に橋が水面下に沈むようになっている、欄干が無い橋である。ここの橋は名越屋沈下橋と言い、仁淀川で最も下流にある沈下橋で、長さ191mと仁淀川に架かる沈下橋の中で一番長い橋とのこと。車を止めて、橋や周囲を散策。車一台分ほどの幅しかないが、住民の生活道路の一部でもある。車が通るときの、通行人の一時退避場所も確保されていて、なるほどこういう仕組みなのかと納得。



広い河原、美しい水と川、周囲を覆う緑。いかにも四国っぽい風景に暫し浸る。のどかな風景の一部となった心地よさは格別だ。



【にこ淵】
更に、上流に上って、「仁淀ブルー」で有名なにこ淵に向かう。途中で本流から離れるので、正確には仁淀川では無い。名護屋橋から30キロ程、30-40分で到着。
山に囲まれた谷合の淵なので、谷にかかった金属製の急階段を80段ほど降りて、淵に到着。確かに美しい水が輝くさまは神秘的な美しさである。時間は丁度11時前。太陽が頂点に向かって上がっている最中で、時間が経つに従って、光に反射して水の青緑の度合いが高まり、どんどん美しさを増していく。ここの美しさは、天気と時間に大きく左右されることが実感として分かった。天気はパーフェクトだったが、時間帯は太陽が一番上に上る(谷を上から照らす)正午前後がベストだろう。逆に朝方や夕刻では、淵に陽が当たらず、輝きは味わえないだろう。



しばしその場に佇み、エリア一杯に満たされているマイナスイオンを浴び、吸い、体を浄める。とっても涼しいというまでには至らないが、下界の暑さはここでは感じない。エネルギーが満たされていく感覚を味わった。

仁淀川には、まだまだ渓谷や他の沈下橋などまだまだ見どころはあるようだが、後ろ髪引かれる思いで、この日のもう一つの目的である久礼大正市場に向けて出発した。

※「にこ淵」に行かれる方は、天気や訪問時刻を最大限考慮したほうが良いです。天気はコントロール難しいですが、極力、太陽が出る日。訪問時刻はお天道様が高く上がる正午付近。きっと季節により陽の位置も違うだろうから影響しそうですが、私にはわかりませんでした。
(3日目 午前)