0150909
ミンガラ春庭ニッポニアニッポン教師日誌>2015ヤンゴン教師日誌(3)ヤンゴンの留学生たち
私の授業のTA(ティーチングアシスタント)をつとめてくれているのは、派遣元大学で学んでいる学生たちです。1年生のときにショートステイで1ヶ月のヤンゴン生活をするプログラムは必修ですが、3,4年生のときに1年間の留学を希望する者は毎年数名。
2014年12月から始まった学期に留学してきたのは、学部生3人と修士課程院生1人。女性2人男性2人です。その4人が、月火、木金の担当を決めてTAをしてくれることになっていたのですが、月曜日担当の修士院生は「修論の資料集めが忙しい」という理由で、デング熱にもかかって苦労した火曜日担当の女子学生は「体調が悪い」という理由で、TAは担当できず、木金だけTAがいます。
日本語教室の手伝いにはあまり来られない院生も、私のためにヤンゴン用のケータイを買ってきてくれるなど、みな親切です。4人ともとても優秀な、性格のよい人たちでしたが、日本語教育への興味の持ちかたは、学生それぞれです。
派遣元大学からTAには「心ばかりの謝金」が出ます。日本円にすれば最低料金にも届かない額ですが、それでも90分授業を手伝うと、こちらの学食でなら数回回食事ができるくらいにはなります。学食は安いので。
1年留学の最後の時期に当たるので、留学生たちのビルマ語は、相当上達しています。9月末に日本に帰国したら、10月からはビルマ語で卒論や修論を書く人たちなので、日常会話はむろんのこと、学術的なことも言えます。
8月中は、ショートステイの学生が10名学生寮に滞在していました。その中で日本語教育に興味を持った学生が、授業を見学したいと、申し込んできました。私は日本語教授法の教師でもありますから、「見学するだけなら、お断り。毎回TA補助員として、授業のお手伝いをしてもらいます」と、見学を許可しました。毎回3~5名が顔を出し、私の指示によってリピート練習の範読を担当しました。
90分授業全部をひとりでこなし、リピート練習の声出しをしていると、のどが枯れます。小さい声でマイクを使う先生もいますが、私は地声でやりたい人なので。
リピート練習で同じことを繰り返し範読するのが嫌い、という私のわがままもあります。範読を繰り返すだけなら、教師はテープレコーダーと同じじゃないの、と思ってしまうからです。むろん、教師の生声でリピートしたほうが、ずっといい効果が出ます。学生の出身地にによって多少のアクセント違いなどがありますが、訓練されたアナウンサーの標準アクセントのCDを聞かせるより、生の声のほうがリピートにもはりあいがあります。
TAおよびTA補助員のおかげで、リピート嫌いの私でも、リピート中心の当地の語学教育の伝統を壊すこと無く授業を進められました。感謝です。日本から来てビルマ語を学んでいる学生と、日本語を学んで日本へ留学したいミャンマー人学生の交流も果たせたことは、当地に日本語教室を開いた成果のひとつだと思います。
授業に出席し日本語教育を受けた受講生のうち、3名の女子学生は、10月からの日本派遣が決定しました。日本語の定着度はそこそこですが、これから日本でさらに日本語学習に励んでくことでしょう。
行
ショートステイ日本人留学生が20日間の短期留学を終えて修了式を迎え、学科長主催の食事会が開催。されました。日本へ留学することが決まった3人娘が「修了式の手伝い」として出席し、修了証を手渡すときの補助などを務めていました。
修了式の会場レストランに入る日本人ショートステイ留学生と、日本へ留学する3人のミャンマー人女子学生。送迎のバスの車体には「シャトー猿ヶ京」と書いてありました。中古バスの再利用です。群馬県の温泉ホテル。「わぁ、なつかしい、この温泉ホテルに泊まったことがあります」と言いました。

3人とも黄色い衣装を着ているので、打ち合わせたのかと思ったら、「日本の人が同席する会だから、ミャンマーの国花の色のロンジーを着ようと思って選んだら、3人とも同じ考えだった」と、服装が同じような黄色になった秘密を教えてくれました。私が青いシャツを着ているのは、月曜日と金曜日、教師は青系の衣装を着る、という伝統によるものです。私は外国人教師なので、ロンジーを着るかどうかも自由です。
当地の女性教師のロンジーは、同じような青い色に見えても、柄によって、准教授なのか、教授なのかなど、細かい身分差があるのだと、聞いたので、セヤマー(女教師)のひとりに尋ねてみました。そんなことはない、どんな柄を選ぶのでも自由です、というこたえでした。
中国清朝の官僚制度でも、自宅の門構えやら階段の段数にまで身分による細かい差がありましたが、当地の「青い衣装の柄によって身分がわかる」というのも、昔はそういうしきたりがあったのかも。
日本へ留学することが決まった日本語受講生3人娘。みな笑顔がかわいいです。

<つづく>
ミンガラ春庭ニッポニアニッポン教師日誌>2015ヤンゴン教師日誌(3)ヤンゴンの留学生たち
私の授業のTA(ティーチングアシスタント)をつとめてくれているのは、派遣元大学で学んでいる学生たちです。1年生のときにショートステイで1ヶ月のヤンゴン生活をするプログラムは必修ですが、3,4年生のときに1年間の留学を希望する者は毎年数名。
2014年12月から始まった学期に留学してきたのは、学部生3人と修士課程院生1人。女性2人男性2人です。その4人が、月火、木金の担当を決めてTAをしてくれることになっていたのですが、月曜日担当の修士院生は「修論の資料集めが忙しい」という理由で、デング熱にもかかって苦労した火曜日担当の女子学生は「体調が悪い」という理由で、TAは担当できず、木金だけTAがいます。
日本語教室の手伝いにはあまり来られない院生も、私のためにヤンゴン用のケータイを買ってきてくれるなど、みな親切です。4人ともとても優秀な、性格のよい人たちでしたが、日本語教育への興味の持ちかたは、学生それぞれです。
派遣元大学からTAには「心ばかりの謝金」が出ます。日本円にすれば最低料金にも届かない額ですが、それでも90分授業を手伝うと、こちらの学食でなら数回回食事ができるくらいにはなります。学食は安いので。
1年留学の最後の時期に当たるので、留学生たちのビルマ語は、相当上達しています。9月末に日本に帰国したら、10月からはビルマ語で卒論や修論を書く人たちなので、日常会話はむろんのこと、学術的なことも言えます。
8月中は、ショートステイの学生が10名学生寮に滞在していました。その中で日本語教育に興味を持った学生が、授業を見学したいと、申し込んできました。私は日本語教授法の教師でもありますから、「見学するだけなら、お断り。毎回TA補助員として、授業のお手伝いをしてもらいます」と、見学を許可しました。毎回3~5名が顔を出し、私の指示によってリピート練習の範読を担当しました。
90分授業全部をひとりでこなし、リピート練習の声出しをしていると、のどが枯れます。小さい声でマイクを使う先生もいますが、私は地声でやりたい人なので。
リピート練習で同じことを繰り返し範読するのが嫌い、という私のわがままもあります。範読を繰り返すだけなら、教師はテープレコーダーと同じじゃないの、と思ってしまうからです。むろん、教師の生声でリピートしたほうが、ずっといい効果が出ます。学生の出身地にによって多少のアクセント違いなどがありますが、訓練されたアナウンサーの標準アクセントのCDを聞かせるより、生の声のほうがリピートにもはりあいがあります。
TAおよびTA補助員のおかげで、リピート嫌いの私でも、リピート中心の当地の語学教育の伝統を壊すこと無く授業を進められました。感謝です。日本から来てビルマ語を学んでいる学生と、日本語を学んで日本へ留学したいミャンマー人学生の交流も果たせたことは、当地に日本語教室を開いた成果のひとつだと思います。
授業に出席し日本語教育を受けた受講生のうち、3名の女子学生は、10月からの日本派遣が決定しました。日本語の定着度はそこそこですが、これから日本でさらに日本語学習に励んでくことでしょう。
行
ショートステイ日本人留学生が20日間の短期留学を終えて修了式を迎え、学科長主催の食事会が開催。されました。日本へ留学することが決まった3人娘が「修了式の手伝い」として出席し、修了証を手渡すときの補助などを務めていました。
修了式の会場レストランに入る日本人ショートステイ留学生と、日本へ留学する3人のミャンマー人女子学生。送迎のバスの車体には「シャトー猿ヶ京」と書いてありました。中古バスの再利用です。群馬県の温泉ホテル。「わぁ、なつかしい、この温泉ホテルに泊まったことがあります」と言いました。

3人とも黄色い衣装を着ているので、打ち合わせたのかと思ったら、「日本の人が同席する会だから、ミャンマーの国花の色のロンジーを着ようと思って選んだら、3人とも同じ考えだった」と、服装が同じような黄色になった秘密を教えてくれました。私が青いシャツを着ているのは、月曜日と金曜日、教師は青系の衣装を着る、という伝統によるものです。私は外国人教師なので、ロンジーを着るかどうかも自由です。
当地の女性教師のロンジーは、同じような青い色に見えても、柄によって、准教授なのか、教授なのかなど、細かい身分差があるのだと、聞いたので、セヤマー(女教師)のひとりに尋ねてみました。そんなことはない、どんな柄を選ぶのでも自由です、というこたえでした。
中国清朝の官僚制度でも、自宅の門構えやら階段の段数にまで身分による細かい差がありましたが、当地の「青い衣装の柄によって身分がわかる」というのも、昔はそういうしきたりがあったのかも。
日本へ留学することが決まった日本語受講生3人娘。みな笑顔がかわいいです。

<つづく>










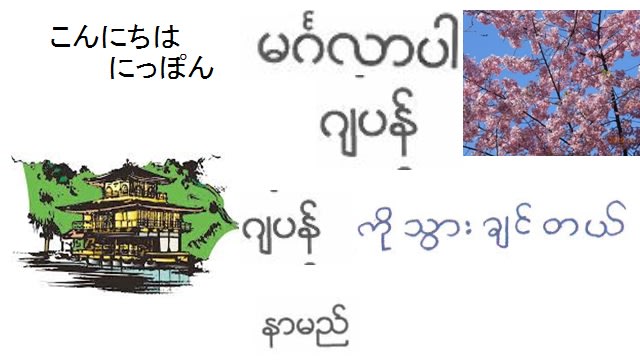
 ・
・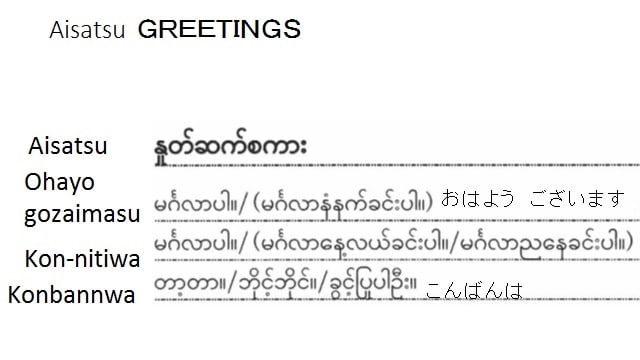

 20150903
20150903



























