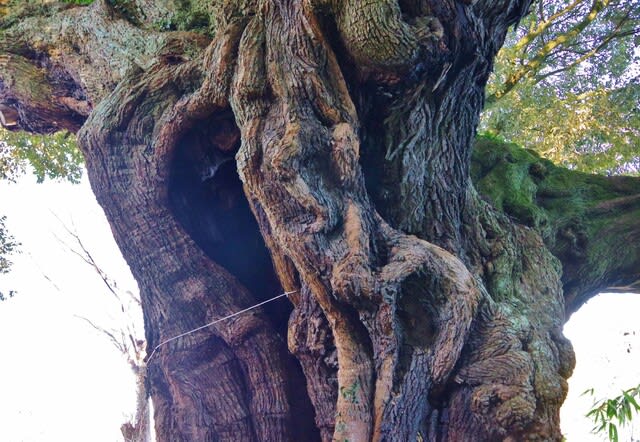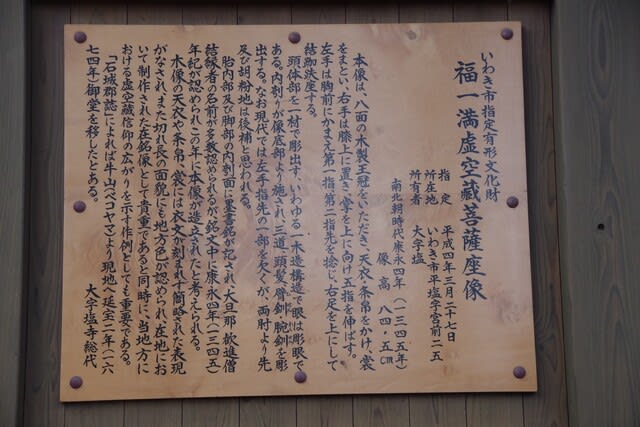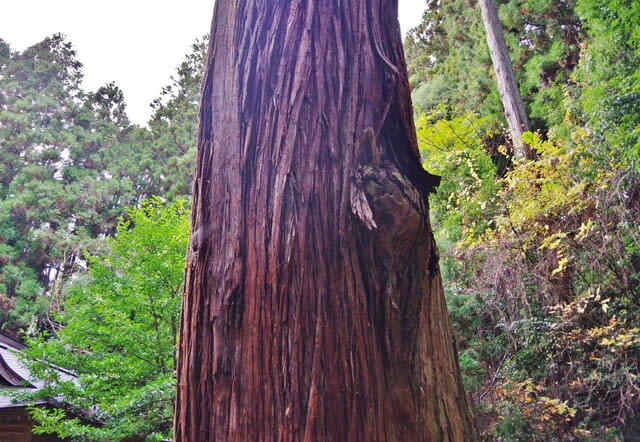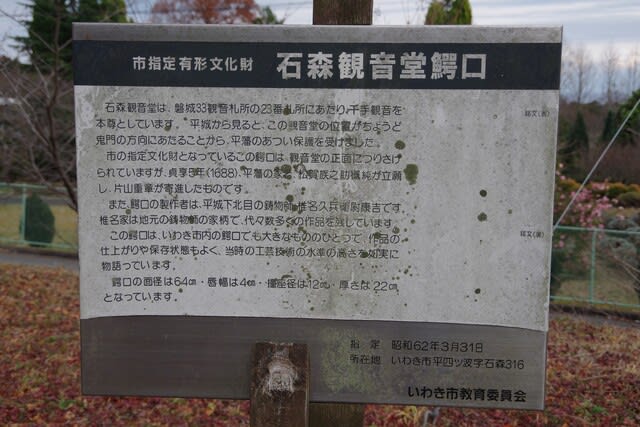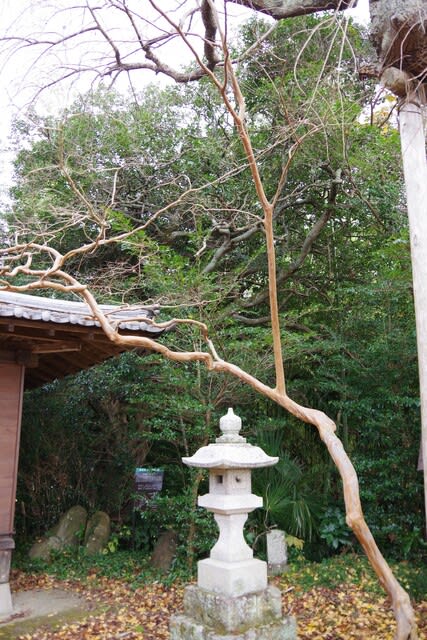関本町才丸地区は、北茨城市役所の北西約14kmのところ
県道69号線を北西へ、磐越自動車道の高架を潜って間も無く左からの県道10号線となります
道成りに進んで、華川小学校西信号からは県道153号線となって進みます
水沼ダムのダム湖を右に見て花園川沿いを進みます
右からの県道27号線と合流するところを右へ県道27号線を北へ進みます
約2.3kmで県道が右へカーブするところを斜め左(北)へ入ると

正面に諏訪神社が南向き参道で丘の上に鎮座します 、参道入口に
、参道入口に 車を止めさせて頂きました
車を止めさせて頂きました
*この直ぐ北側にスギの巨木があるはずなのですが、見つかりませんでした

諏訪神社のアカガシを見て行きましょう

参道入口左手の石碑です

右手には、湯殿山・十八夜塔・馬頭観音・庚申塔などの石碑や仏像が並びます、参道を上ります



石段中段南側下から境内南端に目的のアカガシです



南南西下側から見上げました



境内に上がって西側から

説明版です
北茨城市「みどりの文化財」 第5号
表示名 アカガシ
科名 ブナ
樹齢 推定300年
平成24年3月
北茨城市教育委員会
*サイズ(規模)は、樹高15.0m、目通り幹囲5.0mとのことですが、残念ながらそこまでのサイズでは無いようです


北東側から

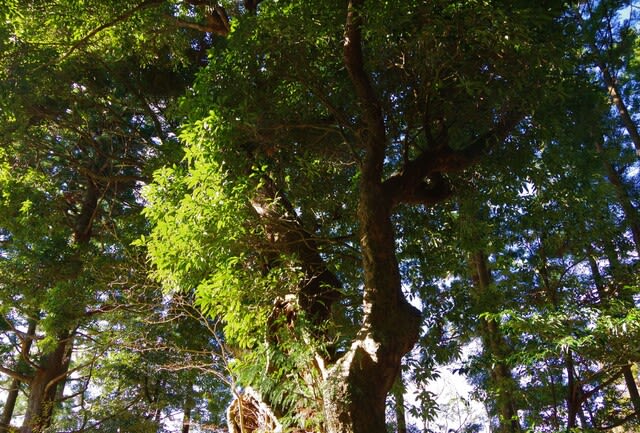

東側から

拝殿脇(北西側)から見ました

拝殿です



本殿です



境内東側のスギは、雷の傷と思われる跡が残っています



本殿の裏側には、モミノキの大木が数本見えました
では、次へ行きましょう

県道69号線を北西へ、磐越自動車道の高架を潜って間も無く左からの県道10号線となります
道成りに進んで、華川小学校西信号からは県道153号線となって進みます
水沼ダムのダム湖を右に見て花園川沿いを進みます
右からの県道27号線と合流するところを右へ県道27号線を北へ進みます
約2.3kmで県道が右へカーブするところを斜め左(北)へ入ると

正面に諏訪神社が南向き参道で丘の上に鎮座します
 、参道入口に
、参道入口に 車を止めさせて頂きました
車を止めさせて頂きました*この直ぐ北側にスギの巨木があるはずなのですが、見つかりませんでした


諏訪神社のアカガシを見て行きましょう


参道入口左手の石碑です


右手には、湯殿山・十八夜塔・馬頭観音・庚申塔などの石碑や仏像が並びます、参道を上ります




石段中段南側下から境内南端に目的のアカガシです




南南西下側から見上げました




境内に上がって西側から


説明版です
北茨城市「みどりの文化財」 第5号
表示名 アカガシ
科名 ブナ
樹齢 推定300年
平成24年3月
北茨城市教育委員会
*サイズ(規模)は、樹高15.0m、目通り幹囲5.0mとのことですが、残念ながらそこまでのサイズでは無いようです



北東側から


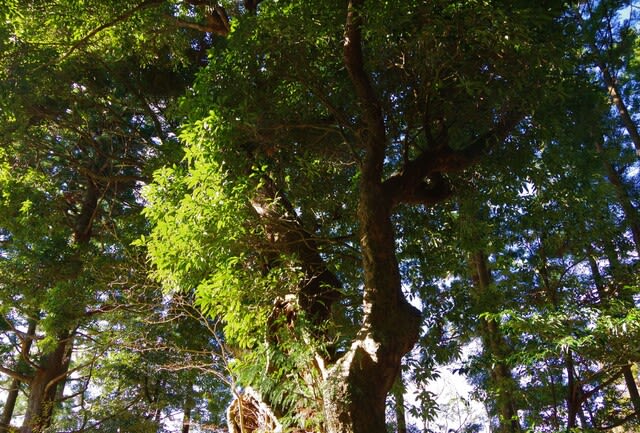

東側から


拝殿脇(北西側)から見ました


拝殿です




本殿です




境内東側のスギは、雷の傷と思われる跡が残っています




本殿の裏側には、モミノキの大木が数本見えました

では、次へ行きましょう