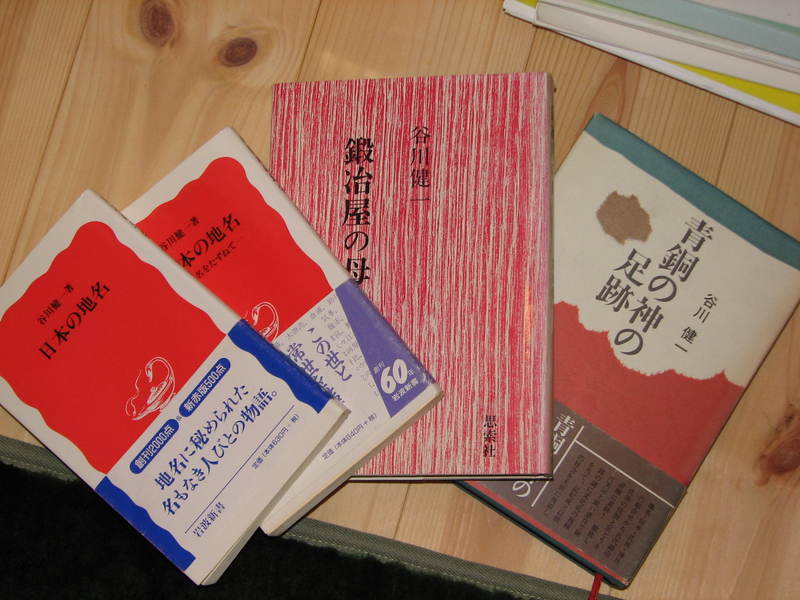2010.6.13(日)雨
じょんのび究極のメニューシリーズで自慢が出来るというのか、まともなものは今のところ梅干しと柚子大根とちりめん山椒である。このうち最も歴史があるのはちりめん山椒だ。といっても3回目の作製だが、梅干しは今年は不作で作れないし、柚子大根は昨年一回作っただけだ。
最初に作ったちりめん山椒はべちょっとしてしかも塩っぽいという欠点があった。昨年はその反省を活かし、ちりめんじゃこの塩抜きをしっかりして、水分を少なく、しかも天日干しをするなどの工夫をし、ほぼ完璧に仕上がった。私は超辛くて、唇のしびれるようなのが好きなので、ゆであがり後の冷水さらしを短くして超辛に仕上げたが、他の人びとには人気が悪かった。今年はややマイルドに仕上げるべく、さらしの時間を一時間としたが、山椒の辛みはどうもそれだけで決まるようでもないようだ。更にいいものをつくろうと、レシピを色々探ってみる。
わりかし単純な調理だけにまあレシピも千差万別だ。それぞれにうんちくが書いてあって、なるほどなあと思わせる反面どうすればいいのか迷ってしまう。例えば最初の山椒のゆで時間でも、一分以上は絶対駄目というのもあれば、しっかりゆであげるというのもある。どちらも根拠が示されていないので判断のしようがない。ちりめんが高価なだけに失敗は許されない。結局無難に昨年までのレシピに基づいて作ることとする。
【材料】
山椒の実 大さじ8杯
濃口醤油 大さじ6杯
みりん 大さじ3杯
縮緬じゃこ 140g
酒 適当
山椒の実は中身が少し堅くなっていて、黒っぽくなっている。収穫時期が少し遅いようだ。自前で採れるようにならないとこの調節は難しい。昨年までは濃口と薄口を半々に使ったが、薄口醤油が無かったため濃口だけになってしまった。塩気は少なくなるだろうが、色合いは濃いものになりそうだ。みりんはよく見たらみりん風味調味料であった。これはみりんとは全然違うもので、合成の調味料である。本みりんを買うように言ったら、「高いもん」と一蹴された。一度原材料を見て欲しい。
酒は料理酒というのが購入してあった。酒を飲まない家ならともかく、料理酒をわざわざ買う方が不経済と思うのだが、、、。しかし、安物の、あるいは偽物の材料で旨く作るのが究極の調理人なのかもしれない。
(1)山椒の葉っぱや枝をとる。今回は手でとったが、残った山椒は冷凍して簡単に取れる方法を試しているので、うまくいけば来年はその方法を紹介したい。
(2)ほぐした実を5分ゆで、冷水に一時間さらす。ここのところの時間加減がいろいろあるようだ。
(3)ちりめんじゃこは熱湯をとうして塩気を抜き、汚れを落とす。しっかり塩気を抜いた方がよろしい。
(4)鍋にじゃこを入れ、1/3の水を入れ酒を適当に足す。じゃこをほぐしながら水気が無くなるまでゆでる。じゃこの形が崩れないように注意する。
(5)水気が無くなったら、先程の醤油を入れて弱火で炊きあげる。しっかりしょうゆがしみこんだら、みりんを入れてこくを出す。
(6)再度水気が無くなったら、山椒を入れて混ぜる。水気が無くなったら、笊にあげて天日干しする。
(7)好みの問題だが、私は硬くてカリッとしたのが良いので半日ぐらい干す。あとは瓶に詰めて終了。いただきます。
京都の老舗なら何万円としそうな量のちりめん山椒が千円以下で出来上がる。二ヶ月ぐらいは楽しめそうだ。
今日のじょん:メーパパが「じょんは情けない顔をさしたら日本一やなあ」などと妙なほめ方をするもんだから、人の息子に失礼なことを言うもんだと思いつつも、なるほど情けない顔しとるなあと感心したりする。記事がないときに情けない顔シリーズでも出しとこう。2010.4.18、ベランダで日向ぼっこ。