言語に関する考察・前章2
前章1で民族の移動の話をしました。今日はそれを踏まえた上でのお話です。『五色人』ってご存知ですか。古代にいたとされる世界の人種の言い伝えで『竹内文書』(偽書とされている)の記録です。また九州阿蘇の幣立神社には五色人の面が伝わっており、毎年8月にはお祭り(五色人祭)が行われています。何時でしたか特別な例大祭に久司先生もお参りなさったと聞いています。
この五色人は赤人、青人、黒人、白人、黄色人でそれぞれ各人種にあてはめられていますが、今ひとつ疑念や訳の分らぬもやもやを払拭するに足る説明がありません。それに幣立神社にはその五色人が集まってお祭りをしてきたというのです。これは私にとって長年の謎でした。それが何時でしたかお話した、川崎真治先生の『混血の神々』に出会って新しい波動と遭遇し新しいインスピレーションにまきこまれ、『カタカムナが人類最初の言語である』という命題の新しいステージが開けました。
川崎先生によると(私は先生を正しいと思いますが)、約三万年前以来中国大陸に存在した民族はシンボルマークをもっており、五種族だったそうです。そのシンボルマークをトーテムと呼び、これは三万年前に始まったことではなく五万年前のメソポタミアにもあり、多分十万年前の出アフリカ時にもあったであろうと思われています。何故かというと前章1にも書きましたが、アフリカを出る、メソポタミアを出る、などという画期的な事件は必要性が無ければ起きようはずもありません。一人や二人なら冒険に出るということもありましょうが、一族郎党を引き連れて・・・・などというのは族長の決断なしにはありえません。
最もあり得る筋書きは、そこに(後から見れば)居座った部族による迫害を逃れて、つまり支配階級を追われてということだろうと思います。何時も草原のヌーが引き合いに出されますが、ヌーの数が少ないうちは十分に草原内の草(食べ物)を分かち合えるはずです。ヌーの場合は数が増えればライオンが増えるという仕組で適正数が維持されて食糧が保全されていますが、ライオン(天敵)がいなくなった人類は弱い方が出て行かざるを得なかったのだろうと思います。つまり当時の人類社会は部族を形成するに十分な人口があり、食糧と権益を分かち合うための身内と外部という区別がすでにあったのです。つまり身内だと認識する、あるいは身内でないと区別するための符牒があったはずです。
以前私の『ヒレフリ山教室』で名前を使わずに自己紹介をするという実験(?)をしたことがあります。その難しさをみんな実感しました。名前というものの持つ意味を深く感じたものです。名前はその人をその人と分からせるための符牒です。名前には姓と名があります。姓は属している物の符牒、名はその人だけを呼ぶ符牒です。家族には家族の姓が、平戸人には平戸という地名が、長崎県人には長崎県という県名が、日本人には日本という国名が、属している符牒です。そしてこの符牒が古代社会にあってはトーテムというものだったのです。誰かを呼ぶ時は、『どのトーテムの誰とかさん』と呼んだのです。日本史でも耳慣れていますよね、そがのうまこ(蘇我馬子)さん、おののいもこ(小野妹子)さん、たいらのきよもり(平清盛)さん、みなもとのよりとも(源頼朝)さん!!!
古代社会のトーテムにはどんなものがあったかというと、(川崎先生によれば)メソポタミア人は牛を、その中からインドネシア・ポリネシアに進出して海洋民族となった人々は蛇を、そこから中国大陸に進出して原初シナ民族を形成した人々は鳥を、ヨーロッパに進出した人々が作った民族は犬を、南シベリアで遊牧民族となった人々は馬を選んだらしいのです。これが現生人類のもっとも大まかな、現代の国籍を超えた民族の姓です。私達は忘れていますが、人類と国籍の間に入れるべき民族の姓です。たとえば私なら、人類、牛・蛇・鳥・犬・馬のどれか族、日本人、長崎県本籍、柿本という家族の和子です。現生人類はこの五族のどれかにみな属しているのです。勿論牛にも色々、蛇にも色々、鳥にも色々、犬にも色々、馬にも色々います。
牛、蛇、鳥、犬、馬という各トーテム族には、部族員が増えて地域の特色や複雑さが増すにつれ、トーテムはダブルになりトリプルになっていきます。ちょうど電話番号が地域番号の桁数を増やすと格段に許容量が増えるのと一緒です。牛族にも牛、塩(猿)・・・・、蛇族にも蛇、龍、象・・・・、犬族にも犬、狼、ライオン(獅子)・・・・、馬族にも馬、鹿・・・・・などとさらに分かれて行きました。副トーテムに牛族はフクロウ、犬族は鷲や鷹などと種類を増して行きました。
ここで川崎先生とちょっと意見が違ってくるのかもしれませんが、インドシナ地方の蛇族と原初シナ人の鳥族とは元々同じだったと思います。その根拠は
1.もともとメソポタミアから移動した風の神を祭る海洋民族だった。
2.基本トーテムがともに風神ゆかりの蛇と鳥で、ともに卵生である。
3.古代中国で生まれた王権のシンボルが龍(蛇)と鳳凰(鳥)で、ともに風神の権化である。
などです。川崎先生はともに黄色人種と言われています。(マクロビオティックによれば、そういう食生活の地域であったということになります。)
もともと蛇族はメソポタミア地方で牛の一族であった塩(ソルト・サルト→サル→猿)族の一部が海上交易術を編み出してインド方面に進出したドラビダ族だろうと川崎先生は言われています。そして川崎先生によれば、そのドラビダなる語もdu‐ur、つまり次の牛という意味らしいのです。それでメソポタミアに残った塩族はそのまま牛族にとどまりましたが、海洋進出をした塩族が蛇をトーテムとする蛇族になりました。後代のギリシャの都市国家でもそのマークは使われましたし、今でも蛇は交易のマークです。それで北上して内陸部に入りこんだ塩族が海洋交易のマークを捨て海を支配する風神のお使いであるもう一つのトーテム・鳥を採って独自の文明を開きました。
それが三皇五帝に始まる中国の文明です。三皇五帝をご存知ですか。第一皇は風姓・太昊伏羲(たいこうふっき、または ふくぎ)氏、第二皇は姜(きょう)姓・炎帝神農氏、第三皇は姫(き)姓・黄帝公孫氏、第一帝は風姓・少昊(しょうこう)金天氏、第二帝は風姓・顓頊(せんぎょく)高陽氏、第三帝は風姓・帝嚳(こく)高辛氏、第四帝は伊祁(いき)姓・帝堯陶唐氏、第五帝は姚(よう)姓帝舜有虞氏です。この後夏・殷・周・秦・漢と続いていきます。ちなみに伏羲は蛇身人首、神農は人身牛首とも伝えられています。これはどういうことかと言いますと、身は母に譲り受けられるものですから、その母の出自が蛇族で、首、つまり系譜はこの王朝の創始者・人(鳥)族であると言っているのです。神農は母が鳥、父方が牛で牛族だと言っているのです。
こういうわけで中国の王朝はまず鳥族、次に牛族、牛族と続いて、五帝になると鳥族、鳥族、鳥族と続いて犬族、牛族と受け継がれました。夏は娰(じ)姓夏后氏で牛、太祖は禹ですね。殷の王朝は風神に連なる風姓ですから鳥ですね。(こういうのは文字や言葉を見ればわかるのですが、もし詳しく知りたいと思われるのなら、川崎先生やその方面の研究書で自由に勉強なさってください。)というわけで少なくとも三皇五帝の時代は鳥、蛇、牛、犬の各部族がいたことになります。夏は牛、殷は鳥、周も牛です。そして春秋戦国時代を迎えます。周礼は乱れ秩序を失い、犬の秦の始皇帝の登場となり、次に中国の王朝の正統と自負する漢王朝が続きます。漢王朝はその自負や国名の漢字から蛇か鳥だと思われます。こうして中国大陸(漢字文化圏)の王権は『龍』と『鳳凰』が象徴することになりました。
この王朝の交代劇は当然周囲の満州地域、朝鮮半島、我らが日本列島をも巻き込んで行きます。満州や朝鮮は陸続きですからなおのことです。そうした関係が中国の王朝を常に脅かす東夷西戎南蕃北狄と言われる周辺民族を作りだしたのです。鳥の殷王朝からすれば、南蕃は親類筋の蛇族ですが、王朝内には西戎の牛、犬がいたことが伝説で分かります。前身の夏は牛でありそのまま残留した者もいたでしょうし、殷には犬侯と称する官位があったとの記録があります。殷には犬が藩屏部族としていたことになります。殷という国号も犬が強かったことを示しているのかもしれません。そして牛や犬が来ていたならば当然馬もいたことでしょう。ですが馬は遊牧民であり、なかなか定住になじまなかったと思われます。そしてこうした部族社会はなかなか入り混じらずにその部族の独立性を長く維持するのです。
私達はその証拠を12~13世紀の元王朝に見ることが出来ます。私達は元が部族階梯社会であり、クリルタイと呼ばれる部族長会議で国事の決定が行われ、全盛期のクビライ汗の死後は5つの汗国に分かれたことを習いました。クビライ汗国、キプチャク汗国、イル汗国、オゴタイ汗国、そしてバツ汗国・・・・・・?この元王朝の始祖は有名なチンギス汗、『青い狼』と称された英雄です。狼は大型犬のことで、つまり犬ですね。『元』という国号も犬であることを暗示しています。この部族階梯社会というのは王位の継承すらクリルタイの同意がないと出来ないのです。つまり国の中は全てが分権状態で、効率よく政治をする国家権力は無かったのです。
ここでやっといつもお話している《チュモン》と《ムヒュル》の出番がやってきました。この韓国映画のおかげで私は自分の謎を解くことが出来たのです。皆様ご存知の《チュモン》は高句麗建国のお話、《ムヒュル》はチュモンの孫が偉大なる高句麗の基礎固めに登場し扶余を滅ぼすまでの話です。チュモンの出自である北部満州にあった扶余の社会構造は、馬加(まか、orまが)・牛加(うかorうが)・豬加(ちょが)・狗加(くが)の四族で、王族は馬加の一族で鹿をトーテムとしていました。まあ映画は映画で、各部分のシナリオがどれだけ事実を反映しているか分かりませんが、それでも良く出来たいろいろ考えさせられるお話でした。そして扶余王クムワ(金蛙)も高句麗の始祖チュモン(朱蒙)もともに卵生神話を残していて、鳳凰か龍の化身、つまり持って生まれた王者の出自を後世に伝えています。東アジアでは大王は第一皇風姓・太昊伏羲氏の後継者でなければならないのです。
高句麗は映画ではチュモンと桂婁(ける)とが協同して建国をはたすストーリーになっていました。桂婁は卒本(チョルボン)の一部で、卒本には他に沸流(ピリュ)、灌奴(カンナ、貫奴・桓奴の字も用いられる)、順奴(チュンナ)の部族がありました。そこにチュモン率いる一族が王直轄部族として加わります。このお話に出てくる様々な筋書きは伝説をつなぎ合わせて想像したものですから、現実がどういうものだったかは分かりません。高句麗についての史書では、チュモンが沸流川をさかのぼって松穣(ソンヤン)を降伏させ沸流を提那都(?)と改名したとあります。また高句麗の社会構造は涓奴部、絶奴部、順奴部、灌奴部、桂婁と書かれています。高句麗は時代が下っても五部貴族社会でしたし、この記録は魏志の内容なので三世紀くらいのものです。建国当時はもっと独自の部族名だったかもしれません。
扶余の部族はトーテム名そのままですが、高句麗は漢字の意味を体した“仮借”が行われて、どのトーテムか分かりにくくなっています。詳しい説明は省略しますが、川崎先生は扶余の豬加を鳥に、高句麗の涓奴部を馬に、絶奴部を沸流の牛に、順奴部を豬(鳥)に、桂婁を犬に当て、残りの灌奴部を高句麗の地理的特性による蛇族だろうと言っておられます。扶余は内陸部だったので海洋性の濃い蛇族は部族としてはいなかったのだろうと言っておられます。つまり高句麗社会には世界の五族がいたことになります。初期の高句麗でも王族は馬、映画のソソノは桂婁でしたが、当時の卒本四部族で優勢だったのは沸流の牛で二代王から王妃は沸流(絶奴部)から出すことになり、ムヒュルの母も沸流の松(ソン)氏です(ソンヤンの娘)。
ですが三世紀の魏志には王族は桂婁と書いてあるそうです。そしてまた王族の桂婁を五部族の最後に記載しています。また高句麗と言わず句麗とも言っています。句麗は狗麗でもあり、狗は犬を矮小化した文字でもあるのです。中原王朝は周囲に卑しんだ字を用いることが多いのです。後世の史家は資料を大切にするので(それしか資料が出ていないので)仕方ありませんが、身近には魏志倭人伝の邪馬台国があります。邪馬は東夷伝にも用いられた豬(つまり鳥)族を卑しんだ言葉です。豬自体がすでにバカにした言葉なのですが・・・・・そして魏志倭人伝では日本の2~3世紀の支配国も豬(鳥)族だと言っているのです。高句麗に戻りますが、高句麗では王族が馬から犬になりました。どうやってかというと想像するに外戚の力だろうと思います。高句麗最後の宰相(?)淵蓋蘇文は東部太夫で字面からは順奴部で豬(鳥)だと思われますが、日本書紀ではイリカスミとなっていて犬だと記されています。
こうした王朝の交代劇、つまり部族の放逐劇が周囲の民族に影響をもたらしました。当然朝鮮半島南部、日本列島にまで及んだのです。やっと我が日本に辿り着きました。我らが日本列島には約3~4万年前インドネシア地方から蛇族が渡ってきて住みつきました。ここに中原が牛、犬、馬の勢力が強まるにつれて、蛇と同種の鳥(豬)が土地を追われ日本海を渡ってきて原始日本人を形成しました。そして中原から朝鮮半島の王朝の交代劇のたびに牛、犬、馬が追われて渡ってきたのです。そしてわが日本にも五族が揃うことになったのです。当に我が日本はアジア大陸の東の果て、行きどまりです。結論を言いますとこの五族が五色人です。それぞれに何色を当てるかについては次章『五色人の謎Ⅱ』に譲りたいと思います。
それでは今日も:
私達は横田めぐみさん達を取り戻さなければならない!!!!
最新の画像[もっと見る]
-
 蠟梅
4日前
蠟梅
4日前
-
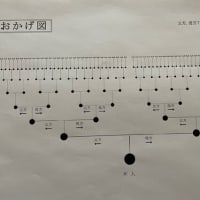 私達は種・タネである。
1ヶ月前
私達は種・タネである。
1ヶ月前
-
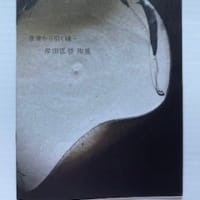 同窓生の近況
4ヶ月前
同窓生の近況
4ヶ月前
-
 同窓生の近況
4ヶ月前
同窓生の近況
4ヶ月前
-
 あの日はどこに行ったのだろう!
8ヶ月前
あの日はどこに行ったのだろう!
8ヶ月前
-
 春の味
12ヶ月前
春の味
12ヶ月前
-
 立春を迎えました。
1年前
立春を迎えました。
1年前
-
 立春を迎えました。
1年前
立春を迎えました。
1年前
-
 秋ナスの季節になりました。
1年前
秋ナスの季節になりました。
1年前
-
 平戸の長茄子
3年前
平戸の長茄子
3年前
















蘇我馬子なんとなく昔から変な名前と納得してませんでしたが再考するヒントを選ったような気がします。何度も読み直し考えてみます。ありがとうございました。
こういうことに興味がおありですか。私の場合マクロビオティックとは関係が無いと言えばそれまでの話なんですが、マクロビオティックによって生涯のテーマが色々と開けています。それでどうしてもこうなってしまいます。ブログというものが本来どういう性格のものなのか私にはわかりませんが、なんとも都合のよい発表の場で楽しんでいます。どうぞよろしくお願いします